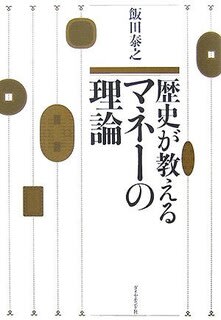飯田泰之 「歴史が教えるマネーの理論」読了
もうちょっと楽に読める本かと思ったがかなり硬派な本であった。というか、一応僕も経済学部卒業ということになっているのだが、こんなにも経済学についての知識がないものかと愕然としてしまった。
コロナ、戦争で物の値段が上がり、燃料の価格もどんどん上がり、政府はいっぱいいろいろなところで補助金を乱発しているがこの国は大丈夫なのか、円もどんどん安くなり世界の中で日本はいったい生き残れるのだろうか・・。そんなことよりも僕の生活はこれから先大丈夫なのか・・。そんなことを思いながら何か読み物はないかとこの本を探した。
経済学とは特にマクロ経済の部分においては「経験の科学」と言われるそうだ。経済学におけるデータは過去のデータであり、言い換えればそのデータには再現性がないということを意味する。科学というものは再現性があることでその現象なり理論が科学的であるということが証明されるのであるから、「学」という名前がついていながら残念ながら経済学には再現性がないのである。
昨日の新聞では、リーマンショックのとき、エリザベス女王は、「なぜ誰もこの事態を予測できなかったのですか?」と自国の経済学者たちに問いかけたといい、今日の夕刊には、2012年のアベノミクスによる金融緩和策を始めたとき、黒田総裁は、「2年程度で物価安定目標(2%程度)を達成できる。おそらくどのような経済モデルで計算しても、物価だけ上がって賃金が上がらないということにはならない。」と言っていたと書いていた。
まったくどんな経済モデルを使って計算していたのかと思うが、それほど再現性もなく過去のデータも当てにならないのが経済学であるということだ。
逆にいうと、様々な経済法則通りにことが運べば世の中に不況はなくなる。少なくとも為政者たちがまともであれば。もちろん、国際社会では国と国が自国を豊かにしようと競うわけだからうまくいかないこともある。しかし、それも国際協調の時代でもあるのだから共存共栄という方策もあるはずだ。
それがうまくいかないのは人々の「気分」がそこに関わっているというのである。
そういったことを世界の歴史、日本の歴史の中で行われた金融政策、財政政策の内容と結果を例に挙げて分析しようというのがこの本だ。
中心になるのは、「貨幣数量説」「購買力平価説」であるが、これは経済学という学問上では相当古典的な考え方だが、大まかには国際収支や物価の変動の仕組みがわかるそうだ。経済学部を卒業しているにもかかわらずその内容はほとんどわからないのだが、物価変動についてはお金の回転数(収入のうちどれだけ消費に回すか)と将来の期待値(これからさき、お金に困らないかどうか)、市場にどれだけお金が流通しているかという3つのことで決まるそうだが、それを、「貨幣数量説」をもとに説明がされている。
市場に流通するお金が増えればお金の価値が下がって物の値段が高くなるというのはよくわかるし、お金の回転数についても同じ考え方であるということもよくわかる。「貨幣数量説」で説明できるのはここまでの話だ。
そこに加わる、「将来の期待値」というのは、今、お金を残しておかないと将来困ったことになるのではないかというような考え方だ。そう思うと人はお金を使わなくなる。そうするとお金の回転数が下がり物価も下がる。デフレになるということだ。
それはある意味まったくの「気分」である。日本では経済の6割を個人消費が占めているという。そこの部分が「気分」で動いているといのだから理論通りにことを運ぶのは難しい。
基本的にはインフレ気味のほうが個人所得も増えるはずなので経済成長しやすい。しかし、日銀の金融政策は史上空前の緩和政策で市場へのお金の流通量を増やしてインフレ基調になるのを目指しているが、もう何年もそれが実現していない。そこには「気分」が入っているからだ。
非正規雇用者が増え、収入も上がらなさそうだと世間全体が予想するとそこそこ豊かなひとでも支出を控えておこうと考えるのは無理からぬことだ。
黒田総裁はそういうことがわかっているのだろうか。日銀の総裁なのだから経済学のすべてを理解しているはずなのだろうが、それは貨幣数量説までで、ひょっとして庶民の「気分」についてはまったく理解をしていなかったのではないだろうか。
この先、昇給も見込めず、一応、借金がない生活をしているので、インフレよりデフレのほうがありがたいという年金生活をしているという人たちとまったく変わらない家計生活をしている身のうえからすると、無理してインフレにしてもらわなくても全然かまわないと思っているので黒田総裁の政策にはまったく共感を覚えないのである。
為替相場についてはどうだろうか。この本では、固定相場の時代の中で、為替相場をどう設定するかということと、兌換制度の中で貨幣の質を落とすと(改鋳する)と自国での経済はどうなるのかということをもとに説明しているが、やっぱり経済学部を卒業しているにも関わらずほとんどわからないのである。まあ、僕の記憶の中で、大学の授業で改鋳についての講義を聞いたという経験はなかったのでも無理からぬことではあるのであるとここでもとりあえずは弁解をしておく。
為替相場については「購買力平価説」をもとに説明がされている。これは、二国間の為替レートというのは一物一価の原則で、それぞれの国の通貨でひとつの物がどの値段で買えるかというところに自動的に落ち着くというものだ。
しかし、現実はかなり不安定である。何が原因となっているのかというと、ここでも将来においてそれぞれの国において流通するお金の量に対する期待と予測が不安定だからであるそうだ。金融引き締め策で金利が上がりお金の流通量が減ると予測するとその国のお金の価値は上がるが、「今」を基準に考えるとその価値は購買力平価説には沿っていない。
しかし、金利を上げてしまうとその国ではデフレという不況を呼び込むことになる。
今日、円は1ドル146円を超える円安になってしまった。アメリカは原材料費や賃金の高騰で引き起こされたインフレを抑制するために金利を上げているからなのであるが、それでも今のところデフレ方向には振れていないらしい。かたや日本は円の価値が下がってインフレになるはずだが実はアメリカほどまだまだ物価が上がっていない。それでも、所得が伸びない中では1万近い品目がわずかずつでも値上がりされると生活は苦しくなる。
なぜこんな矛盾が起こるのかというと、よいインフレというのは、経済規模の拡大と同等の物価の上昇と所得の上昇であれば人々の生活は豊かになったといえるのであるが、経済規模が拡大しないのに物価だけが上がっているからなのである。経済規模が拡大していないから所得が上がらず物価だけが上がっているのだからそれは生活が苦しくなるのはあたり前だ。
これは幕末の頃にオールコックという英国外交官の提案によっておこなわれた万延小判の発行による大幅なインフレによる生活水準の低下とよく似ているらしい。
万延小判はそれまでの天保小判の3分の1しか金の含有量がなく、要はお金の流通量が一気に3倍になってしまったということなのだが、江戸時代は大規模な工業化社会ではなく経済規模が拡大する余地がなくインフレによる需要拡大→失業の減少→景気の改善ではなく、需要だけが膨らんでしまったというものである。
今の日本も、金融緩和でお金の量だけが増えても経済規模はまったく拡大していなくて物価だけが上がっているので僕の生活はますます苦しくなっているというのはまったく幕末と同じように見えるのである。幸か不幸か、流通量が増えたお金のすべてが市場に出回るのではなく、将来に不安のある企業や個人は内部留保や貯蓄という形で仕舞い込んでしまっているので黒田総裁が期待しているほど物価が上がらないのでこれだけで済んでいということだろうか。
どちらにしても、黒田総裁は庶民の「気分」というものをまったく理解できていないのではないかということと、岸田総理が言う、「成長と分配の好循環による新しい資本主義」などという幻想にしがみついているということが現在の僕の生活の苦しさの元凶であると思うのだ。
すでにこの時代、経済成長などというのは少なくともこの日本では期待できないであろう。そうであれば江戸時代のようにゼロ成長でインフレでもデフレでもない経済を目指すのが一番妥当ではないのだろうか。
これからの日本は「鎖国」に向かうのが一番なのだと思うのである。インバウンドなどはくそくらえだと主張する政治家は出てこないものだろうか・・。
ニュースではさらに円安は進むだろうと言っていたが、この先、僕の生活はどうなってゆくのだろう。円安だけを見てももっと物の値段が上がっていきそうだ。
今日はG20の財務相・中央銀行総裁会議が始まったがそれほど為替にはそれほどの影響はなかったようだ。日本の財務大臣のコメントも人ごとのようだ。
来月にはアメリカ議会の中間選挙があるが、共和党がちょっと盛り返すという予想らしい。そうなってくると、トランプの息のかかった人たちはもっと強いアメリカを主張し、為替レートももっと円安に振れるだろう。
どんどん日本の力が弱くなっていく。「円安を追い風に経済成長を目指すのだ。」とはどこの阿呆が言っているのだろうか。
とりあえず僕も、円安とドルの金利が高いということの恩恵を受けるべく、外貨預金のようなものをやってみようかしらと思っている今日この頃なのである。
もうちょっと楽に読める本かと思ったがかなり硬派な本であった。というか、一応僕も経済学部卒業ということになっているのだが、こんなにも経済学についての知識がないものかと愕然としてしまった。
コロナ、戦争で物の値段が上がり、燃料の価格もどんどん上がり、政府はいっぱいいろいろなところで補助金を乱発しているがこの国は大丈夫なのか、円もどんどん安くなり世界の中で日本はいったい生き残れるのだろうか・・。そんなことよりも僕の生活はこれから先大丈夫なのか・・。そんなことを思いながら何か読み物はないかとこの本を探した。
経済学とは特にマクロ経済の部分においては「経験の科学」と言われるそうだ。経済学におけるデータは過去のデータであり、言い換えればそのデータには再現性がないということを意味する。科学というものは再現性があることでその現象なり理論が科学的であるということが証明されるのであるから、「学」という名前がついていながら残念ながら経済学には再現性がないのである。
昨日の新聞では、リーマンショックのとき、エリザベス女王は、「なぜ誰もこの事態を予測できなかったのですか?」と自国の経済学者たちに問いかけたといい、今日の夕刊には、2012年のアベノミクスによる金融緩和策を始めたとき、黒田総裁は、「2年程度で物価安定目標(2%程度)を達成できる。おそらくどのような経済モデルで計算しても、物価だけ上がって賃金が上がらないということにはならない。」と言っていたと書いていた。
まったくどんな経済モデルを使って計算していたのかと思うが、それほど再現性もなく過去のデータも当てにならないのが経済学であるということだ。
逆にいうと、様々な経済法則通りにことが運べば世の中に不況はなくなる。少なくとも為政者たちがまともであれば。もちろん、国際社会では国と国が自国を豊かにしようと競うわけだからうまくいかないこともある。しかし、それも国際協調の時代でもあるのだから共存共栄という方策もあるはずだ。
それがうまくいかないのは人々の「気分」がそこに関わっているというのである。
そういったことを世界の歴史、日本の歴史の中で行われた金融政策、財政政策の内容と結果を例に挙げて分析しようというのがこの本だ。
中心になるのは、「貨幣数量説」「購買力平価説」であるが、これは経済学という学問上では相当古典的な考え方だが、大まかには国際収支や物価の変動の仕組みがわかるそうだ。経済学部を卒業しているにもかかわらずその内容はほとんどわからないのだが、物価変動についてはお金の回転数(収入のうちどれだけ消費に回すか)と将来の期待値(これからさき、お金に困らないかどうか)、市場にどれだけお金が流通しているかという3つのことで決まるそうだが、それを、「貨幣数量説」をもとに説明がされている。
市場に流通するお金が増えればお金の価値が下がって物の値段が高くなるというのはよくわかるし、お金の回転数についても同じ考え方であるということもよくわかる。「貨幣数量説」で説明できるのはここまでの話だ。
そこに加わる、「将来の期待値」というのは、今、お金を残しておかないと将来困ったことになるのではないかというような考え方だ。そう思うと人はお金を使わなくなる。そうするとお金の回転数が下がり物価も下がる。デフレになるということだ。
それはある意味まったくの「気分」である。日本では経済の6割を個人消費が占めているという。そこの部分が「気分」で動いているといのだから理論通りにことを運ぶのは難しい。
基本的にはインフレ気味のほうが個人所得も増えるはずなので経済成長しやすい。しかし、日銀の金融政策は史上空前の緩和政策で市場へのお金の流通量を増やしてインフレ基調になるのを目指しているが、もう何年もそれが実現していない。そこには「気分」が入っているからだ。
非正規雇用者が増え、収入も上がらなさそうだと世間全体が予想するとそこそこ豊かなひとでも支出を控えておこうと考えるのは無理からぬことだ。
黒田総裁はそういうことがわかっているのだろうか。日銀の総裁なのだから経済学のすべてを理解しているはずなのだろうが、それは貨幣数量説までで、ひょっとして庶民の「気分」についてはまったく理解をしていなかったのではないだろうか。
この先、昇給も見込めず、一応、借金がない生活をしているので、インフレよりデフレのほうがありがたいという年金生活をしているという人たちとまったく変わらない家計生活をしている身のうえからすると、無理してインフレにしてもらわなくても全然かまわないと思っているので黒田総裁の政策にはまったく共感を覚えないのである。
為替相場についてはどうだろうか。この本では、固定相場の時代の中で、為替相場をどう設定するかということと、兌換制度の中で貨幣の質を落とすと(改鋳する)と自国での経済はどうなるのかということをもとに説明しているが、やっぱり経済学部を卒業しているにも関わらずほとんどわからないのである。まあ、僕の記憶の中で、大学の授業で改鋳についての講義を聞いたという経験はなかったのでも無理からぬことではあるのであるとここでもとりあえずは弁解をしておく。
為替相場については「購買力平価説」をもとに説明がされている。これは、二国間の為替レートというのは一物一価の原則で、それぞれの国の通貨でひとつの物がどの値段で買えるかというところに自動的に落ち着くというものだ。
しかし、現実はかなり不安定である。何が原因となっているのかというと、ここでも将来においてそれぞれの国において流通するお金の量に対する期待と予測が不安定だからであるそうだ。金融引き締め策で金利が上がりお金の流通量が減ると予測するとその国のお金の価値は上がるが、「今」を基準に考えるとその価値は購買力平価説には沿っていない。
しかし、金利を上げてしまうとその国ではデフレという不況を呼び込むことになる。
今日、円は1ドル146円を超える円安になってしまった。アメリカは原材料費や賃金の高騰で引き起こされたインフレを抑制するために金利を上げているからなのであるが、それでも今のところデフレ方向には振れていないらしい。かたや日本は円の価値が下がってインフレになるはずだが実はアメリカほどまだまだ物価が上がっていない。それでも、所得が伸びない中では1万近い品目がわずかずつでも値上がりされると生活は苦しくなる。
なぜこんな矛盾が起こるのかというと、よいインフレというのは、経済規模の拡大と同等の物価の上昇と所得の上昇であれば人々の生活は豊かになったといえるのであるが、経済規模が拡大しないのに物価だけが上がっているからなのである。経済規模が拡大していないから所得が上がらず物価だけが上がっているのだからそれは生活が苦しくなるのはあたり前だ。
これは幕末の頃にオールコックという英国外交官の提案によっておこなわれた万延小判の発行による大幅なインフレによる生活水準の低下とよく似ているらしい。
万延小判はそれまでの天保小判の3分の1しか金の含有量がなく、要はお金の流通量が一気に3倍になってしまったということなのだが、江戸時代は大規模な工業化社会ではなく経済規模が拡大する余地がなくインフレによる需要拡大→失業の減少→景気の改善ではなく、需要だけが膨らんでしまったというものである。
今の日本も、金融緩和でお金の量だけが増えても経済規模はまったく拡大していなくて物価だけが上がっているので僕の生活はますます苦しくなっているというのはまったく幕末と同じように見えるのである。幸か不幸か、流通量が増えたお金のすべてが市場に出回るのではなく、将来に不安のある企業や個人は内部留保や貯蓄という形で仕舞い込んでしまっているので黒田総裁が期待しているほど物価が上がらないのでこれだけで済んでいということだろうか。
どちらにしても、黒田総裁は庶民の「気分」というものをまったく理解できていないのではないかということと、岸田総理が言う、「成長と分配の好循環による新しい資本主義」などという幻想にしがみついているということが現在の僕の生活の苦しさの元凶であると思うのだ。
すでにこの時代、経済成長などというのは少なくともこの日本では期待できないであろう。そうであれば江戸時代のようにゼロ成長でインフレでもデフレでもない経済を目指すのが一番妥当ではないのだろうか。
これからの日本は「鎖国」に向かうのが一番なのだと思うのである。インバウンドなどはくそくらえだと主張する政治家は出てこないものだろうか・・。
ニュースではさらに円安は進むだろうと言っていたが、この先、僕の生活はどうなってゆくのだろう。円安だけを見てももっと物の値段が上がっていきそうだ。
今日はG20の財務相・中央銀行総裁会議が始まったがそれほど為替にはそれほどの影響はなかったようだ。日本の財務大臣のコメントも人ごとのようだ。
来月にはアメリカ議会の中間選挙があるが、共和党がちょっと盛り返すという予想らしい。そうなってくると、トランプの息のかかった人たちはもっと強いアメリカを主張し、為替レートももっと円安に振れるだろう。
どんどん日本の力が弱くなっていく。「円安を追い風に経済成長を目指すのだ。」とはどこの阿呆が言っているのだろうか。
とりあえず僕も、円安とドルの金利が高いということの恩恵を受けるべく、外貨預金のようなものをやってみようかしらと思っている今日この頃なのである。