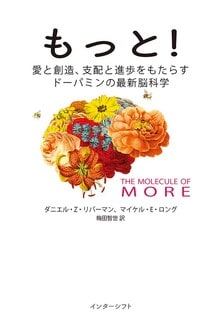ダニエル・Z・リーバーマン マイケル・E・ロング/著 梅田智世/訳 「もっと! : 愛と創造、支配と進歩をもたらすドーパミンの最新脳科学」読了
ドーパミンについて書かれた本というのは何冊か読んだが、この本は正真正銘、ドーパミンを中心にして書かれた本だ。
ドーパミンというと、脳の中で分泌される快楽物質だと要約されるが、その働きはもっと多岐に渡ると著者たちは分析する。
それは人の情動のほとんどを司っているというほどなのである。
著者は情動を司っている様々な物質を影響を及ぼす距離感で分類している。その区分は、手の届く範囲(身体近傍空間)とそれよりも広い範囲(身体外空間)に対してである。
手の届く範囲に対して影響を及ぼす物質はその現状に満足し、愛しむ効果を生みだす。それそれよりも広い範囲に影響を及ぼす物質は、すぐに掴める領域の外にある世界を追いかけ、支配し、所有したいという欲求を生み出している。すなわち、今よりもより良く、より速く、より安いもの、より美しいものを求める情動である。それがドーパミンである。
ドーパミンが求めるのは報酬予測誤差というものである。それは、予測もしていないサプライズのことであり、そのようなサプライズがあったとき、ドーパミンは活性化され、人は脳の中で快楽を感じる。その快楽を求めて新たなものを探し求めるのである。
言い換えれば、新しいものを求め続ける冒険心ともいえる行動をもたらすのがドーパミンであり、現状を維持し愛する行動をもたらすのがこの本ではH&N(ヒア&ナウ)と呼ぶ物質である。それはセロトニン、オキシトシン、エンドルフィン、エンドカンナビノイドなどである。
ドーパミンを生産する細胞は脳細胞の中の0.0005%、20万個にひとつしかない。そのわずかな細胞が手の届かない広い範囲を求める原動は、それは人類が生き残るための原動力となり、地上の支配者となる原動力となった。
この本では、そういったドーパミンの特性を『もっと』という言葉で表現している。
人間の人生の中での情動の遷移とはこんな感じだ。
新たなものを手に入れた人間は、そのものに対して愛情を注ぐようになり、新たなものに対しては興味を失う。脳の中ではドーパミンの働きによって新たなものを探し求め、H&N物質がその得られたものを愛しませる。
典型的な例は、人の人生のなかに現れている。恋をして家庭を持ち家族に愛情を注ぐという過程だ。ドーパミンが司る初期の恋愛すなわち、「熱愛」は、12ヶ月から18ヶ月しか続かないという。その後もカップルが絆を保とうとすれば、「友愛」と呼ばれる違う愛を育まねばならない。それを司るのがH&N物質なのである。
ドーパミンはその働きで個人の性格や民族性までも決定づけているという。著者たち自身もそれは極論かもしれないがと断ってはいるが、なるほどと思える事実がある。
例えば、アーティストと呼ばれる人たちだ。この人たちはドーパミンの影響が強い種類の人たちだとされている。常に新しい表現を追い求めているのがその特性で、それは恋の対象に対してもである。落ち着いたと思ってもすぐに次の恋の対象を追い求める。だから離婚率も高くなってゆくのであるというのだ。
また、移民も同じである。新天地を求める人たちもドーパミンの支配を大きく受ける。そういった人たちには起業家が多く、その代表的な国がアメリカである。シリコンバレーのスタートアップ企業の創業者の52%は移民か移民の子孫である。アメリカの総人口に占める移民の割合が13%だというので、その数値は相当なものである。
政治家の中では、リベラルな考えを持つ人たちはドーパミンの支配が大きいとされている。現状に不満を持ち、体制に対して異議を申し立てる。対して保守派の人たちはH&N物質に支配されている傾向が強いのである。
そういう意味では粘り強さというものもドーパミンが関係している。
ドーパミンには「もっと」という欲望のおもむくままの行動をさせる部分と、もう少し冷静に考え、自分にとって価値のある「もっと」は何かということを考えて行動させる部分もある。これをこの本では「制御ドーパミン」と呼んでいる。
人間の場合、成功を可能にするためには、まず成功できると信じる必要がある。それは粘り強さに影響を与えるのだが、それを「自己効力感」と呼ぶ。そして、自己効力感は他者にも影響を及ぼすことがある。成功を確信していると、それを無意識に感じ取とった相手から譲歩を引き出せてしまうという効果だ。制御ドーパミンを原動力とする圧倒的な自己効力感は相手を無意識のうちに服従させることもあるというのである。負ける喧嘩は避けたほうがよいというのである。
これ、今回のワールドベースボールクラシックの日本の優勝に至る道そのものではないだろうか。決勝前の大谷選手のスピーチがそれを象徴しているように見えた。
また、チームのように、目標達成のために形成される人間関係は「代理的関係」と呼ばれ、これもドーパミンに統制されている。こうした関係では、他者が自分の延長として機能し、自分の目標達を助ける代理人の役割を果たす。
対してH&N物質は「親和的関係」という平和的な関係をもたらす。
概ね人間関係というのは両者の要素があり、代理的関係が強すぎると搾取的になり冷静でよそよそしい雰囲気になり、親和的関係が強すぎると馴れ合い的だが愛情深い雰囲気になる。その塩梅がよい集団が強い集団であるというのだが、栗山監督やダルビッシュはきっとH&N、大谷選手など(侍ジャパンで僕が知っている名前の人は残念ながらこの3名しかいないのだ・・)はドーパミンタイプだったのだろう。
このように、何事もバランスが大切だ。バランスが崩れることは不幸なことである。バランスを崩したことで世の中を革新的に変えてきた人たちも大勢いるがそういった人たちが幸せな人生を送ったかというとそうとも言えない。優れた芸術家や科学者、ビジネスリーダーの多くは精神疾患を抱えていたと考えられるし、精神崩壊、自己破滅をも引き起こしかねなかったのである。
「もっと」、「もっと」という感情は歩みを止めさせない。気を緩めることはないし、立ち止まって手にした幸運を楽しむこともない。ただひたすら未来の構築で頭をいっぱいにしている。けれども、その未来は決して訪れない。なぜなら、未来が現在になったとき、それを楽しむためのH&N物質を活性化する必要があるが、ドーパミン活性の高い人はそれを忌み嫌い避ける傾向にある。未来が現在になった時点ですぐにまた未来を見始めるという繰り返しがおこるのだ。
それでは確かに心が休まらない・・。
自分を省みると、う~ん、その通りだと思えることがたくさんある。僕は明らかにドーパミンが不足している。
新しいことを追い求めることはないし、恋もしない。二つの関連からもドーパミンが少ないと考えられる。新しいものを買いたいとも思わないし、むしろ古いものを修理して使いたいと思う方だ。そして修理がうまくいくと前にも増して愛着が湧いてくるのである。
こまめにいろいろなところに行くが、毎年同じことしかしていない。むしろ、この季節のこの時期にここでこれをやると決まっているほうが安心するのである。
釣りの仕掛けでも新しい発想が生まれることがあるがそれを作ってみても試すことがない。
もちろん代理的関係を構築して目標を達成させようという気もない。
要は、“面倒くさい”のである。ドーパミンが少ないというのは面倒くさいと同義であるあるというのがこの本を読んでの結論であった。
バランスが大切である。ドーパミンが少ない時は、「ドーパミン!COME ON!!」と叫んでみようと思うのだ。