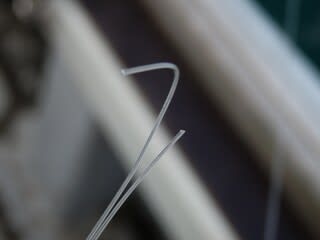河合雅司 「未来の年表 人口減少日本でこれから起きること」読了
「穏やかな死を」なんて前回のブログに書いてみたけれども、本当に穏やかな死を迎えることができるのだろうかとこんな本を読んでみた。この本は椎名誠の本で紹介されていたのだが、けっこう話題になった本らしい。
人口減少という問題をキーワードにして、これから先、約50年の間にどんな問題が起きるか、そしてそれに対処するためには今から何をすべきか、そういうことが書かれている。
まず、日本の人口だが、2015年に1億2700万人超だったものが、出生者が2016年に初めて100万人を切り、このままいくと現在の予想では2055年には9000万人以下になるそうだ。そして問題なのが、高齢者の比率が増え、労働力人口の比率が著しく減ってしまうことだ。
まあ、今でもそうだが、どこを見ても確かにご高齢の人たちがよく目立つ。僕がいた業界もまさにそのとおりで、そのご高齢者に企業の存続がほぼゆだねられているのではないかという感じであった。記憶は不確かだが、売り上げの4割くらいは65歳以上の年齢の人たちの買い物であったと思う。あと10年経ったらその人たちも半分くらいは買い物に来てもらえないほど体が弱り、そうなったらわが社は一体どうなるのかと考えたりしていたことがあったがこれはわが社だけの問題ではなく、日本の社会にも同じようなことが起こりつつあるというのがこの本の内容である。
会社の場合は、おそらく取り返しがつかないような事態が起こる頃にはすでに退職しているはずなのでどうにでもなれというくらいにか思っていなかったけれども、僕の人生がどうなるのかとなってくるとそこは知っておかねばならない。
僕は今57歳だが、父親が死んだ年齢まで生きるとしたらあと14年、男性の平均寿命くらいの80歳まで生きるとしたらあと23年だ。これくらいの残り時間ならなんとか逃げきれるかと思っていたけれども、どうもそれまでにもじわじわといろいろな問題が周りに起こってきそうである。
人口減少の大きな要因になるのは団塊の世代の家族である。団塊ジュニアを含めるとこんな年表となる。
2021年 団塊ジュニア世代が50代になる
2023年 企業の人件費がピークとなる
2024年 団塊世代がすべて75歳以上になる
2040年 団塊ジュニア世代がすべて65歳以上になる
2042年 高齢者数がピークになる
2050年 世界人口は97億3000万人
団塊ジュニア世代がすべて75歳以上になる
世間では2025年問題として、団塊の世代がすべて75歳以上となるときが危ないと言われている。
医療費の高騰、年間死亡者数の増大、それにともなう空き家問題、地方の空洞化、インフラの維持・・・。問題はさまざまだが、著者は2042年がもっと危ないという。この年はどんな年かというと、高齢者数(65歳以上)がピークを迎える年である。団塊ジュニア世代がすべて高齢者となり、その親世代も90歳台でまだ生きているという状態だ。
若者世代が高齢者を支えるという年金構造で見ると、現在でも高齢者ひとりを若者世代2.3人で支えているという状態で、2042年ごろになるとひとりでひとりを支える肩車構造になるという。
この年、僕は78歳。生きているかどうか微妙なときだ。そのときに本当に誰かに支えてもらえるような社会なのか、確かに不安になる。
おカネもそうだが、受け入れてくれる介護施設は満杯で、家でひとり咳をしながら寝たきりみたいなことになっているかもしれない。まあ、それも自業自得で、その後は色々な人に迷惑をかけるが、誰にも面倒をかけずに孤独死するというのもいいのじゃないかとひそかに思っていたりする。
現在でも未婚の男性の率というのは5人に一人くらいはいるらしい。そんな人たちは孤独死の候補になる可能性があるわけで、この頃になると、けっこう孤独死というのも普通に見られるようになるのかもしれない。
そして、著者はその対策を、「日本を救う10の処方箋」として示している。現政府(この本が書かれた当時は安倍政権であったが。)は「外国人労働者の受け入れ」「AIの活用」「女性の労働力の活用」「高齢者の労働力の活用」という、労働力を増やして経済を回そうという政策になるが、これには限界があるとして、「戦略的に縮む」「豊かさを維持する」「脱・東京一極集中」「少子化対策」をキーワードにした政策を提言しているのだ。
現政権への批判として、「外国人労働者の受け入れ」に対しては、外国人が増えすぎることへの危険性を懸念する。現在の労働力を確保するために見合う労働力を外国人で賄おうとすると、外国人の人口が増えすぎて、日本の国が外国人に乗っ取られてしまうというのである。そのまえに、主にアジア地域から集まってくる外国人であるが、この頃には向こうも経済成長を遂げ、わざわざ日本に働きにくる外国人なんていなくなっているというのだ。「AIの活用」はどうだろう、これは著者のいうことは確かで、AIってそれほど賢くもなく、人間の代わりになるためにはもっと長い時間がかかりそうだ。「女性の労働力の活用」については、日本は家族が介護をする場合が多く、これだけ老人が増えてくると女性の力は家族介護に回らざるをえないのではないかという。「高齢者の労働力の活用」では、これは個人差があるのでどうかわからないが、75歳になってまだ働けと言われてもな~と思ってしまう。
そういうことだからこれらの政策は現状の問題解決にはならないという。
それに対する10の処方箋とはこんなものだ。
①高齢者を削減するために新たな年齢区分を作る。
高齢者の線引きを75歳にし、働ける人は働いてもらう。
②24時間社会からの脱却をし、労働力不測の解消をする。
便利な生活を抑制してその分の労働力を他の産業に回す。
③非住居エリアを明確化し、コンパクトな街づくりでインフラの維持費を削減する。
④都道府県を飛び地合併。
協力できる自治体は地続きでなくても行政を一本化する。たとえば新幹線でつながった都市などを合併する。
⑤国際分業を徹底し、国として得意な分野に資本を集中させる。
⑥匠の技を活用し、地方に埋もれている技術や産業を掘り起こし、高付加価値製品の開発をおこなう。
⑦国費学生制度で国家に必要な人材育成をおこなう。
⑧日本版CCRC(高齢者が健康なうちに入居し、終身で過ごすことが可能な生活共同体Continuing Care Retirement Community)を作り、中高年を地方に移住させる。
⑨セカンド市民制度を創設し、第二の定住先を作り、二重生活を進めることで比較的楽に地方移住を推進し、納税も第二の定住先に分配することで税収も分配する。
⑩第3子以降に1000万円の給付をして出産数を増やす。
なかなかよい提案にも思えるが、これを民主主義、資本主義の国で実現させようとすると憲法から改正してゆかねばならないのではないだろうか。
住居エリアを制限するというのは憲法に保障された居住移転の自由に真っ向から抵触しそうだ。そして、⑩の財源は社会保障循環制度という考えで、死んだときにそれまで公費で賄われてきた社会保障サービス分のお金を返還させるというものだが、何も残さずに死んだ人からは取れない。なにがしかの財産を残した人たちだけから取るというのでは財産権の侵害になるのではないだろうか。そもそもだが、この本には、出生者の減少は出生率が下がっているのが原因ではなく、出産可能な年代の女性の人口が減っているからだと書かれている。1000万円もらえたら3人でも4人でも産もうと思う人は出てくるだろうが、それにも限界があるというものだ。②の24時間社会からの脱却といっても、サービスは自由競争のなかで行われるものだ、それを制限するとなるとそれはもう資本主義の社会ではなくなる。
①の新たな年齢区分を作るという案に至っては、よくわからない。区分を変えて人は若返るのだろうか。
そこで考えてしまうのが、腐った民主主義よりも、公正な独裁者の元の専制政治のほうがはるかに健全ではないのかということだ。人材を含めて資源を最も効率的に運用しようというのが著者の考えであることはよくわかる。それは、『拡大路線でやってきた従来の成功体験と決別し、戦略的に縮むことである。』という言葉にもよく現れているが、経済は成長しなければならないという資本主義の根本を否定することであり、極論では社会主義に移行することを意味するのではないかと思う。少なくともこの、「日本を救う10の処方箋」を成功させるためにはそうならなければ無理だろう。だから選挙があっても誰もそういう主張はしない。負けるとわかっているからだ。新しい総理も、「新しい資本主義」としか言っていない。基本は資本主義の作法にのっとり、そこには成長ありきというのが前提なのである。「分配なくして次の成長はない。」と言っているが、「成長はしません。今保有している国の全財産を国民に公平に分配することを目指します。そのために社会の構造を変えます。気に入らない人はこの国から出ていってください。ただし財産は持ち出させません。」なんて言い始めたら、誰もその人に投票はしないだろう。
だから、おそらく「日本を救う10の処方箋」はただ、この本に書かれただけのこと終わるのは間違いがなく、未来の年表に書かれたようなことがすべて現実となっていくのかもしれないし、水道橋の崩落もそのひとつだったのかもしれない。
民主主義の社会では不都合な真実は隠しきれるところまでは隠し通されるというのが常だから・・。
ただ、この年表の2021年には何が起こるか書かれていたかというと、『介護離職者が急増する。』であった。今のところそんなニュースは聞かないので案外当たっていそうで当たっていないのがこの年表かもしれないのでこれほどまでにトホホと思わなくてもいいのかもしれない。
マクロ的には難題がいっぱいだが、ミクロ的、それは僕の生活についてだが、今住んでいる場所は意外と便利で人口減少もそれほど深刻でもなく、だからインフラも弱体化するようには思えない。銀行が無くなるとか、交通手段が消えるとかはおそらく心配することはないだろう。体がどこまで動くか、おカネはどこまで続くかは心配だがその時はその時だろう。
世を憂うというような立場でもなく、なんとか逃げ切る。それだけが目標だ。
結局は心配を煽って読者数を稼ごうというのがこの本の編集方針だったということだろうか・・。
「穏やかな死を」なんて前回のブログに書いてみたけれども、本当に穏やかな死を迎えることができるのだろうかとこんな本を読んでみた。この本は椎名誠の本で紹介されていたのだが、けっこう話題になった本らしい。
人口減少という問題をキーワードにして、これから先、約50年の間にどんな問題が起きるか、そしてそれに対処するためには今から何をすべきか、そういうことが書かれている。
まず、日本の人口だが、2015年に1億2700万人超だったものが、出生者が2016年に初めて100万人を切り、このままいくと現在の予想では2055年には9000万人以下になるそうだ。そして問題なのが、高齢者の比率が増え、労働力人口の比率が著しく減ってしまうことだ。
まあ、今でもそうだが、どこを見ても確かにご高齢の人たちがよく目立つ。僕がいた業界もまさにそのとおりで、そのご高齢者に企業の存続がほぼゆだねられているのではないかという感じであった。記憶は不確かだが、売り上げの4割くらいは65歳以上の年齢の人たちの買い物であったと思う。あと10年経ったらその人たちも半分くらいは買い物に来てもらえないほど体が弱り、そうなったらわが社は一体どうなるのかと考えたりしていたことがあったがこれはわが社だけの問題ではなく、日本の社会にも同じようなことが起こりつつあるというのがこの本の内容である。
会社の場合は、おそらく取り返しがつかないような事態が起こる頃にはすでに退職しているはずなのでどうにでもなれというくらいにか思っていなかったけれども、僕の人生がどうなるのかとなってくるとそこは知っておかねばならない。
僕は今57歳だが、父親が死んだ年齢まで生きるとしたらあと14年、男性の平均寿命くらいの80歳まで生きるとしたらあと23年だ。これくらいの残り時間ならなんとか逃げきれるかと思っていたけれども、どうもそれまでにもじわじわといろいろな問題が周りに起こってきそうである。
人口減少の大きな要因になるのは団塊の世代の家族である。団塊ジュニアを含めるとこんな年表となる。
2021年 団塊ジュニア世代が50代になる
2023年 企業の人件費がピークとなる
2024年 団塊世代がすべて75歳以上になる
2040年 団塊ジュニア世代がすべて65歳以上になる
2042年 高齢者数がピークになる
2050年 世界人口は97億3000万人
団塊ジュニア世代がすべて75歳以上になる
世間では2025年問題として、団塊の世代がすべて75歳以上となるときが危ないと言われている。
医療費の高騰、年間死亡者数の増大、それにともなう空き家問題、地方の空洞化、インフラの維持・・・。問題はさまざまだが、著者は2042年がもっと危ないという。この年はどんな年かというと、高齢者数(65歳以上)がピークを迎える年である。団塊ジュニア世代がすべて高齢者となり、その親世代も90歳台でまだ生きているという状態だ。
若者世代が高齢者を支えるという年金構造で見ると、現在でも高齢者ひとりを若者世代2.3人で支えているという状態で、2042年ごろになるとひとりでひとりを支える肩車構造になるという。
この年、僕は78歳。生きているかどうか微妙なときだ。そのときに本当に誰かに支えてもらえるような社会なのか、確かに不安になる。
おカネもそうだが、受け入れてくれる介護施設は満杯で、家でひとり咳をしながら寝たきりみたいなことになっているかもしれない。まあ、それも自業自得で、その後は色々な人に迷惑をかけるが、誰にも面倒をかけずに孤独死するというのもいいのじゃないかとひそかに思っていたりする。
現在でも未婚の男性の率というのは5人に一人くらいはいるらしい。そんな人たちは孤独死の候補になる可能性があるわけで、この頃になると、けっこう孤独死というのも普通に見られるようになるのかもしれない。
そして、著者はその対策を、「日本を救う10の処方箋」として示している。現政府(この本が書かれた当時は安倍政権であったが。)は「外国人労働者の受け入れ」「AIの活用」「女性の労働力の活用」「高齢者の労働力の活用」という、労働力を増やして経済を回そうという政策になるが、これには限界があるとして、「戦略的に縮む」「豊かさを維持する」「脱・東京一極集中」「少子化対策」をキーワードにした政策を提言しているのだ。
現政権への批判として、「外国人労働者の受け入れ」に対しては、外国人が増えすぎることへの危険性を懸念する。現在の労働力を確保するために見合う労働力を外国人で賄おうとすると、外国人の人口が増えすぎて、日本の国が外国人に乗っ取られてしまうというのである。そのまえに、主にアジア地域から集まってくる外国人であるが、この頃には向こうも経済成長を遂げ、わざわざ日本に働きにくる外国人なんていなくなっているというのだ。「AIの活用」はどうだろう、これは著者のいうことは確かで、AIってそれほど賢くもなく、人間の代わりになるためにはもっと長い時間がかかりそうだ。「女性の労働力の活用」については、日本は家族が介護をする場合が多く、これだけ老人が増えてくると女性の力は家族介護に回らざるをえないのではないかという。「高齢者の労働力の活用」では、これは個人差があるのでどうかわからないが、75歳になってまだ働けと言われてもな~と思ってしまう。
そういうことだからこれらの政策は現状の問題解決にはならないという。
それに対する10の処方箋とはこんなものだ。
①高齢者を削減するために新たな年齢区分を作る。
高齢者の線引きを75歳にし、働ける人は働いてもらう。
②24時間社会からの脱却をし、労働力不測の解消をする。
便利な生活を抑制してその分の労働力を他の産業に回す。
③非住居エリアを明確化し、コンパクトな街づくりでインフラの維持費を削減する。
④都道府県を飛び地合併。
協力できる自治体は地続きでなくても行政を一本化する。たとえば新幹線でつながった都市などを合併する。
⑤国際分業を徹底し、国として得意な分野に資本を集中させる。
⑥匠の技を活用し、地方に埋もれている技術や産業を掘り起こし、高付加価値製品の開発をおこなう。
⑦国費学生制度で国家に必要な人材育成をおこなう。
⑧日本版CCRC(高齢者が健康なうちに入居し、終身で過ごすことが可能な生活共同体Continuing Care Retirement Community)を作り、中高年を地方に移住させる。
⑨セカンド市民制度を創設し、第二の定住先を作り、二重生活を進めることで比較的楽に地方移住を推進し、納税も第二の定住先に分配することで税収も分配する。
⑩第3子以降に1000万円の給付をして出産数を増やす。
なかなかよい提案にも思えるが、これを民主主義、資本主義の国で実現させようとすると憲法から改正してゆかねばならないのではないだろうか。
住居エリアを制限するというのは憲法に保障された居住移転の自由に真っ向から抵触しそうだ。そして、⑩の財源は社会保障循環制度という考えで、死んだときにそれまで公費で賄われてきた社会保障サービス分のお金を返還させるというものだが、何も残さずに死んだ人からは取れない。なにがしかの財産を残した人たちだけから取るというのでは財産権の侵害になるのではないだろうか。そもそもだが、この本には、出生者の減少は出生率が下がっているのが原因ではなく、出産可能な年代の女性の人口が減っているからだと書かれている。1000万円もらえたら3人でも4人でも産もうと思う人は出てくるだろうが、それにも限界があるというものだ。②の24時間社会からの脱却といっても、サービスは自由競争のなかで行われるものだ、それを制限するとなるとそれはもう資本主義の社会ではなくなる。
①の新たな年齢区分を作るという案に至っては、よくわからない。区分を変えて人は若返るのだろうか。
そこで考えてしまうのが、腐った民主主義よりも、公正な独裁者の元の専制政治のほうがはるかに健全ではないのかということだ。人材を含めて資源を最も効率的に運用しようというのが著者の考えであることはよくわかる。それは、『拡大路線でやってきた従来の成功体験と決別し、戦略的に縮むことである。』という言葉にもよく現れているが、経済は成長しなければならないという資本主義の根本を否定することであり、極論では社会主義に移行することを意味するのではないかと思う。少なくともこの、「日本を救う10の処方箋」を成功させるためにはそうならなければ無理だろう。だから選挙があっても誰もそういう主張はしない。負けるとわかっているからだ。新しい総理も、「新しい資本主義」としか言っていない。基本は資本主義の作法にのっとり、そこには成長ありきというのが前提なのである。「分配なくして次の成長はない。」と言っているが、「成長はしません。今保有している国の全財産を国民に公平に分配することを目指します。そのために社会の構造を変えます。気に入らない人はこの国から出ていってください。ただし財産は持ち出させません。」なんて言い始めたら、誰もその人に投票はしないだろう。
だから、おそらく「日本を救う10の処方箋」はただ、この本に書かれただけのこと終わるのは間違いがなく、未来の年表に書かれたようなことがすべて現実となっていくのかもしれないし、水道橋の崩落もそのひとつだったのかもしれない。
民主主義の社会では不都合な真実は隠しきれるところまでは隠し通されるというのが常だから・・。
ただ、この年表の2021年には何が起こるか書かれていたかというと、『介護離職者が急増する。』であった。今のところそんなニュースは聞かないので案外当たっていそうで当たっていないのがこの年表かもしれないのでこれほどまでにトホホと思わなくてもいいのかもしれない。
マクロ的には難題がいっぱいだが、ミクロ的、それは僕の生活についてだが、今住んでいる場所は意外と便利で人口減少もそれほど深刻でもなく、だからインフラも弱体化するようには思えない。銀行が無くなるとか、交通手段が消えるとかはおそらく心配することはないだろう。体がどこまで動くか、おカネはどこまで続くかは心配だがその時はその時だろう。
世を憂うというような立場でもなく、なんとか逃げ切る。それだけが目標だ。
結局は心配を煽って読者数を稼ごうというのがこの本の編集方針だったということだろうか・・。