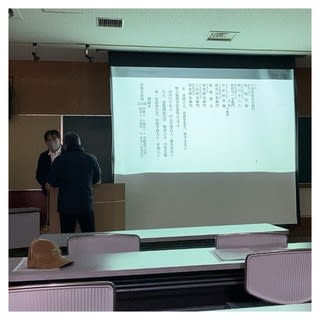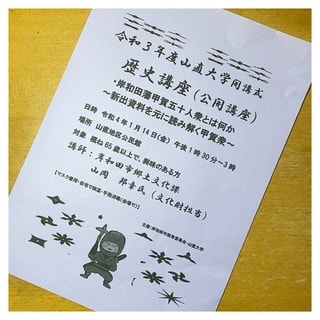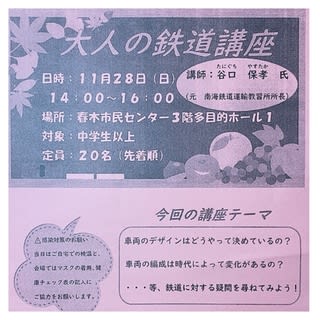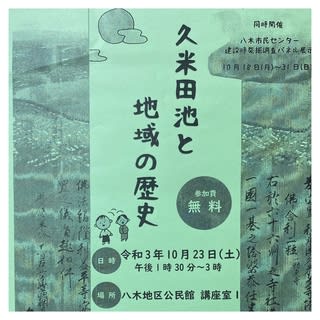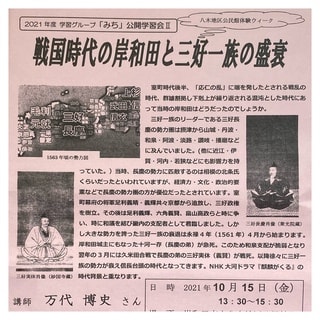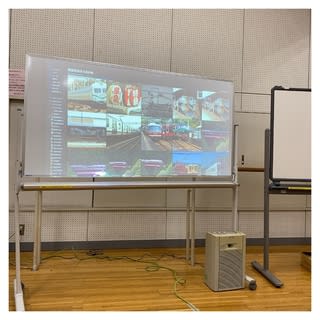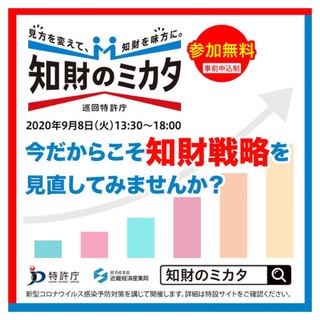「関西ローカル鉄道のここがすごい!」
ナカノシマ大学・2020年2月講座・
今回の、ナカノシマ大学は、
「関西ローカル鉄道物語」・田中輝美さんの出版記念の講演会。
「大阪」
阪堺電軌軌道・・・愛される「ちん電」、その波瀾万丈。
水間鉄道・・・由緒正しき参詣鉄道の挑戦。
「和歌山」
紀州鉄道・・・日本最短のローカル私鉄・
和歌山鉄道・・・たま電車に乗って、ローカル鉄道について考えてみた。
「滋賀」
近江鉄道・・・「わざと古い」のも生きる道。
信楽高原鉄道・・・4度もの危機を乗り越えて。
「兵庫」
北条鉄道・・・力を合わせてつくる、「みんなの鉄道」。
神戸電鉄・・・街から山へ。登って下りて。
「京都」
叡山電鉄・・・日常と非日常をデザインでつなぐ。
京都丹後鉄道・・・街と一緒に人をつくる。
京福電気鉄道・・・古都を駆け抜ける路面電車。
近場ですが、車で行くのではなく、逆に電車に乗りに、
ゆっくりと歩いて探索、歳をとればとるほど、この電車の探索は・・
からだにも、こころにも、良いようで・・・
是非、春になれば「散歩人生」、実践したいですな。
「関西ローカル鉄道のここがすごい!」
これは、水間鉄道の列車の前につけられている、ヘッドマーク。
10日間、一万円でオリジナルのを付けて走って貰える。
家族の誕生日や結婚記念日、お祝いごとや応援メッセージ、
プロポーズまで自由に使われている。
今回、版元に出版のお祝いにと約束ごとで実現、3月には実際走るらしい。
著者の田中輝美さん
その出来あがったばかりのヘッドマークの前で、田中さん、パチリ。
お話は、鉄道大好き、ローカル心から応援。
衰退してゆくローカル鉄道と思われながら、この10年間の間に
全国で6割りの会社がお客様が企業努力で増えている。
でも、鉄道と地域は運命共同体、一度止めてしまうと、二度と復活はありえない。
だからこそ、ローカル鉄道を、地域資源ととらえ、、地域の暮らす人、
全国の鉄道ファンで、その鉄道資源を活かさなければと、力説される。
「関西ローカル鉄道物語」・田中輝美
2月27日発売、その前に手にすることができました。
前田さんが大いに刺激を受けた、
黒田一樹さんの「すごいぞ!私鉄王国・関西」
水間鉄道貸切車両でゆく車庫見学の旅
来たる、2月24日(月・祝日)の午後、貝塚駅から水間観音駅の車庫へ。
日本で唯一、「オリジナル」東急7000系が見れるとか、
正直言って、鉄道オタクでは無いので、その価値はあまり解かっては
いないんですが、まあ鉄道好きの息子と一緒に出かけてみようと・・・・。