口にするとなんだか占いのようなゲームのような感覚がありますが、まあ漢字にすると難しい文字
ですよね。
お神籤・お御籤・お仏籤・御御籤・御仏籤・神籤・ 御籤・仏籤
「クジ」 というだけに 「くじびき」 に繋がるのでしょうね。
今年は元旦の住吉大社で【凶】を引き当て、3日の橿原神宮で【小吉】と復活しました。
このくじの種類は主に「大吉」「中吉」「小吉」「吉」「末吉」「凶」「大凶」の7種類が全国的なそうで
どこだったか「平」というのがあったように記憶しています。
玉生八幡大神社というところでは
大吉、中吉、小吉、吉、半吉、末吉、末小吉、凶、小凶、半凶、末凶、大凶の十二通り
大抵の神社などでは八角形の形をした筒状のものに木星の棒が入っていて、これも何処か
忘れたけど金属製の円柱状の上下と真中に縄模様の鉢巻見たいな筒にステンレスの棒で
冬場にはとても冷たかったことだけ記憶している、お寺だったかも?
比叡山延暦寺?
いずれにしてもよく考えたら当たり障りのないことが書かれていることが多い。
それでもその時の運勢みたいな気がして、ついつい運試しに買っちゃいます。
内容については願望が叶うかどうか、吉方について、旅行について、移転(引っ越しなど)、
争い事、出産、縁談、待ち人、病気(やまひ)、学業、金銭、取引などなどなど。
良くても悪くても、精進を重ねるのを勧めたり無理をしないで運気を待てとかありますよね。
最近ではそういう全般的なものから『恋御籤』『子供みくじ』などと言った対象を絞ったものや、
その社寺仏閣の名物とかの『花みくじ』『姫みくじ』『宝珠みくじ』『だるまみくじ』など???ってな
変わり種もあります。
おみくじを引いて読んだ後はどうするのか?
良くても悪くてもその神社に結んで帰る人や、良い場合は持って帰り悪い物は結んで帰る人
神社によっては処分に困るのか「財布など身に着ける物に収めてお持ち帰りください」なんて
書いてあるところもありますね。
住吉大社では「今年のものは持ち帰り、次に来られた時に良いものは結んで悪しきものは
縛ってお帰りください」と看板に書いてありました。
傍に居た若いカップルの男の方が「縛るって結ぶとどう違うねん?」とつぶやいていたので
これ見よがしに凶の御神籤を縦長く折りたたんで縄にグルグル三重巻にして端っこをギュッ
と括り付けてやったら、尊敬のまなざしでコチラを見ていました。
そんな作法、このオッチャンだって知らんのですが、あまりに自信たっぷりな動作だったので
感心したのだと思います。
彼女らしき女の子に「外れんようにぐるぐる巻きにくくるのが縛るやねんてー」と説明してました。
どっちにしても何にしてもロクな御籤を引いてない筈なんだよね。
そういう軟弱な人間だから大吉が巡って来ないんじゃ! と笑ってやりたかったけど
それをすると自分もミジメになるので後ろ向きに舌を出しながら去りました。
ほとんどの神社は大凶・大吉は一割未満で真ん中の小市民的な、小吉、末吉の数が多く
押しなべられているそうです。
ほら、あの棒を引くときカラカラとかき混ぜるでしょ?
クジの棚というか引き出しを見ると何十もあるのに、あの筒の中にそのすべてが
詰まっているとは思えない軽さだし音からしても10本入っている?ぐらいの感じ
でしょ?
理系人間はついついそんなどうでもいいことを推理したくなったりするんですよね。
そんなに疑い深いんだったら御籤自身を疑って引かなきゃいいのに試してみたくなる
ロマンみたいなものも求める、変なオッサンですよね。
ついでに言うと浅草の雷門や仲見世で知られている浅草寺さん、100あったら30は凶
なのだそうです。
ホームページを見てもワザワザと言うかご丁寧に説明がありました。
「浅草寺のおみくじは凶が多い」とよく言われますが、古来の“おみくじ”そのままです。
また凶が出た人もおそれることなく、辛抱強さをもって誠実に過ごすことで、吉に転じます。
凶の出た人は観音さまのご加護を願い、境内の指定場所にこの観音百籤を結んで、ご縁
つなぎをしてください」
それだけにここで『吉』系をひくとより一層運がいいと人気が落ちないのだそうです。
江戸の人の考えそうな話ですね。
知り合いに社寺仏閣を訪ねるのが趣味な人が居まして、まあどこへ行っても必ず
おみくじを引かないと気が済まないのだそうです。
百円玉を入れてガチャッとやる自販機型のしかなくても必ず引くから笑っちゃいます。
それでいてサッと流し読みしたら100円でも300円のでも吉でも凶でも結んで
持ち帰ったりはしないんですねぇ。
はい、どうでもいいことを長々と。 おつきあい ありがとうございました。
















 と聞き違えて
と聞き違えて





 やり出しました。
やり出しました。









 23時。
23時。 の8回目の誕生日だそうです。
の8回目の誕生日だそうです。





 たらふく = 鱈腹 ?
たらふく = 鱈腹 ? って海
って海 の底の方に居てエサが少ない場所に居るために食べるときは何でも食べる雑食性らしい
の底の方に居てエサが少ない場所に居るために食べるときは何でも食べる雑食性らしい






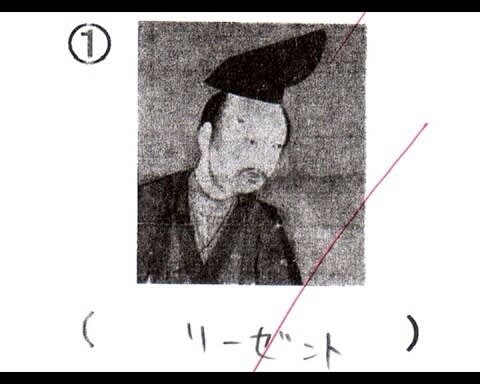
 これで合格したら b2d70c5e84a45d6ff4948e
これで合格したら b2d70c5e84a45d6ff4948e












 今年5月にFOMAからスマホに買い替えた携帯電話。
今年5月にFOMAからスマホに買い替えた携帯電話。 代替え貸出機を貸してはくれたけれど、機種が違うのでこれまた大変。
代替え貸出機を貸してはくれたけれど、機種が違うのでこれまた大変。



 【のぼうの城】 も、本とはまたひと味違って野村萬斎氏の良さが光りました。
【のぼうの城】 も、本とはまたひと味違って野村萬斎氏の良さが光りました。