■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市職員の実態について、7月2日付で、前橋市長に関する措置請求書を、前橋市監査委員あてに発出しました。すると、7月4日付で前橋市監査委員事務局から内容確認の依頼があり、7月6日に同事務局あてに確認結果を提出していたところ、7月11日付前監第2号で受理通知が、同13日に当会事務局に届きました。それには8月1日に証拠の提出及び陳述について機会を当たる旨の通知内容が記載されてありました。そこで当会の代表と事務局長、および会員2名が、8月1日(水)午前10時前に前橋市役所を訪れて約1時間にわたり陳述しました。そして、8月30日(木)に、前橋市監査委員事務局から、監査委員4名の名義で監査結果通知が送られてきました。
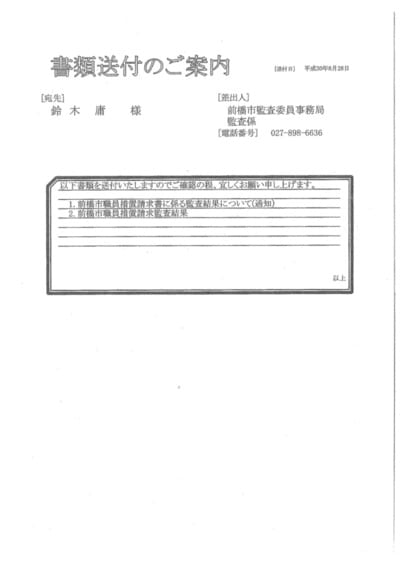
↑前橋市監査委員事務局から届いた監査結果の送り状。↑
なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
■では、さっそく前橋市から送られてきた住民監査請求の監査結果を見てみましょう。
*****送り状*****PDF ⇒ 201808281_maebasisi_kansaiinn_jimukyoku_karano_okurijou.pdf
書類送付のご案内 [送付日] 平成30年8月28日
[宛先] 鈴木 庸 様
[差出人] 前橋市監査委員事務局 監査係 [電話番号]027-898-6636
以下書類を送付いたしますのでご確認の程、宜しくお願い申し上げます。
1.前橋市職員措置請求書に係る監査結果について(通知)
2.前橋市職員措置請求監査結果
以上
*****監査結果通知*****PDF ⇒ 201808282_maebasisi_kansaiinn_karano_tuuchisho.pdf

前監第13号
平成30年8月28日
鈴 木 庸 様
前橋市監査委員 福 田 清 和
同 田 村 盛 好
同 中 里 武
同 笠 原 久
前橋市職員措置請求に係る監査結果について(通知)
このことについて、平成30年7月2日付けで提出のあった前橋市職員措置請求につい て、地方自治法第242条第4項の規定に基づく監査を実施しましたので、その結果を次 のとおり通知します。
記
1 請求に対する判断
平成29年6月10日の不正(請求事項1)及び平成29年6月13日の不正(請 求事項2)については、請求できる要件を満たしていないため、却下する。
病気休暇の取得に係る不正(請求事項4)については、請求に理由がないため、棄却する。
平成29年6月18日の不正(請求事項3)については、請求人の主張に理由があるものと認める。
2 監査結果
別添のとおり
*****監査結果*****PDF ⇒ 201808283_maebasisi_kansaiin_karano_kansakekka_tuuchi.pdf
<P1>
前橋市職員措置請求監査結果
第1 請求の受付
1 請求人
住所 前橋市文京町一丁目15番10号
氏名 鈴 木 庸
2 請求書の収受日
平成30年7月2日
3 請求の内容
請求人から提出された請求書による主張の要旨は、次のとおりである(請求書に記載されている請求の要旨を要約して記載した。また、事実証明の添付は省略した。)。
(1) 請求の要旨
請求人には、2018年3月末まで南橘公民館・南橘市民サービスセンターで勤務していた市役所の職員とその関係相手の職員の仰天すべき行動について、複数の市民から情報提供が寄せられました。そして、その情報の内容からうかがえる前橋市のこの一部職員の行状は、あまりにも酷すぎるため、こうした一部職員による不正行為の実態について、前橋市のトップである貴殿をはじめ、ひろく情報を知っていただくことが再発防止の為にも必要だと考えで、2018年5月2日付で前橋市長に書面で直接報告し、善処を求めました。しかし、いまだに当該職員らによって前橋市に与えられた損害に対する回収のための措置が取られていないため、ここに 措置請求を行わせていただきます。
この南橘公民館における不正の対象者は2名です。
所長のA氏(49歳)とB氏(25歳)であります。
<不正その①>平成29年6月10日(土)
前橋市田口町のホタル祭において、B氏は配偶者と子供と参加しました。子供と配偶者と参加しているだけにも関わらず、時間外勤務手当が支給されるように申請されていました。この日の時間外勤務申請は、「17:30~20:30」 と記載されていました。
この時間外勤務については、その後、平成29年6月28日(水)に職場で同僚たちから「不正受給だ」と追及を受けたため、B氏は「A氏が勝手に記載しただけだから」と自ら不満そうに取消しました .
<P2>
<不正その②>平成29年6月13日(火)
このときの不正は、公民館事務所内で行われました。
不正に取得された時間外受給は「17:15~19:30」と記載されております。この日もいつものようにA氏とB氏の二人で残業するとのことだったので、 「本当に 業務をしているのかどうか」を確かめるべく、ひとりの職員が張り込みました。 ここで彼らがしていたのは、地域行政に関わる残業などではなく、おしゃべりなどだったのです。ここでの状況につきましては、当該張り込み職員が確認をしております。そして、19時25分に二人は職場を後にしております。
ここは市民の行政窓口であり、税金で建設されている公民館です。残業と嘘をつき、このような行為をして、税金による時間外手当を受給している事は市民感情として到底許せることではありません。
<不正その③>平成29年6月18日(日)
この日は前橋地域づくりフェスタが開催されました。ここでもB氏は配偶者と子供と参加しました。その様子は南橘公民館の職員のかたがたが確かに目撃しております。家族連れで参加しているにも関わらず、時間外勤務手当が「10:00~12:00」分が支給されてしまっています。
しかもB氏は、この地域づくりフェスタの担当者ではありませんでした。わざわざ休日出勤をする必要もない事は明らかですので、誰がみても不自然な出勤です。
本来の担当者はA氏と出勤していますので、南橘公民館の職員からも「なぜ、担当者が出動しているのに、担当者以外が休日出勤をして時間外勤務手当を受給するのだ?」との声も上がっておりました。
こうした事実を見れば、上記の行為は、まさに正当な理由のない「時間外手当」の支給、すなわち「不正受給」と疑われても反論の余地は無いのではないでしょうか。
<不正その④>【不正行為に対する前橋市の事なかれ主義】
A氏・B氏の目に余る秩序を乱す行動そして、公務員として地域行政に携わる者としての、品格の欠如や業務不履行に我慢できなくなったある職員のかたは、平成29年7月10日(月)夜半、この二人に対して、これ以上職場の規律が乱されないようにすべく懇願しました。
ここで大きな問題かつ重要な項目は、問題が明るみになるや否や、B氏は 平成29年7月14日(金)に傷病休暇申請をし、平成29年7月18日(火)より以後4か月間の傷病休暇を取得したことです。これは言わば、自らの立場が悪くなったと察すれば、傷病休暇で雲隠れをしておいて、しかし給料はしっかりともらい受けるという、民間では有り得ないウルトラC(今でいうG難度やH難度)を発揮したことです。
<P3>
そして、こうした社会のコンプライアンスに反する行動さえも、市役所さえ容認していることが最大の問題であると言うことができます。
<前橋市が被る損害>
前述の通り、前橋市が被る損害額は、表面的には、時間外勤務については、不正その①に関して2時間、不正その②に関しては2時間15分、不正その③に関しては2時間、不正その④に関しては、4か月分の給与が不正に支出されたことになり ます。このほかにも、当該職員とその相手方の職員による不正行為の存在が強く推認できますが、これらについては前橋市当局の調査が不可欠です。
よって請求人は、上記に特定した違法又は不当な「財務会計上の行為又は怠る事実」について、請求人は、前橋市長に対して、当該職員らから前橋市が被った損害をきちんと回収するよう勧告することを求めます。
4 請求書の要件審査
請求書に記載の事項のうち、下記の事項について平成30年7月3日付けで事務局から請求人に確認を求めた。
(1) 今回の措置請求の内容(勧告を求めるもの)は、職員に対する不当な時間外勤務手当の支出(不正その①から不正その③)と給与の不当な支出(不正その④)についてということになるか。
(2) 不正その①について、「前橋市が被る損害」で2時間の損害としているが、3時間の誤りではないか。
(3) 不正その①について、「職場で同僚たちから「不正受給だ」と追及を受けたため、自ら取消した」旨の記載があるが、今回の措置請求の内容に含めるのか。
(4) 「財務会計上の行為又は怠る事実」について、損害を回収するように勧告することを求める旨の記載があるが、 「怠る事実」に該当する請求内容(勧告を求めるもの)があるか。 (5) 今回提出された「事実証明書」の他に請求内容の事実が確認できるものはあるか。
平成30年7月5日に請求人が来局し、(1) については、そのとおり、(2) については、記載誤り、(3) については、実際に支給されていないことを確かめる術がないため、今回の措置請求に含める、(4) については、怠る事実の請求はない、(5) については、その他の事実証明はない旨を事務局が説明を受けた。これらを踏まえ、本件措置請求については、地方自治法第242条第1項及び第2項に規定する要件を具備しているものと認められたので、平成30年7月11日に受理を決定した。
<P4>
第2 監査の実施
1 監査対象項目
請求の要旨から、以下の事項を監査対象項目とした。
(1) 不正行為の確認
勤務実態のない時間外勤務が行われていたか、また、正当な理由なく病気休暇を取得していたか。
(2) 公金支出の事実及び損害の有無の確認
時間外勤務手当や病気体暇取得による給与等の公金が支出されているか。そして、その公金の支出が違法若しくは不当な財務会計上の行為に該当し、市に損害が生じているか。
(3) 求められた措置への対応
請求人から求められた措置を行う必要があるか。
なお、請求人は措置請求書において、傷病休暇と表現しているが、これは前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「休暇等に関する条例」という。)で規定する病気休暇のことを指していると考えられるため、請求の要旨以外では、病気体暇と表現する。
2 監査対象部局
本件監査請求に係る事務を所管している、総務部職員課及び市民部生活課と職員措置請求書で対象としているB職員及び時間外勤務を命ずる立場にあったA職員を監査の対象とした。
3 請求人の証拠の提出及び陳述
請求人に対し、地方自治法第242条第6項の規定により、平成30年8月1日に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。そして、同日追加資料の提出を受けた。
なお、個人のプライバシーに関する内容を含んでおり、公開することにより個人の権利を害するおそれがあるため、陳述は非公開とした。また、同様の理由から、関係職員等の立会いも認めなかった。
4 監査対象部局の書類の提出及び関係職員の陳述等
監査対象部局から、監査対象事項に関する資料の提出を求め、書類審査を行うとともに、平成30年7月18日にB職員から、同年8月1日に総務部職員課長、同課課長補佐、同課副主幹から請求書に記載された内容に対する陳述の聴取を行った。な
<P5>
お、前述の理由から、陳述は非公開とし、請求人の立会いについても認めなかった。
また、A職員については、文書による聴き取り調査を実施した。なお、B職員については、陳述の内容を補足するため、追加で文書による聴き取り調査を実施した。さらに、市民部生活課南橘市民サービスセンター(以下「南橘市民サービスセンター」という。)の職員のうち、平成29年度に在席していた職員を対象に、監査委員が事情聴取を行った。
第3 事実関係の確認
1 監査対象事項に関する書類審査による事実確認
(1) 平成29年6月10日の不正その①(以下「請求事項1」という。)について
ア B職員の平成29年6月分の時間外勤務等命令簿において、該当する日の時間外勤務の記載がないことを確認した。
イ B職員の給与等支給明細書等において、該当する日に対する手当の支給がないことを確認した。
(2) 平成29年6月13日の不正その②(以下「請求事項2」という。)について
ア B職員の平成29年6月分の時間外勤務等命令簿において、該当する日の時間外勤務の記載があることを確認した。なお、勤務の予定時間は「17:15~19:30」であり、終了時間は「19:30」であったことを確認した。
イ B職員の給与等支給明細書等において、当該時間外勤務に対する手当が支給されていることを確認した。
ウ B職員の平成30年6月分の給与等支給明細書等において、当該時間外勤務に対する手当が返還(当該金額を差し引いて支給)されていることを確認した。
(3) 平成29年6月18日の不正その③(以下「請求事項3」という。)について
ア B職員の平成29年6月分の時間外勤務等命令簿において、該当する日の時間外勤務の記載があることを確認した。なお、勤務の予定時間は「10:00~12:00」であり、終了時間は「12:00」であったことを確認した。
イ B職員の給与等支給明細書等において、当該時間外勤務に対する手当が支給されていることを確認した。
ウ 当該時間外勤務に対する手当について、返還されたことを示す書類は確認できなかった。
エ 南橘市民サービスセンターの時間外勤務等命令簿により、平成27年度、平成28年度及び平成30年度に開催された地域づくりフェスタにおける職員の勤務状況をみると、平成27年度はA職員と嘱託職員であった担当職員(勤務日の割振り変更などで対応し勤務していたと考えられる)及び担当職員ではない職員
<P6>
が勤務していたことを確認した。また、平成28年度はA職員と担当職員、平成30年度は現南橘市民サービスセンター所長と担当職員が勤務しており、それ以外の職員の勤務は確認できなかった。
オ 職員課がA職員に対して行った聴き取り調査において、「事前に時間外勤務命令を出した」、「B職員が確実に出られるかは分からなかったが、なるべく来るようにとはお願いした」、「地域づくりの副担当を養成するため」、「副担当の養成が課題であつた」、「B職員は、仕事への意欲があり、バイタリティーもある。副担当として、地域づくりの全体を見てもらいたいと考え、地域づくりフェスタヘの参加も要請した」、「時間外勤務として認めた時間帯については、当然、家族と一緒ではなかった」と回答していることを確認した。
カ 職員課が地域づくりフェスタに参加した職員(A職員、B職員及び担当職員を除く)に対して行った聴き取り調査において、「家族でイベント会場に来た」、「家族で遊びに来ているようにしか見えなかった」、「仕事をしているようには見えなかった」と回答していることを確認した。
(4) 病気体暇の取得に係る不正その④(以下「請求事項4」という。)について
ア B職員の休暇等承認簿(病気体暇、特別休暇等)により、平成29年7月18日から平成29年10月15日までの期間について、体暇等に関する条例第13条に規定する病気体暇を取得していることを確認した。
イ B職員の体暇等承認簿(病気体暇、特別体暇等)により、病気体暇の取得に当たっては、休暇等に関する条例第17条に規定する任命権者の承認を受けていることを確認した。なお、前橋市事務決裁規程(以下「事務決裁規程」という。)第4条に基づく別表第2の定めにより、病気体暇の承認の専決区分は市民部長であり、職員課長の合議が必要となるが、適正な決裁及び合議を受けていること、また、B職員が疾病のため、当該病気体暇を取得した期間について、安静療養する必要がある旨医師から診断を受けた診断書が添付されていることを確認した。
ウ B職員の休職発令に関する起案文書により、平成29年10月16日から平成29年12月31日までの期間について、地方公務員法第28条第2項第1号 の規定による休職が発令されていることを確認した。
エ 休職の発令に当たっては、事務決裁規程第4条に基づく別表第4の定めにより、総務部長の専決事項とされているが、B職員の休職発令に関する起案文書により、適正な決裁を受けていることを確認した。また、B職員が疾病のため、当該病気休職が発令された期間について、安静療養する必要がある旨医師から診断を受けた診断書が添付されていることを確認した。
オ B職員の給与等支給明細書において、病気体暇を取得している期間及び休職
<P7>
している期間の給与が支給されていることを確認した。
2 陳述等による事実確認
(1) 監査対象部局職員(職員課)の陳述による事実確認(職員課職員が陳述時に述べたことを要約して記載した。)
ア 請求事項1について、時間外勤務命令は取り消しとなったため、時間外勤務手当は支給されていない。そのため、不当な公金の支出には該当しないと考える。
イ 請求事項2について、時間外勤務手当は支給されたが、その後に判明した非違行為により、平成30年6月12日に取り消し、同月20日支給の給与から返還されているため、必要な措置は既に講じられていると考える。
ウ 請求事項3について、事前にA職員から口頭で出席するように命令されたものであり、 当日は家族で来訪したものの、 イベントの最中においては家族と離れ、イベントブースの案内や留守番などを行っていたことを確認した。イベントの担当者である職員が目撃したところによっても、家族と遊んでいるのではなく、イベントブースで手伝っていたというような証言が得られたことから、時間外勤務であると判断した。
エ 請求事項4について、病気休暇においては、医師の診断書に基づき、病気により従事不可能と判断された期間をもとに、休暇及び休職を承認している。今回のケースにおいても、同様に処理したものであり、休暇及び休職している間に支払われた給与については、制度に基づいて支払われたものであることから、不当な公金の支出には該当しないと考える。
(2) A職員に対する文書での聴き取り調査による事実確認(主に請求事項3についての確認内容)
ア 『B職員に対し時間外勤務命令を行った事実はあるか』の問に対して、「あります」との回答を得た。
イ 『命令を行った場合、いつ時間外勤務命令を行ったか』の問に対して、「口頭で16日 (金)に行い、時間外勤務等命令簿の処理は、週明けの19日(月)だったと記憶しております」との回答を得た。
ウ 『時間外勤務を命ずる際に、集合時間、終了時間、従事するべき業務内容、副担当養成のためである旨を伝えていたか。伝えていた場合、その具体的な指示内容を教えて欲しい』の間に対して、「集合時間の10時と、地域づくりフェスタの活動の様子と概要把握を伝えたと記憶しています」との回答を得た。
エ 『B職員は業務であることを認識していたか』の問に対して、「認識していたと思います」との回答を得た。
オ 『地域づくりフェスタヘの参加のほかに、地域づくり推進事業において、副担
<P8>
当の養成のために行ったことがあれば教えて欲しい』の問に対して、「地域づくりフェスタ以降、B職員は傷病(病気)休暇に入ってしまい、養成は行えませんでした」との回答を得た。
(3) B職員の陳述等による事実確認(B職員が陳述時に述べたことを要約して記載した。)
ア 請求事項1について、当日は時間外勤務の認識はなく、月末にその時の時間外勤務手当のことを知って、驚いて取り消した。なお、取り消した方法については、時間外勤務等命令簿を書き直した。
イ 請求事項2について、職員課の聴き取りがあり、誤った支給であったということが分かったので、職員課の指示に従って返還した。
ウ 請求事項3について、何かお手伝いがあればいいと思って行った。時間外勤務の認識はなく、何ができることがあればやろうと思い、実際に行ってお手伝いをやっていた。手伝っていたことを勤務と捉えたのは、A職員だと思う。
A職員からの参加の指示について、来られたら来てというようなことを言われたと思う。 時間外勤務手当の処理については、 私の全く知らないところである。
(4) B職員に対する文書での聴き取り調査による事実確認(全て請求事項3についての確認内容)
ア 『地域づくりフェスタヘの参加は任意であったか、または、参加を強制されるものであったか』の問に対して、「陳述で述べた通り、「来られたら来て」という言葉を任意での参加で良いととらえました」との回答を得た。
イ 『A職員から「来られたら来て」ということを言われたとしているが、その他に、地域づくりフェスタの活動の様子と概要把握をするように言われたか』の問に対して、「言われたかどうかについては覚えていないが、地域づくりフェスタに来たら、職員として全体の様子を把握してほしいと思う。活動の様子等を報告する必要があると思う」との回答を得た。
ウ 『開始時間と終了時間について、A職員から具体的な指示はあったか。または、自分の意思で参加する時間・帰る時間を決定できたか』の問に対して「正確に覚えていないが、始まりの時間は聞いていたと思う。午前中いっぱいと聞いていた」との回答を得た。
エ 『地域づくりフェスタ当日に、A職員から具体的な作業について指示や拘束があったか。もしくは、参加していた時間の全てについて自分の意思だけで行動できていたか』の問に対して、「関係者へあいさつするよう指示があった。その他はよく覚えていないが、他イベントに参加していた時は、全体の様子を見てイベント内容を把握するよう指示があるため、今回も色々なブースを見て来てと言わ
<P9>
れていたと思う」との回答を得た。
オ 『A職員は、地域づくりの副担当養成のためにB職員に対してイベント参加を促したと回答しているが、副担当養成についてA職員から話をされたことはあるか』の問に対して、『職員には事務分担に地域づくり事業の副担当がついており、そのことについて話をされたことはある。また、公民館事業のイベント等は把握しておきたいという考えがあったため、その他のイベントにも担当ではなくても参加していた」との回答を得た。なお、平成29年度の南橘市民サービスセンターにおける事務分掌において、嘱託職員と育児休暇明けの職員を除く全ての職員に地域づくり事業の副担当が割り当てられていたことを確認した。
カ 『地域づくりフェスタには家族で参加しているが、家族で行動を共にしたか』の間に対して、「一緒にフェスタに行った以上、行動を共にしていた時間はあった」との回答を得た。
(5) 南橘市民サービスセンターの職員のうち、平成29年度に在席していた職員を対象とした事情聴取による事実確認(事情聴取時に述べたことを要約して記載した。)
ア 地域づくりフェスタの担当職員
(ア) 『地域づくりフェスタでは、どのような業務に従事していたか』の問に対して、「出店のお手伝いから後片付けまで、イベント中の進行のお手伝いというのが業務であった」との回答を得た。
(イ) 『B職員は担当であったか』の問に対して、「担当ではない」との回答を得た。
(ウ) 『B職員が会場にいたのを見たか、また、業務をしていたか』の問に対して、「会場にいたのは確認している。テーブルの中に入って地域づくりのお手伝いをしていたのも確認している。ただ、いつ頃、どんなというのまで、私も動き回っていたので確認はしていない」との回答を得た。
(エ) 『B職員の当日の業務について、A職員から聞いていたか』の問に対して、「事前には聞いていなかった」との回答を得た。
(オ) 『週休日等に開催されるイベントで担当職員以外の職員が顔を出すというのはよくあることか』の問に対して、「大きな規模のイベントだと、担当職員以外の我々でも手伝いに出る」、「事前に業務命令がでて、役割もある」との回答を得た。
(カ) 『単に、イベントに行って少し手伝ったから超過勤務ということはないか』の問に対して、「それはないです」との回答を得た。
イ 平成28年度の地域づくりフェスタに参加した担当職員以外の職員
(ア) 『地域づくりフェスタについて、A職員から「来られる人は来て」という
<P10>
ような話を受けたことがあるか』の問に対して、「一昨年は受けたので、行きました」との回答を得た。また、その他に「参加した際は、少しお手伝いをしました」、「参加して手伝わないと来た意味がない」、「みんな顔見知りなので、大変そうな時は手伝った」との回答を得た。
(イ) 『手伝いをしたときに、時間外勤務の処理をしたか』の問に対して、「していないと思います」との回答を得た。なお、平成28年度の時間外勤務等命令簿において、該当する日の時間外勤務の記載がないことを確認した。
(ウ) 『「来られたら来て」というような声掛けについて、A職員は全員にしていたのか』の問に対して、「ホタル祭は、朝会のときに話はしていたが、地域づくりフェスタに関しては個別であり、全員ではない」との回答を得た。
(エ) 『ホタル祭、地域づくリフェスタについては、自由参加で時間外勤務ではない、これは一般的な考えでよいか』の問に対して、「少なくとも私はそう思います」との回答を得た。
1ウ 平成27年度の地域づくりフェスタ業務に従事した担当職員以外の職員
(ア) 平成27年度の地域づくりフェスタ業務に従事したことについて、「当時の担当職員から参加して欲しいという依頼があって参加した」、「自主的に時間外勤務を付けたわけではない」、「仕事という感覚で出勤しており、参加というより出勤である」との回答を得た。
(イ) 『平成27年度は参加して、平成28年度と平成29年度は参加していないが、その差は何か』の問に対して、「特に業務の依頼がなかったので、参加していない」との回答を得た。
(ウ) 『週休日等に開催されるイベントで担当職員以外の職員が顔を出すというのはよくあることか』の問に対して、「業務でないところに顔を出すことは基本的にはなく、人手が足りないので手伝いを業務依頼して出勤してもらうケースはある」との回答を得た。この回答を受けて『自ら進んで出た場合は自主参加であって、仕事ではないのか』との問に対して「はい」との回答を得た。
エ 平成29年度の地域づくりフェスタに参加した職員
(ア) 『地域づくりフェスタについて、A職員から「来られる人は来て」という話を受けたか』の問に対して、「受けていません」との回答を得た。
(イ) 『B職員が会場で何をしていたか、どのような行動をしていたか』の問に対して、「南橘地区のブースに来ていたのを見た」との回答を得た。
オ その他の職員
(ア) 『地域づくりフェスタについて、A職員から「来られる人は来て」という話を受けたか』の問に対して、「受けていません」との回答を得た。
<P11>
(イ) 『週休日等に開催されるイベントで担当職員以外の職員が顔を出すというのはよくあることか』の問に対して、「よくあります」、「顔を出すというよりは、仕事も割り当てられるので、もちろん勤務という形で時間外を付けます」との回答を得た。そして、『たまたま来て忙しそうだから手伝って、超過勤務だということはないか』の問に対しても、「そういうことはないです」との回答を得た。
第4 監査委員の判断
地方自治法第242条第1項は、住民監査請求について、普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員について、違法・不当な公金の支出等の財務会計上の行為又は違法・不当に公金の賦課・徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止・是正若しくは怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる旨を規定している。
本規定を踏まえて、これまでの事実関係の確認の結果、本件措置請求について次のとおり判断する。
1 請求事項1について
第3事実関係の確認1 (1) に記載のとおり、時間外勤務手当は支給されておらず、請求人がいう違法又は不当な財務会計上の行為の存在は認められなかったことから、地方自治法第242条第1項で規定する住民監査請求の要件を満たしていないものと判断する。
2 請求事項2について
第3事実関係の確認1 (2)、2 (1) イ、(3) イに記載のとおり、時間外勤務手当は支給されたが、その後、当該時間外勤務手当を市に返還したことが確認できたことから、当該時間外勤務手当の支給が違法又は不当であったか判断するまでもなく、地方自治法第242条第1項で規定する住民監査請求の要件を満たしていないものと判断する。
3 請求事項3について
時間外勤務については、前橋市職員服務規程(以下「服務規程」という。)第14条第1項で、職員は、所属長の命令があったときは、正規の勤務時間外、週休日又は休日等であっても、勤務に服さなければならない旨を規定している。また、服務規程第
<P12>
14条第4項では、所属長は、正規の勤務時間外、週休日又は休日等に勤務を命ずるときは時間外勤務等命令簿により行わなければならない旨を規定している。なお、本件において、所属長として命ずる者は、事務決裁規程第4条に基づく別表第2の定めにより出先の長であるA職員となる。
また、時間外勤務手当の支給については、労働基準法第37条第1項で、使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働について、割増賃金を支払わなければならない旨を規定している。さらに、前橋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条第1項で、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する旨を規定している。なお、一般職の地方公務員については、地方公務員法第58条第3項の規定により、労働基準法の適用を除外している規定を除いて労働基準法が適用されることから、労働基準法で規定する労働時間が、本件についても適用されるものと判断する。
本件において職員課は、第3事実関係の確認1 (3) アに記載のとおり、地域づくりフェスタに係るB職員の時間外勤務等命令簿が作成されていること、また、第3事実関係の確認1 (3) オに記載のとおり、時間外勤務を命ずる立場にあったA職員は、B職員に対し時間外勤務を命令したとする証言があったこと、さらには、第3事実関係の確認2 (1) ウに記載のとおり、イベントブースで手伝っていたとする担当職員の証言もあったことから、B職員が地域づくりフェスタにおいて時間外勤務として業務に従事したとすることについて、前述の服務規程に基づいた形式的な要件は整っていると判断し、勤務したとする時間に対して時間外勤務手当を支給したものである。
しかしながら、職員課の判断においては、第3事実関係の確認2 (3) ウに記載のとおり、B職員は業務としての認識がなかったこと、また、B職員の認識からは、A職員からB職員に対して時間外勤務命令があったと判断するには疑義が残ること、さらには、第3事実関係の確認1 (3) カに記載のとおり、担当職員以外で地域づくりフェスタに参加した職員が、B職員は「家族で遊びに来ているようにしか見えなかった」と証言していること、これらを踏まえたものとなっていない。
したがって、本件を判断する上で、時間外勤務等命令簿の作成などの形式的な要件のほかに、実際に業務としての勤務実態があったか否かについても考察する必要があると考える。
平成29年1月20日付けで厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」における労働時間の考え方をみると、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」としている。
<P13>
また、最高裁判例(平成12年3月9日/最高裁判所第一小法廷判決)においても、「労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めいかんにより決定されるべきものではない」として いる。
以上のことから、本件については、B職員が地域づくりフェスタに参加したこと及び当日行っていた行為が、客観的にA職員の指揮命令下に置かれていたと評価できるか、そして、それにより労働基準法上の労働時間に該当するか判断すべきものと考える。
そのためまず、B職員が地域づくりフェスタに参加することについて、一定の拘束を受けたことにより、指揮命令下に置かれていたと評価できるか考察する。
第3事実関係の確認2 (2) イに記載のとおり、A職員は、イベントの開催前に時間外勤務命令を口頭で行ったとしているにもかかわらず、時間外勤務等命令簿の処理を週明けに行っており、B職員が地域づくりフェスタに従事するか当日まで不確定な状態であったこと、さらには、第3事実関係の確認2 (3) ウに記載のとおり、「来られたら来て」という曖昧な表現からも推認できるように、地域づくりフェスタに従事するか否かを明確にせず、B職員に委ねていたことから、A職員はB職員に対して、地域づくりフェスタに従事することについて明確に時間外勤務を命令していたと考えることはできない。
また、明確な時間外勤務命令がされていない状況における労働時間について、高等裁判所判決(平成13年6月28日/大阪高等裁判所判決/確定)では、当該業務ヘの従事が常態的であり、それが特殊なものではないことと、業務への従事が義務付けられている性質のものであることを理由の一つとして、労働時間と評価する旨判示している。
そこで、 南橘市民サービスセンターにおける実際の時間外勤務の運用状況をみると、第3事実関係の確認2 (5) において、平成28年度の地域づくりフェスタに参加した担当職員以外の職員は、A職員の呼びかけに応じて、地域づくりフェスタに参加し手伝いをしたが、時間外勤務として処理していないこと、平成27年度の地域づくりフェスタに時間外勤務として従事した担当職員以外の職員は、事前に業務として指示を受け、業務として認識のもと従事していたこと、また、全ての南橘市民サービスセンターの職員が週休日等に開催されるイベントにおいて、担当職員以外の職員が従事することについては、事前に業務命令があり、時間外勤務として従事していたとして
<P14>
おり、自主参加は業務ではないという認識で一致していたことから、明確な時間外勤務の指示がなく、週休日等のイベントに参加したことを時間外勤務として取り扱うことは、南橘市民サービスセンターにおいて常態的ではなかったことが確認できた。
そのため、B職員がA職員から「来られたら来て」と言われたことに対して、当時の状況から業務として認識しなかったことは当然のことであり、また、担当職員以外のB職員が地域づくりフェスタに時間外勤務として従事することは、南橘市民サービスセンターにおいては特殊なものであり、先に述べたとおり、従事するか否か をB職員に委ねていた以上は、その従事は義務付けられていたものではなかったと推認できることから、A職員の指揮命令下に置かれていたと評価することはできない。
次に、B職員が地域づくりフェスタに従事するべき時間、遂行するべき業務内容により一定の拘束を受け、指揮命令下に置かれていたと評価できるか考察する。
最高裁判例(平成19年10月19日/最高裁判所第二小法廷判決)における、住み込みで勤務していたマンション管理員の日曜日及び祝日の休日労働ないし時間外労働の判断では、雇用契約において休日とされていた日曜日及び祝日については、指示されていた業務以外には労務の提供が義務付けられておらず、労働からの解放が保障されていたということができ、会社が指示したと認められる業務に現実に従事した時間に限り、休日労働又は時間外労働をしたものというべきである旨判示している。
これを本件についてみると、従事するべき時間については、第3事実関係の確認2 (4) ウに記載のとおり、B職員は、「始まりの時間は聞いていたと思う。午前中いっぱい」とする旨回答しているが、地域づくりフェスタヘの従事については、第3事実関係の確認2 (4) アに記載のとおり「任意での参加で良いと捉えた」と回答しており、あくまでイベントの開始時間等を伝えられたものと捉えたと推認できる。
また、遂行するべき業務内容については、第3事実関係の確認2 (4) イ、エに記載のとおり、A職員から地域づくリフェスタの活動の様子と概要把握をするように言われたか記憶しておらず、当日の具体的な指示について明確に記憶しているのは、関係者への挨拶だけであり、それ以外は過去の他のイベント参加時の様子をもとに本人が推測する程度のものであった。そのため、当日は、業務への従事及び業務内容について、関係者への挨拶以外はA職員からの明確な指示はなく、第3事実関係の確認2 (3) ウ、(4) オに記載のとおり、「何かお手伝いがあればいいと思って行った」、「公民館事業のイベント等は把握しておきたいという考えがあったため、その他のイベントにも担当ではなくても参加していた」と 回答しているように、全て本人の意思により行動していたものと推認できる。
したがって、A職員からの明確な指示があったものは関係者への挨拶という儀礼
<P15>
的な範囲のものだけであり、B職員は本人の意思で参加しイベントブースを手伝っていたのであって、当日の行為について労務の提供が義務付けられておらず、労働からの解放も保障されていたと推認できることから、A職員の指揮命令下に置かれていたと評価することはできない。
さらに、B職員が地域づくりフェスタに参加した際、第3事実関係の確認1 (3) カに記載のとおり、家族で来ていたとしているが、職員課は、第3事実関係の確認2 (1) ウに記載のとおり、家族で遊んでいるのではなく、イベントブースで手伝っていたとする証言が得られたとし、A職員も第3事実関係の確認1 (3) オに記載のとおり、時間外勤務として認めた時間帯については、当然、家族と一緒ではなかったとして、その適正性を判断している。
しかし、地方公務員は、地方公務員法第35条の規定により職務に専念する義務があり、それに反する家族との行動について、第3事実関係の確認2 (4) カ、(5) ア (ウ) に記載のとおり、担当職員もB職員の全ての行動を見ていない旨回答し、B職員も「一緒にフェスタに行った以上、家族と行動を共にしていた時間はあった」とする旨回答している。これらを踏まえると、地域づくりフェスタに参加すること又はイベントブースを手伝うことを時間外勤務として取り扱うのであれば、家族と共に行動した時間を業務として認めることは妥当ではない。さらには、当該時間を時間外勤務とするのであれば、指揮監督をするべきA職員は是正を求めなければならなかったところ、家族と行動を共にしていたことを把握、是正せずに、時間外勤務として全体を承認したことは適当ではなく、また一定の拘束を受けているとは言えず、そのような状況を踏まえても、A職員の指揮命令下に置かれていたと評価することはできない。
以上のことから、B職員が地域づくりフェスタに参加してイベントブースの手伝いなどを行った行為について、A職員の指揮命令下に置かれていたと評価することはできず、そのため、当該時間は労働基準法で定める労働時間ということはできないものであり、当該時間外勤務手当の支給は法令等の根拠に基づかない公金の支出であると判断する。
4 請求事項4について
病気体暇については、休暇等に関する条例第11条で職員の休暇とする旨を規定している。また、休暇等に関する条例第13条では、病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、市規則で定める期間内において必要と認められる期間とする旨を規定し、前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条において、
<P16>
その期間は、私傷病については90日以内とする旨を規定している。さらに、給与条例第11条において、休暇による場合は給与を減額しなぃ旨を規定している。
また、病気体職については、地方公務員法第28条第2項において、心身の故障のため、長期の体養を要する場合は、休職することができる旨を規定しており、前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(以下「分限に関する手続等に関する条例」という。)第9条第1項において、休職の期間は休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内において、 個々の場合について任命権者が定める旨を規定している。 そして、分限に関する手続等に関する条例第10条第2項において、休職者は、休職の期間中法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されないと規定しているが、給与条例第23条第3項において、私傷病により休職にされ たときは、その体職の期間が満1年に達するまでは給与等の100分の80を支給する旨を規定している。
これらを踏まえると、B職員が病気体暇を取得し、また、 休職することについて、第3事実関係の確認1 (4) に記載のとおり、それぞれ該当する期間について、医師から安静療養を要すると診断されており、それをもって、病気休暇の承認及び休職発令を行い、その期間中、給与等の支払をしたことについては、法令、条例、規則に基づいた適正な手続及び支給であり、また、その判断は決裁権者の裁量の範囲内と認められることから、違法若しくは不当な財務会計上の行為とする請求人の主張には理由がないものと判断する。
以上の判断により、本件措置請求において、請求事項1及び請求事項2については、住民監査請求できる要件を満たしていないため却下、請求事項4については、違法又は不当な財務会計上の行為とは認められず、請求に理由がないため棄却する。請求事項3については、請求に理由があると認められるため、地方自治法第242条第4項の規定により、市長に対して、次のとおり勧告する。
第5 勧告
B職員が、平成29年6月18日(日)に開催された地域づくりフェスタ業務に従事したとして時間外勤務手当を受給したことについて、 当該時間外勤務として認定した時間 は、労働基準法で定める労働時間と認定することができないと判断した。したがって、支給された時間外勤務手当は法令等の根拠に基づかない公金の支出であるため、B職員に対して当該時間外勤務手当を返還させる措置を講ずることを前橋市長に対して勧告する。
なお、地方自治法第242条第9項の規定に基づき、平成30年9月28日(金)までに講じた措置について通知することを求める。
<P17> `
第6 意見
監査の結果については以上であるが、本件請求における法令等の根拠に基づかない時間外勤務手当の支出が発生した要因を考察すると、南橘市民サービスセンターにおいては、時間外勤務命令等の処理に適切性を欠いていたことなどから、管理職をはじめとして、職員一人ひとりの時間外勤務制度の適正な運用に対する意識の欠如がその要因であったと考える。 また、 本件は出先機関である市民サービスセンターで発生した事案であるとともに、 時間外勤務命令の決裁が出先の長に認められ、同様の出先機関が多数存在する本市の現状 からも、本件を特殊なケースとして看過することはできないと考える。
これらのことから、出先機関における職員の時間外勤務に対する意識向上に努めること はもとより、全庁的にも、時間外勤務制度の更なる適正な運用に向けて、下記の事項に留意しながら、現行規程の見直しを含め必要な改善に取り組むことを要望するものである。
1 時間外勤務命令については、管理職において、当該勤務が真に必要なものか的確に判断するとともに、やむを得ない事情がある場合などを除き、事前の明確な命令を徹底すること
2 時間外勤務手当については、市民の税金を原資とした公金の支出であることを職員一人ひとりが再認識し、計画的かつ効率的な事務の執行に努めること
3 時間外勤務等命令簿の処理については、適時かつ正確に行うこと
4 出先機関における時間外勤務の履行確認について必要なチェック体制を整えること
**********
■どうやら部分的には不正申告による時間外手当分の返還を、当該職員に求める勧告を山本龍・前橋市長に対して行い、9月28日(金)までに、その措置内容について、監査委員に通知するよう求めたことがわかります。
しかし、返還の必要を認めたのは、2017年6月18日(日)の10時から正午までの時間外手当の2時間分のみであり、当会が陳述の際、今回の監査請求の追加対象として説明した同年5月4日(木・祝)の件は、まったく触れられていません。
また、今回の監査結果で、公民館で所長と部下が淫行をしていた2017年6月13日(火)の17:15~19:30に亘る時間外手当の不正給付については、当会が、今回の住民監査請求を行った2018年7月2日の直前の6月の給与を差し引く形で、返還済みであることが分かりました。
つまり前橋市は、一部の時間外手当については不正申告であることを自ら調査して、返還を求めたわけですが、それ以外の不正は、当会から指摘されて渋々、返還の必要性を認めざるを得なくなったのです。
それでも、当会から指摘された部分だけを調査の対象としているだけで、他にも不正申告が日常化していたことが伺われるのに、前橋市は少しも積極的に調査しようとする気概が見えてきません。
■今回の住民監査請求では、所長の不倫相手の若い職員のみが、不正申告を問われて、時間外手当の返還に追い込まれたわけですが、所長のほうは、なんのおとがめもありません。
驚かされるのは、2017年6月10日(土)の時間外手当の不正について、不倫相手の職員が「当日は時間外勤務の認識はなく、月末にその時の時間外勤務手当のことを知って、驚いて取り消した。なお、取り消した方法については、時間外勤務等命令簿を書き直した」と職員課に対して証言していることです。
つまり、自分の勤怠簿について、きちんと自分で記載しているのではなく、不倫相手の所長が代筆していることが伺えます。あるいは、もし自分で虚偽の記載をされていることが月末になって初めて分かったのであれば、所長が勝手に不倫相手の若い職員の印鑑を、勤怠簿に押印したり、時間外の期間を記入していたことになります。これは、明らかに有印私文書偽造ないし変造行為にあたります。
この所長は、自らの勤怠簿でも、用もないのに休日出勤して、不倫の時間をつくるために、それを平日の代休に振り替えるため、退職して不在の職員の同じ名字の印鑑を買って、それを使って不正に勤怠簿を改竄したため、文書偽造で警察沙汰になった経緯もあります。
おそらくこうした文書偽造行為を、この所長は日常的に行っていたはずですが、職員課には少しも調査する気配が見られず、このことは当会が陳述でも詳述したのですが、やはり監査委員もまったく関心がないことが、今回の監査結果で明らかになりました。
ほかにも、都合で長期に休みたい場合、医師の診断書があれば、役所では簡単に長期休暇が認められることも分かりました。これは安中市の公立碓氷病院を舞台にした勤怠情報の不正申告や、診療記録の不正記載の事件の当事者の理学療法士の場合も、不正発覚直後に、同様に、精神的なストレスを理由に意思から診断書を出してもらい、それを役所に提出して3か月間自宅療養をしていました。
この間、我々の血税が給与として支払われていたと思うと、まことに複雑な思いがいたします。
■この監査結果を受けて、当会としてどのような対応を取るか、9月28日までに決定する必要があります。次回、9月15日の当会の定例会で、参加者の皆さんと協議の上、方針を決める所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
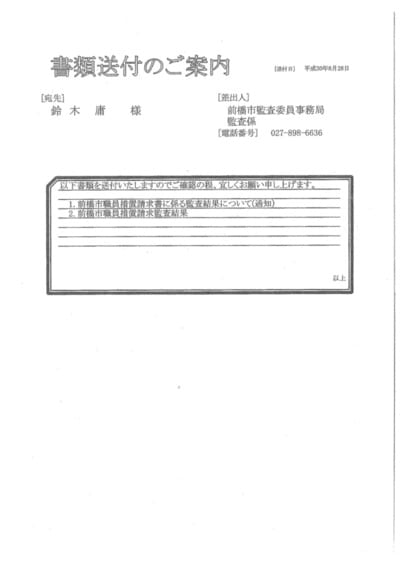
↑前橋市監査委員事務局から届いた監査結果の送り状。↑
なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
■では、さっそく前橋市から送られてきた住民監査請求の監査結果を見てみましょう。
*****送り状*****PDF ⇒ 201808281_maebasisi_kansaiinn_jimukyoku_karano_okurijou.pdf
書類送付のご案内 [送付日] 平成30年8月28日
[宛先] 鈴木 庸 様
[差出人] 前橋市監査委員事務局 監査係 [電話番号]027-898-6636
以下書類を送付いたしますのでご確認の程、宜しくお願い申し上げます。
1.前橋市職員措置請求書に係る監査結果について(通知)
2.前橋市職員措置請求監査結果
以上
*****監査結果通知*****PDF ⇒ 201808282_maebasisi_kansaiinn_karano_tuuchisho.pdf

前監第13号
平成30年8月28日
鈴 木 庸 様
前橋市監査委員 福 田 清 和
同 田 村 盛 好
同 中 里 武
同 笠 原 久
前橋市職員措置請求に係る監査結果について(通知)
このことについて、平成30年7月2日付けで提出のあった前橋市職員措置請求につい て、地方自治法第242条第4項の規定に基づく監査を実施しましたので、その結果を次 のとおり通知します。
記
1 請求に対する判断
平成29年6月10日の不正(請求事項1)及び平成29年6月13日の不正(請 求事項2)については、請求できる要件を満たしていないため、却下する。
病気休暇の取得に係る不正(請求事項4)については、請求に理由がないため、棄却する。
平成29年6月18日の不正(請求事項3)については、請求人の主張に理由があるものと認める。
2 監査結果
別添のとおり
*****監査結果*****PDF ⇒ 201808283_maebasisi_kansaiin_karano_kansakekka_tuuchi.pdf
<P1>
前橋市職員措置請求監査結果
第1 請求の受付
1 請求人
住所 前橋市文京町一丁目15番10号
氏名 鈴 木 庸
2 請求書の収受日
平成30年7月2日
3 請求の内容
請求人から提出された請求書による主張の要旨は、次のとおりである(請求書に記載されている請求の要旨を要約して記載した。また、事実証明の添付は省略した。)。
(1) 請求の要旨
請求人には、2018年3月末まで南橘公民館・南橘市民サービスセンターで勤務していた市役所の職員とその関係相手の職員の仰天すべき行動について、複数の市民から情報提供が寄せられました。そして、その情報の内容からうかがえる前橋市のこの一部職員の行状は、あまりにも酷すぎるため、こうした一部職員による不正行為の実態について、前橋市のトップである貴殿をはじめ、ひろく情報を知っていただくことが再発防止の為にも必要だと考えで、2018年5月2日付で前橋市長に書面で直接報告し、善処を求めました。しかし、いまだに当該職員らによって前橋市に与えられた損害に対する回収のための措置が取られていないため、ここに 措置請求を行わせていただきます。
この南橘公民館における不正の対象者は2名です。
所長のA氏(49歳)とB氏(25歳)であります。
<不正その①>平成29年6月10日(土)
前橋市田口町のホタル祭において、B氏は配偶者と子供と参加しました。子供と配偶者と参加しているだけにも関わらず、時間外勤務手当が支給されるように申請されていました。この日の時間外勤務申請は、「17:30~20:30」 と記載されていました。
この時間外勤務については、その後、平成29年6月28日(水)に職場で同僚たちから「不正受給だ」と追及を受けたため、B氏は「A氏が勝手に記載しただけだから」と自ら不満そうに取消しました .
<P2>
<不正その②>平成29年6月13日(火)
このときの不正は、公民館事務所内で行われました。
不正に取得された時間外受給は「17:15~19:30」と記載されております。この日もいつものようにA氏とB氏の二人で残業するとのことだったので、 「本当に 業務をしているのかどうか」を確かめるべく、ひとりの職員が張り込みました。 ここで彼らがしていたのは、地域行政に関わる残業などではなく、おしゃべりなどだったのです。ここでの状況につきましては、当該張り込み職員が確認をしております。そして、19時25分に二人は職場を後にしております。
ここは市民の行政窓口であり、税金で建設されている公民館です。残業と嘘をつき、このような行為をして、税金による時間外手当を受給している事は市民感情として到底許せることではありません。
<不正その③>平成29年6月18日(日)
この日は前橋地域づくりフェスタが開催されました。ここでもB氏は配偶者と子供と参加しました。その様子は南橘公民館の職員のかたがたが確かに目撃しております。家族連れで参加しているにも関わらず、時間外勤務手当が「10:00~12:00」分が支給されてしまっています。
しかもB氏は、この地域づくりフェスタの担当者ではありませんでした。わざわざ休日出勤をする必要もない事は明らかですので、誰がみても不自然な出勤です。
本来の担当者はA氏と出勤していますので、南橘公民館の職員からも「なぜ、担当者が出動しているのに、担当者以外が休日出勤をして時間外勤務手当を受給するのだ?」との声も上がっておりました。
こうした事実を見れば、上記の行為は、まさに正当な理由のない「時間外手当」の支給、すなわち「不正受給」と疑われても反論の余地は無いのではないでしょうか。
<不正その④>【不正行為に対する前橋市の事なかれ主義】
A氏・B氏の目に余る秩序を乱す行動そして、公務員として地域行政に携わる者としての、品格の欠如や業務不履行に我慢できなくなったある職員のかたは、平成29年7月10日(月)夜半、この二人に対して、これ以上職場の規律が乱されないようにすべく懇願しました。
ここで大きな問題かつ重要な項目は、問題が明るみになるや否や、B氏は 平成29年7月14日(金)に傷病休暇申請をし、平成29年7月18日(火)より以後4か月間の傷病休暇を取得したことです。これは言わば、自らの立場が悪くなったと察すれば、傷病休暇で雲隠れをしておいて、しかし給料はしっかりともらい受けるという、民間では有り得ないウルトラC(今でいうG難度やH難度)を発揮したことです。
<P3>
そして、こうした社会のコンプライアンスに反する行動さえも、市役所さえ容認していることが最大の問題であると言うことができます。
<前橋市が被る損害>
前述の通り、前橋市が被る損害額は、表面的には、時間外勤務については、不正その①に関して2時間、不正その②に関しては2時間15分、不正その③に関しては2時間、不正その④に関しては、4か月分の給与が不正に支出されたことになり ます。このほかにも、当該職員とその相手方の職員による不正行為の存在が強く推認できますが、これらについては前橋市当局の調査が不可欠です。
よって請求人は、上記に特定した違法又は不当な「財務会計上の行為又は怠る事実」について、請求人は、前橋市長に対して、当該職員らから前橋市が被った損害をきちんと回収するよう勧告することを求めます。
4 請求書の要件審査
請求書に記載の事項のうち、下記の事項について平成30年7月3日付けで事務局から請求人に確認を求めた。
(1) 今回の措置請求の内容(勧告を求めるもの)は、職員に対する不当な時間外勤務手当の支出(不正その①から不正その③)と給与の不当な支出(不正その④)についてということになるか。
(2) 不正その①について、「前橋市が被る損害」で2時間の損害としているが、3時間の誤りではないか。
(3) 不正その①について、「職場で同僚たちから「不正受給だ」と追及を受けたため、自ら取消した」旨の記載があるが、今回の措置請求の内容に含めるのか。
(4) 「財務会計上の行為又は怠る事実」について、損害を回収するように勧告することを求める旨の記載があるが、 「怠る事実」に該当する請求内容(勧告を求めるもの)があるか。 (5) 今回提出された「事実証明書」の他に請求内容の事実が確認できるものはあるか。
平成30年7月5日に請求人が来局し、(1) については、そのとおり、(2) については、記載誤り、(3) については、実際に支給されていないことを確かめる術がないため、今回の措置請求に含める、(4) については、怠る事実の請求はない、(5) については、その他の事実証明はない旨を事務局が説明を受けた。これらを踏まえ、本件措置請求については、地方自治法第242条第1項及び第2項に規定する要件を具備しているものと認められたので、平成30年7月11日に受理を決定した。
<P4>
第2 監査の実施
1 監査対象項目
請求の要旨から、以下の事項を監査対象項目とした。
(1) 不正行為の確認
勤務実態のない時間外勤務が行われていたか、また、正当な理由なく病気休暇を取得していたか。
(2) 公金支出の事実及び損害の有無の確認
時間外勤務手当や病気体暇取得による給与等の公金が支出されているか。そして、その公金の支出が違法若しくは不当な財務会計上の行為に該当し、市に損害が生じているか。
(3) 求められた措置への対応
請求人から求められた措置を行う必要があるか。
なお、請求人は措置請求書において、傷病休暇と表現しているが、これは前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「休暇等に関する条例」という。)で規定する病気休暇のことを指していると考えられるため、請求の要旨以外では、病気体暇と表現する。
2 監査対象部局
本件監査請求に係る事務を所管している、総務部職員課及び市民部生活課と職員措置請求書で対象としているB職員及び時間外勤務を命ずる立場にあったA職員を監査の対象とした。
3 請求人の証拠の提出及び陳述
請求人に対し、地方自治法第242条第6項の規定により、平成30年8月1日に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。そして、同日追加資料の提出を受けた。
なお、個人のプライバシーに関する内容を含んでおり、公開することにより個人の権利を害するおそれがあるため、陳述は非公開とした。また、同様の理由から、関係職員等の立会いも認めなかった。
4 監査対象部局の書類の提出及び関係職員の陳述等
監査対象部局から、監査対象事項に関する資料の提出を求め、書類審査を行うとともに、平成30年7月18日にB職員から、同年8月1日に総務部職員課長、同課課長補佐、同課副主幹から請求書に記載された内容に対する陳述の聴取を行った。な
<P5>
お、前述の理由から、陳述は非公開とし、請求人の立会いについても認めなかった。
また、A職員については、文書による聴き取り調査を実施した。なお、B職員については、陳述の内容を補足するため、追加で文書による聴き取り調査を実施した。さらに、市民部生活課南橘市民サービスセンター(以下「南橘市民サービスセンター」という。)の職員のうち、平成29年度に在席していた職員を対象に、監査委員が事情聴取を行った。
第3 事実関係の確認
1 監査対象事項に関する書類審査による事実確認
(1) 平成29年6月10日の不正その①(以下「請求事項1」という。)について
ア B職員の平成29年6月分の時間外勤務等命令簿において、該当する日の時間外勤務の記載がないことを確認した。
イ B職員の給与等支給明細書等において、該当する日に対する手当の支給がないことを確認した。
(2) 平成29年6月13日の不正その②(以下「請求事項2」という。)について
ア B職員の平成29年6月分の時間外勤務等命令簿において、該当する日の時間外勤務の記載があることを確認した。なお、勤務の予定時間は「17:15~19:30」であり、終了時間は「19:30」であったことを確認した。
イ B職員の給与等支給明細書等において、当該時間外勤務に対する手当が支給されていることを確認した。
ウ B職員の平成30年6月分の給与等支給明細書等において、当該時間外勤務に対する手当が返還(当該金額を差し引いて支給)されていることを確認した。
(3) 平成29年6月18日の不正その③(以下「請求事項3」という。)について
ア B職員の平成29年6月分の時間外勤務等命令簿において、該当する日の時間外勤務の記載があることを確認した。なお、勤務の予定時間は「10:00~12:00」であり、終了時間は「12:00」であったことを確認した。
イ B職員の給与等支給明細書等において、当該時間外勤務に対する手当が支給されていることを確認した。
ウ 当該時間外勤務に対する手当について、返還されたことを示す書類は確認できなかった。
エ 南橘市民サービスセンターの時間外勤務等命令簿により、平成27年度、平成28年度及び平成30年度に開催された地域づくりフェスタにおける職員の勤務状況をみると、平成27年度はA職員と嘱託職員であった担当職員(勤務日の割振り変更などで対応し勤務していたと考えられる)及び担当職員ではない職員
<P6>
が勤務していたことを確認した。また、平成28年度はA職員と担当職員、平成30年度は現南橘市民サービスセンター所長と担当職員が勤務しており、それ以外の職員の勤務は確認できなかった。
オ 職員課がA職員に対して行った聴き取り調査において、「事前に時間外勤務命令を出した」、「B職員が確実に出られるかは分からなかったが、なるべく来るようにとはお願いした」、「地域づくりの副担当を養成するため」、「副担当の養成が課題であつた」、「B職員は、仕事への意欲があり、バイタリティーもある。副担当として、地域づくりの全体を見てもらいたいと考え、地域づくりフェスタヘの参加も要請した」、「時間外勤務として認めた時間帯については、当然、家族と一緒ではなかった」と回答していることを確認した。
カ 職員課が地域づくりフェスタに参加した職員(A職員、B職員及び担当職員を除く)に対して行った聴き取り調査において、「家族でイベント会場に来た」、「家族で遊びに来ているようにしか見えなかった」、「仕事をしているようには見えなかった」と回答していることを確認した。
(4) 病気体暇の取得に係る不正その④(以下「請求事項4」という。)について
ア B職員の休暇等承認簿(病気体暇、特別休暇等)により、平成29年7月18日から平成29年10月15日までの期間について、体暇等に関する条例第13条に規定する病気体暇を取得していることを確認した。
イ B職員の体暇等承認簿(病気体暇、特別体暇等)により、病気体暇の取得に当たっては、休暇等に関する条例第17条に規定する任命権者の承認を受けていることを確認した。なお、前橋市事務決裁規程(以下「事務決裁規程」という。)第4条に基づく別表第2の定めにより、病気体暇の承認の専決区分は市民部長であり、職員課長の合議が必要となるが、適正な決裁及び合議を受けていること、また、B職員が疾病のため、当該病気体暇を取得した期間について、安静療養する必要がある旨医師から診断を受けた診断書が添付されていることを確認した。
ウ B職員の休職発令に関する起案文書により、平成29年10月16日から平成29年12月31日までの期間について、地方公務員法第28条第2項第1号 の規定による休職が発令されていることを確認した。
エ 休職の発令に当たっては、事務決裁規程第4条に基づく別表第4の定めにより、総務部長の専決事項とされているが、B職員の休職発令に関する起案文書により、適正な決裁を受けていることを確認した。また、B職員が疾病のため、当該病気休職が発令された期間について、安静療養する必要がある旨医師から診断を受けた診断書が添付されていることを確認した。
オ B職員の給与等支給明細書において、病気体暇を取得している期間及び休職
<P7>
している期間の給与が支給されていることを確認した。
2 陳述等による事実確認
(1) 監査対象部局職員(職員課)の陳述による事実確認(職員課職員が陳述時に述べたことを要約して記載した。)
ア 請求事項1について、時間外勤務命令は取り消しとなったため、時間外勤務手当は支給されていない。そのため、不当な公金の支出には該当しないと考える。
イ 請求事項2について、時間外勤務手当は支給されたが、その後に判明した非違行為により、平成30年6月12日に取り消し、同月20日支給の給与から返還されているため、必要な措置は既に講じられていると考える。
ウ 請求事項3について、事前にA職員から口頭で出席するように命令されたものであり、 当日は家族で来訪したものの、 イベントの最中においては家族と離れ、イベントブースの案内や留守番などを行っていたことを確認した。イベントの担当者である職員が目撃したところによっても、家族と遊んでいるのではなく、イベントブースで手伝っていたというような証言が得られたことから、時間外勤務であると判断した。
エ 請求事項4について、病気休暇においては、医師の診断書に基づき、病気により従事不可能と判断された期間をもとに、休暇及び休職を承認している。今回のケースにおいても、同様に処理したものであり、休暇及び休職している間に支払われた給与については、制度に基づいて支払われたものであることから、不当な公金の支出には該当しないと考える。
(2) A職員に対する文書での聴き取り調査による事実確認(主に請求事項3についての確認内容)
ア 『B職員に対し時間外勤務命令を行った事実はあるか』の問に対して、「あります」との回答を得た。
イ 『命令を行った場合、いつ時間外勤務命令を行ったか』の問に対して、「口頭で16日 (金)に行い、時間外勤務等命令簿の処理は、週明けの19日(月)だったと記憶しております」との回答を得た。
ウ 『時間外勤務を命ずる際に、集合時間、終了時間、従事するべき業務内容、副担当養成のためである旨を伝えていたか。伝えていた場合、その具体的な指示内容を教えて欲しい』の間に対して、「集合時間の10時と、地域づくりフェスタの活動の様子と概要把握を伝えたと記憶しています」との回答を得た。
エ 『B職員は業務であることを認識していたか』の問に対して、「認識していたと思います」との回答を得た。
オ 『地域づくりフェスタヘの参加のほかに、地域づくり推進事業において、副担
<P8>
当の養成のために行ったことがあれば教えて欲しい』の問に対して、「地域づくりフェスタ以降、B職員は傷病(病気)休暇に入ってしまい、養成は行えませんでした」との回答を得た。
(3) B職員の陳述等による事実確認(B職員が陳述時に述べたことを要約して記載した。)
ア 請求事項1について、当日は時間外勤務の認識はなく、月末にその時の時間外勤務手当のことを知って、驚いて取り消した。なお、取り消した方法については、時間外勤務等命令簿を書き直した。
イ 請求事項2について、職員課の聴き取りがあり、誤った支給であったということが分かったので、職員課の指示に従って返還した。
ウ 請求事項3について、何かお手伝いがあればいいと思って行った。時間外勤務の認識はなく、何ができることがあればやろうと思い、実際に行ってお手伝いをやっていた。手伝っていたことを勤務と捉えたのは、A職員だと思う。
A職員からの参加の指示について、来られたら来てというようなことを言われたと思う。 時間外勤務手当の処理については、 私の全く知らないところである。
(4) B職員に対する文書での聴き取り調査による事実確認(全て請求事項3についての確認内容)
ア 『地域づくりフェスタヘの参加は任意であったか、または、参加を強制されるものであったか』の問に対して、「陳述で述べた通り、「来られたら来て」という言葉を任意での参加で良いととらえました」との回答を得た。
イ 『A職員から「来られたら来て」ということを言われたとしているが、その他に、地域づくりフェスタの活動の様子と概要把握をするように言われたか』の問に対して、「言われたかどうかについては覚えていないが、地域づくりフェスタに来たら、職員として全体の様子を把握してほしいと思う。活動の様子等を報告する必要があると思う」との回答を得た。
ウ 『開始時間と終了時間について、A職員から具体的な指示はあったか。または、自分の意思で参加する時間・帰る時間を決定できたか』の問に対して「正確に覚えていないが、始まりの時間は聞いていたと思う。午前中いっぱいと聞いていた」との回答を得た。
エ 『地域づくりフェスタ当日に、A職員から具体的な作業について指示や拘束があったか。もしくは、参加していた時間の全てについて自分の意思だけで行動できていたか』の問に対して、「関係者へあいさつするよう指示があった。その他はよく覚えていないが、他イベントに参加していた時は、全体の様子を見てイベント内容を把握するよう指示があるため、今回も色々なブースを見て来てと言わ
<P9>
れていたと思う」との回答を得た。
オ 『A職員は、地域づくりの副担当養成のためにB職員に対してイベント参加を促したと回答しているが、副担当養成についてA職員から話をされたことはあるか』の問に対して、『職員には事務分担に地域づくり事業の副担当がついており、そのことについて話をされたことはある。また、公民館事業のイベント等は把握しておきたいという考えがあったため、その他のイベントにも担当ではなくても参加していた」との回答を得た。なお、平成29年度の南橘市民サービスセンターにおける事務分掌において、嘱託職員と育児休暇明けの職員を除く全ての職員に地域づくり事業の副担当が割り当てられていたことを確認した。
カ 『地域づくりフェスタには家族で参加しているが、家族で行動を共にしたか』の間に対して、「一緒にフェスタに行った以上、行動を共にしていた時間はあった」との回答を得た。
(5) 南橘市民サービスセンターの職員のうち、平成29年度に在席していた職員を対象とした事情聴取による事実確認(事情聴取時に述べたことを要約して記載した。)
ア 地域づくりフェスタの担当職員
(ア) 『地域づくりフェスタでは、どのような業務に従事していたか』の問に対して、「出店のお手伝いから後片付けまで、イベント中の進行のお手伝いというのが業務であった」との回答を得た。
(イ) 『B職員は担当であったか』の問に対して、「担当ではない」との回答を得た。
(ウ) 『B職員が会場にいたのを見たか、また、業務をしていたか』の問に対して、「会場にいたのは確認している。テーブルの中に入って地域づくりのお手伝いをしていたのも確認している。ただ、いつ頃、どんなというのまで、私も動き回っていたので確認はしていない」との回答を得た。
(エ) 『B職員の当日の業務について、A職員から聞いていたか』の問に対して、「事前には聞いていなかった」との回答を得た。
(オ) 『週休日等に開催されるイベントで担当職員以外の職員が顔を出すというのはよくあることか』の問に対して、「大きな規模のイベントだと、担当職員以外の我々でも手伝いに出る」、「事前に業務命令がでて、役割もある」との回答を得た。
(カ) 『単に、イベントに行って少し手伝ったから超過勤務ということはないか』の問に対して、「それはないです」との回答を得た。
イ 平成28年度の地域づくりフェスタに参加した担当職員以外の職員
(ア) 『地域づくりフェスタについて、A職員から「来られる人は来て」という
<P10>
ような話を受けたことがあるか』の問に対して、「一昨年は受けたので、行きました」との回答を得た。また、その他に「参加した際は、少しお手伝いをしました」、「参加して手伝わないと来た意味がない」、「みんな顔見知りなので、大変そうな時は手伝った」との回答を得た。
(イ) 『手伝いをしたときに、時間外勤務の処理をしたか』の問に対して、「していないと思います」との回答を得た。なお、平成28年度の時間外勤務等命令簿において、該当する日の時間外勤務の記載がないことを確認した。
(ウ) 『「来られたら来て」というような声掛けについて、A職員は全員にしていたのか』の問に対して、「ホタル祭は、朝会のときに話はしていたが、地域づくりフェスタに関しては個別であり、全員ではない」との回答を得た。
(エ) 『ホタル祭、地域づくリフェスタについては、自由参加で時間外勤務ではない、これは一般的な考えでよいか』の問に対して、「少なくとも私はそう思います」との回答を得た。
1ウ 平成27年度の地域づくりフェスタ業務に従事した担当職員以外の職員
(ア) 平成27年度の地域づくりフェスタ業務に従事したことについて、「当時の担当職員から参加して欲しいという依頼があって参加した」、「自主的に時間外勤務を付けたわけではない」、「仕事という感覚で出勤しており、参加というより出勤である」との回答を得た。
(イ) 『平成27年度は参加して、平成28年度と平成29年度は参加していないが、その差は何か』の問に対して、「特に業務の依頼がなかったので、参加していない」との回答を得た。
(ウ) 『週休日等に開催されるイベントで担当職員以外の職員が顔を出すというのはよくあることか』の問に対して、「業務でないところに顔を出すことは基本的にはなく、人手が足りないので手伝いを業務依頼して出勤してもらうケースはある」との回答を得た。この回答を受けて『自ら進んで出た場合は自主参加であって、仕事ではないのか』との問に対して「はい」との回答を得た。
エ 平成29年度の地域づくりフェスタに参加した職員
(ア) 『地域づくりフェスタについて、A職員から「来られる人は来て」という話を受けたか』の問に対して、「受けていません」との回答を得た。
(イ) 『B職員が会場で何をしていたか、どのような行動をしていたか』の問に対して、「南橘地区のブースに来ていたのを見た」との回答を得た。
オ その他の職員
(ア) 『地域づくりフェスタについて、A職員から「来られる人は来て」という話を受けたか』の問に対して、「受けていません」との回答を得た。
<P11>
(イ) 『週休日等に開催されるイベントで担当職員以外の職員が顔を出すというのはよくあることか』の問に対して、「よくあります」、「顔を出すというよりは、仕事も割り当てられるので、もちろん勤務という形で時間外を付けます」との回答を得た。そして、『たまたま来て忙しそうだから手伝って、超過勤務だということはないか』の問に対しても、「そういうことはないです」との回答を得た。
第4 監査委員の判断
地方自治法第242条第1項は、住民監査請求について、普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員について、違法・不当な公金の支出等の財務会計上の行為又は違法・不当に公金の賦課・徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止・是正若しくは怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる旨を規定している。
本規定を踏まえて、これまでの事実関係の確認の結果、本件措置請求について次のとおり判断する。
1 請求事項1について
第3事実関係の確認1 (1) に記載のとおり、時間外勤務手当は支給されておらず、請求人がいう違法又は不当な財務会計上の行為の存在は認められなかったことから、地方自治法第242条第1項で規定する住民監査請求の要件を満たしていないものと判断する。
2 請求事項2について
第3事実関係の確認1 (2)、2 (1) イ、(3) イに記載のとおり、時間外勤務手当は支給されたが、その後、当該時間外勤務手当を市に返還したことが確認できたことから、当該時間外勤務手当の支給が違法又は不当であったか判断するまでもなく、地方自治法第242条第1項で規定する住民監査請求の要件を満たしていないものと判断する。
3 請求事項3について
時間外勤務については、前橋市職員服務規程(以下「服務規程」という。)第14条第1項で、職員は、所属長の命令があったときは、正規の勤務時間外、週休日又は休日等であっても、勤務に服さなければならない旨を規定している。また、服務規程第
<P12>
14条第4項では、所属長は、正規の勤務時間外、週休日又は休日等に勤務を命ずるときは時間外勤務等命令簿により行わなければならない旨を規定している。なお、本件において、所属長として命ずる者は、事務決裁規程第4条に基づく別表第2の定めにより出先の長であるA職員となる。
また、時間外勤務手当の支給については、労働基準法第37条第1項で、使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働について、割増賃金を支払わなければならない旨を規定している。さらに、前橋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条第1項で、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する旨を規定している。なお、一般職の地方公務員については、地方公務員法第58条第3項の規定により、労働基準法の適用を除外している規定を除いて労働基準法が適用されることから、労働基準法で規定する労働時間が、本件についても適用されるものと判断する。
本件において職員課は、第3事実関係の確認1 (3) アに記載のとおり、地域づくりフェスタに係るB職員の時間外勤務等命令簿が作成されていること、また、第3事実関係の確認1 (3) オに記載のとおり、時間外勤務を命ずる立場にあったA職員は、B職員に対し時間外勤務を命令したとする証言があったこと、さらには、第3事実関係の確認2 (1) ウに記載のとおり、イベントブースで手伝っていたとする担当職員の証言もあったことから、B職員が地域づくりフェスタにおいて時間外勤務として業務に従事したとすることについて、前述の服務規程に基づいた形式的な要件は整っていると判断し、勤務したとする時間に対して時間外勤務手当を支給したものである。
しかしながら、職員課の判断においては、第3事実関係の確認2 (3) ウに記載のとおり、B職員は業務としての認識がなかったこと、また、B職員の認識からは、A職員からB職員に対して時間外勤務命令があったと判断するには疑義が残ること、さらには、第3事実関係の確認1 (3) カに記載のとおり、担当職員以外で地域づくりフェスタに参加した職員が、B職員は「家族で遊びに来ているようにしか見えなかった」と証言していること、これらを踏まえたものとなっていない。
したがって、本件を判断する上で、時間外勤務等命令簿の作成などの形式的な要件のほかに、実際に業務としての勤務実態があったか否かについても考察する必要があると考える。
平成29年1月20日付けで厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」における労働時間の考え方をみると、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」としている。
<P13>
また、最高裁判例(平成12年3月9日/最高裁判所第一小法廷判決)においても、「労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めいかんにより決定されるべきものではない」として いる。
以上のことから、本件については、B職員が地域づくりフェスタに参加したこと及び当日行っていた行為が、客観的にA職員の指揮命令下に置かれていたと評価できるか、そして、それにより労働基準法上の労働時間に該当するか判断すべきものと考える。
そのためまず、B職員が地域づくりフェスタに参加することについて、一定の拘束を受けたことにより、指揮命令下に置かれていたと評価できるか考察する。
第3事実関係の確認2 (2) イに記載のとおり、A職員は、イベントの開催前に時間外勤務命令を口頭で行ったとしているにもかかわらず、時間外勤務等命令簿の処理を週明けに行っており、B職員が地域づくりフェスタに従事するか当日まで不確定な状態であったこと、さらには、第3事実関係の確認2 (3) ウに記載のとおり、「来られたら来て」という曖昧な表現からも推認できるように、地域づくりフェスタに従事するか否かを明確にせず、B職員に委ねていたことから、A職員はB職員に対して、地域づくりフェスタに従事することについて明確に時間外勤務を命令していたと考えることはできない。
また、明確な時間外勤務命令がされていない状況における労働時間について、高等裁判所判決(平成13年6月28日/大阪高等裁判所判決/確定)では、当該業務ヘの従事が常態的であり、それが特殊なものではないことと、業務への従事が義務付けられている性質のものであることを理由の一つとして、労働時間と評価する旨判示している。
そこで、 南橘市民サービスセンターにおける実際の時間外勤務の運用状況をみると、第3事実関係の確認2 (5) において、平成28年度の地域づくりフェスタに参加した担当職員以外の職員は、A職員の呼びかけに応じて、地域づくりフェスタに参加し手伝いをしたが、時間外勤務として処理していないこと、平成27年度の地域づくりフェスタに時間外勤務として従事した担当職員以外の職員は、事前に業務として指示を受け、業務として認識のもと従事していたこと、また、全ての南橘市民サービスセンターの職員が週休日等に開催されるイベントにおいて、担当職員以外の職員が従事することについては、事前に業務命令があり、時間外勤務として従事していたとして
<P14>
おり、自主参加は業務ではないという認識で一致していたことから、明確な時間外勤務の指示がなく、週休日等のイベントに参加したことを時間外勤務として取り扱うことは、南橘市民サービスセンターにおいて常態的ではなかったことが確認できた。
そのため、B職員がA職員から「来られたら来て」と言われたことに対して、当時の状況から業務として認識しなかったことは当然のことであり、また、担当職員以外のB職員が地域づくりフェスタに時間外勤務として従事することは、南橘市民サービスセンターにおいては特殊なものであり、先に述べたとおり、従事するか否か をB職員に委ねていた以上は、その従事は義務付けられていたものではなかったと推認できることから、A職員の指揮命令下に置かれていたと評価することはできない。
次に、B職員が地域づくりフェスタに従事するべき時間、遂行するべき業務内容により一定の拘束を受け、指揮命令下に置かれていたと評価できるか考察する。
最高裁判例(平成19年10月19日/最高裁判所第二小法廷判決)における、住み込みで勤務していたマンション管理員の日曜日及び祝日の休日労働ないし時間外労働の判断では、雇用契約において休日とされていた日曜日及び祝日については、指示されていた業務以外には労務の提供が義務付けられておらず、労働からの解放が保障されていたということができ、会社が指示したと認められる業務に現実に従事した時間に限り、休日労働又は時間外労働をしたものというべきである旨判示している。
これを本件についてみると、従事するべき時間については、第3事実関係の確認2 (4) ウに記載のとおり、B職員は、「始まりの時間は聞いていたと思う。午前中いっぱい」とする旨回答しているが、地域づくりフェスタヘの従事については、第3事実関係の確認2 (4) アに記載のとおり「任意での参加で良いと捉えた」と回答しており、あくまでイベントの開始時間等を伝えられたものと捉えたと推認できる。
また、遂行するべき業務内容については、第3事実関係の確認2 (4) イ、エに記載のとおり、A職員から地域づくリフェスタの活動の様子と概要把握をするように言われたか記憶しておらず、当日の具体的な指示について明確に記憶しているのは、関係者への挨拶だけであり、それ以外は過去の他のイベント参加時の様子をもとに本人が推測する程度のものであった。そのため、当日は、業務への従事及び業務内容について、関係者への挨拶以外はA職員からの明確な指示はなく、第3事実関係の確認2 (3) ウ、(4) オに記載のとおり、「何かお手伝いがあればいいと思って行った」、「公民館事業のイベント等は把握しておきたいという考えがあったため、その他のイベントにも担当ではなくても参加していた」と 回答しているように、全て本人の意思により行動していたものと推認できる。
したがって、A職員からの明確な指示があったものは関係者への挨拶という儀礼
<P15>
的な範囲のものだけであり、B職員は本人の意思で参加しイベントブースを手伝っていたのであって、当日の行為について労務の提供が義務付けられておらず、労働からの解放も保障されていたと推認できることから、A職員の指揮命令下に置かれていたと評価することはできない。
さらに、B職員が地域づくりフェスタに参加した際、第3事実関係の確認1 (3) カに記載のとおり、家族で来ていたとしているが、職員課は、第3事実関係の確認2 (1) ウに記載のとおり、家族で遊んでいるのではなく、イベントブースで手伝っていたとする証言が得られたとし、A職員も第3事実関係の確認1 (3) オに記載のとおり、時間外勤務として認めた時間帯については、当然、家族と一緒ではなかったとして、その適正性を判断している。
しかし、地方公務員は、地方公務員法第35条の規定により職務に専念する義務があり、それに反する家族との行動について、第3事実関係の確認2 (4) カ、(5) ア (ウ) に記載のとおり、担当職員もB職員の全ての行動を見ていない旨回答し、B職員も「一緒にフェスタに行った以上、家族と行動を共にしていた時間はあった」とする旨回答している。これらを踏まえると、地域づくりフェスタに参加すること又はイベントブースを手伝うことを時間外勤務として取り扱うのであれば、家族と共に行動した時間を業務として認めることは妥当ではない。さらには、当該時間を時間外勤務とするのであれば、指揮監督をするべきA職員は是正を求めなければならなかったところ、家族と行動を共にしていたことを把握、是正せずに、時間外勤務として全体を承認したことは適当ではなく、また一定の拘束を受けているとは言えず、そのような状況を踏まえても、A職員の指揮命令下に置かれていたと評価することはできない。
以上のことから、B職員が地域づくりフェスタに参加してイベントブースの手伝いなどを行った行為について、A職員の指揮命令下に置かれていたと評価することはできず、そのため、当該時間は労働基準法で定める労働時間ということはできないものであり、当該時間外勤務手当の支給は法令等の根拠に基づかない公金の支出であると判断する。
4 請求事項4について
病気体暇については、休暇等に関する条例第11条で職員の休暇とする旨を規定している。また、休暇等に関する条例第13条では、病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、市規則で定める期間内において必要と認められる期間とする旨を規定し、前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条において、
<P16>
その期間は、私傷病については90日以内とする旨を規定している。さらに、給与条例第11条において、休暇による場合は給与を減額しなぃ旨を規定している。
また、病気体職については、地方公務員法第28条第2項において、心身の故障のため、長期の体養を要する場合は、休職することができる旨を規定しており、前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(以下「分限に関する手続等に関する条例」という。)第9条第1項において、休職の期間は休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内において、 個々の場合について任命権者が定める旨を規定している。 そして、分限に関する手続等に関する条例第10条第2項において、休職者は、休職の期間中法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されないと規定しているが、給与条例第23条第3項において、私傷病により休職にされ たときは、その体職の期間が満1年に達するまでは給与等の100分の80を支給する旨を規定している。
これらを踏まえると、B職員が病気体暇を取得し、また、 休職することについて、第3事実関係の確認1 (4) に記載のとおり、それぞれ該当する期間について、医師から安静療養を要すると診断されており、それをもって、病気休暇の承認及び休職発令を行い、その期間中、給与等の支払をしたことについては、法令、条例、規則に基づいた適正な手続及び支給であり、また、その判断は決裁権者の裁量の範囲内と認められることから、違法若しくは不当な財務会計上の行為とする請求人の主張には理由がないものと判断する。
以上の判断により、本件措置請求において、請求事項1及び請求事項2については、住民監査請求できる要件を満たしていないため却下、請求事項4については、違法又は不当な財務会計上の行為とは認められず、請求に理由がないため棄却する。請求事項3については、請求に理由があると認められるため、地方自治法第242条第4項の規定により、市長に対して、次のとおり勧告する。
第5 勧告
B職員が、平成29年6月18日(日)に開催された地域づくりフェスタ業務に従事したとして時間外勤務手当を受給したことについて、 当該時間外勤務として認定した時間 は、労働基準法で定める労働時間と認定することができないと判断した。したがって、支給された時間外勤務手当は法令等の根拠に基づかない公金の支出であるため、B職員に対して当該時間外勤務手当を返還させる措置を講ずることを前橋市長に対して勧告する。
なお、地方自治法第242条第9項の規定に基づき、平成30年9月28日(金)までに講じた措置について通知することを求める。
<P17> `
第6 意見
監査の結果については以上であるが、本件請求における法令等の根拠に基づかない時間外勤務手当の支出が発生した要因を考察すると、南橘市民サービスセンターにおいては、時間外勤務命令等の処理に適切性を欠いていたことなどから、管理職をはじめとして、職員一人ひとりの時間外勤務制度の適正な運用に対する意識の欠如がその要因であったと考える。 また、 本件は出先機関である市民サービスセンターで発生した事案であるとともに、 時間外勤務命令の決裁が出先の長に認められ、同様の出先機関が多数存在する本市の現状 からも、本件を特殊なケースとして看過することはできないと考える。
これらのことから、出先機関における職員の時間外勤務に対する意識向上に努めること はもとより、全庁的にも、時間外勤務制度の更なる適正な運用に向けて、下記の事項に留意しながら、現行規程の見直しを含め必要な改善に取り組むことを要望するものである。
1 時間外勤務命令については、管理職において、当該勤務が真に必要なものか的確に判断するとともに、やむを得ない事情がある場合などを除き、事前の明確な命令を徹底すること
2 時間外勤務手当については、市民の税金を原資とした公金の支出であることを職員一人ひとりが再認識し、計画的かつ効率的な事務の執行に努めること
3 時間外勤務等命令簿の処理については、適時かつ正確に行うこと
4 出先機関における時間外勤務の履行確認について必要なチェック体制を整えること
**********
■どうやら部分的には不正申告による時間外手当分の返還を、当該職員に求める勧告を山本龍・前橋市長に対して行い、9月28日(金)までに、その措置内容について、監査委員に通知するよう求めたことがわかります。
しかし、返還の必要を認めたのは、2017年6月18日(日)の10時から正午までの時間外手当の2時間分のみであり、当会が陳述の際、今回の監査請求の追加対象として説明した同年5月4日(木・祝)の件は、まったく触れられていません。
また、今回の監査結果で、公民館で所長と部下が淫行をしていた2017年6月13日(火)の17:15~19:30に亘る時間外手当の不正給付については、当会が、今回の住民監査請求を行った2018年7月2日の直前の6月の給与を差し引く形で、返還済みであることが分かりました。
つまり前橋市は、一部の時間外手当については不正申告であることを自ら調査して、返還を求めたわけですが、それ以外の不正は、当会から指摘されて渋々、返還の必要性を認めざるを得なくなったのです。
それでも、当会から指摘された部分だけを調査の対象としているだけで、他にも不正申告が日常化していたことが伺われるのに、前橋市は少しも積極的に調査しようとする気概が見えてきません。
■今回の住民監査請求では、所長の不倫相手の若い職員のみが、不正申告を問われて、時間外手当の返還に追い込まれたわけですが、所長のほうは、なんのおとがめもありません。
驚かされるのは、2017年6月10日(土)の時間外手当の不正について、不倫相手の職員が「当日は時間外勤務の認識はなく、月末にその時の時間外勤務手当のことを知って、驚いて取り消した。なお、取り消した方法については、時間外勤務等命令簿を書き直した」と職員課に対して証言していることです。
つまり、自分の勤怠簿について、きちんと自分で記載しているのではなく、不倫相手の所長が代筆していることが伺えます。あるいは、もし自分で虚偽の記載をされていることが月末になって初めて分かったのであれば、所長が勝手に不倫相手の若い職員の印鑑を、勤怠簿に押印したり、時間外の期間を記入していたことになります。これは、明らかに有印私文書偽造ないし変造行為にあたります。
この所長は、自らの勤怠簿でも、用もないのに休日出勤して、不倫の時間をつくるために、それを平日の代休に振り替えるため、退職して不在の職員の同じ名字の印鑑を買って、それを使って不正に勤怠簿を改竄したため、文書偽造で警察沙汰になった経緯もあります。
おそらくこうした文書偽造行為を、この所長は日常的に行っていたはずですが、職員課には少しも調査する気配が見られず、このことは当会が陳述でも詳述したのですが、やはり監査委員もまったく関心がないことが、今回の監査結果で明らかになりました。
ほかにも、都合で長期に休みたい場合、医師の診断書があれば、役所では簡単に長期休暇が認められることも分かりました。これは安中市の公立碓氷病院を舞台にした勤怠情報の不正申告や、診療記録の不正記載の事件の当事者の理学療法士の場合も、不正発覚直後に、同様に、精神的なストレスを理由に意思から診断書を出してもらい、それを役所に提出して3か月間自宅療養をしていました。
この間、我々の血税が給与として支払われていたと思うと、まことに複雑な思いがいたします。
■この監査結果を受けて、当会としてどのような対応を取るか、9月28日までに決定する必要があります。次回、9月15日の当会の定例会で、参加者の皆さんと協議の上、方針を決める所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】














