■次回第3回口頭弁論期日を1週間後に控える4月7日(金)付で、被告である群馬高専=国立高専機構の訴訟代理人弁護士事務所から、準備書面と関連する証拠説明書及び乙号証が当会事務局に郵送されてきました。1ヶ月も時間を要した割には、内容の薄い準備書面なので、あきらかに時間稼ぎという感が否めません。
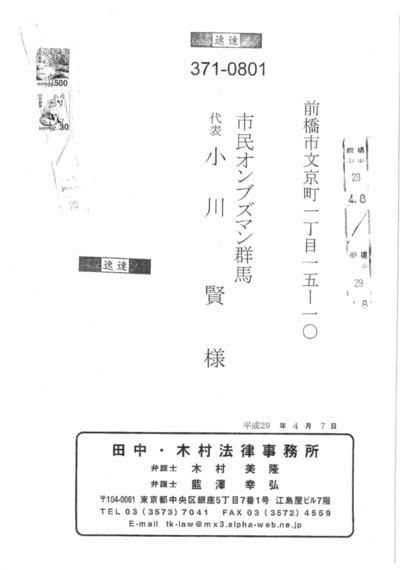
↑4月8日に当会事務局に届いた被告群馬高専=国立高専機構からの準備書面等が同封された封筒。↑
西尾校長の意を組んだ弁護士が時間稼ぎをしたおかげで、群馬高専では人事異動により新校長に代わってしまいました。今回の準備書面の内容についても、どの程度新校長のハラスメント事件に関する見解や再発防止対策に向けた新体制下の学校の対処方針が反映されているのか、判断に苦しむところです。
というのは、今回、裁判長の訴訟指揮により、保護者に向けた学校からの通知のチラシについて被告群馬高専=国立高専機構は、ほぼ黒塗り状態の文書を渋々提出してきましたが、その他のアカハラ事件関連文書は、個人識別情報とアカハラ事件の様子が表裏一体で区分できないから、という被告にとって都合の良い論理を盾に、一切開示を拒否する主張を出して来たからです。
それに、4月7日という被告準備書面の発出のタイミングが、本当に群馬高専の山崎新校長がアカハラ問題を問うこの裁判に向けた新体制のメッセージを反映したものであるのかどうか、確証がないからでもあります。
ちなみに、本日現在、群馬高専のHPの校長からのメッセージのコラムには、依然として「校長メッセージ 平成29年4月、山崎 誠(やまざき まこと)が校長として着任いたしました。準備が整い次第、本ページを更新します。」と書かれたままです。
■それでは、4月8日に当会事務局に届けられた被告準備書面を見てみましょう。
*****被告からの準備書面送付書*****PDF ⇒ 201704071t.pdf
準備書面等の送付書
平成29年4月7日
下記のとおり書類をご送付いたします。
受領書棚に記名・押印のうえ、この書面を当職及び裁判所宛FAX等でお送り下さい。
送付先 東京地方裁判所民事第3部B2係 御中
FAX 03-3580-5706
原 告 市民オンブズマン群馬 御中
FAX 027-224-6624
発信者 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
被告訴訟代理人弁護士 木 村 美 隆
TEL:03-3573-7041 FAX:03-3572-4559
事件番号 平成28年(行ウ)第499号
当事者名 原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 独立行政法人国立高等専門学校機構
次回期日 平成29年4月↓4日(金)午前11時30分
文 書 名 準備書面・証拠説明書(H29.4.7付)、乙第3号証の1~第5号証の3
送信枚数 枚 (送信書を除く)
相手方への送達の有無 有
受 領 書
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中 (FAX:03-3580-5706)
被告訴訟代理人 弁護士 木村美隆 宛 (FAX:03-3572-4559)
上記書類を受領しました。
平成 年 月 日
原 告 市民オンブズマン群馬
通信欄
*****被告準備書面*****PDF ⇒ 201704072.pdf
<P1>
平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件
原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 独立行政法人国立高等専門学校機構
準 備 書 面
平成29年4月7日
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中
被告訴訟代理人弁護士 木 村 美 隆
同 藍 澤 幸 弘
記
原告の準備書面(1)について
原告の準備書面(1)のうち,原告の開示請求①ないし③に対する被告の不開示決定処分との関係で必要と解される部分について,以下反論する。
1 法5条1号ロについて
(1)原告は,「ハラスメントにより被害者がうつ病になったり,中には自殺しかねない精神状況に追い込まれたりする場合もあるわけだから,当然,被害者(ママ)のプライバシー保護より,被害者の生命・健康等の保護が大切であることは自明の理である」とする(準備書面2頁)。
(2)しかし原告の上記指摘は,一般論にすぎず,その内容が当をえているかどう
<P2>
かにも議論の余地があろう。これに対し,本件開示請求にかかる文書が,法5条1号ロの[人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報]が不開示の除外事由に当たるかどうかの判断は,当該情報にかかる個人の権利利益よりも,人の生命,健康,生活又は財産の保護の必要性が上回るかどうか,という比較衡量によることは答弁書(4頁)で指摘したとおりであり,この比較衡量は,文書に記載のある特定の対象者の利益と,開示により生命等を保護される具体的な関係者の利益との比較衡量となることは,きわめて当然である。
ハラスメントに係る事実の有無が,加害者とされる側,被害者とされる側双方にとってプライバシーのなかでも秘匿性の高い情報であること,これに対して,ハラスメントの事実の有無の調査等は人事管理に関する事項として被告ないし群馬高専が対応すべき事柄であり,文書開示と生命等の保護に関連性がないか,きわめて低いことは,上記の具体的な比較衡量にもとづく主張であり,文書を非開示とすることによりハラスメント事案を隠蔽しようとしているとの原告の指摘は,まったく当たらない。
開示請求①から③にかかる文書にはハラスメントとされる申告の対象となっている者の所属先や,申告者の属性,申告の経緯や申告された事実の概要,群馬高専の調査方法と申告対象となった者への対応の概要が記載されている。さらに開示請求②及び③にかかる文書には,申告者とハラスメントとされる行為を行った者(被申告者)の所属先,氏名,ハラスメントとされる行為に至った経緯,申告者と被申告者との関係,ハラスメントとされる行為の具体的な内容,時期,頻度,申告者が説明する被害の内容,申告者が見聞きした,申告者以外を対象とするハラスメントとされる行為の内容や相手方の氏名,所属が具体的に記載され,開示請求③にかかる文書には,これらに加えて関係当事者からの聴取内容が実名で記載されている。
これらの記載は,ハラスメントの被害者とされる者を含めた各関係者のプライ
<P3>
バシーに関連する情報であることは明らかであり,群馬高専という教育機関での出来事であることからしても,原告の情報公開請求に応じて対象情報を開示することは,関係者のプライバシー保護や学生の健全な育成を期するという少年保護観点から相当でないことは明らかである。また,被申告者との関係でいえば,申告された行為がハラスメントと認定された場合には,対象者の勤務態度,個人の資質や処分歴等の名誉に関わる情報となり得るのであり,本人としては一般的にこれを他人に知られたくないと望み,そのように望むことが正当の理由のあるもの(当会注:本件のアカハラ事件は「一般的に」というレベルで括れるような生易しいものではないことを被告は強く認識すべきだ)として,みだりに公開されるべきではない情報となる(東京地,平10.11.12判,判タ1003号171頁。乙4)。この点は,ハラスメントに該当するとして懲戒処分の対象となった場合だけでなく,ハラスメントの嫌疑を掛けられたにすぎない場合(当会注:被害者が続出しているのにハラスメントの嫌疑などと言っていること自体、被告群馬高専がアカハラ事件について強い隠ぺいの意思を持っていることが分かる)にも同様に当てはまると解される。
以上からすれば,原告の開示請求①から③にかかる文書は,いずれも個人に関する情報としての不開示情報(法5条1号柱書)が記録された文書であり,被告の不開示決定処分に違法性はない。
(3)なお,被告及び群馬高専では,教職員を懲戒処分にした場合にはその旨の情報を提供することとなっているところ(乙3の1及び2),平成26年4月以降に群馬高専のハラスメント事案に関して情報提供を実施した事実はない(甲6の1,6頁3行目,「また,当審査会事務局職員をして(以下略)」の段落参照)。このことからも,開示請求①から③に係る書面には,懲戒処分となりうるようなハラスメントの事実は記載されていないことが伺われる(当会注:どうやら群馬高専ではあれだけ深刻なアカハラ事件の発生にもかかわらず懲戒処分レベルと見なしていないらしい。自ら懲戒書分を不作為にしておいて、この言い草は普通の感覚ではありえない)のであり,同書面には「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」は記載されていないことは,この点からも明らかである。
2 法5条1号ハについて
(1)原告は,要旨,法5条1号ハは,公務員(ママ,以下略)の職務執行情報報の
<P4>
開示の重要性を定めており,公務員の職務執行状況をきちんと国民に知らせることにより,公務員の職務の健全陛や遵法性を担保することが大切である,という趣旨の規定であり,この観点からすれば,開示請求①から③にかかる文書は,法5条1号ハの適用を受ける,と主張する(原告準備書面(1)4頁)。
(2)しかし,開示請求の対象文書が公務員が職務上作成したものであり,その内容が公務員の公務に関連する情報であったとしても,当該情報の内容によっては,「個人に関する情報」に該当することは,前記裁判例のとおりであり(乙4),この裁判例の判断は独立行政法人の職員が職務上作成した文書についてもそのまま当てはまるものである。
開示請求①から③にかかる文書が,個人に関する情報としての不開示情報(法5条1号柱書)が記載されたものであり,被告がこれを理由として不開示決定処分をしたことは前記のとおりである。原告は開示請求①から③にかかる文書が,公務員が職務上作成した文書であることを主張するが,公務員が職務上作成した文書であることと,当該文書に個人に関する情報としての不開示情報が含まれることは両立しうるのであり,原告の主張は失当と言うほかない。
2 部分開示について
(1)原告は,開示請求②に含まれるであろう情報として,「名前・生年月日といったイ固人情報」と,「アカデミックハラスメント事件の存在及び経緯に関する情報」については容易に分離可能であり,法6条の除外事由に当たらないものとして,部分開示を実施すべきと主張する。
(2)まず,原告の言う前記の「アカデミックハラスメント事件の存在及び経緯に関する情報」も,その他の記載等と相まって不開示情報としての個人に関する情報に該当することを指摘しておく。
<P5>
部分開示は,「法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき」(法6条1項)を要件としている。
しかし,開示請求②にかかる文書は,申告者が,被申告者のハラスメント行為とされる行為の内容やその経緯,申告者の説明する被害内容や,他の当事者に関するハラスメントとされる行為の内容が記載(当会注:アカハラ事件の被害者が勇気を振り絞って校長に事件の態様と被害の深刻さを通報して善処を要請したのに、個人の問題として矮小化しようとする学校側の思惑が見え隠れする)されており,個人に関する情報に係わらない部分の記載はない。
開示請求③にかかる文書も,関係者から聴取した結果として,ハラスメントとされる行為の経過や当事者が記載されていることは,上記開示請求②にかかる文書と同様である。開示請求③にかかる文書には,このほか調査に至った経緯や調査担当者,調査方法と調査結果に関する記載があるが、これらにも関係当事者の氏名や具体的な聴取内容が記載されており,個人に関する情報が渾然一体となって記載されているので,不開示情報が記録されている部分を容易に区分することはできない。また,開示請求③にかかる文書は,法5条4号へ「人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」のある情報が記載された文書であり,その記載はいずれも人事管理に関する事項として一体の内容をなすものであるから,記載内容はいずれも人事管理に関する不開示情報に該当すると解すべきである。
他方,開示請求①にかかる文書には,ハラスメントの加害者及び被害者とされる者の属性(所属)や,群馬高専において行った調査の期間及び概要と,学校としての対象者への対応状況が明記されているが,他に一般論として,学校としてのハラスメントに対する対応方針が記載された部分もある。後者については,個人に関する情報に係わらないものと解されるものの,「アカデミックハラスメント事件の存在及び経緯に関する情報」に関する情報公開という,原告の開示請求の趣旨からすれば,上記の後者の部分のみの開示で有意性(法6条1項但書)があるか疑問であるが,念のため不開示情報に該当する部分を抹消して,書証とし
<P6>
て提出する(乙5の1から3)。
この乙5号証の1から3により,原告が開示請求①について部分開示を請求する点については,原告は訴えの利益を喪失すると考えられるので,原告の訴状,請求の趣旨1項①に対して,予備的に請求の却下を求める。
以上
*****被告証拠説明書*****PDF ⇒ 201704073i35j.pdf
平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分決定取消請求事件
原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 独立行政法人国立高等専門学校機構
証拠説明書
平成29年4月7日
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中
被告訴訟代理人弁護士 木 村 美 隆
同 藍 澤 幸 弘
記
●号証:乙3の1
〇標目:独立行政法人国立高等専門学校機構教職員懲戒規則
〇原本・写:写
〇作成年月日:H25.7.29
〇作成者:被告
〇立証趣旨;被告の規定上,教職員を懲戒処分とした場合には,その旨の情報が原則として公開されることになっていること(開示請求①ないし③にかかる文書には,懲戒対象となる情報が記載されていないこと)
●号証:乙3の2
〇標目:独立行政法人国立高等専門学校機構における懲戒処分の公表基準
〇原本・写:写
〇作成年月日:H23.4.21
〇作成者:被告:
〇立証趣旨:同上
●号証:乙4
〇標目:裁判例(東京地方裁判所判決平成10年11月12日)
〇原本・写:写
〇作成年月日:H28.5
〇作成者:株式会社ウェストロージャパン
〇立証趣旨:ある事実がハラスメントに該当するかどうかは,対象者の勤務態度,個人の資質や処分歴等の名誉に関わる情報となり得るものとして,みだりに公開されるべきではない情報となること
●号証:乙5の1から3
〇標目:保護者宛書面
〇原本・写:写
〇作成年月日:H27.4.1,H27.6.2
〇作成者:群馬高専校長 西尾典眞
〇立証趣旨:開示請求③にかかる文言のうち,不開示情報と区分して部分開示が可能と解される余地がある箇所の内容について
*****乙3の1*****PDF ⇒ 201704074131.pdf
<P1>
独立行政法人国立高等専門学校機構教職員懲戒規則
独立行政法人国立高等専門学校機構規則第30号
平成16年4月1日
一部改正 平成18年4月4日
一部改正 平成25年7月29日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則(独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)規則第6号。以下「教職員就業規則」という。)第48条及び第49条第2項並びに独立行政法人国立高等専門学校機構船員就業規則(機構規則第7号。以下「船員就業規則」という。)第52条及び第53条第 2項の規定に基づき,機構の教職員の懲戒並びに訓告及び厳重注意(以下「訓告等」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 懲戒
(懲戒処分の原則)
第2条 理事長は,教職員就業規則第47条及び船員就業規則第51条に規定する懲戒の事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する行為でなければ,教職員に対し,懲戒処分を行うことができない。
2 教職員は,懲戒処分を受けた事案について,重ねて懲戒処分又は訓告等を受けない。
3 理事長は,第4条に定める懲戒審査委員会の審査を経て,懲戒処分を行うものとする。
ただし,懲戒の事由に該当することが客観的に明らかであって,かつ,緊急に懲戒解雇を行う必要がある場合に限り,懲戒審査委員会の審査を経ないで懲戒処分を行うことができる。
(処分量定)
第3条 懲戒処分の種類及び程度(以下この章において「処分量定」という。)の決定に当たっては,次に掲げる事項を総合的に考慮のうえ,相当なものとしなければならない。
一 懲戒事由に該当すると思料される非違行為(以下この章において「非違行為」という。)の動機,態様及び結果
二 故意又は過失の程度
三 非違行為を行った教職員の職責並びに職責及び非違行為の関連
四 他の教職員及び社会に与える影響
五 過去の非違行為の有無
<P2>
六 日頃の勤務態度及び非違行為後の対応
七 その他処分量定の決定に当たって,考慮すべき事項
(懲戒審査委員会)
第4条 理事長は,懲戒処分に関する審査を行うため,その指名する者により懲戒審査委員会を設置する。
2 懲戒審査委員会は,公正かつ中立な立場で,次に掲げることを行う。
一 非違行為の存否及び内容を調査すること。
二 処分量定を審査すること。
三 その他懲戒処分を行う上で必要な事項の審査等を行うこと。
3 懲戒審査委員会は,懲戒審査委員会へ参考人の出席を求め,又はその意見を徴することができる。
(弁明の機会の付与)
第5条 懲戒審査委員会は,処分量定の審査を行う前に,対象となる教職員に次に掲げる事項を記載した書面を交付し,弁明の機会を与えなければならない。ただし,対象となる教職員の所在を知ることができない場合はこの限りではない。
一 対象となる教職員の所属及び氏名
二 非違行為の内容
三 口頭弁明の日時及び場所スは弁明書の提出期日
(懲戒処分書)
第6条 懲戒処分を行うに当たってば,対象となる教職員に懲戒処分書を交付しなければならず,その懲戒処分の効力は,懲戒処分書を当該教職員に交付したときに発生する。
2 懲戒処分書は,別紙様式1のとおりとし,処分の内容欄には,当該処分に応じて次の各号に掲げる事項を記入するものとする。
一 懲戒解雇する場合 「 (教職員就業規則第47条又は船員就業規則第51条に掲げる該当号を表示)により,懲戒処分として,解雇する。」
二 諭旨解雇する場合 「 (教職員就業規則第47条又は船員就業規則第51条に掲げる該当号を表示)により,懲戒処分として,諭旨解雇する。」
三 停職する場合 「 (教職員就業規則第47条又は船員就業規則第51条に掲げ
る該当号を表示)により,懲戒処分として, 月(日)間停職する。」
四 減給する場合 「 (教職員就業規則第47条又は船員就業規則第51条に掲げる該当号を表示)により,懲戒処分として, 月分給与のうち 円を減給する。」
五 戒告する場合「 (教職員就業規則第47条又は船員就業規則第51条に掲げる該当号を表示)により,懲戒処分として戒告する。」
3 懲戒処分書を受けるべき教職員の所在を知ることができない場合においては,第1項の規定にかかわらず,その内容を民法(明治29年法律89号)第98条第2項に定める方法によって公示することによって懲戒処分の意思表示を行う。この場合において,民法第98条第3項の規定により,公示された日から2週間を経過したときに懲
<P3>
戒処分書の交付があったものとみなす。
(処分説明書)
第7条 懲戒処分を行うに当たっては,懲戒処分書のほか処分説明書を併せて交付するものとする。
2 処分説明書は,別紙様式2のとおりとする。
(減給)
第8条 減給は,懲戒処分の効力が発生した日の直後の給与の支給目に支給される給与から減ずるものとする。ただし,効力が発生した日とその直後の給与の支給日とが近接している場合には,その翌月の給与の支給日から減ずるものとする。
(停職)
第9条 停職の期間は,1日以上1年以下とする。
2 停職の期間の計算は,暦日計算による。
3 停職の期間の起算日は,処分の効力発生日の翌日とする。
(不服申立て)
第10条 懲戒処分を受けた教職員は,その処分について不服があるときは,理事長に対して,懲戒処分書及び処分説明書を受領した日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをすることができる。
2 理事長は,前項の不服申立てがあった場合,その翌日から起算して30日以内に回答するものとする。
(刑事裁判との関係)
第11条 理事長は,非違行為が刑事裁判所に係属する間においても,同一事件について,懲戒の手続を進めることができる。
(再雇用教職員)
第12条 教職員就業規則第24条又は船員就業規則第25条の規定により再雇用される教職員(以下「再雇用教職員」という。)が,再雇用前の在職期間中に教職員就業規則第47条又は船員就業規則第51条に規定する懲戒の事由に該当した場合には,当該再雇用教職員に対し教職員就業規則第46条又は船員就業規則第50条の規定に基づき懲戒処分を行うことができる。
(期間を定めて雇用される教職員)
第13条 期間を定めて雇用される教職員の停職及び減給は,現に雇用されている期間内
に限られるものとする。
(公表)
<P4>
第14条 理事長は,管理運営の透明性を確保するとともに,教職員の服務に関する自覚を促し,不祥事の再発防止に資するため,別に定める基準により,懲戒処分事案について公表することがある。
第3章 訓告等
(訓告等の原則)
第15条 教職員は,訓告等を受けた事案について,懲戒処分又は訓告等を重ねて受けない。
2 訓告は,文書により,厳重注意は,文書又は口頭により行うものとする。
(量定)
第16条 訓告等の種類及び程度(以下この章において「量定」という。)の決定に当たっては,次に掲げる事項を総合的に考慮のうえ,相当なものとしなければならない。
一 訓告等に該当すると思料される非違行為(以下この章において「非違行為」という。)の動機,態様及び結果
二 故意又は過失の程度
三 非違行為を行った教職員の職責並びに職責及び非違行為の関連
四 他の教職員及び社会に与える影響
五 過去の非違行為の有無
六 日頃の勤務態度及び非違行為後の対応
七 その他量定の決定に当たって,考慮すべき事項
(訓告等審査委員会)
窮17条 理事長は,訓告等に関する審査を行うため,その指名する者により訓告等審査委員会を設置することができる。
2 訓告等審査委員会は,公正かつ中立な立場で,次に掲げることを行う。
― 非違行為の存否及び内容を調査すること
二 量定を審査すること
三 その他訓告等を行う上で必要な事項の審査等を行うこと
3 訓告等審査委員会は,訓告等審査委員会へ参考人の出席を求め,又はその意見を徴することができる。
(弁明の機会の付与)
夥18条 訓告等審査委員会(訓告等審査委員会を設置しない場合においては,理事長)は,量定の審査を行う前に,対象となる教職員に次に掲げる事項を記載した書面を交付し,弁明の機会を与えなければならない。ただし,対象となる教職員の所在を知ることができない場合はこの限りではない。
一 対象となる教職員の所属及び氏名
<P5>
二 非違行為の内容
三 口頭弁明の日時及び場所又は弁明書の提出期日
(文書)
第19条 訓告等(口頭によるものを除く)を行うに当たっては,対象となる教職員に文書を交付しなければならず,その訓告等の効力は,文書を当該教職員に交付したときに発生する。
2 前項における文香は,別紙様式3のとおりとする。
3 第1項の文書を受けるべき教職員の所在を知ることができない場合においては,同項の規定にかかわらず,その内容を民法第98条第2項に定める方法によって公示することによって訓告等の意思表示を行う。この場合において,民法第98条第3項の規定により,公示された日から2週間を経過したときに当該文書の交付があったものとみなす。
(刑事裁判との関係)
第20条 理事長は,非違行為が刑事裁判所に係属する間においても,同一事件について,訓告等の手続を進めることができる。
(再雇用教職員)
第21条 再雇用教職員が,再雇用前の在職期間中に訓告等の事由に該当した場合には,当該再雇用教職員に対し教職員就業規則第49条又は船員就業規則第53条の規定に基づき,訓告等を行うことができる。
第4章 雑則
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,教職員の懲戒処分に関し必要な事項は,理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条による懲戒処分を受けた者については,なお従前の例により,同条第1項各号に規定する事由に該当していた場合で,教職員就業規則第47条各号又は船員就業規則第51条各号と同様の事由に該当し,まだ処分を受けていないときは,機構の教職員として処分を行う。
<P6>
3 前項の規定は,訓告等を行う場合に準用する。
附 則
(施行期日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月29日一部改正)
この規則は,平成25年8月1日から施行する。
*****乙3の2*****PDF ⇒ 201704074232.pdf
独立行政法人国立高等専門学校機構における懲戒処分の公表基準
平成23年4月21日
理 事 長 裁 定
1 目的
独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)における懲戒処分事案を公表することにより,機構の管理運営の透明性を確保するとともに,教職員の服務に関する自覚を促し,不祥事の再発防止に資することを目的とする。
2 公表の対象とする懲戒処分事案
教職員に対し懲戒処分を行った事案で,次のいずれかに該当する懲戒処分は,公表するものとする。
(1)職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(独立行政法人国立高等専門学校機構教職員倫理規則(機構規則第25号)に違反したことを理由としたものを含む。)
(2)職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職である懲戒処分
3 公表する内容
事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,役職段階等の被処分者の属性に関する情報を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。ただし,個別の事案に関し,当該事案の社会的影響,被処分者の職責等を勘案して,別途の取扱いをすることがある。
1 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等2及び3によることが適当でないと認められる場合は,2及び3にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないこともあることとする。
5 公表の時期及び方法
2の懲戒処分事案については処分発令後,処分者が速やかに公表するものとし,公表の方法は,原則として関係記者会等への資料配付及び各高専(理事長が懲戒処分を行った場合にあっては機構本部)のホームページヘの掲載によるものとする。
なお,特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については記者会見を行う。
**********
■被告は、今回のアカハラ事件では原因者の学科長を懲戒処分にした経緯はないから、事件について公表する義務はなく、事件に関する情報公開請求についても、同様に公開する責務はないと主張しています。しかし、これは自らの不作為を糊塗するものに過ぎません。
本来であれば、これだけ深刻なアカハラ事件を引き起こしたのだから、被害者からの直訴を受けて、直ちに懲戒処分をするのが校長の義務のはずです。
それなのに加害者をかばうことを優先し、懲戒処分もせずに、学科長の任務を解いただけで放任した校長の責任は、どこにも被告の準備書面で触れられていません。
このことから見ても、今回の準備書面は、西尾典眞・前校長の意向が反映されたまま、原告の当会に出されてきたのではないか、つまり、前校長の最後っ屁の準備書面ではないか、というのが当市民オンブズマン群馬の見方です。
引き続き、被告から準備書面と一緒に出されてきた乙号証をこの後、見ていきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この記事➁へと続く】
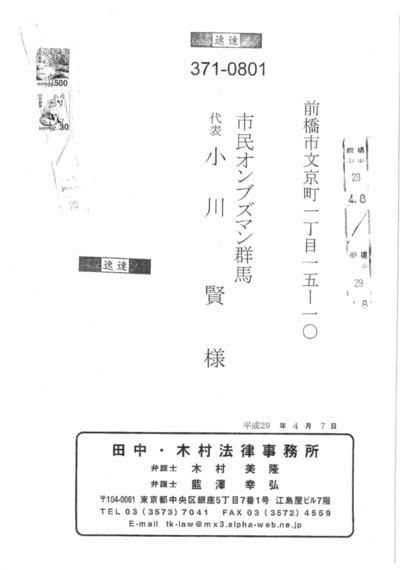
↑4月8日に当会事務局に届いた被告群馬高専=国立高専機構からの準備書面等が同封された封筒。↑
西尾校長の意を組んだ弁護士が時間稼ぎをしたおかげで、群馬高専では人事異動により新校長に代わってしまいました。今回の準備書面の内容についても、どの程度新校長のハラスメント事件に関する見解や再発防止対策に向けた新体制下の学校の対処方針が反映されているのか、判断に苦しむところです。
というのは、今回、裁判長の訴訟指揮により、保護者に向けた学校からの通知のチラシについて被告群馬高専=国立高専機構は、ほぼ黒塗り状態の文書を渋々提出してきましたが、その他のアカハラ事件関連文書は、個人識別情報とアカハラ事件の様子が表裏一体で区分できないから、という被告にとって都合の良い論理を盾に、一切開示を拒否する主張を出して来たからです。
それに、4月7日という被告準備書面の発出のタイミングが、本当に群馬高専の山崎新校長がアカハラ問題を問うこの裁判に向けた新体制のメッセージを反映したものであるのかどうか、確証がないからでもあります。
ちなみに、本日現在、群馬高専のHPの校長からのメッセージのコラムには、依然として「校長メッセージ 平成29年4月、山崎 誠(やまざき まこと)が校長として着任いたしました。準備が整い次第、本ページを更新します。」と書かれたままです。
■それでは、4月8日に当会事務局に届けられた被告準備書面を見てみましょう。
*****被告からの準備書面送付書*****PDF ⇒ 201704071t.pdf
準備書面等の送付書
平成29年4月7日
下記のとおり書類をご送付いたします。
受領書棚に記名・押印のうえ、この書面を当職及び裁判所宛FAX等でお送り下さい。
送付先 東京地方裁判所民事第3部B2係 御中
FAX 03-3580-5706
原 告 市民オンブズマン群馬 御中
FAX 027-224-6624
発信者 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
被告訴訟代理人弁護士 木 村 美 隆
TEL:03-3573-7041 FAX:03-3572-4559
事件番号 平成28年(行ウ)第499号
当事者名 原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 独立行政法人国立高等専門学校機構
次回期日 平成29年4月↓4日(金)午前11時30分
文 書 名 準備書面・証拠説明書(H29.4.7付)、乙第3号証の1~第5号証の3
送信枚数 枚 (送信書を除く)
相手方への送達の有無 有
受 領 書
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中 (FAX:03-3580-5706)
被告訴訟代理人 弁護士 木村美隆 宛 (FAX:03-3572-4559)
上記書類を受領しました。
平成 年 月 日
原 告 市民オンブズマン群馬
通信欄
*****被告準備書面*****PDF ⇒ 201704072.pdf
<P1>
平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件
原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 独立行政法人国立高等専門学校機構
準 備 書 面
平成29年4月7日
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中
被告訴訟代理人弁護士 木 村 美 隆
同 藍 澤 幸 弘
記
原告の準備書面(1)について
原告の準備書面(1)のうち,原告の開示請求①ないし③に対する被告の不開示決定処分との関係で必要と解される部分について,以下反論する。
1 法5条1号ロについて
(1)原告は,「ハラスメントにより被害者がうつ病になったり,中には自殺しかねない精神状況に追い込まれたりする場合もあるわけだから,当然,被害者(ママ)のプライバシー保護より,被害者の生命・健康等の保護が大切であることは自明の理である」とする(準備書面2頁)。
(2)しかし原告の上記指摘は,一般論にすぎず,その内容が当をえているかどう
<P2>
かにも議論の余地があろう。これに対し,本件開示請求にかかる文書が,法5条1号ロの[人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報]が不開示の除外事由に当たるかどうかの判断は,当該情報にかかる個人の権利利益よりも,人の生命,健康,生活又は財産の保護の必要性が上回るかどうか,という比較衡量によることは答弁書(4頁)で指摘したとおりであり,この比較衡量は,文書に記載のある特定の対象者の利益と,開示により生命等を保護される具体的な関係者の利益との比較衡量となることは,きわめて当然である。
ハラスメントに係る事実の有無が,加害者とされる側,被害者とされる側双方にとってプライバシーのなかでも秘匿性の高い情報であること,これに対して,ハラスメントの事実の有無の調査等は人事管理に関する事項として被告ないし群馬高専が対応すべき事柄であり,文書開示と生命等の保護に関連性がないか,きわめて低いことは,上記の具体的な比較衡量にもとづく主張であり,文書を非開示とすることによりハラスメント事案を隠蔽しようとしているとの原告の指摘は,まったく当たらない。
開示請求①から③にかかる文書にはハラスメントとされる申告の対象となっている者の所属先や,申告者の属性,申告の経緯や申告された事実の概要,群馬高専の調査方法と申告対象となった者への対応の概要が記載されている。さらに開示請求②及び③にかかる文書には,申告者とハラスメントとされる行為を行った者(被申告者)の所属先,氏名,ハラスメントとされる行為に至った経緯,申告者と被申告者との関係,ハラスメントとされる行為の具体的な内容,時期,頻度,申告者が説明する被害の内容,申告者が見聞きした,申告者以外を対象とするハラスメントとされる行為の内容や相手方の氏名,所属が具体的に記載され,開示請求③にかかる文書には,これらに加えて関係当事者からの聴取内容が実名で記載されている。
これらの記載は,ハラスメントの被害者とされる者を含めた各関係者のプライ
<P3>
バシーに関連する情報であることは明らかであり,群馬高専という教育機関での出来事であることからしても,原告の情報公開請求に応じて対象情報を開示することは,関係者のプライバシー保護や学生の健全な育成を期するという少年保護観点から相当でないことは明らかである。また,被申告者との関係でいえば,申告された行為がハラスメントと認定された場合には,対象者の勤務態度,個人の資質や処分歴等の名誉に関わる情報となり得るのであり,本人としては一般的にこれを他人に知られたくないと望み,そのように望むことが正当の理由のあるもの(当会注:本件のアカハラ事件は「一般的に」というレベルで括れるような生易しいものではないことを被告は強く認識すべきだ)として,みだりに公開されるべきではない情報となる(東京地,平10.11.12判,判タ1003号171頁。乙4)。この点は,ハラスメントに該当するとして懲戒処分の対象となった場合だけでなく,ハラスメントの嫌疑を掛けられたにすぎない場合(当会注:被害者が続出しているのにハラスメントの嫌疑などと言っていること自体、被告群馬高専がアカハラ事件について強い隠ぺいの意思を持っていることが分かる)にも同様に当てはまると解される。
以上からすれば,原告の開示請求①から③にかかる文書は,いずれも個人に関する情報としての不開示情報(法5条1号柱書)が記録された文書であり,被告の不開示決定処分に違法性はない。
(3)なお,被告及び群馬高専では,教職員を懲戒処分にした場合にはその旨の情報を提供することとなっているところ(乙3の1及び2),平成26年4月以降に群馬高専のハラスメント事案に関して情報提供を実施した事実はない(甲6の1,6頁3行目,「また,当審査会事務局職員をして(以下略)」の段落参照)。このことからも,開示請求①から③に係る書面には,懲戒処分となりうるようなハラスメントの事実は記載されていないことが伺われる(当会注:どうやら群馬高専ではあれだけ深刻なアカハラ事件の発生にもかかわらず懲戒処分レベルと見なしていないらしい。自ら懲戒書分を不作為にしておいて、この言い草は普通の感覚ではありえない)のであり,同書面には「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」は記載されていないことは,この点からも明らかである。
2 法5条1号ハについて
(1)原告は,要旨,法5条1号ハは,公務員(ママ,以下略)の職務執行情報報の
<P4>
開示の重要性を定めており,公務員の職務執行状況をきちんと国民に知らせることにより,公務員の職務の健全陛や遵法性を担保することが大切である,という趣旨の規定であり,この観点からすれば,開示請求①から③にかかる文書は,法5条1号ハの適用を受ける,と主張する(原告準備書面(1)4頁)。
(2)しかし,開示請求の対象文書が公務員が職務上作成したものであり,その内容が公務員の公務に関連する情報であったとしても,当該情報の内容によっては,「個人に関する情報」に該当することは,前記裁判例のとおりであり(乙4),この裁判例の判断は独立行政法人の職員が職務上作成した文書についてもそのまま当てはまるものである。
開示請求①から③にかかる文書が,個人に関する情報としての不開示情報(法5条1号柱書)が記載されたものであり,被告がこれを理由として不開示決定処分をしたことは前記のとおりである。原告は開示請求①から③にかかる文書が,公務員が職務上作成した文書であることを主張するが,公務員が職務上作成した文書であることと,当該文書に個人に関する情報としての不開示情報が含まれることは両立しうるのであり,原告の主張は失当と言うほかない。
2 部分開示について
(1)原告は,開示請求②に含まれるであろう情報として,「名前・生年月日といったイ固人情報」と,「アカデミックハラスメント事件の存在及び経緯に関する情報」については容易に分離可能であり,法6条の除外事由に当たらないものとして,部分開示を実施すべきと主張する。
(2)まず,原告の言う前記の「アカデミックハラスメント事件の存在及び経緯に関する情報」も,その他の記載等と相まって不開示情報としての個人に関する情報に該当することを指摘しておく。
<P5>
部分開示は,「法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき」(法6条1項)を要件としている。
しかし,開示請求②にかかる文書は,申告者が,被申告者のハラスメント行為とされる行為の内容やその経緯,申告者の説明する被害内容や,他の当事者に関するハラスメントとされる行為の内容が記載(当会注:アカハラ事件の被害者が勇気を振り絞って校長に事件の態様と被害の深刻さを通報して善処を要請したのに、個人の問題として矮小化しようとする学校側の思惑が見え隠れする)されており,個人に関する情報に係わらない部分の記載はない。
開示請求③にかかる文書も,関係者から聴取した結果として,ハラスメントとされる行為の経過や当事者が記載されていることは,上記開示請求②にかかる文書と同様である。開示請求③にかかる文書には,このほか調査に至った経緯や調査担当者,調査方法と調査結果に関する記載があるが、これらにも関係当事者の氏名や具体的な聴取内容が記載されており,個人に関する情報が渾然一体となって記載されているので,不開示情報が記録されている部分を容易に区分することはできない。また,開示請求③にかかる文書は,法5条4号へ「人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」のある情報が記載された文書であり,その記載はいずれも人事管理に関する事項として一体の内容をなすものであるから,記載内容はいずれも人事管理に関する不開示情報に該当すると解すべきである。
他方,開示請求①にかかる文書には,ハラスメントの加害者及び被害者とされる者の属性(所属)や,群馬高専において行った調査の期間及び概要と,学校としての対象者への対応状況が明記されているが,他に一般論として,学校としてのハラスメントに対する対応方針が記載された部分もある。後者については,個人に関する情報に係わらないものと解されるものの,「アカデミックハラスメント事件の存在及び経緯に関する情報」に関する情報公開という,原告の開示請求の趣旨からすれば,上記の後者の部分のみの開示で有意性(法6条1項但書)があるか疑問であるが,念のため不開示情報に該当する部分を抹消して,書証とし
<P6>
て提出する(乙5の1から3)。
この乙5号証の1から3により,原告が開示請求①について部分開示を請求する点については,原告は訴えの利益を喪失すると考えられるので,原告の訴状,請求の趣旨1項①に対して,予備的に請求の却下を求める。
以上
*****被告証拠説明書*****PDF ⇒ 201704073i35j.pdf
平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分決定取消請求事件
原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 独立行政法人国立高等専門学校機構
証拠説明書
平成29年4月7日
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中
被告訴訟代理人弁護士 木 村 美 隆
同 藍 澤 幸 弘
記
●号証:乙3の1
〇標目:独立行政法人国立高等専門学校機構教職員懲戒規則
〇原本・写:写
〇作成年月日:H25.7.29
〇作成者:被告
〇立証趣旨;被告の規定上,教職員を懲戒処分とした場合には,その旨の情報が原則として公開されることになっていること(開示請求①ないし③にかかる文書には,懲戒対象となる情報が記載されていないこと)
●号証:乙3の2
〇標目:独立行政法人国立高等専門学校機構における懲戒処分の公表基準
〇原本・写:写
〇作成年月日:H23.4.21
〇作成者:被告:
〇立証趣旨:同上
●号証:乙4
〇標目:裁判例(東京地方裁判所判決平成10年11月12日)
〇原本・写:写
〇作成年月日:H28.5
〇作成者:株式会社ウェストロージャパン
〇立証趣旨:ある事実がハラスメントに該当するかどうかは,対象者の勤務態度,個人の資質や処分歴等の名誉に関わる情報となり得るものとして,みだりに公開されるべきではない情報となること
●号証:乙5の1から3
〇標目:保護者宛書面
〇原本・写:写
〇作成年月日:H27.4.1,H27.6.2
〇作成者:群馬高専校長 西尾典眞
〇立証趣旨:開示請求③にかかる文言のうち,不開示情報と区分して部分開示が可能と解される余地がある箇所の内容について
*****乙3の1*****PDF ⇒ 201704074131.pdf
<P1>
独立行政法人国立高等専門学校機構教職員懲戒規則
独立行政法人国立高等専門学校機構規則第30号
平成16年4月1日
一部改正 平成18年4月4日
一部改正 平成25年7月29日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則(独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)規則第6号。以下「教職員就業規則」という。)第48条及び第49条第2項並びに独立行政法人国立高等専門学校機構船員就業規則(機構規則第7号。以下「船員就業規則」という。)第52条及び第53条第 2項の規定に基づき,機構の教職員の懲戒並びに訓告及び厳重注意(以下「訓告等」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 懲戒
(懲戒処分の原則)
第2条 理事長は,教職員就業規則第47条及び船員就業規則第51条に規定する懲戒の事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する行為でなければ,教職員に対し,懲戒処分を行うことができない。
2 教職員は,懲戒処分を受けた事案について,重ねて懲戒処分又は訓告等を受けない。
3 理事長は,第4条に定める懲戒審査委員会の審査を経て,懲戒処分を行うものとする。
ただし,懲戒の事由に該当することが客観的に明らかであって,かつ,緊急に懲戒解雇を行う必要がある場合に限り,懲戒審査委員会の審査を経ないで懲戒処分を行うことができる。
(処分量定)
第3条 懲戒処分の種類及び程度(以下この章において「処分量定」という。)の決定に当たっては,次に掲げる事項を総合的に考慮のうえ,相当なものとしなければならない。
一 懲戒事由に該当すると思料される非違行為(以下この章において「非違行為」という。)の動機,態様及び結果
二 故意又は過失の程度
三 非違行為を行った教職員の職責並びに職責及び非違行為の関連
四 他の教職員及び社会に与える影響
五 過去の非違行為の有無
<P2>
六 日頃の勤務態度及び非違行為後の対応
七 その他処分量定の決定に当たって,考慮すべき事項
(懲戒審査委員会)
第4条 理事長は,懲戒処分に関する審査を行うため,その指名する者により懲戒審査委員会を設置する。
2 懲戒審査委員会は,公正かつ中立な立場で,次に掲げることを行う。
一 非違行為の存否及び内容を調査すること。
二 処分量定を審査すること。
三 その他懲戒処分を行う上で必要な事項の審査等を行うこと。
3 懲戒審査委員会は,懲戒審査委員会へ参考人の出席を求め,又はその意見を徴することができる。
(弁明の機会の付与)
第5条 懲戒審査委員会は,処分量定の審査を行う前に,対象となる教職員に次に掲げる事項を記載した書面を交付し,弁明の機会を与えなければならない。ただし,対象となる教職員の所在を知ることができない場合はこの限りではない。
一 対象となる教職員の所属及び氏名
二 非違行為の内容
三 口頭弁明の日時及び場所スは弁明書の提出期日
(懲戒処分書)
第6条 懲戒処分を行うに当たってば,対象となる教職員に懲戒処分書を交付しなければならず,その懲戒処分の効力は,懲戒処分書を当該教職員に交付したときに発生する。
2 懲戒処分書は,別紙様式1のとおりとし,処分の内容欄には,当該処分に応じて次の各号に掲げる事項を記入するものとする。
一 懲戒解雇する場合 「 (教職員就業規則第47条又は船員就業規則第51条に掲げる該当号を表示)により,懲戒処分として,解雇する。」
二 諭旨解雇する場合 「 (教職員就業規則第47条又は船員就業規則第51条に掲げる該当号を表示)により,懲戒処分として,諭旨解雇する。」
三 停職する場合 「 (教職員就業規則第47条又は船員就業規則第51条に掲げ
る該当号を表示)により,懲戒処分として, 月(日)間停職する。」
四 減給する場合 「 (教職員就業規則第47条又は船員就業規則第51条に掲げる該当号を表示)により,懲戒処分として, 月分給与のうち 円を減給する。」
五 戒告する場合「 (教職員就業規則第47条又は船員就業規則第51条に掲げる該当号を表示)により,懲戒処分として戒告する。」
3 懲戒処分書を受けるべき教職員の所在を知ることができない場合においては,第1項の規定にかかわらず,その内容を民法(明治29年法律89号)第98条第2項に定める方法によって公示することによって懲戒処分の意思表示を行う。この場合において,民法第98条第3項の規定により,公示された日から2週間を経過したときに懲
<P3>
戒処分書の交付があったものとみなす。
(処分説明書)
第7条 懲戒処分を行うに当たっては,懲戒処分書のほか処分説明書を併せて交付するものとする。
2 処分説明書は,別紙様式2のとおりとする。
(減給)
第8条 減給は,懲戒処分の効力が発生した日の直後の給与の支給目に支給される給与から減ずるものとする。ただし,効力が発生した日とその直後の給与の支給日とが近接している場合には,その翌月の給与の支給日から減ずるものとする。
(停職)
第9条 停職の期間は,1日以上1年以下とする。
2 停職の期間の計算は,暦日計算による。
3 停職の期間の起算日は,処分の効力発生日の翌日とする。
(不服申立て)
第10条 懲戒処分を受けた教職員は,その処分について不服があるときは,理事長に対して,懲戒処分書及び処分説明書を受領した日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをすることができる。
2 理事長は,前項の不服申立てがあった場合,その翌日から起算して30日以内に回答するものとする。
(刑事裁判との関係)
第11条 理事長は,非違行為が刑事裁判所に係属する間においても,同一事件について,懲戒の手続を進めることができる。
(再雇用教職員)
第12条 教職員就業規則第24条又は船員就業規則第25条の規定により再雇用される教職員(以下「再雇用教職員」という。)が,再雇用前の在職期間中に教職員就業規則第47条又は船員就業規則第51条に規定する懲戒の事由に該当した場合には,当該再雇用教職員に対し教職員就業規則第46条又は船員就業規則第50条の規定に基づき懲戒処分を行うことができる。
(期間を定めて雇用される教職員)
第13条 期間を定めて雇用される教職員の停職及び減給は,現に雇用されている期間内
に限られるものとする。
(公表)
<P4>
第14条 理事長は,管理運営の透明性を確保するとともに,教職員の服務に関する自覚を促し,不祥事の再発防止に資するため,別に定める基準により,懲戒処分事案について公表することがある。
第3章 訓告等
(訓告等の原則)
第15条 教職員は,訓告等を受けた事案について,懲戒処分又は訓告等を重ねて受けない。
2 訓告は,文書により,厳重注意は,文書又は口頭により行うものとする。
(量定)
第16条 訓告等の種類及び程度(以下この章において「量定」という。)の決定に当たっては,次に掲げる事項を総合的に考慮のうえ,相当なものとしなければならない。
一 訓告等に該当すると思料される非違行為(以下この章において「非違行為」という。)の動機,態様及び結果
二 故意又は過失の程度
三 非違行為を行った教職員の職責並びに職責及び非違行為の関連
四 他の教職員及び社会に与える影響
五 過去の非違行為の有無
六 日頃の勤務態度及び非違行為後の対応
七 その他量定の決定に当たって,考慮すべき事項
(訓告等審査委員会)
窮17条 理事長は,訓告等に関する審査を行うため,その指名する者により訓告等審査委員会を設置することができる。
2 訓告等審査委員会は,公正かつ中立な立場で,次に掲げることを行う。
― 非違行為の存否及び内容を調査すること
二 量定を審査すること
三 その他訓告等を行う上で必要な事項の審査等を行うこと
3 訓告等審査委員会は,訓告等審査委員会へ参考人の出席を求め,又はその意見を徴することができる。
(弁明の機会の付与)
夥18条 訓告等審査委員会(訓告等審査委員会を設置しない場合においては,理事長)は,量定の審査を行う前に,対象となる教職員に次に掲げる事項を記載した書面を交付し,弁明の機会を与えなければならない。ただし,対象となる教職員の所在を知ることができない場合はこの限りではない。
一 対象となる教職員の所属及び氏名
<P5>
二 非違行為の内容
三 口頭弁明の日時及び場所又は弁明書の提出期日
(文書)
第19条 訓告等(口頭によるものを除く)を行うに当たっては,対象となる教職員に文書を交付しなければならず,その訓告等の効力は,文書を当該教職員に交付したときに発生する。
2 前項における文香は,別紙様式3のとおりとする。
3 第1項の文書を受けるべき教職員の所在を知ることができない場合においては,同項の規定にかかわらず,その内容を民法第98条第2項に定める方法によって公示することによって訓告等の意思表示を行う。この場合において,民法第98条第3項の規定により,公示された日から2週間を経過したときに当該文書の交付があったものとみなす。
(刑事裁判との関係)
第20条 理事長は,非違行為が刑事裁判所に係属する間においても,同一事件について,訓告等の手続を進めることができる。
(再雇用教職員)
第21条 再雇用教職員が,再雇用前の在職期間中に訓告等の事由に該当した場合には,当該再雇用教職員に対し教職員就業規則第49条又は船員就業規則第53条の規定に基づき,訓告等を行うことができる。
第4章 雑則
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,教職員の懲戒処分に関し必要な事項は,理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条による懲戒処分を受けた者については,なお従前の例により,同条第1項各号に規定する事由に該当していた場合で,教職員就業規則第47条各号又は船員就業規則第51条各号と同様の事由に該当し,まだ処分を受けていないときは,機構の教職員として処分を行う。
<P6>
3 前項の規定は,訓告等を行う場合に準用する。
附 則
(施行期日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月29日一部改正)
この規則は,平成25年8月1日から施行する。
*****乙3の2*****PDF ⇒ 201704074232.pdf
独立行政法人国立高等専門学校機構における懲戒処分の公表基準
平成23年4月21日
理 事 長 裁 定
1 目的
独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)における懲戒処分事案を公表することにより,機構の管理運営の透明性を確保するとともに,教職員の服務に関する自覚を促し,不祥事の再発防止に資することを目的とする。
2 公表の対象とする懲戒処分事案
教職員に対し懲戒処分を行った事案で,次のいずれかに該当する懲戒処分は,公表するものとする。
(1)職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(独立行政法人国立高等専門学校機構教職員倫理規則(機構規則第25号)に違反したことを理由としたものを含む。)
(2)職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職である懲戒処分
3 公表する内容
事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,役職段階等の被処分者の属性に関する情報を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。ただし,個別の事案に関し,当該事案の社会的影響,被処分者の職責等を勘案して,別途の取扱いをすることがある。
1 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等2及び3によることが適当でないと認められる場合は,2及び3にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないこともあることとする。
5 公表の時期及び方法
2の懲戒処分事案については処分発令後,処分者が速やかに公表するものとし,公表の方法は,原則として関係記者会等への資料配付及び各高専(理事長が懲戒処分を行った場合にあっては機構本部)のホームページヘの掲載によるものとする。
なお,特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については記者会見を行う。
**********
■被告は、今回のアカハラ事件では原因者の学科長を懲戒処分にした経緯はないから、事件について公表する義務はなく、事件に関する情報公開請求についても、同様に公開する責務はないと主張しています。しかし、これは自らの不作為を糊塗するものに過ぎません。
本来であれば、これだけ深刻なアカハラ事件を引き起こしたのだから、被害者からの直訴を受けて、直ちに懲戒処分をするのが校長の義務のはずです。
それなのに加害者をかばうことを優先し、懲戒処分もせずに、学科長の任務を解いただけで放任した校長の責任は、どこにも被告の準備書面で触れられていません。
このことから見ても、今回の準備書面は、西尾典眞・前校長の意向が反映されたまま、原告の当会に出されてきたのではないか、つまり、前校長の最後っ屁の準備書面ではないか、というのが当市民オンブズマン群馬の見方です。
引き続き、被告から準備書面と一緒に出されてきた乙号証をこの後、見ていきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この記事➁へと続く】

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます