そもそもは,写真の『Basser』p.166での記事がきっかけだった。
以下,『読売新聞オンライン11/4』よりそのまま抜粋します。
%=====抜粋開始
滋賀県の琵琶湖や周辺の河川で今年に入り、北米原産で特定外来生物のナマズ「チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)」の捕獲数が急激に増加している。
2001年に初めて見つかり、昨年までに計39匹が捕獲されたが、今年はすでに40匹。固有種を捕食する外来魚ブラックバスとブルーギルの増加が問題となった琵琶湖では、駆除に力を入れ、ここ7、8年ようやく減少傾向になってきていた。新たな外来肉食魚の出現に県や漁業関係者は危機感を強めている。
環境省によると、アメリカナマズは大きなもので1メートル超。1971年に食用として国内に持ち込まれ、関東を中心に養殖が進んだ。野生化して各地で発見されるようになったのは90年代から。在来の魚を食べ、漁業にも影響を与えるため、2005年には外来生物法で飼育や放流が禁じられた。
琵琶湖や湖から流れ出す瀬田川では01年以降、漁の仕掛けなどにかかるようになり、毎年数匹だったが昨年は18匹を確認。今年は10月末現在で40匹が見つかった。県によると、幼魚もおり、繁殖が進んでいる可能性があるという。
アメリカナマズは在来のアユや、固有種のビワヨシノボリやニゴロブナなどを食べる。これらの魚は、県レッドデータブックで希少種に指定され「琵琶湖の主」と呼ばれるビワコオオナマズ(体長1メートル超)も餌にしており、オオナマズの減少も懸念されている。
アメリカナマズの急増で在来魚が脅かされる事例は、養殖場がある茨城県の霞ヶ浦ですでに起きており、多い年で200トン以上を漁業者らが捕獲・駆除。同県水産試験場は「ヒレの鋭いトゲを警戒して鳥も食べないなど、天敵がいないため増えやすい」という。
滋賀県では約30年にわたってブラックバスとブルーギル対策に取り組んできた。ブラックバスは1974年に琵琶湖で初めて確認され、83年頃に繁殖が拡大。ブルーギルは90年代前半からブラックバスを上回るペースで増えた。
漁業者が駆除にあたるなどし、2003年には、県が釣り人に外来魚のリリース(放流)を禁止する条例を制定。対策に年間1億円前後かけた結果、外来魚の駆除量は1990年の30トンから、ピークの2007年には543トンまで増えた。
これに応じて、ブラックバスとブルーギルの推定生息量も過去10年で、06年の約1900トンをピークに減少。12年には3割減の約1300トンになった。
県水産課の担当者は「長年の外来魚駆除が功を奏し、固有種のニゴロブナなどは増加の兆しが出てきたところ。ここでまた『第2のブラックバス・ブルーギル』にあたる外来肉食魚が増えれば、固有種にとどめを刺しかねない」と懸念。
現在、捕獲後の放流禁止を呼びかけるとともに「生息域がまだ限られているうちに早急に対応しなくては」と検討を進めている。
%======抜粋終わり
記事の信憑性・不確実性についてはここでは言及しない。あくまで「琵琶湖でもアメナマが」というところだけに着目する。
僕の記憶が確かなら,岐阜などで,いまの外来魚規制法が出来る前に「カワフグ」として養殖されていたはずだ。
もうこの時点で,拡散の理由がわかる。それはおそらく,規制法により養殖事業がうまく行かなくなり,近くの琵琶湖,いや流入河川に放流してしまったということ。それがきっかけかもしれないということ。断定はできないが可能性は大きいと思う。
ただ,霞ヶ浦水系と琵琶湖はまったく異なる。たしかに旧来の生態系など存在しないのは共通しているが,たとえば琵琶湖北部の美しさに,アメリカナマズがつけいる隙があるかどうかだ。
外来種は,霞ヶ浦水系でもそうだったが,一時期爆発的に増える。僕の実感として1990年代初頭がまさにピークだった。しかし,かならず減る。それも絶滅したのではと思うほどに減る。2000年頃は釣りを止めようかと思ったほどだ。いま,代表的な減少期というか安定期にあるのは八郎潟だといわれる。霞ヶ浦水系はブルーギルがかなり減ってしまったが,その隙間にアメリカナマズが入ってきているように感じる。
琵琶湖水系の隙間とはなんだろうか。南湖でさえも,沖に行くと飲めそうな水がある。霞ヶ浦のような汚濁とはまったく異なる。ウイードも多い。
それにしても,また「釣り人のせいで」なんて言われると困る。実際彦根で釣りをしていると,とても肩身が狭かった記憶がはっきりしている。ブルーギルを惨殺している自称「釣り人」の横で,僕はブルーギル釣りを楽しんでいたし...。
とにかく,琵琶湖には数年行っていないので状況がわからない。行ってみて,岸釣りでも釣れるようになったら,もう琵琶湖には行かないようになってしまいそう。まあ,バスはバスで生きていくだろうし,さらに大型化が進んでいくだろうけども...。











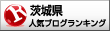



 。
。 。
。 。前のカリーナ1600GTなら,もう記録が残ってもいないようだから,ネ
。前のカリーナ1600GTなら,もう記録が残ってもいないようだから,ネ 。
。 



 。
。 」
」 。
。 。そして28歳のときにEF9に買い換えていまに至っている。
。そして28歳のときにEF9に買い換えていまに至っている。 。発表当時の評価は
。発表当時の評価は 」
」

 している。
している。 。しかし,結果からすれば効果ある出勤
。しかし,結果からすれば効果ある出勤 。予定以上の馬力
。予定以上の馬力 を発揮して定時で終わることができた
を発揮して定時で終わることができた
 。
。 が,前日は21時30分には寝ていたので睡眠不足感はない。それでも寝入りばなに長野北部地震が起きたという。東京では震度1程度だったようでまったく気づかなかった。いまのところ死者が出ていないようだが,
が,前日は21時30分には寝ていたので睡眠不足感はない。それでも寝入りばなに長野北部地震が起きたという。東京では震度1程度だったようでまったく気づかなかった。いまのところ死者が出ていないようだが,
 が大好きだ。
が大好きだ。 」のようである。厳密には初冬だろうけど,例年釣果が急降下
」のようである。厳密には初冬だろうけど,例年釣果が急降下 し,釣行回数も激減するこの時期だ。
し,釣行回数も激減するこの時期だ。
 。
。 。過去の実績はありすぎるポイント。そこヘシャッドラップ投入。秋までならクランクかスピナーベイトを投入するところだが,冬なので,いままでの実績と,驚異的な奇跡(
。過去の実績はありすぎるポイント。そこヘシャッドラップ投入。秋までならクランクかスピナーベイトを投入するところだが,冬なので,いままでの実績と,驚異的な奇跡( 具体的には1993/12/30に横利根で入れ食いをしたことがある
具体的には1993/12/30に横利根で入れ食いをしたことがある )さえも呼び起こしてきたシャッドラップSR-7・FTカラーで勝負するのだ。
)さえも呼び起こしてきたシャッドラップSR-7・FTカラーで勝負するのだ。

 。真夏にバカにされたライギョ
。真夏にバカにされたライギョ 。
。 。またこれでシャッドラップに伝説が吹き込まれた。
。またこれでシャッドラップに伝説が吹き込まれた。 。無事に成長してくれることを祈りながらリリースし,
。無事に成長してくれることを祈りながらリリースし, 。そしてなぜか予備の手袋をもっているのは不思議なものだ
。そしてなぜか予備の手袋をもっているのは不思議なものだ がくる。「45UPですよ
がくる。「45UPですよ 。
。
 。
。 が反応なし。
が反応なし。
 が強くなるばかり。
が強くなるばかり。 。
。 が次回からは本命だろうな
が次回からは本命だろうな






