 ←※投票よろしくお願いします!
←※投票よろしくお願いします!25010Kさま
本免技能試験合格のご連絡ありがとうございました。
仮免許を取得するのには複数回受験されたそうですが、
路上試験は一回でパスできて、良かったです。
もっとも、仮免受験の時とは違って
「しっかり練習してから受験しよう」と思われたわけで、
その心構えができた時点で合格が見えたと言えるんじゃないでしょうか。
取得時講習が少し先になるようですが、
それでも3月中には免許が手にできるスケジュールですので、
4月からの新生活に間に合いますね。
おめでとうございました!
※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
(「自動車(運転技術)」,「自動車(全般)」,「資格受験」,「免許・スクール」の4カテゴリー)
ぜひ1日1クリックの応援をお願いいたします。
↓
人気blogランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)
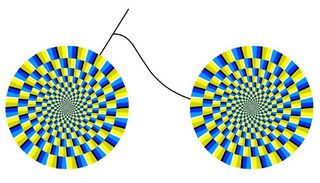
試験 仮免許 路上試験 心構え 取得時講習 新生活















