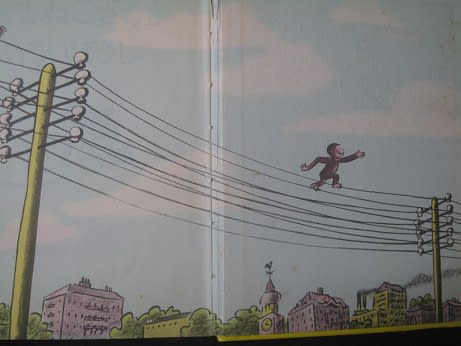この春から、図書館で新刊を借りて読むというマイブームを続けています。
といっても、最近はなかなかはかどらず、貸出期間の2週間で読み終えるのが非常に困難となっております。
それで、延長に延長を重ねたり、次の本と2冊借りたりなどし、結局そのうちの1冊は、別の人のリクエストが来ていて、図書館から督促が来て、読まずじまいで返却なんてこともありました。
前回、読み終えたのが「復興は教育から始まる」と言う本でした。それが、8月10日頃だったので、それから1か月以上もかかってしまいました。
でも、やっと読み終えることができました。
「トコトンやさしい○○の本」というのは、B&Tブックス日刊工業新聞社の「今日からモノ知りシリーズ」というシリーズ本で、とてもたくさんのテーマがあり、今回読んだ「プラスチック成形」はそのうちの1つです。
このシリーズでは、例えば、金属加工・プレス加工・金型・工作機械・軸受・溶接など、理工系のモノ作りの方法の本が多々あります。
これまで、放送大学の自然系や産業系の面接授業などでも、参考書として活用したこともあります。(トコトンやさしい電気自動車の本・トコトンやさしいレンズの本 など)
見開きの片側のページはだいたい図解で示されており、片側は文の説明で、とてもわかりやすく書かれています。
今回の「プラスチック成形の本」は、たまたま図書館の新刊の棚にあったのをみつけて借りてきました。
プラスチックは日常生活に欠かせないもので、身近な存在です。
本来、熱を加えると柔らかくなる「熱可塑性合成樹脂」のことをプラスチックと言いますが、熱を加えると固まる「熱硬化性合成樹脂」のこともプラスチック言うようになり、「合成樹脂」を「プラスチック」というようになっているそうです。
熱硬化性プラスチックがなぜ温度が高くなると固まるのかは、以前から不思議に思っていましたが、分子の鎖が動くと、からまって動けなくなる等、とてもわかりやすいものでした。
プラスチックには、セルロイド・ポチエチレン・ポリスチレン・ポリプロピレン・ポリエチレンテレフタレート(PET)等様々なものがあり、成形方法にも、射出成形・押し出し成形・ブロー成形・圧縮成形など様々な方法があり、その上に模様をつける表面加工の方法やリサイクル方法なども書かれていました。
こういう本は、勉強の参考書として、知りたい該当箇所だけを見るという使い方をすることが多いですが、今回は、ざっと最初から最後まで通読するというのをやってみて、全体の概要がよくわかり良かったと思います。