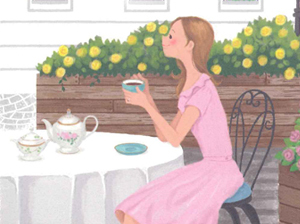五月病(ごがつびょう)とは、
ゴールデンウィーク明け頃から出てくる軽い「適応障害」の事を言います。
新しい環境に適応できないことに起因する精神的な症状を言い、
病院などの診断書で用いられる正式な医学用語ではありません。
新入職員や新入学生が、
入職や入学を済ませて、ひと段落する5月頃から6月頃に、
無意識に蓄積されていた緊張からくる心身の疲れや、
与えられた仕事や新しい人間関係などについていけない精神的ストレスなどで、
「やる気が出ない」「わけもなく憂鬱な気分に陥る」事をいいます。
他には、「不安」「焦り」「食欲がわかない」「寝つきが悪くなる」「疲れやすい」など。
この「適応障害」は、5月、6月だけのものではなく、
人によっては夏休みを過ぎてからの9月頃に発症する場合もあります。
春から秋まで何とか頑張る事が出来ても、
年末年始明け=お正月休み明け頃に発症する場合もあります。
「五月病」の原因は、
・新しい人間関係に不安がある
・新しい環境についていけない
・想像していた新生活と現実のギャップについていけない
・入職・入学といった大きな目標を達成した事により、
次の目標を持てず混乱したり焦りが出て不安になったりする
それは多少の違いがあれ、誰にでもある事ですから、
乗り越えられる人となって、軽く乗り越えていって欲しいと思っています。
・規則正しい生活を送る
・食生活に気を付ける
・睡眠時間をとる努力をする
・気分転換をする
・不必要なプライドを捨てる
・明日を元気に頑張る事だけ考る
・周りから信用される人でいたいという事だけ念頭におく(ミニマム目標)
それらに気を付けて生活を送っていると、
自然に新しい環境に慣れて、新しい人間関係に慣れて、
症状が軽くなっている自分に気付きます。
コミュニケーション能力を高める事だけ考えておけば、
自然と積極的になれて、
自然と社会力もアップしていけるのではないでしょうか?
新しい環境に新しい人間関係の中でスタートするわけですから、
最初から完璧に物事を進められる人などいません。
ゼロから物事を始めた場合、
「自分は何でこんなに出来ないのだ?」
「自分はこんなはずじゃないのに」
「プライドが傷つくばかり」と思いがちです。
そんなものです。
「自分が出来ないから、あれこれ教えて頂けるわけだ」
「これはひとつのチャンスだ」
「自分は出来ないことばかりだったのだ」
と素直に受け入れる事が大切です。
ですから、
まわりの流れに身を任せてみるのもひとつです。
流れに身を任せているうちに、
気付いたら自然と同じ流れにのっていけている自分に気付くはずです。
適度に身体を動かして、
質の良い睡眠をとるように心掛けると、
頭痛やめまいや貧血などとは無縁になっていきます。
壁にぶちあたって、砕けてしまう人間になるのではなく、
壁にぶちあたったら、壁を砕いて次に進める人間になりたいものですね。
新入職員の皆様、新入学の皆様、
心から応援しております。
良い気も、悪い気も、
自分が発するものですから、
良い気を発して、
良い結果を手にしていきたいものです。
ーby事務長ー

 とくおかレディースクリニック
とくおかレディースクリニック

 とくおかレディースクリニック
とくおかレディースクリニック