2012年4月10日(火)(続き)
荒井4丁目の住宅地に、たくさん庭石を積んだりっぱな庭の民家があり、その隅で
モクレンが見ごろになっていた。

県道33号を越えて高尾8丁目に入る。古くからの集落の横を通過して行くと、プラ
ムだろうか白い花の果樹園が幾つか見られる。

北向地蔵の立つ小さい三差路に、背後の南側から回った。

享保14年(1729)の建立。願い事を叶えてくれる地蔵として有名で、泥の団子
を供えて願いが叶ったら米の団子をあげる習慣が、現在でも続いているという。
少し先には須賀神社と氷川神社、それに氷川神社の境内になるという斜面下の弁天池
に祭られた厳島神社の三つが、三差路を挟んで相対している。
正面の氷川神社の、ソメイヨシノもかなり開花が進んでいる。

氷川神社は貞観11年(869)の創建。素戔嗚尊(すさのおのみこと)ほか6つの
神様を祭っている。
西側斜面下、厳島神社側のモミジの新芽が紅葉のように色鮮やか。

西に少しの民家の横から谷間に下ると、県のトラスト保全地域第8号地になっている
「高尾宮岡の景観地」である。

大宮台地の浸食により形成された、谷津とそれを囲む斜面からなり、二か所の湧水が
あるという。
湿地の向こうの広葉樹林を眺めながら景観地の遊歩道を西に抜けて、北本市野外活動
センターへ。野外活動、体験学習などを通しての健康増進を目的として建設された施設
で、キャンプ場や多目的ホール、体験学習室、入浴施設などがある。

手前の黄色は、レンギョウの生け垣。
センターの西端まで進み、北側の民家の横の細道を抜けて、高尾さくら公園に入る。

園内には、全国から集められた桜30種約200本が植えられているが、まだ若木が
多く、これからしばらくは年々花の勢いがよくなるのではないだろうか…。

好天に誘われ、家族連れなど花見の人出も多い。
エドヒガンザクラも、見ごろになっている。

南側、斜面に面した一帯には、シダレザクラが花を競っていた。



台地の終わる西側からは、広々とした麦畑の向こうに、荒川左岸堤防に咲くナノハナ
の帯が遠望できる。


数は少なかったが色鮮やかな木は、「陽光」と呼ぶ品種のよう。


さくら公園を北に抜けると、阿弥陀堂の東側の民家に咲くシダレザクラが目に入る。

阿弥陀堂の山門(右)とお堂(左)。山門にははしごが置かれていて、鐘楼になって
いる2階に上がることもできる。

阿弥陀堂は、中世の館である大宮館の跡だといわれているという。
お堂の背後の墓地に、北本市天然記念物に指定されているエドヒガンザクラの大木が
ある。


山門近くに戻ると、東側の民家のシダレザクラが西日を浴びて、よい彩りを見せる。

山門前の道を北に下った民家の山林にカタクリが咲いていて、「高尾カタクリ自生地」
として保護されている。


カタクリも、ちょうど見ごろ。

傍らで、ニリンソウも花を開き始めていた。

北側の民家の庭先では、ボケが花盛り。

カタクリ自生地への下り口付近は、ショカッサイが花を競っている。

阿弥陀堂に戻り、東側すぐのところには、古墳時代住居跡や奈良時代住居跡などが確認
されたとい「阿弥陀堂遺跡」の発掘跡が保存されていた。

氷川神社や厳島神社のある三差路に戻って県道33号に出て、石戸小学校バス停に16
時12分に着き、間もなく来たバスで北本駅に戻った。
(天気 晴、距離 8㎞、地図(1/2.5万) 鴻巣、歩行地 北本市、歩数
16,200)
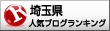 埼玉県 ブログランキングへ
埼玉県 ブログランキングへ

にほんブログ村
荒井4丁目の住宅地に、たくさん庭石を積んだりっぱな庭の民家があり、その隅で
モクレンが見ごろになっていた。

県道33号を越えて高尾8丁目に入る。古くからの集落の横を通過して行くと、プラ
ムだろうか白い花の果樹園が幾つか見られる。

北向地蔵の立つ小さい三差路に、背後の南側から回った。

享保14年(1729)の建立。願い事を叶えてくれる地蔵として有名で、泥の団子
を供えて願いが叶ったら米の団子をあげる習慣が、現在でも続いているという。
少し先には須賀神社と氷川神社、それに氷川神社の境内になるという斜面下の弁天池
に祭られた厳島神社の三つが、三差路を挟んで相対している。
正面の氷川神社の、ソメイヨシノもかなり開花が進んでいる。

氷川神社は貞観11年(869)の創建。素戔嗚尊(すさのおのみこと)ほか6つの
神様を祭っている。
西側斜面下、厳島神社側のモミジの新芽が紅葉のように色鮮やか。

西に少しの民家の横から谷間に下ると、県のトラスト保全地域第8号地になっている
「高尾宮岡の景観地」である。

大宮台地の浸食により形成された、谷津とそれを囲む斜面からなり、二か所の湧水が
あるという。
湿地の向こうの広葉樹林を眺めながら景観地の遊歩道を西に抜けて、北本市野外活動
センターへ。野外活動、体験学習などを通しての健康増進を目的として建設された施設
で、キャンプ場や多目的ホール、体験学習室、入浴施設などがある。

手前の黄色は、レンギョウの生け垣。
センターの西端まで進み、北側の民家の横の細道を抜けて、高尾さくら公園に入る。

園内には、全国から集められた桜30種約200本が植えられているが、まだ若木が
多く、これからしばらくは年々花の勢いがよくなるのではないだろうか…。

好天に誘われ、家族連れなど花見の人出も多い。
エドヒガンザクラも、見ごろになっている。

南側、斜面に面した一帯には、シダレザクラが花を競っていた。



台地の終わる西側からは、広々とした麦畑の向こうに、荒川左岸堤防に咲くナノハナ
の帯が遠望できる。


数は少なかったが色鮮やかな木は、「陽光」と呼ぶ品種のよう。


さくら公園を北に抜けると、阿弥陀堂の東側の民家に咲くシダレザクラが目に入る。

阿弥陀堂の山門(右)とお堂(左)。山門にははしごが置かれていて、鐘楼になって
いる2階に上がることもできる。

阿弥陀堂は、中世の館である大宮館の跡だといわれているという。
お堂の背後の墓地に、北本市天然記念物に指定されているエドヒガンザクラの大木が
ある。


山門近くに戻ると、東側の民家のシダレザクラが西日を浴びて、よい彩りを見せる。

山門前の道を北に下った民家の山林にカタクリが咲いていて、「高尾カタクリ自生地」
として保護されている。


カタクリも、ちょうど見ごろ。

傍らで、ニリンソウも花を開き始めていた。

北側の民家の庭先では、ボケが花盛り。

カタクリ自生地への下り口付近は、ショカッサイが花を競っている。

阿弥陀堂に戻り、東側すぐのところには、古墳時代住居跡や奈良時代住居跡などが確認
されたとい「阿弥陀堂遺跡」の発掘跡が保存されていた。

氷川神社や厳島神社のある三差路に戻って県道33号に出て、石戸小学校バス停に16
時12分に着き、間もなく来たバスで北本駅に戻った。
(天気 晴、距離 8㎞、地図(1/2.5万) 鴻巣、歩行地 北本市、歩数
16,200)
にほんブログ村















