2014年3月12日(水)
今年は、秩父札所三十四ヶ所観音霊場の午歳(うまどし)総開帳の年で、3月から11
月まで、普段は見られないお厨子の扉が開かれ、観音様を拝見することが出来る。
これを機に、西武鉄道と秩父鉄道合同の「秩父札所午歳総開帳記念ハイキング」が6回
にわたり各回とも春秋に2日ずつ開催されるので、その第1回に参加した。
集合は秩父鉄道の和銅黒谷(わどうくろや)駅。平日ながら、同じ電車で下車したのは
100人以上はいたろうか。受付でコース地図をもらい、9時50分に出発する。

東側の国道140号を横断して、平行する旧道に入ると内田家住宅がある。

内田家は江戸時代初期から明治初年まで名主役を勤めた家柄。建物は秩父地方の大工の
優れた技術によるもので、17世紀初期の建築と思われるという。
日影には、まだ2月の2度の大雪の残雪があちこちに見られる。

門前に六地蔵の並ぶ法雲寺や、裏山にツツジが群生し秩父十三仏霊場の一つという瑞巌
寺前を通過し、栃谷の山裾にある一番札所の四萬部寺(しまぶじ)に着いた。

入母屋(いりもや)造りの本堂は元禄10年(1697)の造営、秩父地方における社
寺建造物の規範となった建物のようで、県の文化財である。
境内には、関東三大施餓鬼(せがき)の一つという施餓鬼堂や、その前に立つ元禄10
年に植えた古木の根から芽を吹いたという元禄八重紅梅、本堂前に並ぶ新しい十二支守本
尊、納経堂などが目に付いた。

そばにある古い旅館、「旅籠一番」の前を下り、雪の残る横瀬川の支流を渡る。

本来の巡礼道はその先を南東へ、中郷集落を抜ける谷間を進むのだが、残雪が多いので
迂回路となり、南西への県道11号を回ることになった。

Y字路際にあった八坂神社の小さい社殿には、精巧な木彫が施されていた。高篠小や高
篠中の前を通過し、谷津集落の十字路を左折して東進する車道に入る。
次の十字路を左折すると二番納経所の光明寺(こうみょうじ)だが、そのまま直進して
二番真福寺(しんぷくじ)に向かう。ところがこちらに来る人はほんのわずか。ハイキン
グ参加者のほとんどは、光明寺に入って折り返し、次の四番金勝寺に向かったようだ。

小さい流れ沿いの車道は次第に高度を上げ、両岸の林や流れには残雪が増える。新しい
公衆トイレ前を過ぎて大棚集落の民家が減った辺りから、車道に分かれて真福寺への標識
に従い土道へ。
すぐ先の民家のそばに、県天然記念物「岩棚のキンモクセイ」の古木がある。

二番真福寺の開基大棚禅師が植えたものと伝えられるもの。樹高約10m、推定樹齢
500年以上などと記されていたが、枯れ枝になっていた。
その先から巡礼道は杉林の下になり、残雪が続き傾斜も強まる。

滑らぬよう注意しながら上がるが、久しぶりの山道なのと気温が上がっているので汗が
出る。
やがてヘヤピンカーブの続く車道の中間に出た。そばの寿種茸園のそばに、洞の出来た
古木が立っていたが、何の木か分からない。

ヘヤピンカーブが終わって辺りが開け、数本の紅梅が咲く二番真福寺下の広場に着いた。

石段を上がった民家風の建物の上に、杉木立に囲まれた二番札所真福寺の観音堂がある。

昔は、大きな観音堂のほか、本堂、仁王門、羅漢堂、稲荷社、諏訪社などがあったよう
だが火災で焼失し、現在の小さめの観音堂が再建されたらしい。
本尊の聖観世音は室町時代の作といわれており、現在の寺は無住。お堂には精巧な木彫
が施され、開祖大棚禅師を描いた大きな額が奉納されていた。正午を過ぎたので、観音堂
横のベンチで昼食にする。
寺は標高400mを超える高所にあり、南面に雪の残る山並みが望まれる。

下りは、杉木立などに覆われて残雪の残るヘヤピンカーブの続く車道を戻る。

大棚川沿いに出ると、対岸の岩から雪解けの水が凍ってツララとなっていた。

二番納経所近くまで戻ると、民家の庭先にフクジュソウが咲く。

二番納経所の光明寺は、南に武甲山と相対する開放的で明るい境内。山門は無いが、露
座の仁王像が立つている。

真福寺への往復中に、ハイキング参加者はほとんど立ち去り、納経所も閑散としていた。
寺は、桓武平氏の始祖となった高望王の弟の恒望王が、大同2年(807)に逝去した
邸宅跡に造った祈願所が始まりとか。のち武蔵七党の一つ、丹党の手で中興するなど、秩
父谷随一の格式を持った寺という。
四番金昌寺に向かい、南に道をとる。大棚川を渡って間もなく、重要文化財に登録した
いような水野医院の風格ある日本家屋が目に入る。

正面に武甲山が望まれるが、気温が上がった今日は霞んでいて、残雪の様子などは認識
しにくい。
南東側の山を背にした四番札所金昌寺(きんしょうじ)についた。

大きなわらじの奉納されたりっぱな山門を入ると、境内の斜面にはたくさんの石仏が並
んでいる。

宝永年間(1704~11)以降、全国に分布する信者から菩提供養のために奉納され
たもので、1千体以上あるという。

方形造りの観音堂には、赤子に乳を含ませる姿の慈母観音像↓が奉納され、そばの墓地
には、この地も選挙区とした元運輸大臣、荒船清十郎の墓と胸像が並んでいた。

順序が逆になるが、三番常泉寺(じょうせんじ)を目指して西北に向かう。巡礼道の角
や通りには、石の道しるべや木の札などが置かれていた。


深い渓谷となっている横瀬川を、車の通れぬふるさと歩道橋で渡る。

渡った左岸橋際に、民話「お止めばし」の物語が掲示されていた。

三番札所常泉寺は、西側背後に山を背にした矢追集落の高みにあった。

観音堂には、繊細な木彫が施され、特に龍の刻まれた向背の海老虹梁のかごぼりと呼ぶ
きめ細かな彫刻で知られている。

この観音堂は、明治3年(1870)に秩父神社の薬師堂を移築した江戸後期の建築物
で、本尊聖観世音菩薩は室町町時代のものとか。
高みにある境内からは東側の展望が開け、山田集落やその向こうに広がる山並みが一望
できる。

今日の巡礼はここで終わり、ゴールの秩父駅に向かう。南西へ斜面の土道を上がって行
くと、杉木立に覆われた辺り2か所には残雪があるが、そう長くは続かず、開放的な墓地
が並ぶ聖地公園に上がった。

台地上の公園から延びる車道をを南西へ。横瀬町十五番集落から上がってくる三差路際
に、移築された旧秩父駅舎があった。

大正3年(1914)に、秩父鉄道の前身、上武鉄道が大宮町(現秩父市)に延長され
たときに開設されたもの。昭和58年(1993)に、現在の秩父地域産業振興センター
内の駅舎建設に伴い、翌年移設したもので、駅舎の設計者は当地出身の坂本朋太郎博士と
いわれているという。
日が傾き、武甲山の雪模様も少しずつ望まれるようになってきた。

車道が秩父市外に向かって大きくヘヤピン状に下る辺りからは、秩父市の市街地やその
向こうの長尾根などが展望できる。

市街地に下って国道140号を横断し、西に平行する路地を進む。上宮地町の十字路際、
関根家墓地に「でんでい場のツバキ」と呼ぶツバキの大木が立っていた。

高さ6.6m、目通り1.3m、樹齢約250年という古木で、秩父市の天然記念物に指
定されている。
その通りを西進して秩父鉄道下を抜け、ゴールの秩父鉄道秩父駅には15時18分に着
いた。

下り電車まで時間があるので、駅舎の入っている秩父地場産業センタービルの1階にあ
る、秩父の土産品の並ぶ物産館を少しのぞく。
まだ時間があるので、線路際を進んで隣の御花畑駅を抜け、西武秩父駅まで歩く。西武
秩父駅発16時8分の上り電車で帰途についた。
(天気 快晴後晴、距離 16㎞、地図(1/2.5万) 皆野、歩行地 秩父市、累積
標高差 上り約430m、下り約380m、歩数 29,100)
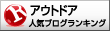 アウトドア ブログランキングへ
アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村
今年は、秩父札所三十四ヶ所観音霊場の午歳(うまどし)総開帳の年で、3月から11
月まで、普段は見られないお厨子の扉が開かれ、観音様を拝見することが出来る。
これを機に、西武鉄道と秩父鉄道合同の「秩父札所午歳総開帳記念ハイキング」が6回
にわたり各回とも春秋に2日ずつ開催されるので、その第1回に参加した。
集合は秩父鉄道の和銅黒谷(わどうくろや)駅。平日ながら、同じ電車で下車したのは
100人以上はいたろうか。受付でコース地図をもらい、9時50分に出発する。

東側の国道140号を横断して、平行する旧道に入ると内田家住宅がある。

内田家は江戸時代初期から明治初年まで名主役を勤めた家柄。建物は秩父地方の大工の
優れた技術によるもので、17世紀初期の建築と思われるという。
日影には、まだ2月の2度の大雪の残雪があちこちに見られる。

門前に六地蔵の並ぶ法雲寺や、裏山にツツジが群生し秩父十三仏霊場の一つという瑞巌
寺前を通過し、栃谷の山裾にある一番札所の四萬部寺(しまぶじ)に着いた。

入母屋(いりもや)造りの本堂は元禄10年(1697)の造営、秩父地方における社
寺建造物の規範となった建物のようで、県の文化財である。
境内には、関東三大施餓鬼(せがき)の一つという施餓鬼堂や、その前に立つ元禄10
年に植えた古木の根から芽を吹いたという元禄八重紅梅、本堂前に並ぶ新しい十二支守本
尊、納経堂などが目に付いた。

そばにある古い旅館、「旅籠一番」の前を下り、雪の残る横瀬川の支流を渡る。

本来の巡礼道はその先を南東へ、中郷集落を抜ける谷間を進むのだが、残雪が多いので
迂回路となり、南西への県道11号を回ることになった。

Y字路際にあった八坂神社の小さい社殿には、精巧な木彫が施されていた。高篠小や高
篠中の前を通過し、谷津集落の十字路を左折して東進する車道に入る。
次の十字路を左折すると二番納経所の光明寺(こうみょうじ)だが、そのまま直進して
二番真福寺(しんぷくじ)に向かう。ところがこちらに来る人はほんのわずか。ハイキン
グ参加者のほとんどは、光明寺に入って折り返し、次の四番金勝寺に向かったようだ。

小さい流れ沿いの車道は次第に高度を上げ、両岸の林や流れには残雪が増える。新しい
公衆トイレ前を過ぎて大棚集落の民家が減った辺りから、車道に分かれて真福寺への標識
に従い土道へ。
すぐ先の民家のそばに、県天然記念物「岩棚のキンモクセイ」の古木がある。

二番真福寺の開基大棚禅師が植えたものと伝えられるもの。樹高約10m、推定樹齢
500年以上などと記されていたが、枯れ枝になっていた。
その先から巡礼道は杉林の下になり、残雪が続き傾斜も強まる。

滑らぬよう注意しながら上がるが、久しぶりの山道なのと気温が上がっているので汗が
出る。
やがてヘヤピンカーブの続く車道の中間に出た。そばの寿種茸園のそばに、洞の出来た
古木が立っていたが、何の木か分からない。

ヘヤピンカーブが終わって辺りが開け、数本の紅梅が咲く二番真福寺下の広場に着いた。

石段を上がった民家風の建物の上に、杉木立に囲まれた二番札所真福寺の観音堂がある。

昔は、大きな観音堂のほか、本堂、仁王門、羅漢堂、稲荷社、諏訪社などがあったよう
だが火災で焼失し、現在の小さめの観音堂が再建されたらしい。
本尊の聖観世音は室町時代の作といわれており、現在の寺は無住。お堂には精巧な木彫
が施され、開祖大棚禅師を描いた大きな額が奉納されていた。正午を過ぎたので、観音堂
横のベンチで昼食にする。
寺は標高400mを超える高所にあり、南面に雪の残る山並みが望まれる。

下りは、杉木立などに覆われて残雪の残るヘヤピンカーブの続く車道を戻る。

大棚川沿いに出ると、対岸の岩から雪解けの水が凍ってツララとなっていた。

二番納経所近くまで戻ると、民家の庭先にフクジュソウが咲く。

二番納経所の光明寺は、南に武甲山と相対する開放的で明るい境内。山門は無いが、露
座の仁王像が立つている。

真福寺への往復中に、ハイキング参加者はほとんど立ち去り、納経所も閑散としていた。
寺は、桓武平氏の始祖となった高望王の弟の恒望王が、大同2年(807)に逝去した
邸宅跡に造った祈願所が始まりとか。のち武蔵七党の一つ、丹党の手で中興するなど、秩
父谷随一の格式を持った寺という。
四番金昌寺に向かい、南に道をとる。大棚川を渡って間もなく、重要文化財に登録した
いような水野医院の風格ある日本家屋が目に入る。

正面に武甲山が望まれるが、気温が上がった今日は霞んでいて、残雪の様子などは認識
しにくい。
南東側の山を背にした四番札所金昌寺(きんしょうじ)についた。

大きなわらじの奉納されたりっぱな山門を入ると、境内の斜面にはたくさんの石仏が並
んでいる。

宝永年間(1704~11)以降、全国に分布する信者から菩提供養のために奉納され
たもので、1千体以上あるという。

方形造りの観音堂には、赤子に乳を含ませる姿の慈母観音像↓が奉納され、そばの墓地
には、この地も選挙区とした元運輸大臣、荒船清十郎の墓と胸像が並んでいた。

順序が逆になるが、三番常泉寺(じょうせんじ)を目指して西北に向かう。巡礼道の角
や通りには、石の道しるべや木の札などが置かれていた。


深い渓谷となっている横瀬川を、車の通れぬふるさと歩道橋で渡る。

渡った左岸橋際に、民話「お止めばし」の物語が掲示されていた。

三番札所常泉寺は、西側背後に山を背にした矢追集落の高みにあった。

観音堂には、繊細な木彫が施され、特に龍の刻まれた向背の海老虹梁のかごぼりと呼ぶ
きめ細かな彫刻で知られている。

この観音堂は、明治3年(1870)に秩父神社の薬師堂を移築した江戸後期の建築物
で、本尊聖観世音菩薩は室町町時代のものとか。
高みにある境内からは東側の展望が開け、山田集落やその向こうに広がる山並みが一望
できる。

今日の巡礼はここで終わり、ゴールの秩父駅に向かう。南西へ斜面の土道を上がって行
くと、杉木立に覆われた辺り2か所には残雪があるが、そう長くは続かず、開放的な墓地
が並ぶ聖地公園に上がった。

台地上の公園から延びる車道をを南西へ。横瀬町十五番集落から上がってくる三差路際
に、移築された旧秩父駅舎があった。

大正3年(1914)に、秩父鉄道の前身、上武鉄道が大宮町(現秩父市)に延長され
たときに開設されたもの。昭和58年(1993)に、現在の秩父地域産業振興センター
内の駅舎建設に伴い、翌年移設したもので、駅舎の設計者は当地出身の坂本朋太郎博士と
いわれているという。
日が傾き、武甲山の雪模様も少しずつ望まれるようになってきた。

車道が秩父市外に向かって大きくヘヤピン状に下る辺りからは、秩父市の市街地やその
向こうの長尾根などが展望できる。

市街地に下って国道140号を横断し、西に平行する路地を進む。上宮地町の十字路際、
関根家墓地に「でんでい場のツバキ」と呼ぶツバキの大木が立っていた。

高さ6.6m、目通り1.3m、樹齢約250年という古木で、秩父市の天然記念物に指
定されている。
その通りを西進して秩父鉄道下を抜け、ゴールの秩父鉄道秩父駅には15時18分に着
いた。

下り電車まで時間があるので、駅舎の入っている秩父地場産業センタービルの1階にあ
る、秩父の土産品の並ぶ物産館を少しのぞく。
まだ時間があるので、線路際を進んで隣の御花畑駅を抜け、西武秩父駅まで歩く。西武
秩父駅発16時8分の上り電車で帰途についた。
(天気 快晴後晴、距離 16㎞、地図(1/2.5万) 皆野、歩行地 秩父市、累積
標高差 上り約430m、下り約380m、歩数 29,100)
にほんブログ村














