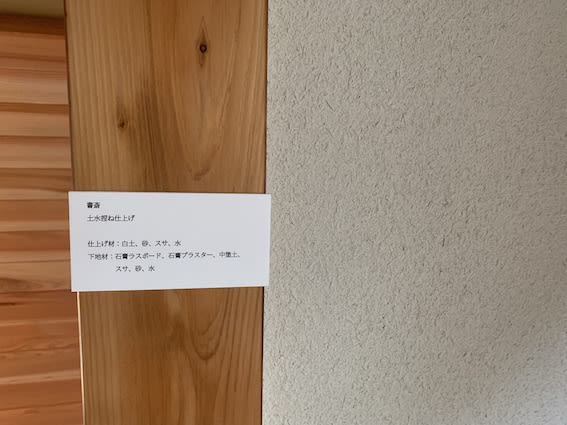先週の土曜日は、前もって申し込んでおいた
美術館の建築トークイベントへ。
会場は、満席。コロナ対策は万全と言えども
なかなかに密な会場でした。
関心が高いテーマでもあり
また、会場には、展示会の故人の建築家の縁の方々も多く。
久しぶり〜と再会を喜ぶ声が、
あちこちの席から聞こえてきます。
私も知ったお顔が何人かいらしたのですが
タイトな時間で来場しているので、おしゃべりはお預けし
急ぎ会場を後にしました。
訪ねた東京都現代美術館は本当に久しぶりでした。
ここ数年、行きたい美術展を何回か見送っていました。
今回は、建築家、吉阪隆正の展覧会。
トークイベントに応募できたこともあり
かなり楽しめました。
模型と、図面と、写真の迫力。
吉阪氏の元に集まった仲間たちの熱量が
ムンムンする会場展示。

会場には、私が大好きな吉阪邸の、
次男さんによる実測断面図が、
なんと壁一面に拡大されていました。

昨日は、描いたご本人もいらして、
お父様そっくりなヒゲのお姿に、密かに感動を、覚えました。
きっと私の世代は、著作などで、
いつの間にか影響を受けた建築家ではないでしょうか。
トークイベントでは、
吉阪氏に学び、ともに建築を創り、
象設計集団を立ち上げた樋口裕康氏の語りにて、
私の知らない故人の人となり、ものづくりの姿勢など、
知ることが出来ました。
樋口氏が話された、
「図面も良いけど、吉阪の言葉に注目して!」のアドバイスに従い、
書籍は「ことばが姿へ」を、買わせて頂きました。

樋口氏からは、今の建築の課題、我々への叱咤激励があり、
情熱を呼び覚ましてもらった感じです。
吉阪隆正氏の著書は、それなりに学生時代に読んだはず。
なのに、まったく詳しくなかった理由がわかりました。
早逝されていたのです。登山家でもあり、山で。
そうだったのですね。。。情報が途絶えるはずです。
笑顔の建築の先生というのは、私の恩師
延藤安弘先生くらいだと思っていましたが、
吉坂氏も、笑顔の写真ばかりでした。
そのヒゲの横顔から、(代表的な写真)
気難しく、神経質な方なのかなと。
でも、違っていたようです。
住まいを中心に考える建築家は、笑顔で居られる?!
というのも、発見でした。
私も笑顔で居たいなぁ。。。
家族思いで、それでいて、海外にも出かけ、
好きな山にも登り、後輩たちを育てつつ、建築を生み出す。
そのエネルギーは、どこから来たのかなぁ。
と探るような気持ちで展覧会を拝見しました。
社会に対する問題意識と、
自分自身を楽しむ生き方かなぁ、、
まぁ、子育てと、家事と、
そういったことを奥様に任せたから?
そういったことを奥様に任せたから?
でもあるのでしょうけれどね。
この方のように、自由に、軽やかに、そして楽しく
建築のものづくりをやってのけることは、
家庭のある女性には
同じようにはできないよなぁ。ではどうするか?
何を、学んで、何を真似られるかしら?
とにかく、研究室に泊まり込むような体制で、
建築の議論と、創作。若いときは、できたけど、笑。
うん。趣味も極めたところとか。
笑顔で周りと楽しく(時に苦しく)やりきったところとか、
でしょうか。
建築の思想や発想。そういったものは
時代の流れと、自身のポリシーがあるので
まったく、同感!というわけにはいきません。
雨が守る住まいとか、はさけたい。ははは。
自然を破壊して大きなものを作るより
分散させて、緑の中に溶け込むような建築を創ったり
来る災害に備え、住まいの防災を重視すべきとか
そういったことから、
雪山登山の経験から、とんがり屋根なら
雪が積もらないのでは?というアイデァが出たりとか、
そういったことを、展示されている写真から読み取りながら
こうして、知恵を次世代につないでいくこともまた
建築家のエネルギーなのかもしれないと、思い至りました。

本人が、創れなかった建築も、形を変えて、
人を変えて、受けつがれていく。。。
そういったことも、建築家の役割なのだなと
改めて感じ入りました。
企業も、何代にも渡って、発展していく。
家庭も、何代にも引き継がれて、継続していく。
建築も、何代か先に、実現できる社会と人材が育っていく。
素晴らしい思想や発想は、次世代で花開く!!
のかもしれない。と、そんなふうに思いました。
自分一人の代で、頑張ろうとするから、
疲れたり焦ったりするのではないか?
今、考えていることが、実現しないもどかさも、
いつか時代が追いついてくるかもしれない。。。
生ききった感のある展示に、うらやましくもあり
心残りもあったことだろうと、同情も抱いたりしながらも、
私は、私の進むべき所に行こうと、、、
諸先輩方の、頑張りも受け止めつつ
会場を後にしました。
企画、展示、そして、故人の建築家に感謝して。