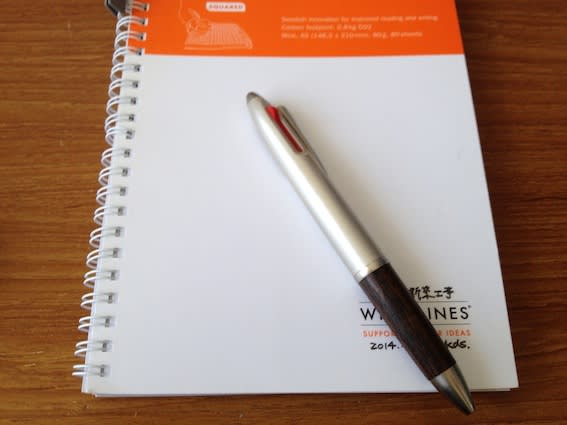マニアですけど、2009年に京都デザイン賞を受賞した
四条にある「木製ビル」の近くに泊まりました。
無垢板のスギ板は、少し日焼けしてましたけど、なかなかに美しかったです。
私が発表したのは、保育室の吸音実験。
私自身が研究者ではなく、正直、参加するかどうか迷いました。
ポスター作成や往復の時間、参加費用等、エネルギーを費やすからです。
しかし、この場で発表しなければ埋もれてしまう、
せっかくのチャンスと気を取り直し、
結果的には行って良かった!です。
その理由は、
1)人との出会い。
これまでのお付き合いのある方との再会と、新たな出会いがありました。
大学の先生や建築のものづくりの仲間、保育園経営者と、今のこども環境の課題と、未来のビジョンとそして手法について話しが出来たことは、何よりも収穫です。
森と樹と暮らしを繋ぐ重要性に気がついておられ、
同じように取り組んでいる方とも出会えて意気投合!嬉しかったですね。
やはり、こども環境アドバイザー1期生は問題意識も似ていました。
2)情報を得たこと。
京都の学校の作られ方の歴史。
『国の制度の前に町民がお金を出し合って建てた!』
↓町民が建てたときの門とコンクリートの学舎
今、熊本で活動しているスクールバスの活動が、国の制度にはないので、市の指導内容では民間委託の必要があり。が、しかし、歴史を作ること、動かすことは、市民の力と市民のシステムだということを実感。勇気をもらいました。
横浜で活動をご一緒していた先生とも再会し、観光バスを乗り合いバスにした事例があると教えて下さいました。感謝です!
3)健康への視点
建築の仲間からは得にくい、というか、ほとんど話さない視点。
健康について。
今回発表カテゴリーは『環境と健康』。建築空間に関するのは私だけでした。
湿度のこと、環境系の先生
照明と発達の関係性を検証、医学の先生
ろうの生徒への支援システム紹介、NPOの方
自閉症の子どもの行動評価、発達障碍研究所の方
こんなメンバーに囲まれて、私が日頃疑問に思っていることを、話せたことが嬉しいです。シックスクールやシックハウスの事例は発表がないことからも、建築と医学が繋がる視点がないことが分かります。
私が研究すべきはこの視点ではないか?と自分の役目がある気がしました。
当方の発表に対しては、
1)子どもの変化の様子が知りたい
2)吸音は湿度との関係があるが、そこは計ったのか?
など、まだ測定したり観察したり出来ていない部分をご指摘頂き、これまた感激ですね。どんどん、広がりそうです。
『木が五感に与える影響を数値化したい』この研究が出来ないか、方法を探って来ました。(←建築の分野ではないと某教授に言われ止まっている)『木の建築と健康』という視点で研究テーマが出来そうな予感!?
そして更に、忙しくなる予感!?、笑。
吸音に関しては高齢者施設も、母校の先生と熊本で調査開始する予定。
ますます時間管理が重要ですね。
めげませんよ===。本質に向かって邁進あるのみですから、笑。