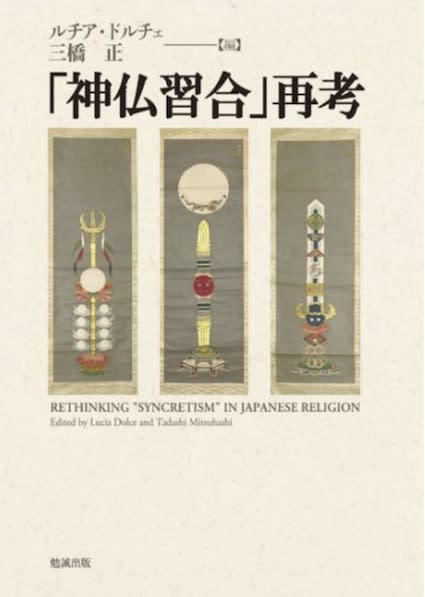今月は「with コロナの暮らし」について、
自分自身の体験、学び、発見、
なども盛り込んで綴っております。
本日のお題「片付け」に、ご興味のある方は、
参考にしてくださいませ。
1)はじめに
写真は、設計監理した
散らからない工夫の洗面脱衣室の例です。
工夫1)ゴチャゴチャしやすい脱衣コーナーは洗面台の奥に。
鏡を見るとき目に入らないように。
感染予防対策としては、手洗いうがいの時に、
着替えもしやすいことでしょうか。
工夫2)花台も兼ねた化粧台天板。きれいにしておくコーナー設置。
余計なものが置かれないように。
工夫3)毎日使う小物は見せて収納。
どこへ行ったか探さなくて済むように。
モノを増やさないで済むように。
(小物を隠したい方は、鏡の裏などに棚を設置してます)
2)次に、片付け本のご紹介
面白い切り口の、「片付け本」に偶然出会いました。
昨年のコロナ禍で、イベントや講師業の方など(男性)
「仕事が休みの分、掃除や片付けが進んだ」
というメールなど頂きました。
それは、それは、とても良いこと。
と、思う一方で、
奥様方にとっては、「普段の片付けに加えて
夫や子どもが家にいることで、
掃除や片付ける時間確保が出来なくなった」
「家族が協力してくれない。。。」
という方も、実際には多いのではないか?
と、にらんでおります。(小耳に挟みます、笑)
「亭主元気で留守が良い」は、
私としては、奥様方の共通認識ではないかと(笑)
そうでない家庭もあるとは思いたいのですが、、、。
私自身は、これまで、
大掃除はゴールデンウィーク(半分仕事しつつも)
と決めていました。
何も暮れの慌ただしい
寒い時にやらなくても、と。
年末は普段の掃除に加えて、
床拭きと、ほこり取りくらい。
しかし、昨今、熊本の行き来や
腰痛で、片付けがいつも通り行かなくなり、
さらに、子も夫も片付けられない症候群。
(その部分の発達が弱い)ので、
さらに散らかし放題に追い討ちをかけられて
手がつけられない状態です。(涙)
途方に暮れていた昨年。
たまたま、図書館の検索で、「すごい片付け」
という本がヒットしました。
別のものを検索していてのヒットなので、
まさに、セレンディピティー(偶然の必然!?)ですね。
その本はなんと、借りたい人が30人ほど待ち。
え〜、そんなに人気本なの?それとも効果あるの?
ということで、予約を申し込み、放っておいたら
昨年暮れ忘れた頃に、順番が来ました。
海外でも有名なト○キ○ク片付け(注)
というメソッドは、抽象的すぎて
どうも、取り入れにくかったのですが
こちらのメソッドは、腑に落ちました。
(注)
前者のメソッドも、某新聞で小説として連載中で、
それはそれで、楽しんで読ませてもらっています。
後者は、各部屋に、数秘術の数字を当てはめ、
その数字の持つ意味と役割と、
片付けられない理由が書いてあり、
当てはまりすぎて、笑えました。
例えば、「子ども部屋の物の多さと散らかりは、
子どものせいではなく、親の期待の表れ」とか。
ネタバレはいけませんので
このくらいにしておきます。
その場所、部屋の片付けの持つ意味と
「片付けられない理由に
隠された才能がある」とも書いてあり、
意味と役割があると
片付けの効果も、いろいろと期待できますし。
俄然、やる気が出ますよ===。
内容は、簡潔なので、
Kindle版でも良いと思います。
(1時間もあれば読めます)
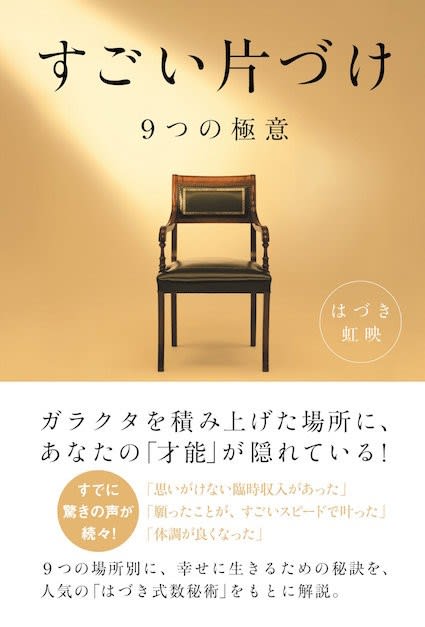
とにかく、肝は
片付けは、人生に、カタをつけること
片付かない人は、人生にカタが付いていない人
ということだそうです。
これはアマゾンで本の紹介にも書いてあるので
掲載OKとしましょうか。
中には、神道の禊祓(みそぎ、はらえ)の
ことなども出てきて、あらまぁ。
「家は神社のように整えよ」など。
へぇ〜、そういうことなの〜と。
私自身は、コロナの感染拡大が、
日本は、他諸国より抑えられているのも
清潔第一の日本人ならでは、
と思っているので、ここは納得。
筆者は、どちらかというと
占いやスピ系のジャンルの方。
たぶん、先のブログに書いたように、
神社系を図書館でかなり借りていたので
検索していて「神社」というキーワードに
ひっかかたんでしょうか。
まぁ、面白かったです。
深刻になりすぎず、真剣に取り組む
という私の人生ポジションには、
ハマりました。
『すごい』の意味は、、、
売るための、キャッチなコピーであり、
売るための、キャッチなコピーであり、
中身につけるタイトルとしては
『片付けと部屋の持つ意味とその役割』ですね。
昨年中に、一部は片付いたので
今年は、腰痛と向き合いつつも、
天気の良い日には、
部屋の役割と意味を「うふふ」と思いながら
片付けに、取り組みたいと思います。
楽しまなきゃ!ですね。
こちらの本では、
9つの数字で分かれているので、
月ごとで、分けて取り組んでも良いかもしれません。
私のように、片付けたいと思っていても
腰が重い方は、
片付いた後の自分の人生の未来と
空間の心地よさに、思いを馳せて、
取り組んでもらえればと思います。
3)自分自身の暮らしから
ここからは、私が心がけていること、
実践していることを少しご紹介します。
片付けても、片付けても
部屋が散らかる方。
家族が物を置いてしまう方。
平日は、掃除ができない方。
オススメは、
正常な場を1箇所だけでも作り
そこに目を向ける、です。
神棚とか、花台とか、洗面台に一輪挿しでもOK
暮らしって、一人だと自由すぎて片付かないし、
家族といれば、散らかるし、、、
何れにせよ、『暮らし=片付け』
と言っても過言ではないですよね。
自分の安定した精神を保つためにも、
花を活ける場所、絵を飾る場所
何か好きなものを置くコーナーなど
1箇所で良いのです。
そこで、毎日心を整えましょう。
そして、夜は、周りのあかりを消せば良いのです。
ごちゃごちゃが、見えないように。。。
綺麗なところだけ、スポットが当たるように
素敵な1角ができたら、置き型か、
クリップタイプの照明を当ててください。
夜のお花は心癒されます。

もし、夫が片付けられない、
妻が片付けられないで、
イライラしている方は、夕食をとる時だけでも
せめて、快適に過ごして欲しいですね。
ダイニングテーブルの上にも
物がごちゃごちゃあるのですって!?
そんな時は、大きめの風呂敷か、
クロスなどで覆っちゃいましょう。
人の欠点ばかり見えてしまうのが人間。
部屋も、そう。
だから、良いところに目を向ける工夫を!
疲れているときは、対処療法も必要です。
with コロナの新生活様式の中でも
どうか、皆様の人間関係のゴタゴタがなく
少しでも心落ち着けて
過ごしていただけますように。。。
お互いに、無理のない範囲で、
健康に暮らせるよう、
一歩一歩できるところから
一歩一歩できるところから
やって参りましょう。