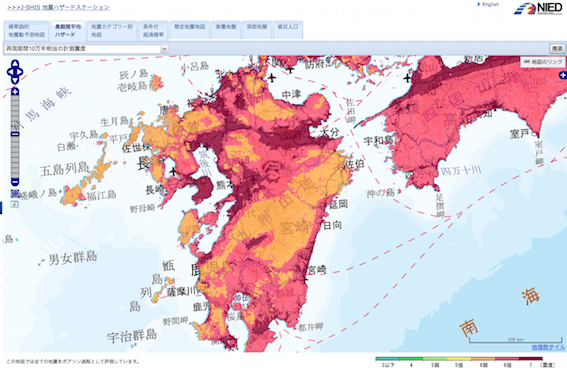木使いの仲間が、
私の絵本を会社の広報誌で紹介してくれている。


↑新星東部センターの瓦版
熊本地震の前に作られたもの。
会う約束もしていて果たせていなかった。
今日やっと、そのコピーを頂いた。ありがとう。
嬉しくて涙腺が緩んでしまいそうだった。
お互いに地震後どう過ごしたかの
報告をしあい。
被災して1階のない建物ばかりの
街をみたりすると、
やっぱりなんだか、ものづくりへの元気でないよね〜。
ため息もでるところ、気分転換の方法なども話しつつ。
私はというと 、いくら資材の価格が上がったとはいえ、
仕事の工事見積もりがあまりに高くて
がっくりきていたところに
お誘いいただき、仕事の愚痴も聞いてもらいながら
新しく挑戦する事業のことを少し話せた。
事業のことは、空白の1ヶ月。
事業計画書の作成も止まり、福岡での説明会にも欠席となり
補助金申請も見送ってしまった。
このタイミングで地震が起きて先に進むことが
止まってしまったことへの
意味を考えても堂々巡りするばかり。
自分のやりたいことがふやけてしまった地震後。
それでも、こうして仲間が励ましてくれることで
また、がんばろうって気になる。
「そろそろ家族を守るための元気から
周りを元気にするいつもの自分に戻ったら?」と言ってもらい、
そうだよ、チャレンジを忘れて停滞している
今の自分は自分らしくないなって思えてきた。
そして、彼が読んでいるという本からこの言葉をもらう。
「小屈大申」
「もし始めに不当な扱いを受けて悔しい思いをする小事があっても、
屈せずに乗り越えていけば、それが大事なる業績に伸展する。」
壬生寺の松浦俊海貫主さん紹介の言葉だそうだ。
そうだ!そうだ!
最初は小さなことからコツコツって、いつも自分に言い聞かせているじゃないか!
自分自身の中から沸き起こる小さな情熱のフツフツを大事にして
温めて、大きく育てていこう!
励ましに感謝して。
私の絵本を会社の広報誌で紹介してくれている。


↑新星東部センターの瓦版
熊本地震の前に作られたもの。
会う約束もしていて果たせていなかった。
今日やっと、そのコピーを頂いた。ありがとう。
嬉しくて涙腺が緩んでしまいそうだった。
お互いに地震後どう過ごしたかの
報告をしあい。
被災して1階のない建物ばかりの
街をみたりすると、
やっぱりなんだか、ものづくりへの元気でないよね〜。
ため息もでるところ、気分転換の方法なども話しつつ。
私はというと 、いくら資材の価格が上がったとはいえ、
仕事の工事見積もりがあまりに高くて
がっくりきていたところに
お誘いいただき、仕事の愚痴も聞いてもらいながら
新しく挑戦する事業のことを少し話せた。
事業のことは、空白の1ヶ月。
事業計画書の作成も止まり、福岡での説明会にも欠席となり
補助金申請も見送ってしまった。
このタイミングで地震が起きて先に進むことが
止まってしまったことへの
意味を考えても堂々巡りするばかり。
自分のやりたいことがふやけてしまった地震後。
それでも、こうして仲間が励ましてくれることで
また、がんばろうって気になる。
「そろそろ家族を守るための元気から
周りを元気にするいつもの自分に戻ったら?」と言ってもらい、
そうだよ、チャレンジを忘れて停滞している
今の自分は自分らしくないなって思えてきた。
そして、彼が読んでいるという本からこの言葉をもらう。
「小屈大申」
「もし始めに不当な扱いを受けて悔しい思いをする小事があっても、
屈せずに乗り越えていけば、それが大事なる業績に伸展する。」
壬生寺の松浦俊海貫主さん紹介の言葉だそうだ。
そうだ!そうだ!
最初は小さなことからコツコツって、いつも自分に言い聞かせているじゃないか!
自分自身の中から沸き起こる小さな情熱のフツフツを大事にして
温めて、大きく育てていこう!
励ましに感謝して。