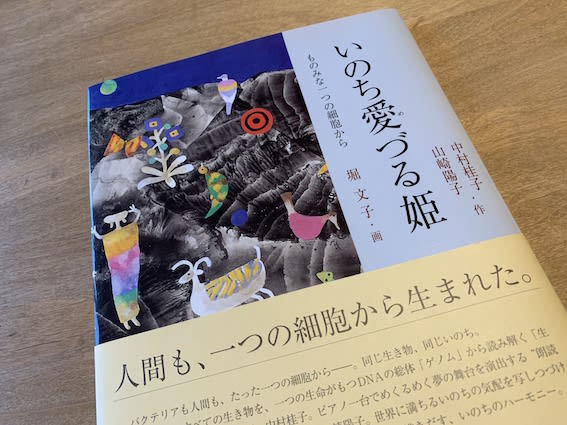サグラダ・ファミリ教会内部:樹木式構造
「好きな建築家は、誰?」
建築の学びの学生の間で、交わされるやりとり。
「最近、何が面白い建築?」
建築学科の、学生の間の日常会話の一つ。
「〇〇の展覧会が良かった!」
興奮気味に、感動を伝え合う仲間たち。
ガウディの建築に触れると、私はあの頃の
キラキラの、そして熱を帯びた学生たちの
建築熱を思い出す。
どこで、何を観るか。アレもコレも欲張りたい。
けれど、資金はなく。。。
一つだけ選べと、言われたたら?の質問に、
私は、迷いなく、「ガウディを観たい」と、答えた。
そして、スペインで実現させた卒業旅行。
今年は、その時の感動が蘇るだろうと、
一番の楽しみにしていたガウディ展が6月から始まった。

東京国立近代美術館で「ガウディとサグラダ・ファミリア展」
を観てきた。やっぱり、今でも、私の中で、一番だなと確信した。

ガウディ建築に初めて出会ったのは、もう、30年以上前なのに、
いつも新鮮で驚きの連続だ。
TVCMで起用された、「サグラダファミリア」を
見た時の衝撃は今でも忘れない。
これが、建築なのか!?と、息を飲んだ。
そして、本当にこれが建築で良いのか!?
という疑問も湧いた。
造形的で、彫刻かと見紛う建物。
そのスケールも、飛び抜けていて、にわかに信じがたい。
それが、実際にその場に立って、目にした時、
このバルセロナという都市で、スペインの いち地域で
全く違和感を感じなかった。
風土に合った建築というは、確かに存在するのだと
実感したものだ。
スペインの車窓から見た赤土の色も、乾いた大地も。
行き交う人々の笑顔も。全て、ガウディ建築にマッチしていた。
私が、知ったガウディの凄さは、
構造計算のない時代に、自然の摂理を建築に生かしたところだ。
コロニア・グエル協会の地下で見た釣り糸の実験に感動。
そのモデルも今回、展示があり、懐かしい。

ガウディのことは、まだ詳しく知らない学生だろうか。

図面を覗き込んで、
「すげぇ。こんな形、構造計算なんかしてないよな」
「してないでしょ。直感でやってんじゃね?」
という会話が微笑ましい。
(計算、してるよ~。数字上ではなくてね。)と、心の中で呟く。
きっと、実験コーナーに行って、感動するに違いない。
その時代にあって、最先端を行こうとすれば、
自分で試すしかないのだ!
現地スペインで、知ったガウディの知識として感動したのは、2点。
その実験と、誕生日が私と同じで6月だったというところ。←えっ、そこ!?
奉仕の星座なのよねぇ。まさか、同じとはねぇ。
建築の実際の体感としては、
もう、凄すぎて、言葉にはできませ~ん。
カーブを描いている椅子の座り心地の、
柔らかさと包まれるような安心感。
厳かなはずの、協会の中の空間が、なぜか懐かしい感覚。
いつまでも、そこに居ていいよと言ってもらえるような
ずっと感じていたい心地よさ。
手仕事と、人間的なデザインからくる
まさに、人に愛を与える空間と表現しても
決して大袈裟にならない。と思う。
今回の展示で、そこには、
「奉仕の愛」があったのだと再認識した。
技術的には、破砕タイル、幾何学、
そういったものを建築に初めての取り込んだのが
ガウディとある。


その発想は、きっと、愛情深い思想からきているのだと、
私は思う。(感じるに近いかも)
出てきた形より、形を導き出した根本の
思想や思考に興味がある。
思想や思考に興味がある。
今回の展示で、学生時代のガウディの学びの精神や、
描こうとしていた世界観への理解が深まった。
その点では、確かに、良かった。
でも、やっぱり、映像や模型、図面では、
本物の感動は超えないあなぁと
本物の感動は超えないあなぁと
ないものねだりもしたりして。
ガウディは、浮浪者のような格好で亡くなり、
国葬は、本人の遺言で、行われずとも、
多くの参列者が列を成した最期だったそうだ。
漫画家が、現地で調べたガウディの生い立ち紹介を
建築雑誌に掲載していたものでは
愛した女性との結婚も出来なかったようだし。
(お相手はお金持ちを選んだらしい)
そんなプライベートでは、恵まれなかった生き様は
ガウディを、建築のものづくりに向かわせた
神の悪戯だったのかもしれない。
歴史からの学び、建築の美への探求と実験、諦めないしつこさは理想の追求の証、
奢らないものづくりは、奉仕の精神から。
そして、サグラダファミリア協会に愛を注いだ一生。
これらが、今回の展示で、私の中に、
より深く刻まれたキーワードである。
より深く刻まれたキーワードである。
そしてガウディの言葉の中では、
「人は創造しない。人は発見し、その発見から出発する」という言葉だ。歴史、自然の造形、
購入した図録で、ゆっくり、じっくり、再確認しよう。

展示では、半分ほど撮影かとなっており、
学生さんの学びの場としても、大いに役立つはず。
これから9月まで。建築学生さん以外にも
ぜひ、足を運んでほしい。
詳しくは、こちらをどうぞ。