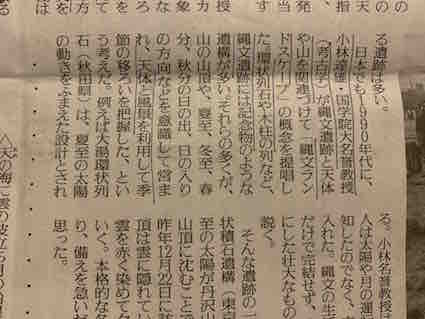変なブログのタイトルだと、思われたでしょうね。
先のブログの続きです。
そう、1日で観て回った内容がこれなのです。
そう、1日で観て回った内容がこれなのです。
もう、帰宅時にはお腹いっぱいでした。
夜も興奮して眠れないほど!?
盛りだくさんな建築とアートと音楽体験。
盛りだくさんな建築とアートと音楽体験。
久しぶりだったからでしょうね。
沢山の感動があったのです。
これまでも、心が鬱々となるとき
アートには随分と助けられてきました。
音楽やダンスにも。
先のブログに書いたように、心が晴れやかになった分、
もっと、素直に感じることが出来たように思います。
洋館に美術館にと付き合ってくれた友人には感謝!
彼女の美的センスと、知識にも、沢山の話ができて、
本当に、私は、何だか救われた感じでした。
最初は、登録有形文化財になった平塚の八幡山の洋館。
横浜ゴムに払い下げられた戦前の建物で、
元はイギリス人のエンジニアを迎えて作られた火薬庫のあった場所に建っていました。

この建物は、神奈川県建築士会の先輩方が保存活用に尽力された経緯があり、勉強会でお話は伺っていました。
ただ、子育て真っ最中で見学会などには参加できず
やっと実物を拝観し、体感出来たというわけです。

外観のピンク色は、黄色の時代もあったのだとか。
パンフレットなどには、書かれていませんが、
戦前イギリス、日本、戦後アメリカが関わる中で、
この建物も翻弄されたようです。
復原と復元の違い、
建築の復原は、いつの時代に戻すかで議論されると、
この時に教わりました。
床からの出窓、特徴的なベイウィンドウ

床下換気グリルの鋳物のデザインもとても可愛らしい。

現在は、移築復原で、市民のイベント会場として、
活発に利用されているようです。
この日は、コンサートが開催されており、コントラバスとピアノの演奏を天井の高い洋館の、それでいてホールほど大規模ではない部屋で、
演奏者の息遣いも聞こえるほどの近距離で満喫しました。
保存される建物は、「市民に愛されている」という条件を、
まさに見せつけられる感じで受付の方から、中の誘導の方まで、
積極的にこの建物の特性を説明してくださいます。
こういう時は、建築の専門であることは内緒にしておくのがベター。
その姿は、市民としての誇りと喜びを感じられるからです。
素敵な空間を味合わせてもらいました。ありがとう。
残してくださった方、そして、活用してくださっている方。
次は、その足で、公園を抜けて、平塚市立美術館へ。

目的は、我らが殿、元熊本県知事で、首相も務めた
細川護煕氏の個展を見るためです。
招待券を頂いていたので、郷里の友人を誘ったのでした。
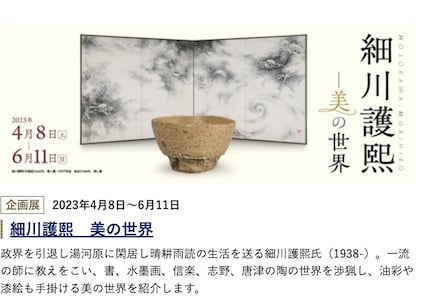
リンク先はこちら
政界を引退後、陶芸家になっているというのは、もう随分前から知ってはいました。
販売もしており、人気も高いとの噂も耳にはしていました。
作品をまじまじと見るのは初めて。そのセンスの良さに、脱帽でした。
友人はお茶をやっているので、私より茶器には詳しく、
実物も何度か観たことがあるそう。
今回は、書や歴代の作品が一堂に介し、
護煕氏の集大成とも言える個展でした。
護煕氏の集大成とも言える個展でした。
信楽焼、美濃焼、楽焼、、、、とあらゆる焼き物がありました。
護煕氏は、様々陶芸家の第一人者の門戸を叩いて、
習っているのだとのこと。
習っているのだとのこと。
「殿が門を叩いたら、開けないわけには、いかないよね。」
と笑い合いました。
と笑い合いました。
観て回って感じたことは、作品に「欲がない」こと。
アーティストの場合、斬新なものを作って見せようとか
売れてやろうとか、突き詰めてやろうとか、
その熱いエネルギーが迸っているものですが
なんというか、素直な作りで、嫌味がない。
それが人気の秘密なのかもしれないなと思いました。
技術レベルは、素晴らしく、芸術性も高いけれど嫌味がない。
さらに、政界のトップだった人という著名人としてのブランド価値。
書籍販売コーナーで、全部作品集は買っているというご婦人と出会い、
客層を垣間見た気がします。
建築家藤森氏が、工房と茶室を創っているので、
その講演会もありました。
その講演会もありました。
裏話で面白かったのが、細川氏は多くの建築家に知り合いがいる。
有名な方から、若手まで。
熊本アートポリス=建築家が熊本に作品を作る事業
を県知事時代に立ち上げた方ですから、そうなのでしょう。
だけれど、その中で、一緒にモノづくりをやってくれそうな方がおらず
藤森氏に白羽の矢が当たったのだとか。
「建築家あるある」の話に思わず、吹き出してしまいました。
スライドでは、殿自ら、銅板の外壁を施工している様子が映されました。
県知事になると箱物を作りたがるのが政治家だと思っていましたが、
このかたは、本当に自分から造りたかったのですね!
「不東」という雅号については、
「東=霞ヶ関」には関わらないという思いが
「東=霞ヶ関」には関わらないという思いが
込められているのだとか。
そんなユニークな話も伺いながら、
再度作品を見て回ると、また新鮮でした。
再度作品を見て回ると、また新鮮でした。
そして、常設展では、モノクロの世界。
私の大好きな白と黒。。。究極だからです。
どんな色よりも奥が深い。
どんな色よりも奥が深い。
それを、様々な手法で描かれた作品を見て、打ちのめされました。
カラーの作品は、観た時は、圧巻されますが、
後々、思い出せるかというと、そうは多くはありません。
撮影可だった作品。写真よりリアル。

こちらの作品は、脳裏に焼き付いてしまいました。
恐るべし、モノクロの世界。。。
建築のモノづくりだと、どう置き換えられるだろうか。。。。
そんなことを考えながら、作品を後にしました。
最後、帰りのバスの時間を待つ間に、
立ち寄った民間の崩壊コーナーでは
西陣織で、若冲の絵を再現しているという紹介がありました。
またまたこれが見事で。
極細の絹糸で仕上がっているそれは、立体感が素晴らしいのです。
若冲の世界観を見事に表現していました。
(写真はありません。数年前から全国で巡回展をされているので
ご覧にった方も多いかもしれません)
このような活動をしているのは、技術を絶やさないためなのだとか。
帯の需要がないために、工房も相当数減ってきているそうです。
うむ。さて、どうしたものか。
「ザ・和」の掛け軸なので、
この作品を、私の設計する空間に合うかと言われると、非常に難しい。
古民家再生か、和室を作る場合か。。。。
額もあります。と見せられたけれど、
額は若冲にはふさわしくないと感じました。
どうしても、
何事も、建築の空間と結びつけて考えてしまいます。
それでも、こうしてリラックスしながら、鑑賞し
我が国のごちゃ混ぜ文化に触れて、
建築も同じだなぁ。。。なんでもありな日本と思いつつ、
リフレッシュできたことに感謝!
そして、いよいよ取り組まねば!
この数年、先送りになっていた事務所のHPの更新!
この数年、先送りになっていた事務所のHPの更新!
リニューアルしたくても、ソフト自体を大幅に変えないとできない
と言われて、時間的な余裕なくそのままになっています。
と言われて、時間的な余裕なくそのままになっています。
さぁ、出すエネルギーばかりだった数年前から
蓄積できつつある昨今。
自分自身のやりたいことに注力していきます!