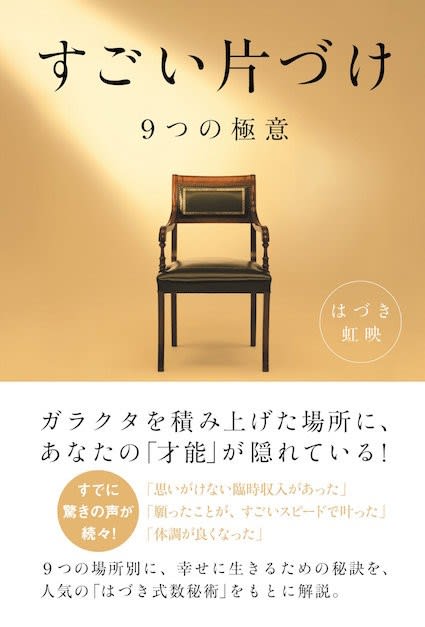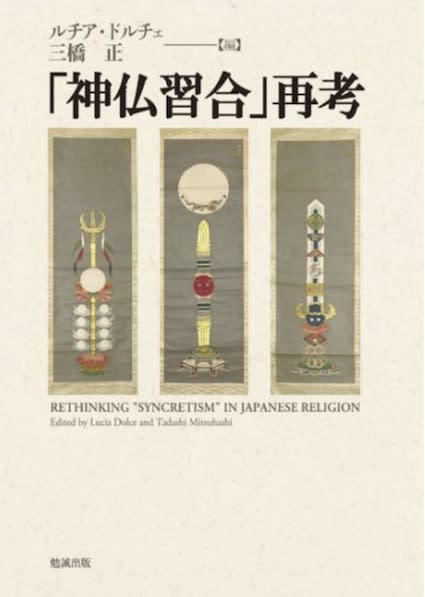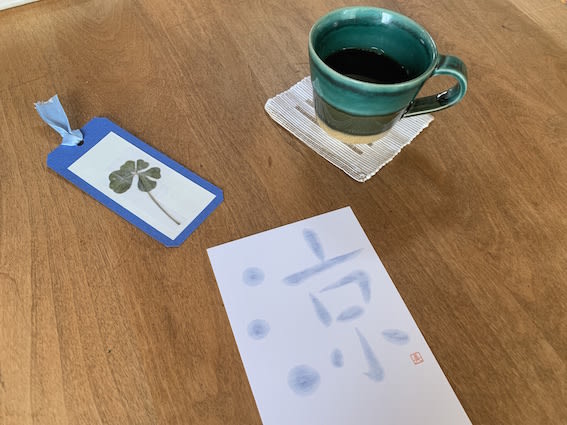
オリンピックも熱いですが、
気温も熱いですねー。
みなさま
お元気でお過ごしでしょうか。
信じられないかもしれませんが、
横浜の家には、リビングダイニングに
クーラーがありません。
風通しと遮蔽で、まぁ過ごしております。
(そういう設計になっております。断熱も効いてます。)
(そういう設計になっております。断熱も効いてます。)
扇風機くらいは回します。
(学生時代からの愛用品、30年以上経過)
あとは、涼しい格好と(笑)、
首の保冷剤巻きでしょうか。。。
我慢大会のような気もしますが、
日が暮れれば、涼しくなりますし、
多分、夏生まれで暑さに強いのかなって思いますね。
食欲も落ちないですし。
オリンピックのネット配信を見ながら
暑中伺いを書きつつ、
コーヒーはいつもよりぬるめで
の夏のダイニング、週末の写真です。
今日のブログのテーマは、
先週末にZOOMで参加した
住総研のシンポジウムから。

ヘリテージマネージャーの講座でもお世話になっている
工学院大学の後藤治先生が出られるとあって、
面白いに違いないと、早々に申し込んでいました。
それから、チラシに
「将来の住まいや暮らしの在り方に、
どう生かせるのかを議論したい
」
と、あったからです。
シンポのタイトルは
「歴史のなかの「あこがれ」の 住まいと暮らし」
とあり、「あこがれ」が将来に生かせるのか?
と、あまりピンとこなかったのですが、
実際には、「和室」の成り立ちや、
海外からの「和室」や「日本」の評価
そして、日本とデンマークの住まいに関する認識が
あまりにも違うというアンケート結果の
講演内容は興味深かったです。
一人暮らしの片付いた部屋のデンマークの写真と
散らかった日本人の部屋。これは極端な例でしょうが
アンケート結果からは、
デンマークでは、人を呼ぶ家、自己実現を行うのが
住まいと考えているのに対し
日本では、自分一人でくつろぐ場所
のんびり過ごす場としての住まい
と、大きな違いがあるという報告は
苦笑いと共に、海外の方の意識の高さに驚きました。
登壇者のメンバーは、チラシの案内に譲るとして、

増えた知識をメモしますと、
和室は、武家社会の「座敷」=「人の集まる場所」がスタート。
鎌倉時代に登場した。というもの。
玄関は、農家にはなく、武家屋敷にだけ
認められた空間であるという認識はあったのですが
公家社会(貴族が政権を握っている)から、
武士という実力主義になっていく過程で、
一同が車座になる場所が必要で、
それが和室を創っていったとの説。
ふむふむ。
社会的背景と住まい空間が直結しているわけですね。
昨年の民家再生協会の連続講座で学んだ
「日本の住まいの源流」では、
農家に座敷が出てきたのは、(それまでは板間と土間のみ)
仏教の普及が理由でした。
つまり、お坊さんを家に招くのに、
座敷が必要になったということでした。
大きな日本社会の歴史的背景が、
実に住まいには、様々に反映されるていくわけです。
日本の住まいは、世界はどう変化していくでしょうか。
この流れで、いくと、このコロナ禍で、
清潔国日本に学んで、各国の土足文化が
減るかもしれませんね!?
すでに、上履きに履き替えるという流れは
かなり、海外にも浸透していますが、
接客の仕方や、住まいの用途が変わってくるかもしれません。
一方で、そう大きく変化もすぐには反映されないのが営み。
社会情勢、人々の需要と課題をにらみつつ、
私も暮らし方の在り方を提案していきたいですね。
結局シンポジウムでは、結論的なものは出ず
次回の講演に引き継ぐというものでした。
主催者の団体から「和室学」という本が出版され、
その紹介がありました。

畳が海外からSDGdの視点で
高評価を得ているようですね。
書籍にも学びながら、
研究者の先生方の最先端の報告も伺いながら
今の社会を乗り切る住まい・暮らしを考えて参ります。