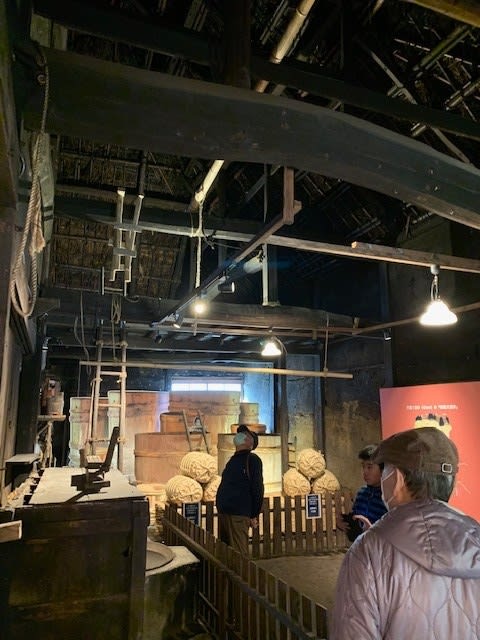「くまもと木の空間づくり支援事業」を受けて、
熊本県産木材を活用した、店舗の内装木質化も進み、
週末のリニューアルオープンに向けて、
ブラッシュアップ中です。

依頼主さまは、熊本地震から、ご自宅再建後
やっとここまで来られました。
当方のHPでは、工事進捗状況と
http://www.mk-ds.jp/newworks/2019/01/2019-1.html
イベントの案内をしています。
http://www.mk-ds.jp/news/2019/01/-normal-0-10-pt-0-2-false-false-false-3.html
今年の干支のイノシシも登場。

森と樹と暮らしを繋ぐプロジェクトFBでもご案内しています。
下記チラシは、拡大してご覧ください。

一人でも多くの方に、くまもとの木の空間を
感じていただけたら幸いです。