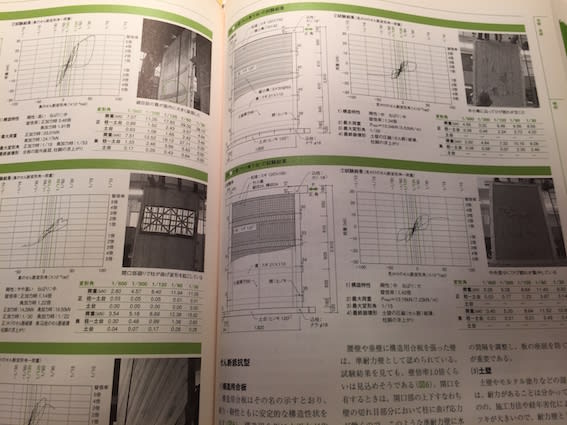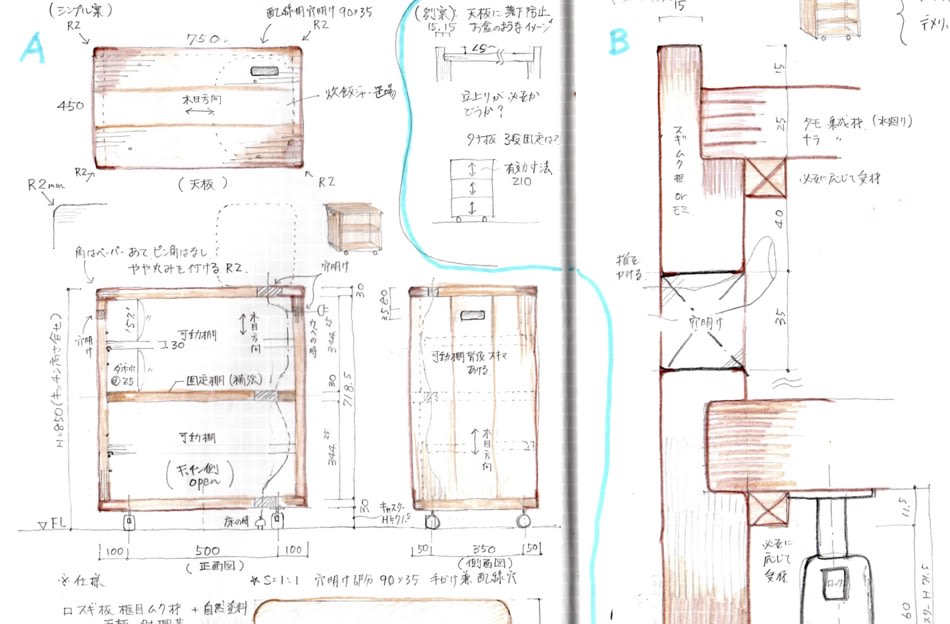
設計中の改修工事の中で、
ちょっとした「家具が欲しい」のご要望にお応えして
家具のスケッチ中。
木の家具やディテールは、どうもCADでは表現しにくいし、
イメージも伝わりにくい。
手書きスケッチに色塗りの方が、
依頼主さんにも職人さんにも伝わる気がしてなりません。
最近、マウスの使いすぎで右肘を痛めているから!?
という理由ではありません、笑。
面白いところに針を打ったりして、
行きつけ!?の整骨院で治療してもらったこの夏。

冗談はさておき、
国産木材、杉、ヒノキの家具は部材が肉厚になりがち。
下手すると重厚感が増しすぎます。
割り切って木目をスッキリ見せるB案が良いなぁ。
と、家具製作者に打診中。
うまくいくとありがたいですねどね〜。ご予算の方も。
日本の木と向き合う時、本当にありのままの木目を綺麗に見せる
というポイントで使う方がデザイン的には良いと思う今日この頃。
勤めている時に、公共建築の家具をデザインしていた時は、、、
それはそれは懲りました。
今は、どれだけシンプルにそぎ落とすか
というのがテーマのような気がします。
それに、製作してくださる方の温もりも伝わるような。。。。
手仕事感が伝わる木。
できれば、末長く使って欲しいですね!