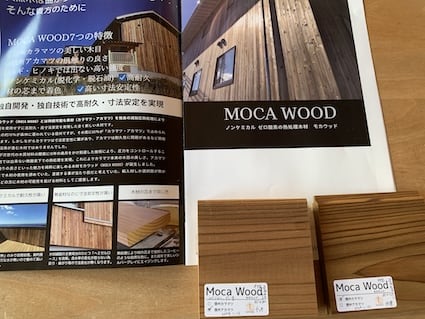オンラインの発達のおかげで
これまで参加できなかったようなシンポジウムや
フォーラムが、視聴できるようになり
本当にありがたいと思います。
特に、地方に居ると、
人からの情報、
広告からの情報、
そして、各種イベントに参加できず、
最先端の情報が得られずに
モヤモヤとしていた時期もありました。
建築の分野は、そんなにメジャーではなく、
一部のメディアを通じてしか、なかなか情報を得られず
書籍や、口コミに頼るということも、多々あり。
それが今では、どうでしょう。
在宅でも、カフェでも、出張先のホテルでも
Wi-fi環境が整っていれば、全く自由にオンラインで
様々な勉強会やイベントに参加できるのです。
当然、交流や名刺交換などはできませんが
情報に関しては、得ることができます。
小さな子どもが居ても、参加出来なくはない!
子どもが小学校を卒業するまでは、
本当にいろいろなことを諦めていました。
まぁ、子育てが一番と割り切って。
でも、今はどうでしょう。
学び続けることが、情報を得続けることは
可能になりました。
仕事に復帰しても、浦島太郎状態にならずに済みます。(笑)
まぁ、子育てに専念する場合には、
(焦ったり、イライラしたりしないためにも)
あえて仕事の情報を遠ざけて集中するという
テクニック!?がむしろ必要なくらい
の世の中になってきました。
そして、コロナ禍では、今まで通りに、思い立ったら行動!
と言うわけには、なかなか出来ない分、
じっと学んだり、作戦を練ったり。。。
の時間が増えました。
昨日参加した、
日経主催のSDGsフォーラム特別シンポジウム
「森林・木材の利活用で実現する脱炭素社会」
も、その一つです。
登壇メンバーと、各発表テーマを拝見して
私の知らない情報がありそう、と判断してのことです。基調講演の一人
結果は、知っている情報が半分、(日本の山の状況や課題)
知らない情報が半分(各企業の取り組みなど)でした。
前置きが長くなりました。本題をまとめます。
1)最新技術の調査解析をどう活かすのか?
新しい情報としては、
ドローンや航空機を使っての
地形解析によるスマート林業支援。
存在は知っていましたが、
どのように解析しているのかということまでは知識になく、
その道のプロのお話は、非常にきめ細やかで
頼もしくなりました。
一方で、
このデータをどう活用していくのか
まだ見えてきません。
登壇者ご自身も
「ここまで調査できるのを、凄いね。で終わらせず
活用して欲しい」と、おっしゃっていました。
いまだ、現場では、
昭和の機械も使われている伐採現場。
いずれ、遠隔操作で、危険な地域などではアバターで操作し、
ロボットで伐採するという日も来るかもしれません。
介護ロボットは、人に直結して見えるので
開発が進んでいますが、
最も危険な産業と言われる林業も
きっと、山猿ロボット(!?)が現れるだろうなと、予感します。
これは、私の考えですが、
急傾斜には、もう、植林しないで、
根を張る自然林にし
土砂災害被害を防ぐというのが、一番
なのですけどね。
2)水脈調査に見る森林の実態
また別の飲料メーカーからは、水脈分析の発表がありました。
天然林の育成と、水資源の活用と、循環型社会の実現。
素晴らしい響きで、聞こえとても良いですね。
水脈は、彼らにとっては鉱脈と同じで、金脈です。
山の資源をタダでもらっているのです。
森づくりは当たり前でしょう!
と、密かなツッコミも入れつつ。
ここまで来たか!と驚きのデータでした。
こちらの企業の森づくりイベントには参加したことがあり
取り組みは正しいと思っています。
一方でもちろん疑問もあります。地域住民への配慮は?
この企業が進出した地域は、井戸が枯れる。との評判です。
水脈が変わるからです。そのうちに戻ってくるらしいのですが、、、、
その量は、確実に減っています。
本来ならば、湧き水となっていたものを飲料にしてきた
古来の日本。
それを、水道という形で、整備し
そのおかげで、このコロナ禍でも、
手洗いうがいがが日常的に出来、
消毒も、清掃もできる清潔大国日本。
全ては、水のおかげです。
その生活以上に、嗜好品として、便利品として
生まれたペットボトルの水。
災害時など、非常時へのストックには便利ですが、
日常で使うのは、どうなのでしょうか。。。
水資源は人間だけのものではなく、
動植物への影響がとても大きいのです。
実際に工場がある地域の、里での
山の植生の貧相さを感じている身としては
そのあたりの解析や分析も今後は
してくれたら良いのにと強く感じました。
3)木材の蓄積炭素量を、売買に使う発想。
さすが、商社は違う。(Jクレジットという商社のアイデァを聴いて)
全て、お金換算するのだなぁと、感心。
脱炭素、カーボンゼロの言葉には、カラクリがあり
CO2を排出した分を、他の地域から購入すれば、
チャラにできるということがります。
工場などで、どんどん排気ガスを出したら、
山の山林を買ってね。クレジット(借り入れ)として。
という仕組みを作ろうということでした。
手入れの行き届いていない、放置林や売りたい山林を
木材の資源地として、買い取り、使うのではなく、あくまで
CO2固定として購入するということですね。
その後は、どうなっていくのか、、、
買った後は、伐採して、新しく植林して
炭素固定量を増やすというところまで、行ければ良いのですが
そこまでの資金力がなければ、持ち主の名義が変わっただけで、
買うだけと、なってしまわないか、、、、
会場に居れば質問したいところでした。
最先端を行く各社の、どの発表にも、なるほどと思う箇所と
はて、どうしていくのか?という部分と両側面あり。
それだけ、この森林の課題は、難しいのでしょう。
SDG sという言葉を多用した、
ええかっこしい〜のスタイルだけというのには、
声を上げるだけで、実質がともなわないという
気持ち悪い側面もあります。
それでも、企業は、絶対に避けて通れなくなりましかたら、
知恵が集まってきたのは、良い傾向だなと思います。
4)現実は、まだまだ改善途中。
行政や研究者のデータからは、相変わらず、
植林の木材1本の価格の安さの指摘がありました。
数年前、行政の森林贈与税の活用に審議委員の会議で
スギの価格が横ばいというデータが出てきました。
そのことはすでに知っていたので、
物価上昇を考えたら、相対的には、もっと低くなるはず
そのデータはないのか?という問いに、
コンサルからは提示されませんでした。
それが今回、林野庁の資料で、
物価上昇と比較した資料が提示されました。林野庁長官の資料より

こちらの発表資料に
物価との差額(黒矢印)を書き入れてみました。
戦後から15年後の1960年代、バブルな1990年代も
差額は、全体の物価とほぼ同じです。
ところが2000年代は、どんどん広がっていき、
以前の3倍以上の差が広がっています。(黒矢印の長さ)
 つまり、横ばいではなく、
つまり、横ばいではなく、どんどん下降しているという証拠が出たわけです。
その開きのあまりの大きさに、私は絶句します。
数十年という長い間、育ててきた樹が
(実際には、ほっておかれた場所もありますが)
時間が経てば経つほど、価値が上がる予定だったのが、、、、
下がっていく現象。
確実に変な現象ですよね。
経営が成り立つはずもありません。
木材の価値を上げる工夫を、
これまでも一部の生産者や製材所、販売者はしてきたわけです。
付加価値をつけたり。。それでも、この結果です。
ここで、大きな気づきがありました。
実際の林業に関わっておられる方は、よく分かると思います。
つまり、現実社会のスピードに追いつかないのが、木材の生産。
様々なことが、効率化、合理化が進み
食(温室栽培や肥料により)も、衣料(機械科により)も、
プラスチック製品も、簡単に製作できるようになりました。
しかし、樹だけは、命が宿るもの。
自然の気候任せそのものです。
(植林だって、最初は肥料をやりますが)
海外の暖かな地域で早く育つ木や、
天然林を伐採したおかげで、
あたかも、効率良く製作できていた
日本の住まい建築の現状。
ウッドショックで分かったように、
これからは、そうはいかなくなります。
成長の早いスギの開発(エリート種)を植える方向もあるそうです。
過去に、ドイツで、上手くいっていなかったエリート種。
仮に、育成期間が短くなったとしても、
数十年も早まるわけではありません。
私は、この植林と、子育ては同じだと思っています。
人間の寿命は長くなったけれど、
子どもの身体的成長が早まったわけではありません。
しっかりと手入れ(下草刈り)、
しっかりと教育
しないとまっすぐ育たない(笑)
個性的に育つ=曲がった木も、もちろんありです。
現状は、英語やプログラミング、投資、、、など
今、こどもの教育現場で取り入れられている授業が
早く大人になるのを促しているようにしか見えない
(国も、試行錯誤なのもわかりますが)
根本的な教育の質の向上になっているのか、疑問も残る中、
植林と、同じような試行錯誤に見えてしまうのです。
自然に介入した効率化、合理化、、、
本来は、自然こそ、循環しているのだけれど、
その中での淘汰の結果なのだけれど、、、、
このテーマは、長くなるので、自分の中への落とし込みに、
今回は留めます。
今回のシンポジウムで、やはり不足しているのは、
仕組みづくりだなと改めて考えさせられました。
様々な、場の提供(プラットフォーム)や開発研究は
もちろん、各分野の専門家に、引き続き継続していただき、
抜けているなと感じる部分を、
建築士×こども環境アドバイザー×木育インストラクターの立場で、
検証していこうと思います。
温めてきたアイデァを実行に移すときでしょうか。。。
(かなり長期戦の予感)