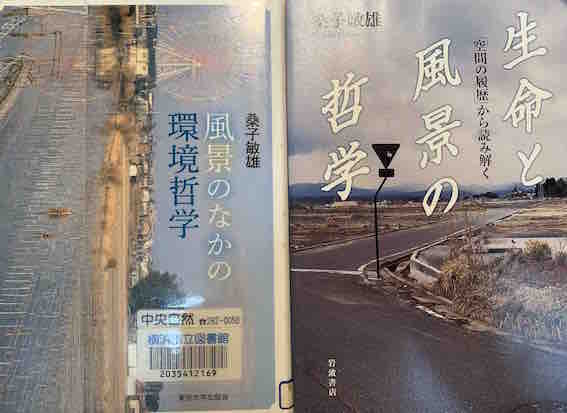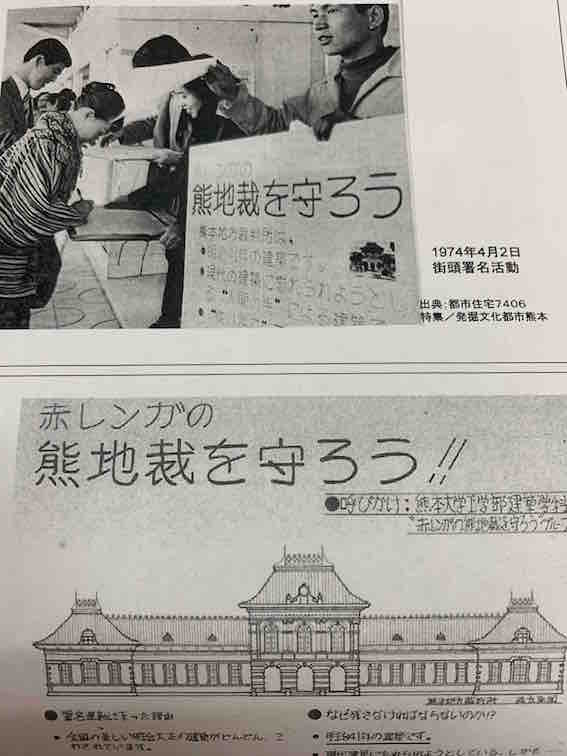私の生まれ故郷でもある八代に、新しい建築ができました。
設計監理は、最近ご活躍の若手の方です。
施設的には、それほど大規模なものではありませんが、
地域の核となる建物です。
第25回くまもとアートポリス推進賞を受賞を受賞しています。
詳しくはこちら
熊本在住時に、この施設を訪れて
色々なことを考えてしまいました。
建築がどうのこうのというわけではなく、
そのプログラム自体についてです。
この施設が計画されたきっかけは、地域のお祭りが
ユネスコの無形登録文化遺産に登録されたことです。
国指定重要無形民俗文化財「八代妙見祭の神幸行事」
お祭りの詳細は、こちら、https://myouken.com
メインの妙見祭が、平成23年に国重要無形民俗文化財に指定。
平成28年1には、全国32の祭りとともに「山・鉾・屋台行事」
平成28年1には、全国32の祭りとともに「山・鉾・屋台行事」
としてユネスコ無形文化遺産に登録されました。
この地域の無形民俗文化財の保存継承,
交流促進の拠点の施設として計画されました。
建物には、地域の笠鉾が全て保管されています。
そして、交代で、展示されます。
劣化を防ぐために、ライトに当て続けないためだそうです。
また、入場料を払って、各傘鉾を見て欲しいという
運営側の意図もあるかもしれません。
その笠鉾の意匠は、まさに、地域それぞれで大変ユニークなものです。
私が訪問した際は、みかんが乗っている笠鉾でした。
ボランティアガイドさんによると、将軍家にも奉納した
みかんなのだとか。

その地域の、誇るもの、由緒のあるもの、大事にしているもの
などが最上段に飾られています。
本当に精密にできていて、個性的。
他のものは、写真やイラストでしか拝見できませんでしたが
感動ものです。
地域の方が、自分達の技術で修復を繰り返しながら
受け継いでこられたことが、手に取るようにわかります。
そこで、ふと感じてしまったのです。
これらは、地域の核として、
地域が大事に保管し続けてきたものではないかと。
そのお宝を、施設に預けてしまって
良いものなのだろうか。。。。と。
一堂に集められたということは、
地域の人が身近に感じられなくなるのではないかと。。。。
「保管庫に集めることを、反対する方も居られたんですけどね。。。」
私の表情を読み取られたのか、ガイドの方が
地域の方の本音を呟かれました。
自分の代で保管はできても、次の代、そしてまた次の代に
うまく引き継がれるのか、、、苦悩の末の決断なのでしょう。
実際に、お祭りの後継者問題、維持管理問題は、
昨今の少子高齢化で、日本中が抱える問題です。
しかしながら、今の大変さを、
こうした一時的な計画で凌いだとしても、
地域の持つプライドというポテンシャルは
下がらないでしょうか?
煌びやかな飾りを見て、
笠鉾の装飾を競うあうこと=地域の競争力を高めること
だったのではないかと、推察しました。
そのお宝が身近にあることで、
その地域への愛着と、誇り、そして共同の助け合い精神を育む土壌、
となっていたはずです。
そうでなければ、ここまで続きません。
お祭りの発生時期を尋ねると、実はよく分かっていないそうです。
今のスタイルは江戸時代に確立したようです。少しづつ変遷しながら。
しかし、妙見信仰自体は、かなり古いものです。
妙見菩薩は、仏教が中国に渡り、道教を集合したらしいのですが
『妙見は武運を守ると信じられ,平将門,加藤清正など武将はこれを守り神とした。』(ウィキペディアより)
とはいえ、
八代神社(妙見宮)は、福島県の相馬妙見、大阪府の能勢妙見と並んで、日本三大妙見と言われ、
「やつしろぷれす」によれば、
末社である、霊符神社は、
由緒が、
『「肥後国誌」には、「妙見山ノ内赤土山ノ上ニアリ」と記され、(省略)『鎮宅霊府縁起集説』には霊府金板を天平十二年(740)肥後国八代郡白木山神宮寺で版木にちりばめた、と記されており、ここから国中に流布され、、』たそうです。
また、実際に神の化身と、亀蛇が出てくるのが、妙見神が渡来した竹原の津跡と言われています。
『「妙見実記」などによると、天武帝白鳳9年(680年)の秋、中国名州(寧波)から妙見神が目深検校、手長次郎、足早三郎の3人に姿を変え、亀蛇の背に載って海を渡り、この八代郡土北郷八千把村竹原の津に上陸し、約3年感仮座したと伝えられています。』
こうなってくると、仏教が伝来した飛鳥時代からの信仰があったと
分かります。
この長い年月を思うと、近代的な建物の中に、
その歴史を物語る地域のお宝であり、
信仰心(地域の繁栄を願う祈り)が、
閉じ込められてしまったような気になる
のは、私だけでしょうか。
なんだかモヤモヤした気持ち。
この地域のお祭りに参加したこともなく、
赤ん坊時代にしか過ごしていない地域で、
詳しく知らない部外者としての私ですが、
建築施設と、展示を見て感じてしまったのです。
そして、つい先日、このモヤモヤした気持ちを
伝統的建築や伝統文化に造詣が深い同業である
お仲間の一人に打ち明けたところ、、、
「それじゃ、地域の魂、抜かれちゃった感じだね。」
と言われて、ハッとしました。
そうなのです。私が、感じたモヤモヤを言葉にしてくれました。
寂しくないでしょうか。。。
私の懸念は、数年後、数十年後に、お祭りの価値や凄さ、意味などの
継承なく、イベントとしての観光の見せものとしての継承になりはしないか。。。
地域の誇りと地域への愛着は、失われていくのではないか。。。
という点にあります。
笠鉾というモノを保管しているようで、モノではない魂が宿っており
魂を保管している。
もし、これが、まちおこしやまちづくりの視点から、祭りや笠鉾を
見たならば、もっと地域の方々が触れられるような
そんな展示があったのではないかと、思えてくるのです。
その地域、地域に拠点を作るべきではないのか???
お祭りの際に、地域から出てくる鉾が、
一堂に介した施設から出てくるということは、
その地域の心意気を背負えるのだろうか。。。
ということです。
土地の問題など、もちろんあるのでしょうけれど。
今ある場所の整備に費用は回せなかったのかなぁ。。。
地域にないとなると、地域力で修復しようとはせずに、
行政などの後押しや補助金などの利用に
なってくるような気がしてなりません。
だって、自分達の宝物って感じではなくなりますからね。
これが、地方の祭りの現状なのか。。。
日本が、均一化、均質化して、どこも同じような都市になり
チェーン店が並ぶ街並みになり、お祭りは観光資源と化する。。。
それしか、解決方法はないのでしょうか。
お祭りの価値を、真の意味を失わずに、
少ない人数でも、開催できるお祭りへのシフト、
開催時期を隔年にして、負担を減らすなど、
(本当は、ハレの日は毎年欲しいところだけど)
さまざまな運営の工夫で、
これまでも、歴史の荒波を乗り越えてきたこの地域のお宝を
引き継いでいってもらえたらと願わずにはいられません。
そして、この展示を拝見して
地域活動を継続するのは、建築はなく、
より求心力のある「場」であるのではないか。。。
自分自身の建築のモノづくりの方向性も含めて、
改めて、そんなことを考えてしまった今回の施設訪問でした。
保管されている場所は、閉ざされており
木組の説明も読みにくい。 もうちょっと見たいですね。

おまけ
以下、建築やとして、ちょいと気になった箇所。
かわいらしいサインは気に入ったのですが、
みなさん、このサインどこか気になりませんか?
男子トイレ

女子トイレ

女子トイレと男子トイレ、
それぞれにベビーチェアがあることを示しています。
パパがベビーづれでも良いのでは?
っていうかママが、男子トイレに入るんかい!
と突っ込みましょう。人々に、先入観を与えて欲しくないですね。
建築雑誌などの写真は、木造の屋根の小屋組がアップで撮られ
カッコ良い木造施設に一瞬勘違いされるのですが、

遠景では、コンクリートと金属の屋根しか見えず、
もう少し景観への配慮も欲しかったなぁ。。。

実は、写真を拝見して、注目して、
現地を伺っただけに、ちょっと残念な気持ち。
建築って、やはり、実際に現地にいってみないと
分からないモノですね。
人のふり見て我がふり直せで、頑張ります!