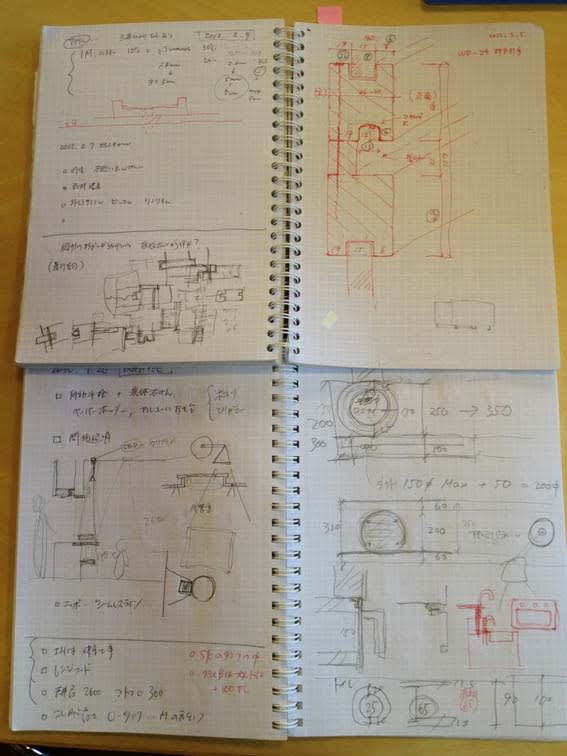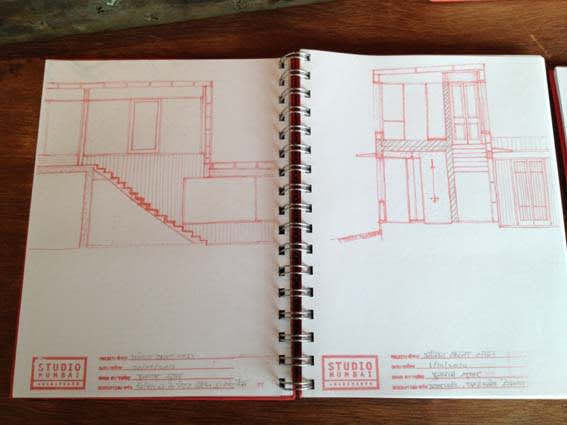実は、ココにも問題があって、認定を受けた工法と違う内容でメーカーが販売していたという違反もあります。
認定仕様そのものに問題があると、材料や工法を選ぶ設計者は、どうしようもないですね。
アルミサッシ、不燃木材、木製サッシでもここ1,2年で違反が発覚しています。
対策は、
1)「認定書」を徹底して読み込むこと。
2)本当にこの材を採用して大丈夫なのか?いい意味で疑ってかかること。
今、私の中では、これしかありません。
認定書は、数ページにわたり、非常に分かりにくく、また様々な組み合わせがあり、読書としては大変面倒なものです。しかし、これを間違うと先のような問題が起きないとも限りません。
また、実際には施工者の意識も大事なので、現場では嫌われ覚悟で、しつこいくらいに、あれはどうなっているか?大丈夫か?と迫ること(笑)
3)施工のしつこいチェック
どんなに忙しい監督さんでも、施工写真の提出を義務付けます。ただし、感謝とお礼の気持ちを込めてチェックしますよ~。監理者も全ては現場を見れませんからね。
チェックしている姿勢を貫くことで、手抜きや間違いも防げます。
余談
監督さん(施工者)は、ほぼ男性なので、最初に女きょうだいが居るか聞きます。なぜなら、女性に怒られたり指示されたことがない男性は凹むからです。
女性に言われるだけで、男性のプライドはズタズタですからね。
(逆に言えば、言われて凹まない方は、精神的にかなりタフです)
ココに誤解のないように書いておきますね!
私の指示(しつこさ)は、男性を傷つけるためにあるのではなく、貴方がた(施工者の瑕疵の部分)を守るための愛のムチですからね!
それから、仕事中は、男女を意識しずぎないこと。これも大事な点ですね。
募集
もちろん、職人さんが施工しやすいように、段取りしたり、配慮したり、行き届いた監督さんも多くいらっしゃいます。こういう方とお付き合いしたいですね。出来上がりが綺麗です。
打合せの中で「それでは(職人さんの)手が入らないな。」とか「こっちから施工してやらないと、○○がやりにくくなります」など、職人さんの立場になった発言が出て来る監督さんは、その時点で、かなりクリア。
心の中で「良い人に当ったなぁ」と喜んでいます。
我こそはそんな監督という方、お仕事ご一緒したいです!!
私自身も完璧ではありません。施工のこと、知らないことがまだまだあります。
良い意味でのコラボレーションで、世の中の「違反建築はなし」にして行きましょう!