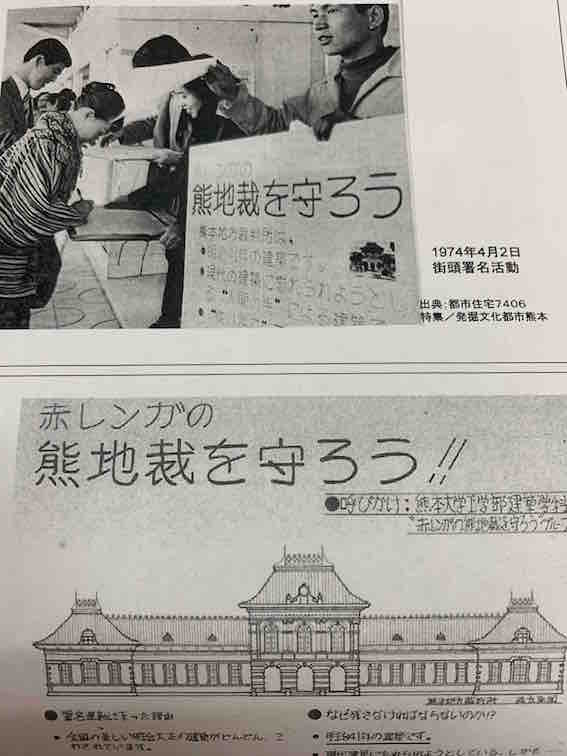先週末は、日本民家再生協会の
技術部会主催の左官の勉強会でした。
建物の2階特別見学に合わせて、
埼玉県の遠山記念館にて
左官の種類、技法を学びました。
公益財団法人遠山記念館HPはこちら https://www.e-kinenkan.com/
1)本物の凄さ
旧遠山家住宅は、昨年、国の重要文化財に指定されたとのこと。
これまで、ほとんど改修も改築工事も行って来なかったという
驚きに美しさです。
ただし、茅葺き屋根は20年に1回の取り換え工事を
行っているそうです。
昭和11年の竣工。戦前の建物。
本物の材料で、本物の技法だとここまでキープできるものなのか!
と、感嘆するばかり。
建具といい、木材といい、最高級です。
そして、日本の匠の手技には、目を見張りました。
地盤も改良も、土の入れ替えなど、
造成工事に半年はかけたというだけあって
地震被害もほとんどありません。
東日本の3.11地震の時は、
漆喰や聚楽壁の砂が落ちたようですが、そ
れも、落ちたものを集めて、再利用して修復済みでした。
下手に、手を加えると、違いが出てしまうらしく
そういったやむにやまれない場合のみ、修復されているとのこと。
見学時も、経年変化で、壁の角などが剥がれていたり、
色あせたりしているところなどありました。
それも味わいと、かえって、建築に深みを出しています。
2)左官の見本市
この建物の、左官の種類の多さ、技法の多さは
左官のプロを唸らせるほどです。
ここの「大津磨き壁」を見て、私も知る左官の第一人者が
復刻を呼びかけ、10年ほど前に、やっと復刻した技法だそうです。
今回の講師の一人は、その復刻した親方です。
素晴らしい探求精神ですね。
いろいろな細かい手業や下地のことなども解説頂き
設計者も知らないことばかりで、
その技法の世界への視野を広げてくれました。
ザクロ石(ガーネット宝石)いりの赤壁(本霞)、
キラキラです。

黄味がかった大津壁の磨き、優しい艶です。

トイレ手洗いの朱赤大津壁磨き、気分が高揚します。

こちらのトイレは明るくグリーンに。顔料を混ぜたのではないか?
の解説。

下地を浮かび上がらせる床の間の左官
色合いが淡いグラデーションに。

などなど、左官の見本市のような茶室群。
思わず、溜息も漏れます。
醤油を混ぜてわざと錆びさせ
下地の色を浮かせた
まるで、ホタルが飛んでいるかのような
ホタル壁など、遊び心も満載。

職方達も部屋毎に違い、
技を競ったようです。職人魂の息使いを感じるほどでした。
3)名建築が生まれる背景
このような名建築が生まれるのは、
どういった背景があるのかも気になりますね。
↓細い竹細工の技巧

当然、お金のある、センスのある、
建主がいて初めて成り立つ建築のものづくり。
この建主は、日興証券を起こした遠山元一氏。
幼い頃に手放した実家の再興を図ったというものでした。
そう、ここは、苦労した母のための家なのです。
(使用人10人ほどと母が暮らしたそう)
建主は、奉公から始まり、事業を起こし
そして、亡き家の再興。
きっとその再興への強い想いが原動力にもなり
成功への道へ突き進まれたのではないでしょうか。
ここには、原風景に本物の木の家と暮らしの体験があったからこそ
資産家になっても、華美で派手なものではなく、
日本の風景である民家と
書院造りや数奇屋づくりに
こだわられたのではないかと想像します。
本物を知る人だったのでしょうね。
現場監理は忙しい兄に変わって、センスの良い弟さんがなさったとか。
兄弟でタッグを組まれたものづくりも、美しい物語ですね。
学んだ日本の粋を、いつか自分の設計にも
活かせるチャンスが訪れますように。。。
同じく伝統的な建物にも携わる建築関係者と、
そんな夢の話もしながらの帰路でした。
このたびは、詳しく、解説下さった講師の方、
企画を立ち上げて、まとめて下さった仲間のみなさんには、感謝です。
ありがとうございました。