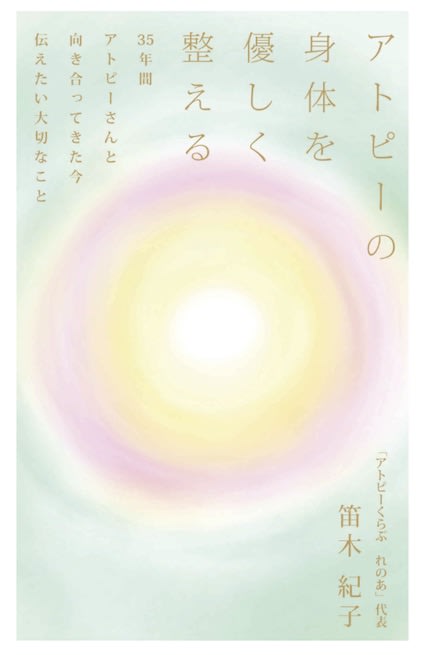昨年に続き、こども環境学会関連のイベントやセミナーは
オンラインで参加しています。
学会に参加した際にも、新しい教育の取り組みや
森の中での子どもたちの活動の様子など、
発表を拝聴して、いろいろと考えさせられました。
まだ、そのレポートもアップできていない中、
なんとか暮れの締めに、これだけはと、
子ども環境のことを綴ります。
今年、映画館では観そびれたひとつの映画があります。
「子どもたちをよろしく」です。
企画者は元官僚の方。
ですが、そこを飛び出して、
子ども環境の改善に取り組んでおられる面々です。
今回のセミナーの主催者は、学会で私も交流のある
スクールコミュ二ティを実践されている方。
映画を観る機会を逃したわ私たちに
ZOOM配信してくださり、
その後、子どもの環境に関わってこられた面々の
トークショーがあるとのことで、参加しました。
『子どもが置かれている辛い現状から目をそらさない』
映画の内容は、子どもの貧困(というけど実際は親の貧困)、
いじめ、性犯罪など、重苦しいものです。
一番の課題は、追い詰められる中学生の子どもらに
学校や、地域の関わりがいっさい描かれていないこと。
そこが、この映画の恐ろしいところでもあり
制作の意図でもあると感じました。
いったい、周りは何をやっていたの?
気がつかなかったの?
手助けできなかったの?
と、大人として、
ひどく落ち込むつくりとなっています。
これが今、子どもが置かれている
一つの象徴的な状況であるということ
それが重く私たちに伸し掛かってきます。
今年は、過去最高の子どもの自殺者数と、
虐待件数という報告もあり、本当に辛くなってきます。
では、どうしたらいいのか?
何ができるのか?
トークショーでは、
学校の先生から
「とにかく、子どもを一人にしない(心の問題も)」
SDGsでは、誰一人として取りこぼさない
というけれど、
その方は、その取り組みを教育としては
ずっとやってきているというお話でした。
今月は、生徒が殺めてしまう事件や
多くの人を巻き込んでの自殺行為など
辛い事件が後を絶ちません。
加害者の孤独、深い闇、それを生み出している社会背景。
つくづく、人は人とうまく関わり、折り合いをつけられないと
生きていけない生き物なのだなと、思うのです。
それには、安心できる居場所が必要です。
家庭や学校、仕事場など、
さまざまな人との関わりの場ですよね。
学校という子どもの居場所が、
多くが、安全基地になっていない現状。
それはなぜか?という問いには、
1)学校の位置付けが古い体勢のまま
制度的には、学校は自治体のもので
地域運営で、国の出先機関ではない!
ところが、学校の位置付けが、戦前をひきずっていて
軍隊的な要素が抜け切れていないという問題。
(規律を重んじるということも
含まれてしまているのがおかしいという指摘、
もっと自由で良いの考え)
2)教員養成への縛りがある
学校の先生、教員の方の免許取得の学びへの縛りがある
学びの自由を教える立場の人に自由な学びがないという現状。
3)地域との関わりがない
学校って、週休2日で、部活を除けば
18%しか駆動していない。のこり82%が使われない施設。
そこで、地域の大人も子どもも活用する
スクールコミュニティ(地域の学びの場へのシフト)
の手法の重要性が出てくる訳です。
など、トークショーでは
学校のあり方についての、課題が少し整理されました。
<少し余談>
教育委員会と学校との関係にも話が及んだ時、
熊本市の例が出されました。
教育委員会で議論が活発との高評価でした。
議題はコロナ禍での子どもの夏休みのあり方だったようです。
実は、今、熊本市の教育関連施設の審議委員をしています。
その会議の時に、こども環境学会の活動の中で
「『熊本は教育熱心』という評価のお声かけをいただくのですよ
教育委員会のみなさまのご尽力のおかげです。」と
話したことがあるのですが、
また、ここでも話題に挙がったので、
ああやはり外から見ると
そういう評価なのか、と笑みがこぼれました。
ふるさとが褒められるのは嬉しいものです。
実情がどうであれ、笑。
年が明けたら、教育委員会の方に、
真相を訪ねてみようと思います。
<光と闇>
最後に、私が一番印象に残った言葉をご紹介します。
それは、先の校長先生が、
自身が差別を受けてこられた地域の方から
「闇に目を向けて欲しい」
と言われたというエピソードでした。
「闇があるところから、光は見えるけれど
光のある方から、闇は見えない。」
「光が当たっている子どもがいれば、
当たっていない子どもがいる」
「光が強くなればなるほど、闇は暗くなる」とも。
暗い部分をちゃんと見るってことを
確かに意識することは、少ないのではないか?と、
ハッとさせられました。
それを考えると、子どもって元来明るいけれど
一方で、わがままでズル賢いかったりもします。
いろいろな心の葛藤もあるはずです。
お話を伺って、抱えている心の闇の部分にも
少し触れてあげないとならないなと
感じ入りました。
この映画&トークショーに私が参加している間、
我が子は友達とクリスマスパーティーでした。
賑やかで楽しそうでした。
まさに、光の部分だなと。
私自身が今は、教育者の立場ではないので
多くの子どもと直接接するわけではありません。
それでも、建築士×こども環境アドバイザーとしては
関われるこども達の、心の闇の部分に目をつぶらないで
接していきたいなと思いました。
そして、想像しようと思います。
人の本質を知るには、
その人の闇の部分も理解することだと。
自分自身の心の問題も含めて、
向き合っていきたいと思います。
<社会の理想は?>
強すぎる光と、深い闇が真に良い世界なのか
(格差社会!?)
均等に光は当たっているけれど、眩しすぎないのが良いのか。
(没個性で、つまらない?!)
私自身の理想は、、、、
昼と夜のように。
均等に、光が当たる時と、
闇になる時と
両方チャンスがあるといいなと思っています。
表舞台に立つ時と、影で支える役割と
時に交代するような。
互いの立場を理解して、大変さもわかります。
そうすると、一人取り残す
という社会ではなくなると思うのです。
子どもには、両方のチャンスを!!!
良い学校って、そうなんじゃないかなと
子育ての体験で思います。
来年は、
意識して闇をみつめて、
光を当てていくことを心がける子育てと、
人間関係を築いていこう!
そんな気づきをもらった暮れです。
企画登壇のみなさま、開催を有難うございました。