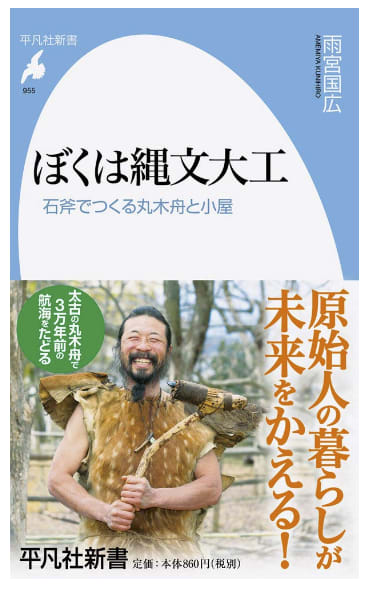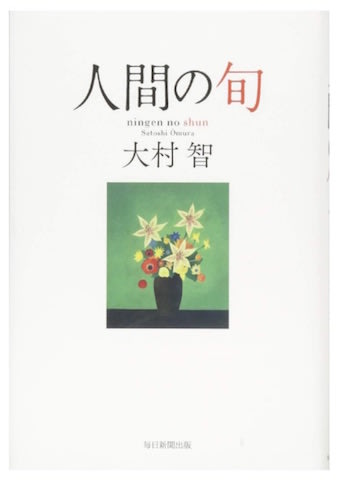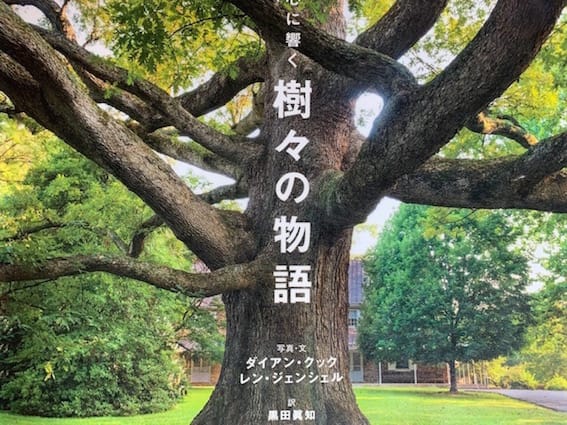先週末の4月16日(土)は、
熊本地震から6年という節目でした。
またまた熊本ネタですが、
熊本発信!で世界に広げていきたい内容ですので
ご紹介します。
今回は、地震関連ではなく、環境問題についてです。
(地震の知見も様々あります。専門的な話は次回)
私がユーザーでもある、熊本の女性たちが商品を
企画販売をしている会社があります。
東京で、あるチラシがきっかけで、、
最初は、地元の女性の会社を応援する気持ちもあり
商品を使ってみました。
それが、思いの外、素晴らしく、
現在では長期ユーザーであり、
同じような悩みを持つ方には、紹介するほどになりました。
環境に配慮した商品であることと
身体にも、とても良いからです。
地元の女性建築家の先輩のお宅訪問した際に、
洗面所で見つけた時は、あら、まぁ!と
問題意識が同じところにあると、嬉しくなったほどです。
そこの女性たちが、環境問題に意識を持って
ここ数年は、商品のチラシとともに、
地球環境に関するレポートを配布されるように
なりました。
森と樹と暮らしを繋ぐプッロジェクトに
関連する内容があった際には、
社長さんとは直接お電話で話をしました。
その時は、いちユーザーとして、でした。
今回の「くまもと地球会議2022」では、
私自身は、登壇者側ではありませんでしたが、
知り合いの林業家、
そして、地元のバイオエネルギーの女性企業家の登壇で、
今後は、もっと積極的に関わっていこうと思った次第です。
その話の中で、一番衝撃的であったのが、
(一財)日本熊守協会の森山まり子会長の講演
メガソーラー(太陽光発電)と
風力発電による森林破壊の話でした。
熊守協会さんの本は拝読していますし
森林保護団体の第一人者であられるので、存じていたのですが
現在、東北では大規模な、メガソーラー設置の計画が進んでおり
住民の方は、なすすべもなく困っておられるのだとか。
関東近郊の山でも、その話は自治体が推奨する側と
ストップをかける市民との間で、
相当なやりとりがあっていることは知っていましたが、
日本全国に、いつの間にか広がっており
九州の島でも起きている!
それを止めるために、
奔走されているということでした。
熊本の拠点でも、景観を壊し、
下草を生えさせなくする民間による開発が進んでいます。
自治会や住み手は反対をしつつも、
放棄耕作地などの問題を解決するという
一方では、過疎化地域にとっては、良さそうな話なので
自治体が許可してしまうのです。
今現在は、何でもかんでも、山に入り込む開発を
食い止める法整備しなくては、ならない段階です。
脱炭素なら、太陽光発電は必須では?
と、思われますよね。
2030年問題は、ご存知でしょうか。
助成金を得て、大量に設置された太陽光発電池が寿命を迎え
大量な廃棄物が出てくると言われている問題です。
埋め立てゴミで、また地球を汚すわけですね。
一面だけ見ると、エコなイメージの太陽光発電も
一方では、地球に還す時のことが、検証されないできました。
柿本がしつこく「創還エネルギーで考えないと!」
と言っているのは、そのためです。
今は、シート状のものや
リサイクルできる商品も出てきました。(完全ではないのですが)
載せたいという方には、その選択をお願いしています。
今回の会長の講演での指摘もまさに、矛盾点への指摘です。
CO2を固定してくれる森を破壊しての、脱炭素って!?
本末転倒な事態です。
都市部もしかり、山でのゾーニングが必要と
森林会議でも訴えてきたのは、このためです。
(林業地、人工林と、動植物の棲める森とのエリア分け)
水も、空気も、森なしでは作れません。
(いろいろな科学的な方法もなくはないですが、圧倒的に量は少ない)
地球が自然に生み出したものは、自然に還るけれど
人間が作り出したものは、自然に還せない矛盾。
負荷をかけない選択をし、長い年月をかけてでも
地球に還っていくものを、選択する
つくり手と、使い手になりたいものです。
まだまだ、私自身も未熟です。
諸先輩方や、熱い思いの熊本おごじょの皆さんに刺激を受けて
逆風にも思える建築業界ですが、
私も、目の前のことを、一歩一歩、取り組んでまいります。
会議の開催と、今後の方向性を示してくださった
皆様に感謝して。
ぜひ、下記をチェックしてみてくださいね。
(一財)日本熊守協会、ここのくまもりNewsがおすすめ
ネーチャー生活倶楽部
地球環境への活動のレポートがおすすめ