僕は羨望を欲望cupiditasの一種として定義しました。この欲望の特徴をもう少し詳しく説明しておきます。
まずこの欲望は,自分の得ていない喜びlaetitiaあるいは自分の得ていない善bonumの観念ideaを原因causaとして伴っています。ところで僕たちの現実的本性actualis essentiaは,喜びを希求し悲しみを忌避するようにできています。ですから,得ていない喜びについては僕たちは,程度の差こそあれそれを希求することになりますので,この欲望は僕たちには発生しやすい欲望であることになります。
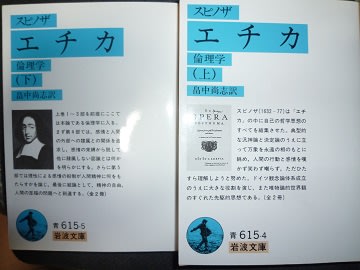
次に,第三部定理三七により,喜びから生じる欲望は,その喜びが大きくなるほど大きくなります。羨望の場合はこれをふたつの観点からいうことができます。ひとつは,自分が手に入れいていない喜びを手に入れた人を表象するimaginariとき,その人がそれを手に入れることによって喜んでいる度合が大きいと表象されるほど,それに対するより大きな羨望を僕たちは感じることになります。もうひとつは,自分が手に入れていないある事柄について,自分がそれを手に入れたときの喜びがより大きくなると表象されるほど,それを手に入れている人への羨望はより大きくなります。
したがって,自分が手に入れていない喜びを他人が手に入れたことを表象したとき,その他人がどんなに喜んでいようと,自分が手に入れたときにはそれほど大きな喜びでないという場合には,それほど強い羨望を僕たちは感じません。同じように,それを手に入れた人がさほど喜んでいないように表象されたとしても,自分がそれを手に入れた場合には大きな喜びになるであろうと表象される事柄については,僕たちは強い羨望を感じる場合があることになります。
まとめれば,僕たちは羨望を感じやすい現実的本性をしていて,かつそれがより大きな喜びを自分に齎すと確信されるほど,それを手に入れた人に対してより大きな羨望を感じることになるのです。もっともこのことは,このように論理づけなくても,経験的に僕たちがよく知っていることかもしれません。
自己原因causa suiを起成原因causa efficiensと認めることがなぜ神学との論争になるのか,もっと分かりやすくいえば,そうした哲学的態度がなぜ神学からの反撥を生むのかということは,現状の考察とはまったく関係ありませんからここでは割愛します。とにかくこの解釈は神学的にこの時代には許されてなかったとしておきます。そこで,これを回避する哲学的技術というか技巧が発生することになりました。その代表的な一例が,僕がデカルトの欺瞞とこのブログでいっている技巧です。デカルトRené Descartesはどんなものにも起成原因を問うことができるということは認めていました。これを神Deusに当て嵌めると,神は自己原因であると論理的にはいわざるを得なくなるのですが,デカルトはこちらの点については認めず,あの手この手を駆使して,神は自己原因であるという結論を導くことを拒否したのです。
理由という語は,実はこの技巧のひとつに該当するのです。僕は,デカルトはどんなものについても起成原因を問うことができるということについては認めていたといいましたが,これは僕がスピノザの立場に立ってデカルトを読むからこその解釈であるという一面があります。実際にデカルトがいっているのは,どんなものについてもその原因ないしは理由を問うことができるということなのです。つまりデカルトはそこで原因と理由を分けることによって,神について問うことができるのは原因ではなくて理由であるという解釈ができるようにしておきました。なのでデカルトは神の存在existentiaについては神が存在する原因という意味でなく,神が存在する理由という意味で問うていると受け取るのが,デカルトの哲学をデカルトの立場から解釈する際には,正しい方法であるといえるかもしれません。実際にスピノザも,『デカルトの哲学原理Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae』の第一部公理十一で,それがなぜ存在するかという原因あるいは理由を求め得ない事物は何も存在しないといういい方をしています。
第一部定理一一は,まさに神の存在を論証しようとしています。そしてその第二の証明において,スピノザは原因ないしは理由あるいは理由ないしは原因といういい方を集中的にしているのです。関連性をみるのは当然でしょう。
まずこの欲望は,自分の得ていない喜びlaetitiaあるいは自分の得ていない善bonumの観念ideaを原因causaとして伴っています。ところで僕たちの現実的本性actualis essentiaは,喜びを希求し悲しみを忌避するようにできています。ですから,得ていない喜びについては僕たちは,程度の差こそあれそれを希求することになりますので,この欲望は僕たちには発生しやすい欲望であることになります。
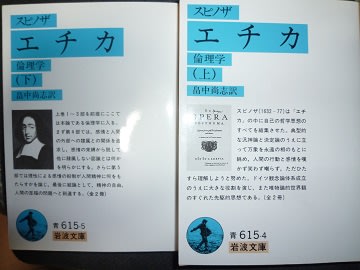
次に,第三部定理三七により,喜びから生じる欲望は,その喜びが大きくなるほど大きくなります。羨望の場合はこれをふたつの観点からいうことができます。ひとつは,自分が手に入れいていない喜びを手に入れた人を表象するimaginariとき,その人がそれを手に入れることによって喜んでいる度合が大きいと表象されるほど,それに対するより大きな羨望を僕たちは感じることになります。もうひとつは,自分が手に入れていないある事柄について,自分がそれを手に入れたときの喜びがより大きくなると表象されるほど,それを手に入れている人への羨望はより大きくなります。
したがって,自分が手に入れていない喜びを他人が手に入れたことを表象したとき,その他人がどんなに喜んでいようと,自分が手に入れたときにはそれほど大きな喜びでないという場合には,それほど強い羨望を僕たちは感じません。同じように,それを手に入れた人がさほど喜んでいないように表象されたとしても,自分がそれを手に入れた場合には大きな喜びになるであろうと表象される事柄については,僕たちは強い羨望を感じる場合があることになります。
まとめれば,僕たちは羨望を感じやすい現実的本性をしていて,かつそれがより大きな喜びを自分に齎すと確信されるほど,それを手に入れた人に対してより大きな羨望を感じることになるのです。もっともこのことは,このように論理づけなくても,経験的に僕たちがよく知っていることかもしれません。
自己原因causa suiを起成原因causa efficiensと認めることがなぜ神学との論争になるのか,もっと分かりやすくいえば,そうした哲学的態度がなぜ神学からの反撥を生むのかということは,現状の考察とはまったく関係ありませんからここでは割愛します。とにかくこの解釈は神学的にこの時代には許されてなかったとしておきます。そこで,これを回避する哲学的技術というか技巧が発生することになりました。その代表的な一例が,僕がデカルトの欺瞞とこのブログでいっている技巧です。デカルトRené Descartesはどんなものにも起成原因を問うことができるということは認めていました。これを神Deusに当て嵌めると,神は自己原因であると論理的にはいわざるを得なくなるのですが,デカルトはこちらの点については認めず,あの手この手を駆使して,神は自己原因であるという結論を導くことを拒否したのです。
理由という語は,実はこの技巧のひとつに該当するのです。僕は,デカルトはどんなものについても起成原因を問うことができるということについては認めていたといいましたが,これは僕がスピノザの立場に立ってデカルトを読むからこその解釈であるという一面があります。実際にデカルトがいっているのは,どんなものについてもその原因ないしは理由を問うことができるということなのです。つまりデカルトはそこで原因と理由を分けることによって,神について問うことができるのは原因ではなくて理由であるという解釈ができるようにしておきました。なのでデカルトは神の存在existentiaについては神が存在する原因という意味でなく,神が存在する理由という意味で問うていると受け取るのが,デカルトの哲学をデカルトの立場から解釈する際には,正しい方法であるといえるかもしれません。実際にスピノザも,『デカルトの哲学原理Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae』の第一部公理十一で,それがなぜ存在するかという原因あるいは理由を求め得ない事物は何も存在しないといういい方をしています。
第一部定理一一は,まさに神の存在を論証しようとしています。そしてその第二の証明において,スピノザは原因ないしは理由あるいは理由ないしは原因といういい方を集中的にしているのです。関連性をみるのは当然でしょう。














