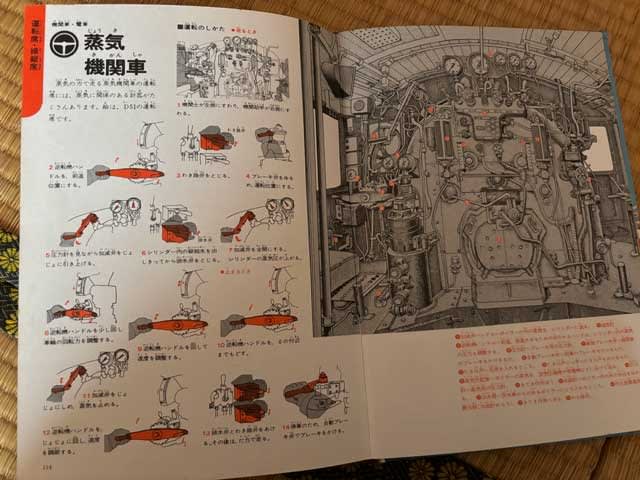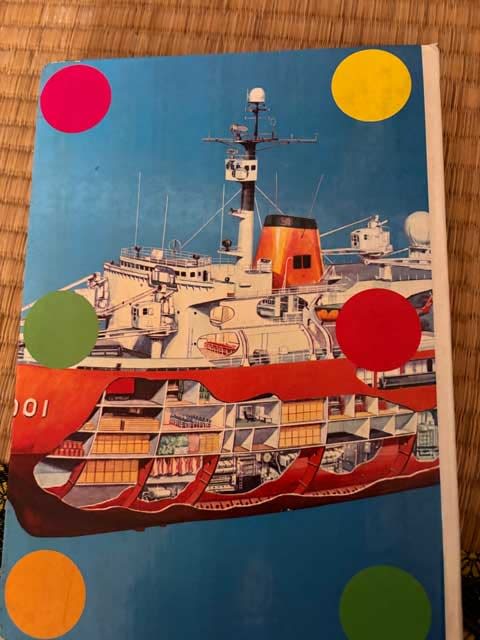今回も帰省の爆買い戦利品から(汗)

今回の戦利品の大きな特徴のひとつは購入した車両の多くが「すでに持っている車両(または編成)の補完的な性格を持つアイテム」だったという点です。
例えばED42は今回の入線で「4重連」が実現しましたし、9600では「手持ちモデルとのパーツのコンバートで走行が復活」キハ26だと「手持ちと併せて4連化する事で準急らしい編成になった」という具合。
なにしろあの趣味のカラー編成ですら「昨年入線のと併せて7連の長編成が実現」しているくらいなのですから。
今回紹介するのもまさにそのひとつ。
マイクロの185系200番台から3両のトレーラーを選んだものです。

だいぶ以前にも紹介していますが、185系200番台「新幹線リレー号」はこの趣味を再開させた直後にKATOのジャンク4連からスタート、その後動力をTOMIXと換装、不動状態だったマイクロのサロはKATOの足回りとコンバートしてトレーラー化。更に同じマイクロのモハ185を2両追加し、内1両にパンタを載せて強引にモハ184化させたという継ぎはぎの極北ともいえる組み合わせで7連化を実現させていたものでした。
今回入手した3両は元々編成物のバラだった並びからクハとモハ184、185の2Mを切り取った3両で、これにより現行の手持ち編成を9連まで伸ばす事ができます。

マイクロのモハ184は今回初めてまみえたモデルなのですが、プラ造形の車体は他社と同じ文法で造形されている物の、信号炎管や避雷器に挽物の金属パーツをあてがっているのが特徴。
これがまた一点物ながらいいアクセントになっていると思いました。
ただ「しなのマイクロエース」時代の客車の時と同じで「T車でも台車の抵抗が大きい」弱点はこの185系でも引き継がれているので旧TOMIX動力と言えども息を切らしそうなのが不安材料だったりします(汗)

今回の戦利品の大きな特徴のひとつは購入した車両の多くが「すでに持っている車両(または編成)の補完的な性格を持つアイテム」だったという点です。
例えばED42は今回の入線で「4重連」が実現しましたし、9600では「手持ちモデルとのパーツのコンバートで走行が復活」キハ26だと「手持ちと併せて4連化する事で準急らしい編成になった」という具合。
なにしろあの趣味のカラー編成ですら「昨年入線のと併せて7連の長編成が実現」しているくらいなのですから。
今回紹介するのもまさにそのひとつ。
マイクロの185系200番台から3両のトレーラーを選んだものです。

だいぶ以前にも紹介していますが、185系200番台「新幹線リレー号」はこの趣味を再開させた直後にKATOのジャンク4連からスタート、その後動力をTOMIXと換装、不動状態だったマイクロのサロはKATOの足回りとコンバートしてトレーラー化。更に同じマイクロのモハ185を2両追加し、内1両にパンタを載せて強引にモハ184化させたという継ぎはぎの極北ともいえる組み合わせで7連化を実現させていたものでした。
今回入手した3両は元々編成物のバラだった並びからクハとモハ184、185の2Mを切り取った3両で、これにより現行の手持ち編成を9連まで伸ばす事ができます。

マイクロのモハ184は今回初めてまみえたモデルなのですが、プラ造形の車体は他社と同じ文法で造形されている物の、信号炎管や避雷器に挽物の金属パーツをあてがっているのが特徴。
これがまた一点物ながらいいアクセントになっていると思いました。
ただ「しなのマイクロエース」時代の客車の時と同じで「T車でも台車の抵抗が大きい」弱点はこの185系でも引き継がれているので旧TOMIX動力と言えども息を切らしそうなのが不安材料だったりします(汗)