病院に行って、薬をもらう。その後、大学へ。1時から4時まで会議。会議が終わると、雪が降り積もっていた。その間、貝塚の資料の整理をしてもらったり、卒論の要旨をもとめたりしたが、ゴミ屋敷みたいな部屋に積み上げられていた資料が崩れ落ちること数度…。性格はいいのだが、生活破綻かな?
修士論文の諮問をしていて、気になったことがあって、そのことを考えていた。
テーマの「集団形成」について、ひっかかったのである。教育実践の性格として「集団づくり」といっていいのかとか考えた…。その論文の研究方法からいえば、エスノグラフィーの手法のフィールドワークなのであるから当然のことながら「集団形成」となるのだが…。しかし、それでいいのだろうか?自然発生的な「集団形成」が、見落とされているという批判もありうるだろうが…。
研究方法としても、客観性を標榜して、没価値的に記述していくわけではないが、エピソードをひろうかたちで取り上げる方法には限界もあるかもしれない。
「形成」か「教育」かという議論がかつてあった。
教育実践は、基本的には、「意図」があっての「制作」行為であるから、それに即して分析される必要がある。難しいのは「意図」が隠れていたり、隠されている場合が多いからである。あるいは、意図通りに行かず、かえって教育実践が壊れていくこともあることである。意図が強いと、逆に、教育実践の必須の要件である関係のゆきき(応答)ができにくいこともある。しかし、意図がないと、惰性でうごいているものとなる。段取りばかりやっていっていて「支援」といっているのも(今は、「支援」の概念は変わったが…)、「指導」を否定して使われた場合もある。
考えてみると、教育はだれのために行われているかということもある。結局は、教師のために行われているわけではなく、子どもや青年、成人が主体ということなのであるから、教育の主体である子どもや青年などが学習していく、そのことを通じて自己形成していくことなのであるが…。
修士論文の諮問をしていて、気になったことがあって、そのことを考えていた。
テーマの「集団形成」について、ひっかかったのである。教育実践の性格として「集団づくり」といっていいのかとか考えた…。その論文の研究方法からいえば、エスノグラフィーの手法のフィールドワークなのであるから当然のことながら「集団形成」となるのだが…。しかし、それでいいのだろうか?自然発生的な「集団形成」が、見落とされているという批判もありうるだろうが…。
研究方法としても、客観性を標榜して、没価値的に記述していくわけではないが、エピソードをひろうかたちで取り上げる方法には限界もあるかもしれない。
「形成」か「教育」かという議論がかつてあった。
教育実践は、基本的には、「意図」があっての「制作」行為であるから、それに即して分析される必要がある。難しいのは「意図」が隠れていたり、隠されている場合が多いからである。あるいは、意図通りに行かず、かえって教育実践が壊れていくこともあることである。意図が強いと、逆に、教育実践の必須の要件である関係のゆきき(応答)ができにくいこともある。しかし、意図がないと、惰性でうごいているものとなる。段取りばかりやっていっていて「支援」といっているのも(今は、「支援」の概念は変わったが…)、「指導」を否定して使われた場合もある。
考えてみると、教育はだれのために行われているかということもある。結局は、教師のために行われているわけではなく、子どもや青年、成人が主体ということなのであるから、教育の主体である子どもや青年などが学習していく、そのことを通じて自己形成していくことなのであるが…。












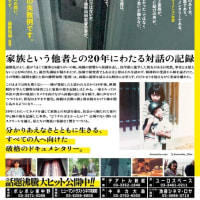




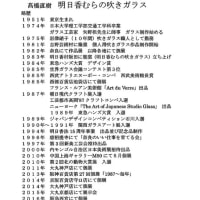

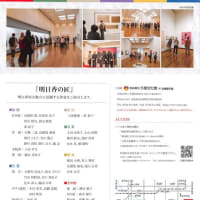
ソビエト崩壊以降ソビエト時代の教育は全面否定され、多くのソビエト教育研究者が「転向」されました。しかし、私には、肯定できるものと否定できるもの等々あったため「転向」に疑義がありました。
クループスカヤはの「総合技術教育」は、キューバの教育でも受けとめられ行われていましたが、1961年頃のキューバでの論争によって創造的発展がされたようです。
1979年7月18日のニカラグア革命そして、その後の選挙でダニエル・オルテガ大統領に就任した2007年1月にニカラグアに行き、オルテガ大統領との会談をはじめ教育関係者とも会談することが出来ました。
この時、ニカラグアの教育改革について話を聞いたところ、今まで私が学んだことのない教育システムだったので、ニカラグアの教育関係者に聞いたところ「これらのことはキューバから学んだ」という返事だったので驚いていろいろと聞いてみました。
「多様性」と「競合」。理解が出来ませんでしたが、キューバの教育の教育がクループスカヤはの「総合技術教育」の模倣ではなく、独自的創造的発展方向を目指していることを知りました。
2007年1月での会談では、「複合主義」「混合主義」という考えが飛び交い、反対勢力を排除するものではなく、「競合」してこそ発展があるというものでした。
本論から外れているかもしれませんが、アメリカの個人契約教育方法をそのまま日本に持ち込むことが多々ある今日の障害児教育の中で、もう一度、集団発達の系を考えるうえで大きなヒントがあると私は考えています。
日本は、一斉授業方式の形態です。その中で集団と個人との関係も重視した教育がなされてきましたが、クラスが多数の生徒で形成されていたため集団と個人のどちらかに傾いて実践がされたように思いますが、かっての集団を重視する教育実践には多くの学び継承されるものが多くあります。
障害児教育でよく話された、基礎集団。異質の集団との混合と共同などは、「複合主義」「混合主義」に繋がるのではないかと考えてきました。
考えてみると、教育はだれのために行われているかということもある。結局は、教師のために行われているわけではなく、子どもや青年、成人が主体ということなのであるから、教育の主体である子どもや青年などが学習していく、そのことを通じて自己形成していくことなのであるが…。
と書かれています。今でも学校の主人公は生徒だとする考えが多くあります。かって、先生は生徒のけらいになれ、などがもてはやされたことがありました。
そう言うことも含めて教育の主体論争があったのですが、ここでも田中昌人先生は熟考して「将来民主的主権者となるための子どもたちの教育」などの表現をして、学校教育の主人公は生徒とする考えに対峙したことばを使われていますが、私も同感でした。
いわゆる発達障害に取り組んでいると自負するS大学の教授がある医学系雑誌に発達障害問題は国民的課題として文章を書いているが、以下のような記述が見られる。
S大学のアセスメントでは、音韻意識にも蹟きが認められた。すなわち、ひらがなの読み、書きでも特殊音節で困難が起きる程度の重度の読み書き障害である。対人関係に問題のない学習障害である。ところが、そうした保護者に対して、担任教師は「お母さん、気にしすぎです」という態度で保護者は相談のしょうがないと考えS大にたどり着いた。こうした事例が今年に入ってから相次いでいる。子どもの困難さと保護者の心配に対するこうした「否認ネグレクト」は決してまれな例ではない。ネグレクトが虐待の一形態であるとするなら、子どもの困難と保護者の心配のネグレクトは、ままさに虐待というべきものであり、子どもの人権の蹂躙に他ならない。
教師が、保護者の心配に「否認ネグレクト」(無視を認める意味?)することが、虐待であり、人権蹂躙であると断定しているのである。そして、あたかもS大学が虐待と人権を守るかのように論じられている。
しかし、担任教師は「お母さん、気にしすぎです」という態度のことは、保護者から聞いた話であって、担任に確かめたのか、どのような場面で担任が言ったのか、がまったく記載されていないし、もし担任がその生徒が「重度の読み書き障害」であるということを理解できていなかったのならどのような対応をしたのかも書かれていない。
ここでは、担任があるひとりの子どもを把握出来ていなければ、虐待・人権蹂躙ということになるのだから、担任はすべての子どもの状態を把握して居なければならないという過酷な負担がかかる。
このことが、教育以外の分野からの問題記述なら理解できないことはないが、まさに教育の専門研究者がこのようなことを公然と書いていることに慄然とする。
その一方では、このS大学教授は、日本では読み書き障害の取り組みの遅れと科学的根拠の蓄積の遅れを指摘しているのである。
私は、担任を責める気もないし、保護者の言ったことを否定するつもりはない。むしろS大学の取り組みと研究なるものに対して大いなる疑問を抱くようになった。
親が問題意識を持って大学に相談に来ること自体、もうそこには目的意識性がある。私の経験では、教育現場では専門的医療機関や専門的研究機関に行って子どもを見てもらうようにすすめても、そのほとんどが受け付けられないという問題に直面してきた。そのため親が自ら子どもを連れて大学の相談機関を訪れるということの先駆性を感じる。
S大学を訪れ、教育相談に応じた教授がそのことを持ってだけで、学級担任を根底から批判している。ひとりの生徒を見て、そのクラスの担任の非人間的行為を責めているのである。
わたしは、このことからも個人と集団の関係がこの文章を書いた教育研究者には、存在していないのである。
保護者の言ったことがすべて事実であったと仮定してみよう。では、なぜ教師が、日常の教育の中でその子どもが、重度の読み書き障害であるのではないか、と気づかなかったのだろうかという分析と原因究明をするのが、S大学の研究者のすべきことではないかと思う。授業をしていたら、何らかのことで生徒の問題点を知ることが出来るものである。そのことと専門研究が結びついていくべきではないだろうか。ところが、逆に教師と保護者と専門研究を分断することを肯定している。
このことは、大変深刻な問題である。今の日本の授業形態が一斉方式であり、一斉到達方式であることを加味しないと、ひとりの生徒からすべてを断定する非科学的発想に陥る。
個別相談と個別指導をしていると、たしかに生徒がのびる面が顕著である場合が多い。だから塾が繁盛するのだろう。
だが、ここで、個人から見ただけで集団を評価してはならないのである。
部分だけを見て、全体を評価してはならないのである。しかし、教育専門家の一部がこのようなことを公表するのだから事態は深刻である。
H県K市の精神科医で学校専門医になった医者が、次のようなことを言っていた。
小学校を5校担当して、授業を見させてもらった。
どこの学校でもクラスの後ろにいる生徒たちが、先生の言うことを聞かない、授業に集中しない、うろうろたち歩く、ひとときも座っていない。この子らの問題を考えなければ、と思って先生に話を聞くと「あ、その子らはそれでいいんです。勉強は中学進学のため(有名校へ)塾でしていますから。」という返事が一様に聞かれて驚いた。クラスの8割近くが地元の中学校に進学しない。前で真剣に授業を受けているのは、地元の中学校に行く生徒。
と言う返事を聞いて驚いた。今の学校は、どうなっているんだろうか。
この精神科医で学校専門医の話と個人と集団の問題が、頭を駆け巡っている。