政府の月例経済報告が、景気判断を3年ぶりに下げました。
やっと出たか・・・という感じです。
1月には、景気拡大期が6年2か月に達し、「戦後最長を更新した」と発表したばかり・・・。
世の中の様子をどう見ても、「戦後最長」などという肌感覚はありません。
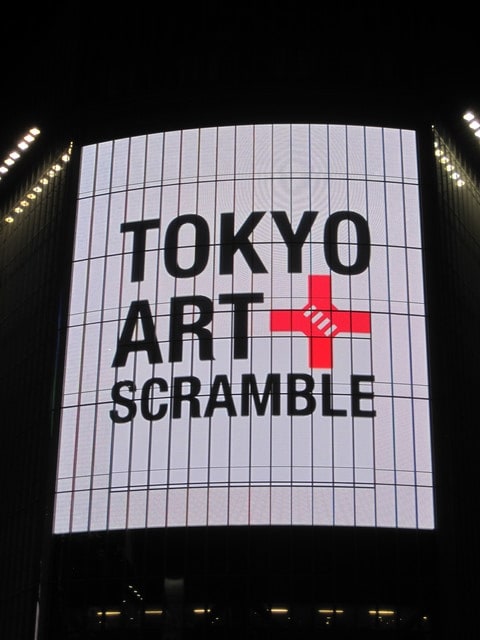
その間、巷では、主要事業の売却、大規模リストラ、産業自体の消滅、品質不良問題、メンタル不全の頻発による職場不全、雇用とスキルのミスマッチによる失業問題、一流企業の崩壊・・・。
今まで考えたこともなかった事象が、産業界で起こっています。
今まで考えたこともなかった事象が、産業界で起こっています。
まあ、そんなもんだよね・・・とインチキ評論家気取りで流している小職です(苦笑)。

1980年代の後半に発生したバブル経済。
行き場のないマネーが、いたるところで狂ったように飛び交いました。
飲む、打つ、買う・・・。
パンと見世物で世紀末的な雰囲気に包まれたローマ帝国の末期のような状況でし
た。
行き場のないマネーが、いたるところで狂ったように飛び交いました。
飲む、打つ、買う・・・。
パンと見世物で世紀末的な雰囲気に包まれたローマ帝国の末期のような状況でし
た。
現在の経済指標は、その時期に匹敵する数字となっています。
有効求人倍率は1.5を超え、貿易収支も大幅黒字、地方経済もわずかながら上向きト
レンドにあります。
有効求人倍率は1.5を超え、貿易収支も大幅黒字、地方経済もわずかながら上向きト
レンドにあります。
ただ、市井の状況は、どんよりした停滞模様・・・。
経済の活力を感じることは、あまりありません。
経済の活力を感じることは、あまりありません。
しかしながら、資産、収入の二極化は確実に進んでいます。
経済社会の主人公である中間層、中流家庭は減少し始め、逆に富裕層、貧困層が増加しています。
格差社会が、ますます拡大しつつあります。
会社組織、特に大手企業は、将来的な不安に備えて、内部留保・・・労働分配率を上げず、キャッシュの貯金を行い続け、今では過去最高のキャツシュを保有しているところが多くなっています。
そして、なかなか脱却できないデフレスパイラル。
政府や中央銀行が、ゼロ金利政策という禁断の封じ手を打っても、日銀総裁の公約の半分も実現できない状況です。
政府や中央銀行が、ゼロ金利政策という禁断の封じ手を打っても、日銀総裁の公約の半分も実現できない状況です。
中小企業の社長さんからも、よく質問を受けます。
「これからのニッポン経済、どうなるんですかねえ。」
「これからのニッポン経済、どうなるんですかねえ。」
基本、ポジティブ、楽観主義の小職ですが、最近、経済分析では、かなり後ろ向き。
「2020年の東京オリンピックまでは、何とかぎりぎりプラス成長を続けていきたいところです。が、その前に米中貿易戦争、ブレグシット、朝鮮半島問題などの不安定な国際情勢、そして、国内では消費税増税、格差社会拡大による個人消費の減退、劣化した政治・・・2019年に一度経済がクラッシュするかもしれませんねえ。」
などと、煮え切らない一般論でお答えしています・・・。
個人的には、2019年の経済景況は、かなりネガティブ。
株は手放し、残っているのは、つみたてNISAの投信ぐらいです。
個人的には、円高株安のトレンドが2019年度を転機としてかなり進んでいくと考えています。
現在の時代の空気は、150年前の明治維新の頃と同じ。
さらには、76年前の太平洋戦争に突入するときと同じように思います。
まさに、社会が大きく変化するときの、変化点と呼ぶべき時期だと思います。
さらには、76年前の太平洋戦争に突入するときと同じように思います。
まさに、社会が大きく変化するときの、変化点と呼ぶべき時期だと思います。
これから、社会や産業界は大きく変わっていくでしょう。
一人ひとりの生き方・働き方・稼ぎ方も、様変わりするでしょう。
こういう状況にありながら、社長と呼ばれる多くの経営者の人たちは毎日の仕事や生活に忙殺されていて、近視眼的に目先のことで精一杯、自分の未来を真剣に考えていないように思います。
いくつもの問題を抱えていながら、それを見ないふりして、日々の目先の諸事を「こなす」ことを優先すること、それに満足する人たちが多いように思います。
いくつもの問題を抱えていながら、それを見ないふりして、日々の目先の諸事を「こなす」ことを優先すること、それに満足する人たちが多いように思います。
ゆでガエル現象・・・
それが、心配でなりません。
それが、心配でなりません。
社員、従業員側としては、「ワークライフバランス」「健康経営」「働き方改革」「パワハラ防止」など、どうしたら働くことを少なくできるか・・・という方向に流されているように思います。
特に、ホワイトカラー。
国際的に見ても、ホワイトカラーの生産性の低さは群を抜いています。
(統計の取り方が、???の部分もありますが・・・)
それなのに、2000時間(正社員)の年間総労働時間を300時間以上減らしてドイツやフランス並みにしようとしている節があります。
「日本は、天然資源に恵まれない国。だから、労働力を大量に突っ込んで加工貿易を回していかないと国がもたない・・・」
今までは、全体が真面目に考えていましたっけ。
勤労は美徳・・・道徳的にも、そんな価値観を植えつけられてきました。
国際的に見ても、ホワイトカラーの生産性の低さは群を抜いています。
(統計の取り方が、???の部分もありますが・・・)
それなのに、2000時間(正社員)の年間総労働時間を300時間以上減らしてドイツやフランス並みにしようとしている節があります。
「日本は、天然資源に恵まれない国。だから、労働力を大量に突っ込んで加工貿易を回していかないと国がもたない・・・」
今までは、全体が真面目に考えていましたっけ。
勤労は美徳・・・道徳的にも、そんな価値観を植えつけられてきました。
政府主導で、「働き方改革」「プレミアムフライデー」「WLB(ワークライフバランス)」というスローガンがあちこちで叫ばれるようになりました。
しかしながら、本当に意味のある、効果が期待される政策は出てきません。
それが、できるのは、親方日の丸・・・公務員だけです(笑)。
こんな状況を、官民一体となって進めていけば、落ちる所は、次のようなもので
しょう。
労働生産性は下がり続ける
残業代は減少し続け個人消費がダウン
国際競争力の低下を招き、YENの力が弱くなる
残業代は減少し続け個人消費がダウン
国際競争力の低下を招き、YENの力が弱くなる
ここに、少子高齢化の加速化、アジア周辺諸国の政治経済の不安定化、地方経済の衰退などが経済停滞に拍車をかけることになります。
それを回避するために、次のような対応策が必要になると考えます。
1 筋肉質の経営を目指し、日々、地道な努力を重ねていくこと。
2 一歩足打法にならないようスーパーサブの事業を打ち立てること。
3 次世代リーダー候補を複数名選定し、実践の場でチャレンジさせること。
4 幹部社員は、数字で事業、経営を語れ、行動できること。
5 日次決算、週次決算などリアルタイムで損益計算、キャッシュフローをつかめる態勢を整えること。
6 経営計画、特に中計を重んじること。
7 ICT、webなどの最新テクノロジーにおいて行かれないリテラシーを持つ
2 一歩足打法にならないようスーパーサブの事業を打ち立てること。
3 次世代リーダー候補を複数名選定し、実践の場でチャレンジさせること。
4 幹部社員は、数字で事業、経営を語れ、行動できること。
5 日次決算、週次決算などリアルタイムで損益計算、キャッシュフローをつかめる態勢を整えること。
6 経営計画、特に中計を重んじること。
7 ICT、webなどの最新テクノロジーにおいて行かれないリテラシーを持つ

VUCA(ヴゥーカ)と呼ばれる、変動・不確実・複雑・曖昧な時代。
スピードと執行力が、サバイバルの鍵を握ります。
さらには、コンプライアンス、CSRといった「やっていて当たり前」の課題も存在します。
スピードと執行力が、サバイバルの鍵を握ります。
さらには、コンプライアンス、CSRといった「やっていて当たり前」の課題も存在します。
経営者は、日々、地道に仕事に全力投球していかなければなりません。
最近、特に思うのが、私を捨てること・・・義と公に生きること・・・。
周りを見渡すと、足るを知り、品格・品性のある経営者しか生き残っていないように思います。
日本経済、国際経済・・・実に、たいへんな時代になってきました。



























