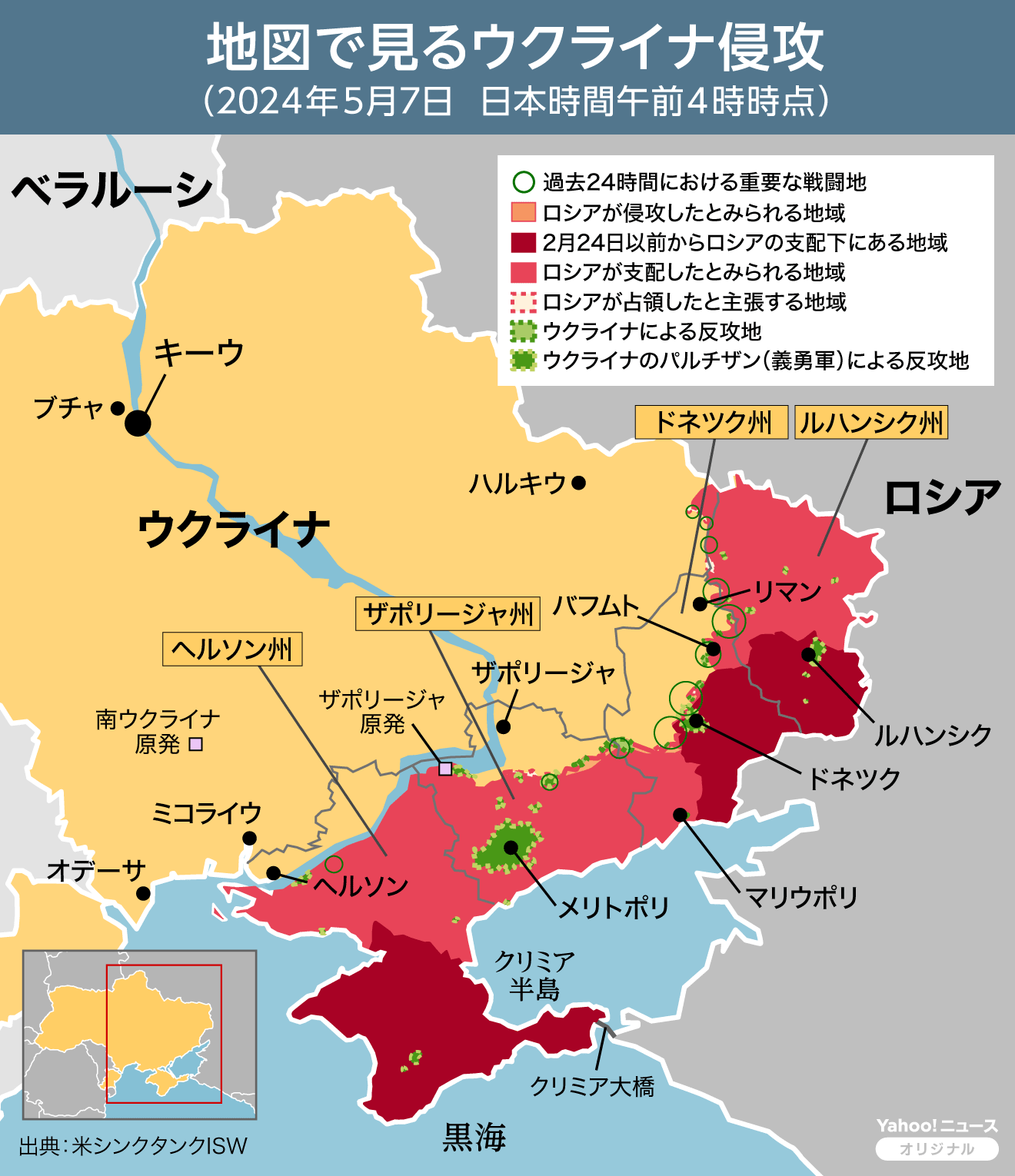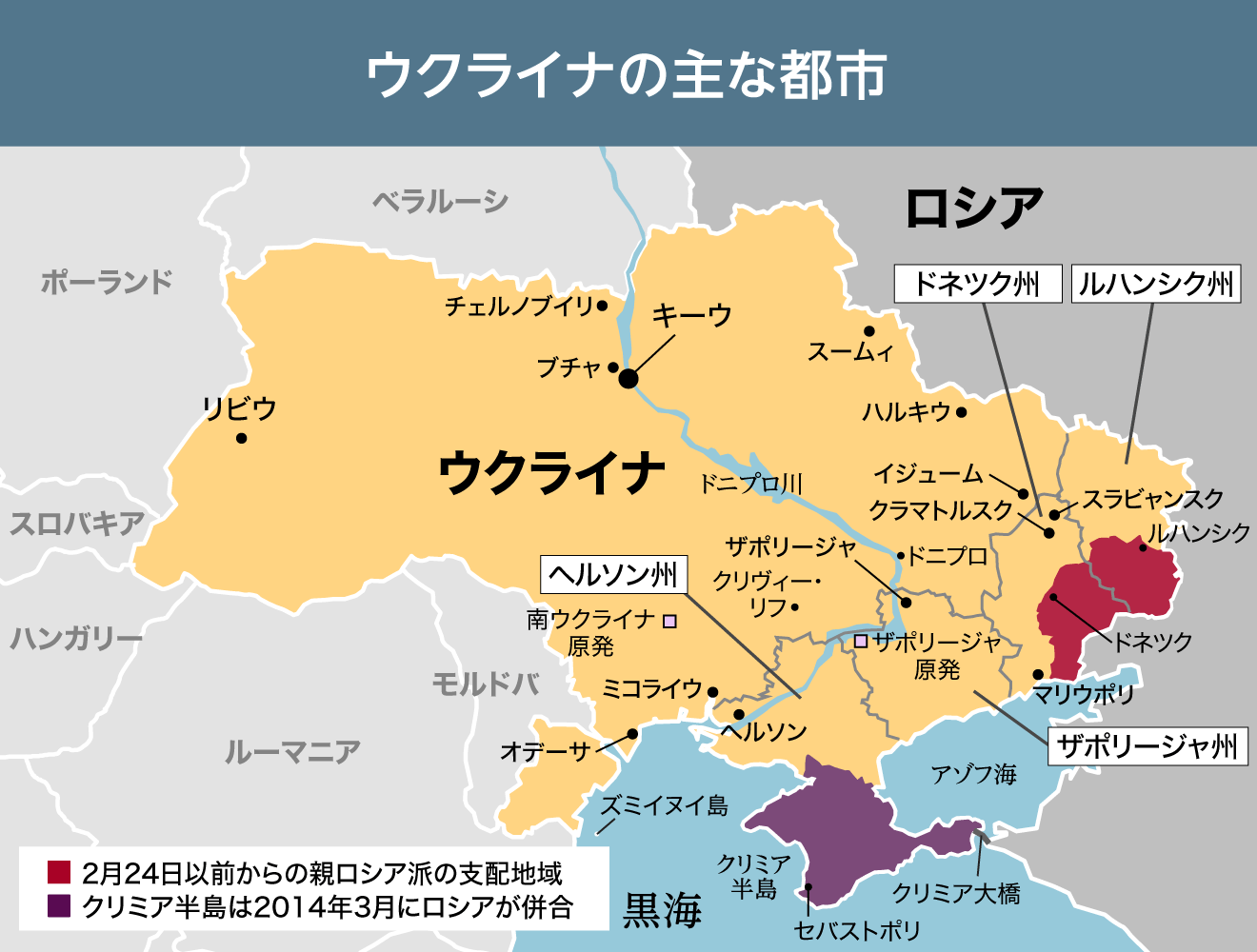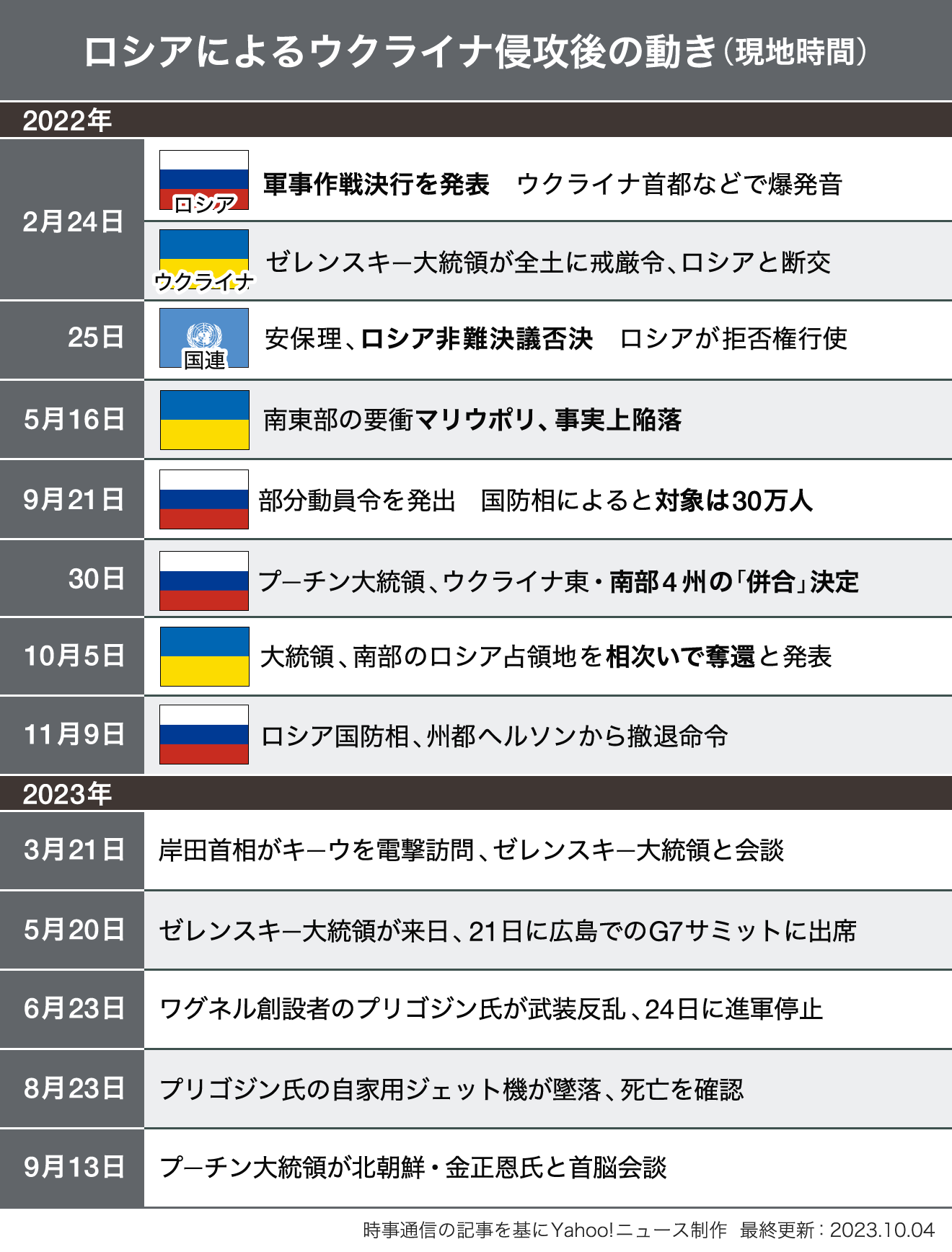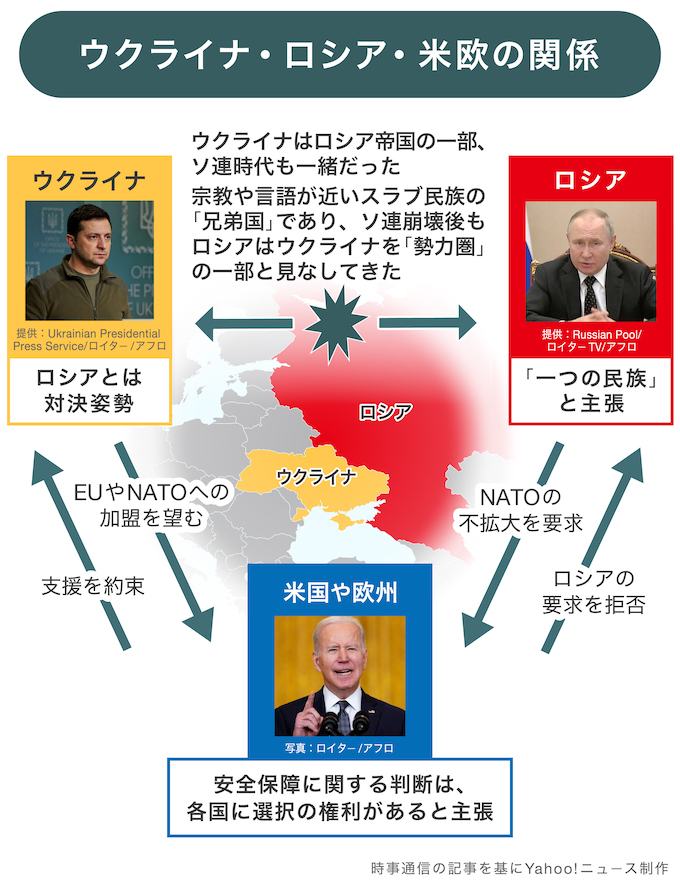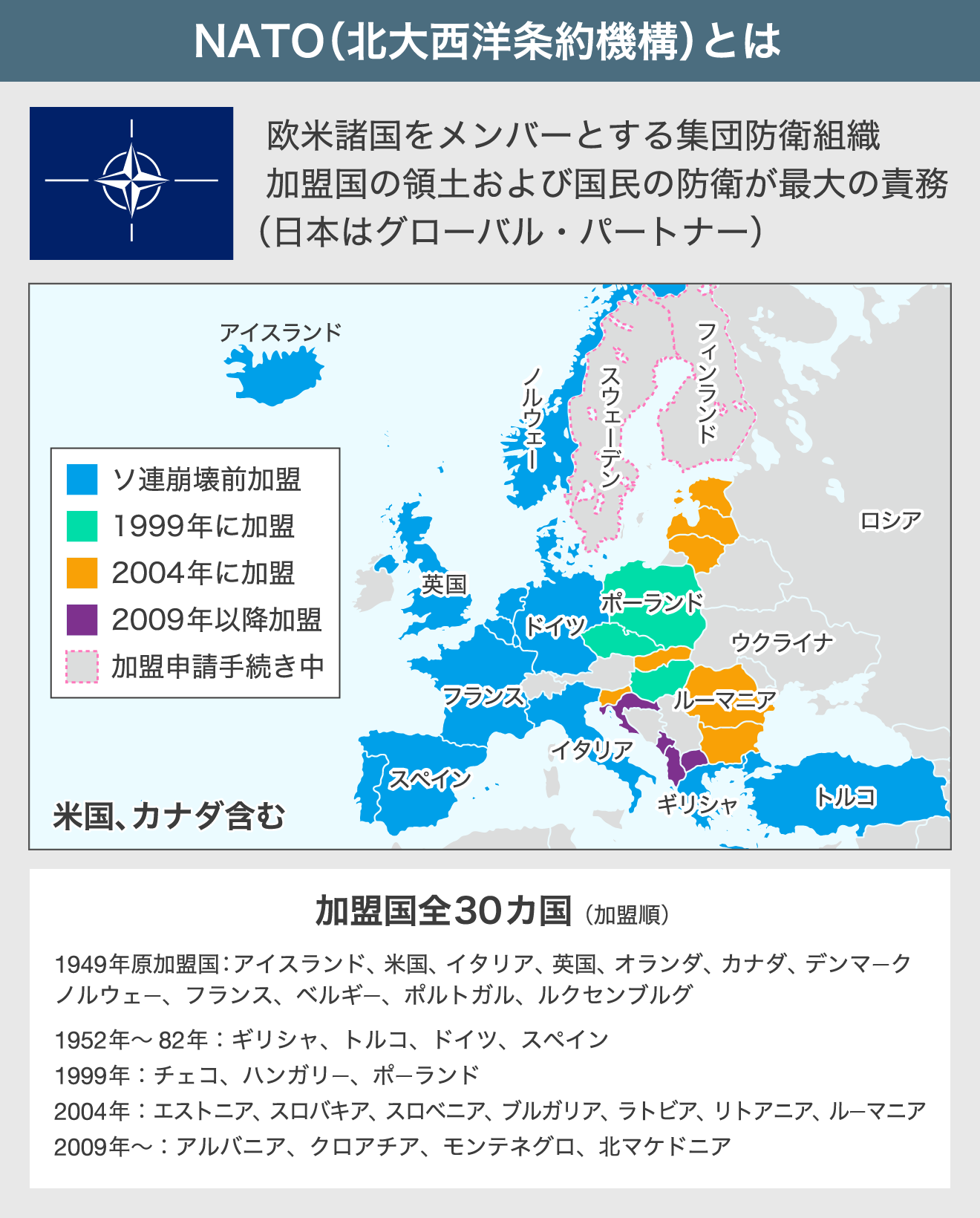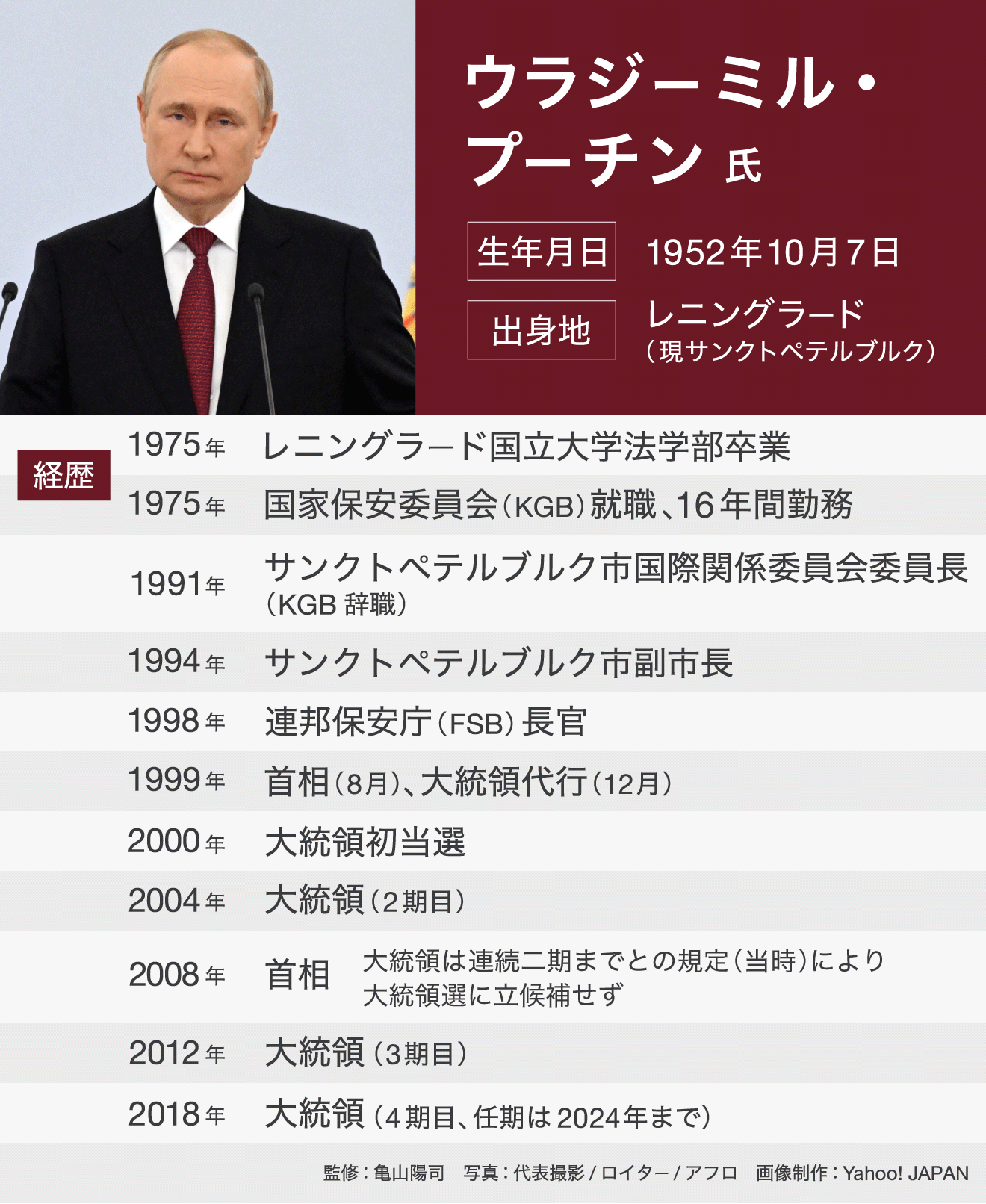K.カール カワカミ (著), 福井 雄三 (翻訳)
内容(「BOOK」データベースより)
支那事変と満州事変は表裏一体のものだが、日本が支那においてとっている行動は決して侵略と破壊を目的としたものではなく、東亜の秩序を確立し混乱を収束するためのものなのだ、日本は国際法にしたがって忠実に行動しているだけであり、欧米列強と事をかまえる意図など少しも無い…。
支那事変前夜の大陸の政治的実情と国際社会の視線を冷静に公平に且つ鋭く見据えていた著者の観察は、日本の正義を主張してやまない。
内容(「MARC」データベースより)
モスクワから中国への軍事援助、中国紅軍の成長、コミンテルンと国民党の同盟など、支那事変前夜の大陸の政治的実情と国際社会の視線を冷静に公平に且つ鋭く見据える。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
福井/雄三
昭和28年7月、鳥取県倉吉市生まれ。東京大学法学部卒業。企業勤務の後、平成3年より大学で教鞭をとる。専攻は国際政治学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
昭和28年7月、鳥取県倉吉市生まれ。東京大学法学部卒業。企業勤務の後、平成3年より大学で教鞭をとる。専攻は国際政治学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
この本は、1931年(満洲事変)から1937年(支那事変)に至るまでの満洲、中国における事実関係を記載した、1938年2月にロンドンで出版されたジャーナリストによる英語本の翻訳である。
1904年、日本は、日露戦争により満洲からロシア軍を排斥した。
1904年、日本は、日露戦争により満洲からロシア軍を排斥した。
日本人の犠牲の下に中華帝国のぐらついた土台を支え、中国を目覚めさせ、中国を安定させるのに中国が協力するとの希望を、日本は抱いていた。
1905年、日本が、ポーツマス条約により南満洲鉄道の経営権と沿線付属地の活用権(特殊権益)を得て、満洲を開発した後、満洲は発展し、漢民族の満洲への移民が増加し、漢民族による満洲人の民族同化が進行した。
米国は、日本による満洲の発展を門戸閉鎖というが、実際は、米国から満洲への輸出は、年々、増大していた。
うち16ケ条については、現状確認であり、アメリカは異議がないことを日本に通告した。
残り5ケ条は、要望として提案されたが、日本は、これを取り下げた。
また、最後通告の85日前に、中国は大部分を受け入れ、30日前に、合意に至った。
また、最後通告の85日前に、中国は大部分を受け入れ、30日前に、合意に至った。
最後通告は、袁世凱が、政敵に対する言訳のために、日本に要求したものであった。
世界は、日本が最後通告により受諾を強制させたと誤解しているとある。
1924〜1927年に掛けて、ソ連から蒋介石や中国共産党に対して、張作霖の没落、武器、資金の援助、西洋列強との敵対関係を維持して日本を孤立化させることが指令されていた(1926年2月ソ連政府からの駐在陸軍武官への指令文書) 。
中国人に寛大な態度で接すると、中国人は、それは弱さの証か収賄の要求とみて、約束は守らないし、国としては多数の条約侵犯があった。
中国人に寛大な態度で接すると、中国人は、それは弱さの証か収賄の要求とみて、約束は守らないし、国としては多数の条約侵犯があった。
条約侵犯の例として、土地の賃借権の拒否、輸出税の4倍の上昇、満鉄平行線の建設、鉄道延長の拒否、中国鉄道による日本商品の輸送料の差別的高料金、大連港の返還、満鉄沿線の警備兵の撤兵、満鉄沿線の日中共同鉱山事業の交渉拒否、大連港におけるタバコ重課税、満鉄建設のための土地売買の禁止、鉄道区域外への日本人の居住及び旅行の禁止、朝鮮人迫害、沿線区域内での不法な税の徴収、日本が資金を提供した中国鉄道に対する日本人の任命の拒否及び監督権行使の拒否、日系資本鉄道の売上金の着服、借款返済の停止などが挙げられている。
これらが、1931年に起こった満洲事変の原因の一つである。
トーマス・エジソンは、この辺の事情について、「日本の事業能力が驚くべき速度で上昇している。日本は進歩的で進取の気性に富んだエネルギッシュな国である。日本がごく自然な流れで拡張して行ける国々にその活動範囲を広げて行くことを、国際社会が一致団結して妨げるならば、日本を静止した平和な満足した状態のままにとどめておく方法を見いだすのは難しいだろう。
トーマス・エジソンは、この辺の事情について、「日本の事業能力が驚くべき速度で上昇している。日本は進歩的で進取の気性に富んだエネルギッシュな国である。日本がごく自然な流れで拡張して行ける国々にその活動範囲を広げて行くことを、国際社会が一致団結して妨げるならば、日本を静止した平和な満足した状態のままにとどめておく方法を見いだすのは難しいだろう。
西洋列強諸国が日本の政策に援助することは、むしろ、列強の利益になる。そうしなけば、いずれ爆発し、武力抗争に発展し、計り知れない犠牲を日本に反対する列強の側に生じさせるであろう。」と述べている。
1927年、国民党の権力を奪う共産党の目論見が明らかになると、蒋介石は共産党員を排斥した。
共産党の紅軍は各地で殺人(60万人)、放火(32万戸)、略奪などの破壊活動を展開し、外モンゴルのソ連軍との合流を目指した。この事実の他、暴動、ストライキ、宣伝工作、排日運動と日貨ボイコットが、日本に共産主義の脅威を与えた。
1936年12月、共産党に協力した張学良が蒋介石を投獄し、釈放の代償として、ソ連の指令により国民党と共産党が共に日本と戦うように蒋介石に誓約させた西安事件が起こった。これが契機となり、中国共産党により仕掛けられた支那事変、蒋介石により拡大された上海事変を経て、日本は中国での争いに巻き込まれて行くことになる。
1936年12月、共産党に協力した張学良が蒋介石を投獄し、釈放の代償として、ソ連の指令により国民党と共産党が共に日本と戦うように蒋介石に誓約させた西安事件が起こった。これが契機となり、中国共産党により仕掛けられた支那事変、蒋介石により拡大された上海事変を経て、日本は中国での争いに巻き込まれて行くことになる。
この本には、ソ連、コミンテルン、中国共産党による日本排斥活動、虐殺行為の偽装写真による宣伝工作、上海の外国租界への空爆を日本軍が行ったとする宣伝工作、南京空爆の宣伝工作、支那人気質など、1931〜1938年における中国の実状が記載されている。
満洲事変、支那事変以後を日本軍による一方的な侵略と思っている日本人は、是非とも、この本を読むべきである。現在の毒ギョーザ事件、尖閣問題、反日暴動、歴史認識の強要に関する中国の態度を見ると、当時は、現在の程度を遥かに超える契約違反、反日排斥暴動が起こっていたことが容易に想像できる。政治家、批評家、マスコミ人は、読むべきである。現在の中国に対する対処法が見える。
満洲事変、支那事変以後を日本軍による一方的な侵略と思っている日本人は、是非とも、この本を読むべきである。現在の毒ギョーザ事件、尖閣問題、反日暴動、歴史認識の強要に関する中国の態度を見ると、当時は、現在の程度を遥かに超える契約違反、反日排斥暴動が起こっていたことが容易に想像できる。政治家、批評家、マスコミ人は、読むべきである。現在の中国に対する対処法が見える。
作者の立場(それは記者であったり外交官のブレーンであったり)を存分に活用した情報収集力、世界を翻弄するうねりに対する観察力、分析力、導き出した結論を世に出せる、わかりやすく伝えることができる伝達力、それらすべてをこの人物が持っていたことは、後世の私達にとって幸運だった。彼は故郷である日本を愛していた。そしてその友人たるアメリカをイギリスを愛していた。
互いの国の間に起きた誤解を何とか解きたいとこの本を書いたのだろう。昔も今も口下手でプライドが高い日本人の代わりに、それぞれの国が抱える問題、目的、事実を、なんとか伝えようとしいてる。広範囲にわたる情報を、わかりやすくまとめ、読む者に飽きさせず伝えてくる。
リアリストである彼が、必死で声を枯らしたであろう言葉を、私達は目で聞くべきだろうと思う。
リアリストである彼が、必死で声を枯らしたであろう言葉を、私達は目で聞くべきだろうと思う。
ロンドンと北京で押収された秘密文書など、さまざまな資料を用いてソ連とコミンテルン、およびその指導下にある中国共産党など共産主義勢力の暗躍を明示している。
これは戦後の研究ではないのだ。世界に潜む狂気は戦前においてすでにここまで明確に暴き出されていたのである。
このような明確な事実が批判されるどころか、追放されていた迷走の戦後。
昭和の狂気は前半よりむしろ後半において顕著に象徴されるのである。
日華事変、およびその原因とされる満州事変について勉強する時、日本の強靭な姿勢というのはどうにも理解しがたいものだ。
日本の中国政策にいつも出てくる「排日取締り」、この重要性は今から「実感」するのはなかなか難しい。
この書においてはその「実感」を得ることができる。
断片的にその暗黒の狂気の尻尾を現す共産勢力にたいする圧倒的な恐怖、この「実感」無くして日本の政策の真意は理解できない。
物心ついてのち、ずっと感じていた、漠然とした、しかしながら確かな疑念;我々の祖国日本が、そんなに愚かな、極悪ともいうべき、現行の戦後史観がいうような、そのようなどうしようもない国”で果たしてあったのか、と同時に、大東亜戦争(米国による名称を訳したものが太平洋戦争)およびWWIIの戦勝国である、現在の国連常任理事国の国々が、本当に”正義”であったのだろうか。本書は、これらを一切合切払拭してくれました。しかも、歴史の事実がその当時への共感なくしては判断しえず、また、戦争や起こってしまった事象においては、一方が悪で、片方だけが正義なんて事は絶対にないということを教示してくれます。これは釈迦の見いだされた真理、すなわち因果=全ての物事は連関しており、何一つ単独で作用するものはない、をいみじくも裏付けるものです。
しかしながら、本書はその一方で、日本人は今なおナイーブな民族であり、まさにその“お人好し”ぶりを再び現代においても繰り返している、おめでたい民族である、という事実をも苦笑とともに明示してくれます。
すなわち、本書は、歴史への共感と透徹する目、そして歴史を真剣に考察すらばこそ、そこには真実があり、さらには現代の動きがそこにすべて濃縮されている、そう、歴史こそ現代の縮図であるということを、我々につきつけてくるのです。現在巷間にあふれている”常識”は、それはある偏向した”常識”でしかないことをも教えてくれます。
私の迷妄たる目を、まさに開かせてくれたのが本書でした。ヘレン・ミアーズの『アメリカの鏡・日本』と併読されると、櫻井よしこさんのレベルにたった一歩ではありますが、近づけるはずです。賢明な読者の中には、イラク戦争の実相が、いかに大東亜戦争のそれと類似しているかをそこに読み取る方もきっとおられることでしょう。ぜひすべての日本人に読んでほしい名著です。
この本を読めば、戦前の中国大陸の実情と日本のおかれた苦しい立場が理解できる。歴史は日本が被害者、中国が被害者という単純な視点では見ることはできない。まず最初に私が暗澹とした気持にさせられるのは、清朝の李鴻章から蒋介石や張学良、その他の軍閥指導者の政治的及び道徳的モラルの低さである。この絶望の大陸にいやがうえでも関与し続けなければならないのが戦前の日本である。
日本の足を引っ張り反日運動を激化させた米国にとって中国は所詮投機の対象でしかない。
どの中国の政権(蒋介石や他の軍閥)も腐敗し住民を酷使し、条約を踏みにじり、なおかつ崩壊寸前である。反日テロを怒号する蒋介石や諸軍閥に対し日本の政府・軍部の対応は本当に冷静である。
しかし日本の紳士的な対応はますます彼らを増長させるだけである。これは今日の日中関係にもあてはまる。米国は今日においても中国に幻想を抱き続けている。何も変わっていない。「日中友好の狗」たちが本書よみ、現実に目覚めてほしい。
何と言っても1938年2月に発刊されたというだけで貴重な本である。
歴史的な発掘といって良いのかもしれない。
この本はシナ事変勃発によって、当時、国際的非難を浴びていた日本を弁護することを趣旨としてイギリスで発刊された本であるため、「反日」的な人は、“何だか、日本に都合が良いように書かれていないか?”と思うのかもしれないが、何故、日本人がわざわざ日本に都合悪く「反日」的な歴史観を持たなくてはいけないのか?
「歴史問題」を外交カードに使い、日本を世界的に貶めようとしている中国・韓国といった国は都合良い・悪いの次元ではなく、嘘だろうが捏造だろうが関係のない、史実を完全に無視した虚言・妄言・暴言のごり押しである。
我々は、日本人らしく正当な史実を持って、正々堂々と彼らの虚言を論破して、国益を守るべきであろう。
同時代に書かれただけあって、当時の空気や、当時でしか知りえない事実まで書かれ、歴史本というよりはルポタージュというべき本である。
もちろん、後に肥大化する捏造事件「南京大虐殺」なんてものは、当時は全く問題にならず存在すらしないプロパガンダであるため触れてもいない。
付録収録された同時代の斉藤博・駐米大使の講演録も秀逸!
この本はシナ事変勃発によって、当時、国際的非難を浴びていた日本を弁護することを趣旨としてイギリスで発刊された本であるため、「反日」的な人は、“何だか、日本に都合が良いように書かれていないか?”と思うのかもしれないが、何故、日本人がわざわざ日本に都合悪く「反日」的な歴史観を持たなくてはいけないのか?
「歴史問題」を外交カードに使い、日本を世界的に貶めようとしている中国・韓国といった国は都合良い・悪いの次元ではなく、嘘だろうが捏造だろうが関係のない、史実を完全に無視した虚言・妄言・暴言のごり押しである。
我々は、日本人らしく正当な史実を持って、正々堂々と彼らの虚言を論破して、国益を守るべきであろう。
同時代に書かれただけあって、当時の空気や、当時でしか知りえない事実まで書かれ、歴史本というよりはルポタージュというべき本である。
もちろん、後に肥大化する捏造事件「南京大虐殺」なんてものは、当時は全く問題にならず存在すらしないプロパガンダであるため触れてもいない。
付録収録された同時代の斉藤博・駐米大使の講演録も秀逸!
翻訳もしっかりしていてすばらしい本だが、値段が高いのと、人名などの固有名詞の調査が適当すぎる。盧溝橋の永定河ぐらい漢字で表記してほしいし、支那駐屯軍司令官の名前ぐらいちゃんと調べてほしい。よって星四つ