▼強い人生を生き抜くことだ。
そのために、精神を鍛練する。
精神を向上させる。
▼太陽をよろこぶところ
どのような憂いもない
われらが世界に散らばるように
そのためにこそ世界はこんなにも広いのだ
ゲーテ
▼人生の幸福を開くのは、生きる喜びである。
その生命の底からの歓喜と感激を自在に探し出し、湧き出す智慧に勝る宝はない。
▼人の悩みにじっと耳を傾け、悩みを受け止める。寄り添うことで、相手自身の本来の力を発動させる。
それ自体が慈悲の発露である。
▼「信」とは、いわゆる妄信では断じてない。
妄信は人の思考や理性を停止させ、人間を弱く、脆くしてしまう。
「信」とは、どこまでも理性を重んじ、知性によって深められるものだ。
▼「信」がさきで、行動と学びがあり、その繰り返しで「信」を深化させていくことで、自身の人生を最高の智慧と創造性を輝かせることができる。
▼各人が自他共の尊厳と限りない可能性を確信する。












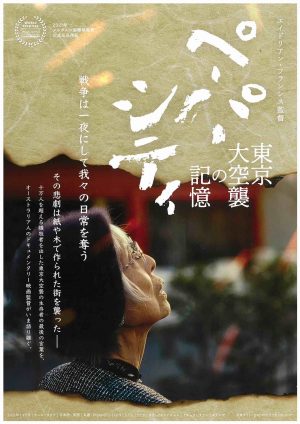



約450ページほどあるが、『永遠の都』より読みやすい。本書は著者の分身でもある悠太をメインにした教養小説のような趣もある。
ただ、登場人物が多いこと、それぞれの関係など『永遠の都』を読んでいないと、やや分かり難いと思われる。
東大医学部に進学した悠太、『永遠の都』ではあまり目立たなかった桜子、菊池透と再び一緒に生活しだした夏江、さらには悠太の高校時代の友人だけでなく、セツルメントで知りあった人々などに関する記述が多くなり、初江はやや後景に退いた感じがする。
本書では、サンフランシスコ講和条約成立前後で、ようやく落ち着きを取り戻しつつも、戦前の価値観などを受け継ぐ人々と、新しい時代を目指す人々の対立が鮮やかに描かれている。特にいわゆる“血のメーデー事件”の部分は印象的。この事件については、様々な見解があるようだが、著者は、権力者サイドの謀略説によるものとして描いている。
加賀乙彦氏(1929-)による自伝的長編小説『雲の都』の第一部「広場」です。
2章から成り
第一章 水辺の街
第二章 広場です。
時代的背景としては1952年2月頃から同年8月頃までをカバーしています。
中でもvividに記述されているのが同年5月1日の「血のメーデー」です。
従って章題・部題の「広場」は皇居前広場を意味あるいは象徴しています。
本書の主人公・小暮悠太も予期しない形で「血のメーデー」に巻き込まれていきます。
‥詳細は本書をお読みになっていただけると誠に幸いです。
小説の内容をくどく説明するのは野暮というものですから。
さて
『雲の都』は『永遠の都』の続編です。
『永遠の都』をお読みになってから『雲の都』をお読みになるといっそう理解が深まることでしょう。
しかし『永遠の都』を読まずに『雲の都』から読み始めてもなぜなら『永遠の都』においては主人公は小暮悠太の母方の祖父時田利平であり時田利平が死ぬところまでが『永遠の都』のお話だからです。
また重要な登場人物である脇晋助も復員後しばらくして亡くなります。
『雲の都』において小暮悠太が真の主人公になるわけです。
「自伝的な」という意味について説明いたします。
主人公・小暮悠太は作者と同一の生年月日を与えられています。
その意味で作者の分身的存在です。
戦前には陸軍幼年学校に行く点や戦後は医学部を出て医師となる点など経歴においても作者の経歴をなぞって行きます。
そもそも『永遠の都』が「2.26事件」から始まるのには理由があって作者の記憶が始まるのが「2.26事件」からという由です。小説においても小暮悠太の2歳年下の駿次は「2.26事件」も覚えていないし軍隊は経験していません。
兄に悠太は陸軍幼年学校という形で陸軍を経験しています。
わずか2歳という年齢差で共感できる歴史的背景が全く異なりなす。
そういう差異を大切に描いたことからも「自伝的な」長編小説と言えると思います。
一方『永遠の都』と『雲の都』を「大河小説」と呼ぶ人もいますが私はこの呼称には反対です。
可能な限り「大河小説」という語は使いません。
理由は多々あります。
①定義が不明確。
‥大河小説はフランス語 roman-fleuve の翻訳と見られます。もともとロマン・ロラン(1866-1944)が自分の小説『ジャン・クリストフ』を大河に例えたことに始まるとされアンドレ・モーロワ(1885-1967)が
使用しました。
しかしアルベール・チボーデ(1874-1936)はそれでは不十分だとして連鎖小説 roman-cycle を提唱したとされます。
ロランもモーロワもチボーデも私は原典を見たことがありません。
おそらく大河小説とは「ある個人・家族・一群の人を中心に一時代の社会を広範に描いたきわめて長い小説」くらいの意味です。
『ジャン・クリストフ』以外には『チボー家の人々』くらいしかありません。
マルセル・プルースト(1871-1922)の『失われた時を求めて』を大河小説として挙げる人もいますが
的外れであろうと思います。
むしろ「意識の流れ」を詳細に追った小説としての方が本質をついています。
マドレーヌを紅茶にひたしたところ「記憶」が一気によみがえった‥という冒頭が世界的に有名な通り
「意識」や「記憶」が大切なキーワードです。
要するに「大河小説」とは1920年代頃のフランス文学の概念に過ぎずあまり成功した作品はありません。
ロシアのトルストイ(1817-1875)の『戦争の平和』やドイツのトーマス・マン(1875-1955)の
『ブッデンブローグ家の人々』は決して「大河小説」とは呼ばれません。
むしろ『戦争と平和』や『ブッデンブローグ家の人々』の方が『永遠の都』『雲の都』に近いと思います。
②作者自身が使っていない
‥例えば『加賀乙彦自伝』(集英社 2013)の「あとがき」において「最近、『永遠の都』と『雲の都』という自伝的長編小説を上梓したが、この二つの作品は、自伝ではなく、あくまでフィクションに力点を置いた
小説である。」(同書 P.274)と書いています。
この自伝はインタビューに対する「語り」がそのまま文字になっていますが少なくとも作者本人は「大河小説」と言っていません。
インタビュー及び構成を担当した人が書き込みを行ったところで安易に「大河小説の完結」などの小見出しをつけているのが実態です。
『永遠の都』と『雲の都』の版元である新潮社も最初のうちは決して「大河小説」とは呼んでいませんでした。
しかし手元にある
『雲の都』第五部「鎮魂の海」(新潮社 2012 )の奥付のさらに後ろの広告のページで「雲の都(全五巻)」の紹介文の中で「自伝的大河小説」という語を使っています。
出版社の編集者の思いつきなのでしょうがたいへんな違和感があります。
③テレビドラマの印象が強過ぎる‥日曜日の夜に公営放送がやっているドラマが今では大河ドラマと呼ばれています。
もともと公営放送は大河ドラマとは自称していませんでした。
「大型時代劇」と正確に名乗っていました。
全国紙であるZ新聞(仮称)が「大河ドラマ」という呼称を使ったのが始まりとされます。
それが公営放送に逆輸入されて後に「大河ドラマ」と名乗るようになりそれがすっかり定着して現在に至ります。
呼称はともかく内容は「大型時代劇」です。
娯楽作品であって決して歴史ではありません。
以前は娯楽であってもよくできた水準のものがありました。
もちろん年度にもよりますが近年は娯楽作品としても荒唐無稽なものも含まれます。
(時代劇が好きで『花の生涯』『赤穂浪士』以来「大型時代劇」をよく見ていた祖母は2011年以来「気持ち悪い」と言って見なくなりました。)
従って『永遠の都』や『雲の都』のような優れた文学作品を「大河小説」と呼ぶのは適切でないと私は考えています。
冒瀆と言ったら表現が強いかもしれませんが大衆迎合というそしりは免れません。
「自伝的長編小説」(作者自身の表現)がいちばん適切な表現と思われます。
版元や編集者の方々は安易な「大河小説」(定義が不明・不適切)という用語の使用について
よく考えてみる必要があると老婆心ながら提言申し上げます。
作曲家で、一連の随筆
『パイプのけむり』で知られる團伊玖磨(1924-2001)はまさにその随筆の中で次のようなことを書いています。
‥日曜の夜
三波伸介(1930-1982)が司会の「減点パパ」
は好きでよく見ていた。
8時になると家族全員でいっせいに『テレビを消せー』と叫んでテレビを消しそれぞれ自室で読書にふけった」という内容です。この時は『勝海舟』(1974)でした。
なみに同年、加賀乙彦氏は『頭医者』の連載を開始し前年『帰らざる夏』で谷崎潤一郎賞を受賞されています。
以上
『永遠の都』『雲の都』が自伝的長編小説であって大河小説ではない理由を述べました。
最後に『永遠の都』『雲の都』とあわせて読むと理解が深まる本を挙げておきます。
ひとつは上述の自伝『加賀乙彦自伝』(発行ホーム社 発売集英社 2013)です。もうひとつは加賀乙彦・岳真也(による対談)
『「永遠の都』は何処に?』(牧野出版 2017です。
特に後者においては『永遠の都』創作の秘密の一端を知ることができます。
例えば『永遠の都』執筆で真似をしたあるいは目指した本を3冊挙げるならば
①紫式部『源氏物語』
②カール・マルクス『資本論』
③トルストイ『戦争と平和』になるというお話です。
その真意はご自分でお読みになっていただけると誠に幸いです。
ナラティブ narrative つまり
「一人称による語り」
という手法を駆使した『永遠の都』と『雲の都』を同時代を生きた方々にお勧めいたします。