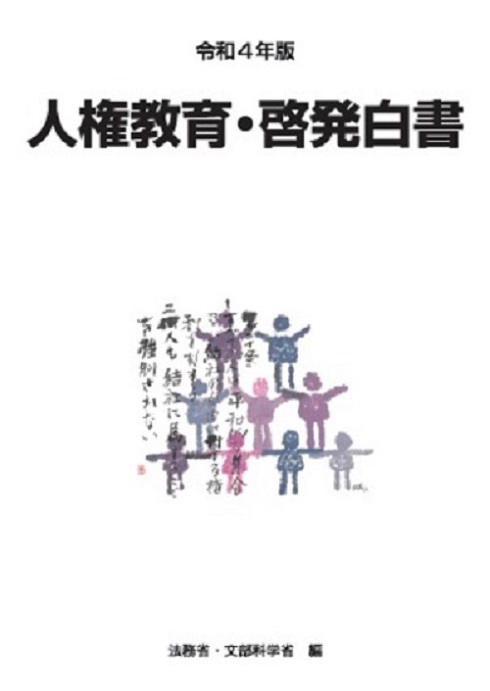1万円を持って地元取手競輪へ行こうとしたが、<相性が悪い>競輪場なので、5000円にした。
「1000円で楽しむ競輪「の提唱者であった牛久の元カーテン屋さんのことが、頭に常にあるのだ。
1レース1000円で楽しむのか元カーテン屋さんの競輪の流儀だった。
競馬を教えてくれた元同僚の森さんも「1000円で楽しむ競馬」の実践者であった。
その森さんは、家庭をもっていたので実に堅実であった。
利根輪太郎のような独身者の放埓さとは無縁であった。
ちなみに、利根輪太郎は26歳で競馬を初めてやった。
東京・亀戸の森さんのアパートに泊まり、翌日の日曜日に中山競馬場へ向かった。
森さんの奥さんは、出産のために富山の実家へ帰省していたのだ。
競馬などは初めてであり、森さんに言われるままに、1-4 2-4 4-8を各100円買ったら1-4と入り、100円が5000円余りとなる。
それ以来、1-4の目に拘ることに。
実は、麻雀を覚えたのは、新潟湯沢のスキー場へ仲間たちと行った30歳の時だった。
麻雀では思えば、性格が災いしたのか? 友人たちには、カモにされるばかっだった。
つまり、狙い撃ちにされたようだ。
「降りることをしない頑な性格」は麻雀には不向きであったようだ。
また、パチンコは、27歳でのめりこむ。
しかし、パチンコで負けた記憶は殆どない。
手打ちのパチンコの時代であり、セミプロごとき連勝を続けたが、電動式のパチンコの時代となり、パチンコとは決別した。