TwitterやInstagramの裏アカウントを作っている若者は少なくありません。
複数のアカウントを用途に合わせて使い分けることで、SNSをもっと楽しむことができるのです。
しかし裏アカの使い方に失敗すると、人間関係に悪影響を及ぼす場合があります。
この記事では、裏アカを持つメリットやデメリット、裏アカウントの作成方法を解説します。
裏アカを作ってみたいという人は、ぜひ参考にしてください。
裏アカウントを作ることには、次のようなメリットがあります。
自由に投稿できてストレス発散になる
本来のアカウントは友人や知人がフォローしているので、ネガティブなことや自分のイメージが崩れてしまいそうなことは気軽に投稿できません。
しかし裏アカは匿名性の高いアカウントなので、自分の思っていることを自由に投稿できます。
日頃我慢している愚痴をたくさん吐いたとしても、知り合いにドン引きされることはありません。
本来のアカウントに投稿すれば友人に非難されそうなことも、裏アカウントであれば自由に投稿できるのでストレス発散になります。
動画&画像のストレージとして活用できる
動画や画像が多すぎて、スマホに保存できなくなったとき、裏アカウントをストレージとして活用することが可能です。
裏垢に動画や画像をアップし、スマホ本体から削除すれば、撮影したコンテンツを保存できずに困ることはありません。
ハッシュタグをつけておけば、見たい画像を探すのも簡単。
見られて困る画像や動画を保存するのであれば、非公開にしておきましょう。
新しい人間関係を構築できる
裏アカウントを作れば、新しい人間関係を構築することができます。
身近に気が合う人がいなくても、SNSを使えば自分と似た人とつながることができるでしょう。
たとえば、オタクと呼ばれるような趣味を持つ人は、本来のアカウントでマニアックな投稿をしても周りの反応はイマイチなはずです。
もしかしたら趣味を理解してくれない人が否定的な反応をするかもしれません。
ところが趣味専用の裏アカウントを作れば、身近な人たちのリアクションに恐れることなく趣味友探しができます。
裏アカによって、趣味の話で盛り上がる仲間を作れるでしょう。
アカBANによってフォロワーを失わずに済む可能性がある
TwitterやInstagramのポリシーに反した投稿をしている人は、アカBAN(アカウント停止)になる可能性もゼロではありません。
万が一、垢BANになったときのため、裏アカをフォローしておいてもらえばフォロワーを一気に失わなくて済みます。
裏アカウントを持つデメリット
裏アカウントを持つことにはデメリットもあります。
大きなトラブルに発展するケースもあるので注意しておきましょう。
アカウント管理がめんどくさくなる
思っていることを自由に投稿できる裏アカウントは、自分を解放できる憩いの場となります。
しかし、そうしたアカウントが増えることで、単純に管理するのがめんどくさくなるケースがあるのです。
「この投稿は本垢」「この投稿は裏アカ」など、投稿内容によっていちいちアカウントを切り替えるのは、意外とめんどうに感じるでしょう。
アカウントが増えるほど、裏アカが憩いの場ではなくなるかもしれません。
本垢での誤爆で知人と気まずくなる恐れがある
裏アカを持つと、アカウントを切り替えるのを忘れて、誤爆してしまう可能性があります。
裏アカのつもりで同僚の悪口を投稿したら本垢だった…なんてときは、顔が真っ青になってしまうでしょう。
また、周りに知られたくない趣味用のアカウントを作っている人は、本垢で誤爆すると「そんな趣味が!?」と知人に知れ渡り、気まずくなる恐れがあります。
誤爆はこれまでに積み上げた信頼やイメージを一気に崩すリスクがあるため、投稿前には必ずアカウントを確認しておきましょう。
SNS依存に拍車がかかる
裏アカを複数作れば、それぞれのアカウントで人間関係を広げることが可能です。
SNSは気軽につながれるツールなだけに、コツさえ掴めばどんどんフォロワーを増やすことができるでしょう。
刺激を与えてくれるSNSの使用は楽しいですが、複数のアカウントを持てば管理に時間を取られます。
その結果、SNS依存に拍車がかかることになるのです。
裏アカウントの作成方法
使い方に注意すれば、裏アカウントを作ることで日々の生活がより充実するでしょう。
ここからは、Twitter・Instagram別に裏アカの作成方法を紹介します。
スマホアプリでTwitterの裏アカウントを作成する手順は、次のとおりです。
- iOS版アプリはメニュー画面右上の「⋯」ボタン、Android版アプリは右上の「v」ボタンをタップし、「新しいアカウントを作成」を選ぶ
- 名前・メールアドレス・生年月日を入力して「次へ」をタップする
※電話番号の枠をタップすると、メールアドレスの入力が可能になる
- 「環境をカスタマイズする」という画面で「次へ」を押し、次の画面で「登録する」をタップする
- 登録したメールアドレスに認証コードが送信されるので、Twitterアプリの画面にコードを入力して「次へ」をタップする
- パスワードを設定して「次へ」をタップする
- プロフィール画像と自己紹介文を設定する
※「今はしない」をタップすれば、後で設定可能
- 「連絡先を同期する」「今はしない」のどちらかをタップする
※裏アカウントを知られたくない場合は「今はしない」を選択する
- 興味のあるトピック・おすすめアカウントの画面では、必要に応じて選択した後「次へ」を押すか「今はしない」をタップする
これで裏アカウントの作成完了です。
Instagramの場合
スマホアプリでInstagramの裏アカウントを作成する手順は、次のとおりです。
- Instagramのプロフィールページを開き、右上にあるメニューアイコンをタップする
- 「設定」をタップする
- 「アカウントを追加」をタップして「新しいアカウントを作成」を選ぶ
- ユーザーネームを入力して「次へ」をタップする
- パスワードを入力して「次へ」をタップする
- 「登録完了」をタップする
- Facebookの友達を検索・連絡先を検索の画面が表示されたら「スキップ」をタップする
- 「写真を追加」または「スキップ」をタップする
- 右上の「次へ」をタップする
これで裏アカウントの作成完了です。
裏アカウントが知り合いにバレるのはなぜ?
裏アカウントの存在を内緒にしていても、知り合いにバレてしまうことがあります。
バレる理由には、次のようなものがあります。
- 本アカと似たアカウント名にしている
- 本アカと同じ画像を使っている
- 個人を特定されるような内容を投稿した
このような行動から、知人に裏アカバレる可能性があるので注意しましょう。
裏アカウントが周囲にバレないための対処法
裏アカウントは知り合いにバレる可能性があるため、バレたくない場合は次のような対処法をとりましょう。
個人情報がバレるような投稿はしない
勤め先や自宅近くの写真など、個人が特定できるような投稿によって裏アカウントが周囲にバレる可能性があります。
友達と行った店や会話などは、同席した友達が見たらすぐに裏アカアカであることがバレてしまうでしょう。
個人情報がバレるような投稿をすると誰かに気づかれる危険性があるため、気をつけてください。
本アカと裏アカの相互フォローはしない
自分の投稿がどのような見え方をしているか確認するため、本アカと裏アカを相互フォローする人もいるでしょう。
しかし、どのようなアカウントをフォローしているかは簡単に確認できるため、投稿内容によっては裏アカということがバレるかもしれません。
Twitterであれば、本垢のリツイートや「いいね」もやめておいた方がよいでしょう。
本アカと裏アカは関連を持たないようにしておくことで、バレるリスクを下げられます。
非公開設定にして使用する
検索機能によって知人に裏アカの存在がバレることもあります。
バレるリスクを下げるためには、アカウントを非公開設定(鍵アカ)にしておきましょう。
非公開設定にしておけば、知人に見つかることがなく安心です。
裏アカウントの使い方次第で人生が豊かになる場合がある!
裏アカウントを作ることで、趣味の友達を作ったり、本音を投稿してストレス解消できたりします。
交友関係が広がり、人生が豊かになる場合もあるでしょう。
ただし、周囲の人に裏垢の存在を内緒にしたい場合は、十分な注意が必要です。
個人情報がバレるような投稿にはくれぐれも気をつけてくださいね。
まとめ
- 裏アカウントは、メインで使用するアカウントとは別に設けたサブアカウントのことを意味する
- 裏アカウントを持つメリットには、自由に投稿できてストレス発散できることや動画などのストレージとして活用できること、新しい人間関係の構築などがある
- 裏アカウントを持つと、本垢の投稿が疎かになったり本垢での誤爆で知人と気まずくなったりする恐れがある
- 裏アカウントが知り合いにバレる理由として、本垢と似たアカウント名を使うことや、個人を特定できる内容の投稿などが挙げられる
- 裏アカウントが周囲にバレないようにするには、本垢と裏垢の相互フォローをしないことや非公開設定にすることがポイント
Twitterで裏アカ女子として卑猥な画像を送ってお金を稼ぐのは犯罪ですか?
















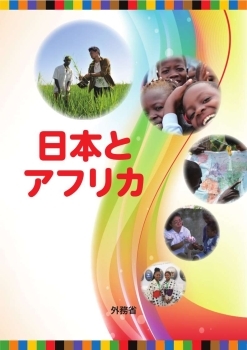















































 </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture>