中村宅での月1回の会合へ行く。
午前11時から1時間、当方が司会をする。
今年の私の漢字1字では「健」の人が5人。
「挑」「和」「信」「明」「平」「飛」などで、当方は「前」それぞれの人が、漢字1字への願いや決意などを語る。
地区部長の大原さんは仕事で欠席して、川島さんが代理を務めた。
ビデオを観て終了する。
中村宅での月1回の会合へ行く。
午前11時から1時間、当方が司会をする。
今年の私の漢字1字では「健」の人が5人。
「挑」「和」「信」「明」「平」「飛」などで、当方は「前」それぞれの人が、漢字1字への願いや決意などを語る。
地区部長の大原さんは仕事で欠席して、川島さんが代理を務めた。
ビデオを観て終了する。
月に1回の亀寿司が楽しみだ。
「お孫さんはどうですか?会ってますか」とマスターに聞くと、「日、月にスキー場へ行きます」とほほ笑む。
長野の斑尾高原スキー場である。
「子どもたちとは、湯沢や苗場スキー場へ行っていた」という。
ところで、娘さんは中学生の時と、高校生の頃にアメリカにホームステイへ行っていたので、英語はペラペラだそうだ。
家人は孫が保育所で英語を習っていることを話していた。
マスターによると、母親が少し、認知症になっているそうだ。
「物が無くなっている。誰かが盗んでいる」と騒ぐそうだ、
「歌が好きで鼻歌を歌っているけど、カラオケには行かない。人との付き合いがないんだ」と明かす。
台宿の空き家が壊され、その跡地に3軒の家が新築された。
「あの空き家の土地は、こんなにも広かったのか!」と驚く。
また、東6丁目の空き家も壊されて、更地となる。
30年前に火事になった隣の空き家が、今年になって更地となる。
その空き家は50年以上も空き家だった。
友人の死により、空き家となった家もある。
通称蛇坂の空き家は、30年前から空き家である。
庭は200坪ほどで家も大きい。
「もったいない」と思う空き家が多い。
どの家もまだ、十分住める状況だ。
独身であった友人の寺田さんの家、奥さんを亡くした村木さんの家も、主が亡くなり空き家となってしまう。
1月22日、「NHKから国民を守る党」の「立花孝志」(登録者数75万人)党首が「自殺します!動画に対する説明動画!」と題する動画を公開しました。
動画で自殺宣言するもその後「生きてますので、心配しないで下さい」と投稿
1月18日、斎藤元彦兵庫県知事をめぐる県議会調査特別委員会(百条委員会)で委員を務めていた元兵庫県議会議員の竹内英明さんが亡くなっているのが見つかりました。死因は自殺とみられています。
すると立花は19日には、「竹内元県議は警察に逮捕されるのが怖くて命を絶った」などとYouTubeで発言。
これを受けて20日に兵庫県警の村井本部長が「明白な虚偽」と明確に否定する事態となりました。
立花は自身の発言を取り消して謝罪しましたが、同日公開した動画で自身が原因なら謝罪したいとしつつ、公人である政治家が少し批判を受けたからといって命を絶つのは「ずるいと思うし残念です」などと語っていました。
「自分がこうやって叩かれてみて、きっと竹内さんもそうだったんだろうな。正しいと思って斎藤知事を責めた。でもそれが正しくないって言われてしんどくなって死んじゃったんでしょうね」と竹内さんについて語るとともに、「僕も正しいと思って責めてたけど、そうじゃなかったんですね」と述べ、マンションから飛び降ると宣言しました。
しかしこの動画を投稿してから40分ほど後、立花はXを更新。「生きてますので、心配しないで下さい」と無事を報告するとともに「出来るだけ早く、説明動画出します!」とコメントていました。
関連記事
・立花孝志、動画で自殺宣言し波紋 その後「生きてますので、心配しないで下さい」と投稿
「自殺する気は全くありません」と宣言するとともに「真っ当な批判でも命を断つ方がいるってことが今回わかりました」
同日夜に公開した動画で立花は、迷惑や心配をかけた警察関係者や支援者に対して謝罪します。
そして、「僕自身、まず自殺を本気で考えていたわけではないです」「自殺する気は全くありません」と、実際には自殺を考えていなかったことを明かします。その一方で、過去に躁うつ病であることを告白している立花は、「自殺願望がないとまでは」「心の部分で自暴自棄にっていうのはゼロではないです」と補足します。
その後、竹内さんについて「やっぱり政治家をしなかったほうが良かったですね」と語る立花。
件を踏まえ、誹謗中傷されたら死んでしまう可能性があると自覚がある人は「直ちに政治家やめてください」と呼びかけます。政治家は「命懸けでやる」仕事だと立花は持論を述べ、誹謗中傷を受けて死んでしまった場合に評価されるのかについて「竹内さんには申し訳ないけど、それは否定したい」と語ります。「批判されたら批判を反論するのが政治家」だと主張し、「なぜそれをされなかったのか、僕は竹内さんに対してはそこについて残念で仕方ない」「争ってほしかった」と振り返ります。
合わせて、「死んで何も解決しない」として「卑怯だっていうことをしっかりと伝えたい」とも強調。
その一方で、竹内さんが逮捕されるという嘘の情報で警察業務を妨害してしまったとして改めて謝罪しました。
最後に立花は「真っ当な批判でも命を絶つ方がいるってことが今回わかりました」と述べ、「他人の批判をされる方はそれを十分気をつけていただきたい」と呼びかけます。
そして誹謗中傷を受けた場合には、命を絶つ前に警察や弁護士、身近な人に相談したり、削除依頼を出す、インターネットに触れないなど対策を自分で取るべきだとしています。
SNS上で犯罪実行役を募集する、いわゆる「闇バイト」が大きな社会問題となっており、青少年が「闇バイト」に応募し、強盗などの犯罪に加担してしまうケースも発生しています。
「闇バイト」は犯罪です。絶対に応募しないでください。
特に、SNS上の「短時間で高収入」、「即日即金」、「ホワイト案件」などの言葉に、絶対にだまされないでください。
こども家庭庁では、青少年を「闇バイト」に加担させないために、関係省庁等と連携し、広報・啓発を推進しています。
三原じゅん子内閣府特命担当大臣による「10代の未来あるみなさんへ」と題する青少年の「闇バイト」への加担防止を呼び掛けるメッセージ動画です。
闇バイトは犯罪です。絶対にだまされないでください。
あなたの未来を大切にしてください。
| 闇バイトは犯罪!(Full Ver.:1分28秒) | 闇バイトにだまされないで!(Vol.1:35秒) | 個人情報は送らない!(Vol.2:37秒) | 家族などに必ず相談!(Vol.3:42秒) |
|---|---|---|---|
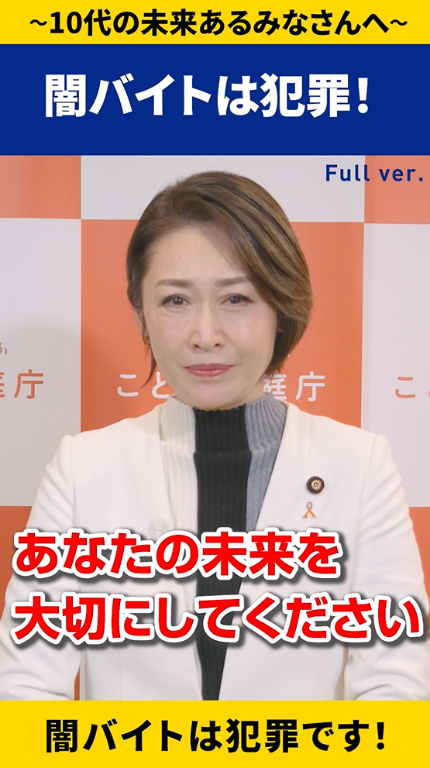 |
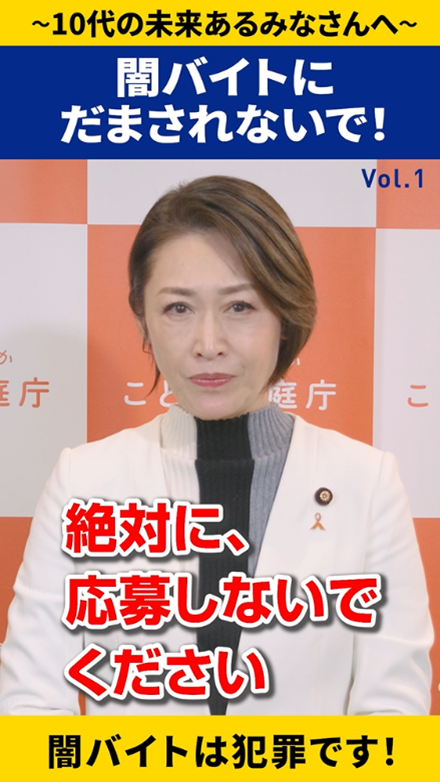 |
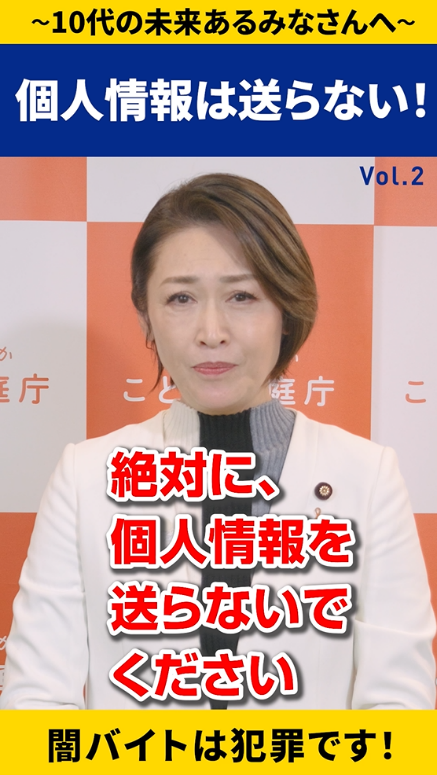 |
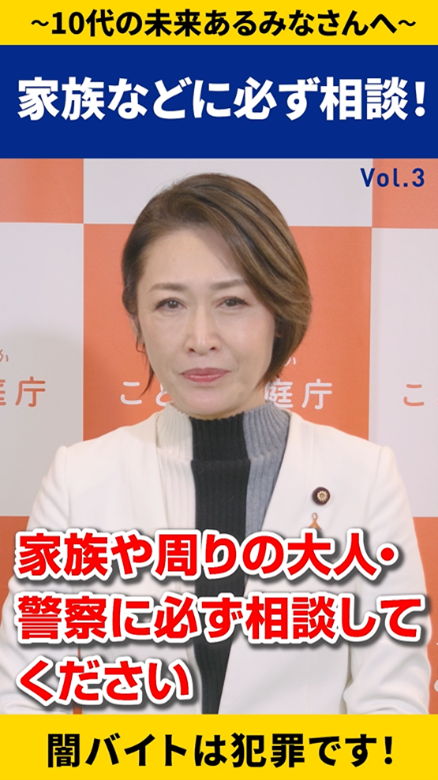 |
こども家庭庁では、警察庁及び文部科学省と共同で啓発資料を作成しました。
青少年が、いわゆる「闇バイト」に応募し、強盗などの凶悪な犯罪に加担させられてしまう事例などについて注意喚起しています。
犯罪に加わる前に、勇気をもって周りの信頼できる大人や近くの警察に相談してください。
「10代のみなさんへ それ、「バイト」ではなく、「犯罪」です!!」(PDF/4.8MB)
(参考)










憩いや遊び、運動、防災などの目的で設置される都市公園。現在、日本全国に10万箇所以上の都市公園があるが、何十年も前からその仕組みや姿を変えていないという公園も多い。そんな中、日本の公園はどう変わろうとしているのだろうか? そのヒントは欧米の公園にある、と教えてくれたのは、誰もが一緒に遊べる公園の普及をめざす市民グループ『みーんなの公園プロジェクト』の矢藤洋子さん。
「欧米では、どんな子どもでも遊べるユニバーサルデザインの視点を取り入れた公園づくりが広がっています。ユニバーサルデザインとは、1980年代にアメリカのロナルド・メイス博士が提唱した、年齢や性別、文化、言語、障がいの有無などに関わらず、どんな人でも利用できるデザインを指したものですが、特にアメリカは、ADA法(障害を持つアメリカ人法※1)があるため、公園のアクセシビリティが着実に改善され、企業やNPOの協力を得ながらよりよい遊び場づくりが進められています。近年は、欧米だけでなくシンガポールや香港などのアジア諸国でもこういったユニバーサルデザインを採用した、インクルーシブ公園(※2)が増えていますね」(矢藤さん)
日本では2006年にバリアフリー法が施行されて以降、公園にも多機能トイレなどのユニバーサルデザインが取り入れられるようになったが、子どものための遊び場に関しては、残念ながらほぼ手付かずの状態。この現状に、声を上げたのが、留学先のアメリカで出産・育児を経験した東京都議会議員の龍円愛梨さんだ。
「スペシャルニーズのあるお子さんやご家族の中には、公園で遊びたい(遊ばせたい)けど、物理的・心理的バリアを感じるから行きたくないという人も少なくありません。でも、インクルーシブ公園はすべての子どもが歓迎され、親御さんや高齢者がコミュニティに参加するきっかけにもなる。単なる遊び場ではなく、人と人をつなぐ場所として機能する可能性を持っているんです」(龍円さん)
※1 ADA法とは、1990年にアメリカで制定された法律「Americans with Disabilities Act of 1990(障害を持つアメリカ人法)」の通称。障がい者に対するあらゆる差別を排除し、合理的配慮がなされるよう定められている。
※2 インクルーシブとは「包括的な」「包み込む」という意味。エクスクルーシブ(排他的、排除的な)の対義語。インクルーシブ公園は、「inclusive playground」を分かりやすく和訳したもので、すべての子どもが共に仲間として遊ぶことを目的として設計された遊具広場を指す。
では、ユニバーサルデザインを取り入れたインクルーシブ公園とは、実際にどんな公園なのだろうか。『みーんなの公園プロジェクト』では、あらゆる子どもが自分の力をイキイキと発揮しながらさまざまな友だちとともに遊べる場所こそが、ユニバーサルデザインの遊び場だと定義している。その上で大切な点は5つ。
① 誰もが公平にアクセスでき、遊びに参加できる(アクセシビリティ)
② 誰もが自分の好きな遊びを見つけられる(選択肢がある)
③ 誰もが遊びを通して互いに理解を深められる(インクルージョン)
④ 誰もが安心・安全な環境でのびのびと遊べる(安心・安全)
⑤ 誰もがワクワクしながら自らの世界を大きく広げられる(楽しい!)
これらに配慮することで、地域に根差した有意義な公園になるという。
その例をいくつか紹介する。

園路と遊びエリアの境界に段差がなくアクセシブル。エリアごとに舗装の色や素材を変えているので、視覚に障がいのある人でも位置を認識しやすい。

車いすや歩行器のままで砂場の中央まで行けるデッキ。その周囲には車いすに乗ったまま遊べるショベルなど、さまざまな仕掛けが配置されている。日除けの下に自然と子どもたちが集まってくるため、交流が生まれやすい。

多様な人が一緒に楽しめる、ベンチや手すりがついた回転遊具。地面との境界に段差がないため、車いすのまま乗り込むことができる。
地元の芸術家が製作した在来の野生動物のリアルな像。視覚障がいのある子どもも触って楽しめる。傍にあるQRコードをスマホで読み込むと、その動物に関する詳しい情報を得られる。

一人がこぐと、もう一方も一緒に揺れる仕掛けのブランコ。押してあげる人、押してもらう人という関係を生まず、きょうだいや友だち、親子が共に楽しめる工夫がされている。

地域の学生やボランティアによるプレイイベントやミニコンサートなどが開かれるステージ。車いすやベビーカーのユーザーもみんなと並んで座れるようベンチなどの配置を工夫してある。

北村 匡平 (著)
【「コスパ」と「管理」から自由になるために】
「コスパ」「タイパ」という言葉が流行し、職場や教育現場、公共施設や都市でも管理化が進む昨今。
そうした流れは子供たちが遊ぶ「公園」にも押し寄せている。
安全性を理由に撤去される遊具が増え、年齢や利用回数の制限も定着しはじめている。
効率化・管理化は、子供たちの自由な発想や創造性を損なう。そのような状況に抗うには、どうすればよいのか。
そのヒントは「利他」と「場所作り」にあった。東京科学大学の「利他プロジェクト」において、全国の公園と遊具のフィールドワークをしてきた著者が、他者への想像力を養う社会の在り方を考える。
【目次】
序 章 21世紀の遊び場
第一章 利他論――なぜ利他が議論されているのか
第二章 公園論――安全な遊び場
第三章 遊びを工学する――第二さみどり幼稚園
第四章 遊びを創り出す――羽根木プレーパーク
第五章 森で遊びを生み出す――森と畑のようちえん いろは
第六章 遊学論――空間を組み替える
第七章 学びと娯楽の環境
終 章 利他的な場を創る
【著者略歴】
北村匡平 (きたむら きょうへい)
映画研究者/批評家。
東京科学大学リベラルアーツ研究教育院准教授。
1982年山口県生まれ。
東京大学大学院学際情報学府修士課程修了、同大学博士課程単位取得満期退学。
日本学術振興会特別研究員(DC1)を経て、現職。専門は映像文化論、メディア論、表象文化論、社会学。
単著に『椎名林檎論――乱調の音楽』(文藝春秋)、『24フレームの映画学――映像表現を解体する』(晃洋書房)、『美と破壊の女優 京マチ子』(筑摩選書)など多数。
▼厳しい冬を乗り越えてこそ、春には美しい花が咲き薫る。
万事、大変な時こそ、本物の強さが身につくんもである。
▼いよいよの心で自身の壁に挑む、人生の指針の要諦について学ぶことだ。
▼「友情」を大切に育てたい。
自分から周囲に声を元気に明るくかけるのである。
それぞれの地域で地道に信頼と友情を広げ、心を通わせ対話を貫きたい。
▼青春時代の本当の失敗とは、失敗を恐れて挑戦しないことである。
へこたれず、諦めなければ、失敗は栄光に変わる。
▼何事も「押しつけ」では身につかない。
子どもを信頼し、任せてみて、自立芽を育ってくるのを待つことも大事である。