私は、自分のブログにいちいち「こんな映画観ました」なんていう感想文は書きたくないのだが、この映画、正直言って「?」だらけの映画で、ひょっとして私のこれまでの音楽家としてのキャリアそのものを否定する映画(?)とまで思えたのでひとこと。
別に難解な映画だとは思わない。
十分エンタテインメントしている。
でも、見てて全然楽しくないしワクワクもしない。
見終わって「これは絶対に音楽映画なんかじゃない!」と思った。
ネタバレも何も気にせずに言うと(けっこう見た人多いと思うし)、主人公とおぼしき音楽大学の初老の白人教師(ほとんどジャズバンドの指揮者として登場しているが)と彼に指導される(というかイジメ抜かれる)若い白人学生ドラマーの二人でほとんどのストーリーが進行していくのに、いわゆる音楽映画のオチとしてあるべき「音楽への愛」も「音楽に対するリスペクト」もまったく存在しない。
なので、私は最後のエンドロールを見ながら言いようのない「不快感」に襲われていた。
これは、きっと私が音楽家で「音楽を愛している」からに違いない(とそう確信した)。
これまで見たどんな音楽映画( A級だろうがB級だろうが、最低のDランクであっても)にも必ず「音楽による救い」はあった。
しかし、この映画にはそれがまったくない。
それは、この二人の主人公(音楽教師と学生)がまったく音楽を愛していないからに他ならない(と私は結論づけた)。
普通、音楽家である私は、どんな音楽映画を観ても「音楽家で良かったナ」という(ちょっとした)優越感に浸れるのだが、この映画を見終わった後はまったく逆の反応だった。
「音楽家であることが恥ずかしい」ぐらいの暗い気持にさせられてしまったのだ。
軍隊式に学生を鍛えようとする教師の姿は、まさしく軍隊の「鬼教官」そのもの。
私が今現役の学生で目の前にこんな教師がいたとしたら間違いなく私の右手は彼の顔面に飛んでいる(はずだ)。
その後の展開がどうなろうと知ったことじゃない(訴えられようが退学になろうが知ったことではない)。
こんな教師が存在すること自体が我慢ならない。
一方の学生の方も、音楽をスポーツと完全に誤解している(救いようのない)学生で、こちらも音楽に対するリスペクトはゼロ。
普通は、こういう「勘違い野郎」が(映画の中で)どんなにバカなことをやっていても、最後には「こうした態度はすべて間違いでした。やはり、音楽は愛です。音楽にかなうものはありません」的な大団円のオチが用意されているはずなのに、それがどこにもないのだ。
以前、ベートーベンはどうしようもない自己中の男で、ヘタしたら「ストーカー」で訴えられてもおかしくない変態野郎みたいに描かれている映画があったが、それでも最後には「やっぱりベートーベンの音楽は素晴らしい」的な救いがあったのだが、この映画『セッション』にはそんな救いすらない。
見終わって「え?この映画、一体何が言いたいの?」と、もう一度オチを懸命に探したぐらいだ。
ただ、この映画、巷の人気は相当なもの(らしい)。
きっと、音楽家の視点と一般の視点は違うのかナと思っていろいろ検索していたら「あった!あった!」。
音楽家の菊地成孔氏と映画評論家の町山智浩氏がお互いのブログで『セッション』をめぐって大バトルをやっていた。
やはり菊池さんは音楽家の視点からこの映画を酷評している(音楽家がこの映画をホメていたらどうしようと思っていたけれど)。
一方の町山氏は、(別に映画評論家だからではないだろうけど)、この映画をそれなりに評価している。
別に、誰がどう言おうと勝手なので、そのどちらの意見にもケチをつける気はないけれども、菊池さん、何を好き好んでわざわざそこまで言わなくてもと思うぐらいこの映画をボロクソに言っている。
たかが映画にちょっとムキになり過ぎる菊池氏に「ちょっとおとなげないですよ」とは思ったものの、彼の意見にはやはり「音楽愛」ということが根底にあるのだナと思って妙に納得。
そして、音楽をスポーツと一緒にするような風潮(この映画のその部分の描写が病的で納得できない)を煽って欲しくないともマジに思う。
音楽とスポーツの目指すものは根本的に違うはずなのに、それを混同する傾向は世の中にけっこうある。
この映画の主人公2人がドラムをいかに早く叩けるかにこだわるところにそれが象徴されているし、クラシックの世界ではそれがあたかも音楽の目的であるかのように考える人も多い。
スポーツは、オリンピックの理念にあるように「より高く、より早く、より強く」が基本だけれど、音楽の理念はそれとはまったく相容れない。
音楽になければならないものは「愛」。
私は、そのひとことだけで十分だと思っている。
それは、もちろん「人への愛」だし「神への愛」だし、「地球という星への愛」でもよい。
とにかく「愛のない音楽なんて音楽じゃない」と私は信じているし、信じているからこそ「死ぬ、その瞬間まで楽器を演奏していたいナ」と毎日のように念じながら練習を続けている。















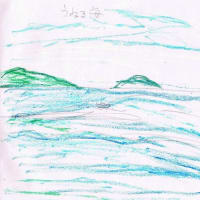


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます