というフレーズは、60年代黒人公民権運動家のマルティン・ルーサー・キング牧師が演説で繰り返し繰り返し使っていたことばだ。
私はこの演説の入ったアナログ・レコードを大学時代に知り合いの牧師さんからいただいてこの演説を暗記するぐらい何度も聞いた。「dream」ということばに敏感に反応したからだ。
イギリスの小説家ルイス・キャロルの有名なお話に『不思議の国のアリス』というのがあるが、この小説の一番最後のページにこんなフレーズが書かれている。
「Life, what is it, but a dream?」。つまり、「夢のない人生なんて何の意味があるのか?」ということばだ。このフレーズにも私はとても敏感に反応して(今現在も反応し続けて)今も「見果てぬ夢」を追い続けている。ある意味、今の私を作ったのはこの2つの「dream」に関するフレーズかもしれない。
昨日たまたまTVにスイッチを入れたら久しぶりにバーブラ・ストレイザンドが写っているのに驚きそのままずっと見入ってしまった。もちろん、地上波ではない。今の地上波に見る値する番組はほとんどないが、BSでやっていたアメリカのアクターズ・スタジオの番組。有名な役者さんたちに映画評論家のジェームズ・リプトンがインタビューするという番組で、この番組を知っている人も多いはずだ。この番組を見るたびに、アメリカには映画文化やきちんとした「文化」が存在しているんだナ実感するのだが、バーブラ・ストレイザンドが登場していたので私は大興奮しながら見ていた。
なにしろ、私が本当のディーバだと思っている歌手は、このバーブラとジャニス・ジョプリン、そしてマリア・カラスしかいないので、この3人に関する番組が少しでもあるとかなり興奮してしまう。
私がこの3人を特別視するのには理由がある。この3人、けっして美声ではない。けっしてきれいな声ではないのに、彼女たちの歌には本当の意味での説得力がある。あまり知られていないがバーブラ・ストレイザンドがクラシックの歌曲ばかりを歌ったアルバムがある。別に企画ものでもないしアレンジものでもない。ひたすら真面目にクラシックの楽曲を歌っている。このアルバム、私の中では本当に最高のアルバムのうちの一つになっている。ジャニスの『パール』とほとんど変わらないぐらいの珠玉の価値を持っている。フォーレの『夢の後に』など、バーブラの歌を聞いた後に、普通のクラシックの歌手の歌っている同じ曲を聞くと、「フォーレを本当に理解しているのはバーブラだけなんじゃないのかナ?」とさえ思えてくる。それぐらい彼女の歌には説得力がある。音楽の説得力というのは、音や技術だけではないということのいい見本かもしれない(ヴィラロボスの名曲『ブラジル風バッハ第5番』のヴォカリーズも、どんなに技巧や声に長けたクラシックの歌手が歌ったものよりもジョン・バエズの歌が最高としか思えないのと同様だ)。
それぐらい、バーブラの歌は素晴らしいし、演技も素晴らしい。シェールにしても、ベット・ミドラーにしても、歌のうまい人は演技もうまい。要は表現力なのだからこれって「当たり前」の話しなのだが、それが「当たり前」のようにできる人はそれほど多くない。
この番組の最後に、ゲーテのことばを引用してバ-ブラが言っていた。
「何かをやろうと決めた時、世界は自分の味方になる」。
人というのは「夢を持ってやり続けなければ」誰も味方につけることはできないのだと、バーブラのことばを聞いて改めて思った次第だ。
私はこの演説の入ったアナログ・レコードを大学時代に知り合いの牧師さんからいただいてこの演説を暗記するぐらい何度も聞いた。「dream」ということばに敏感に反応したからだ。
イギリスの小説家ルイス・キャロルの有名なお話に『不思議の国のアリス』というのがあるが、この小説の一番最後のページにこんなフレーズが書かれている。
「Life, what is it, but a dream?」。つまり、「夢のない人生なんて何の意味があるのか?」ということばだ。このフレーズにも私はとても敏感に反応して(今現在も反応し続けて)今も「見果てぬ夢」を追い続けている。ある意味、今の私を作ったのはこの2つの「dream」に関するフレーズかもしれない。
昨日たまたまTVにスイッチを入れたら久しぶりにバーブラ・ストレイザンドが写っているのに驚きそのままずっと見入ってしまった。もちろん、地上波ではない。今の地上波に見る値する番組はほとんどないが、BSでやっていたアメリカのアクターズ・スタジオの番組。有名な役者さんたちに映画評論家のジェームズ・リプトンがインタビューするという番組で、この番組を知っている人も多いはずだ。この番組を見るたびに、アメリカには映画文化やきちんとした「文化」が存在しているんだナ実感するのだが、バーブラ・ストレイザンドが登場していたので私は大興奮しながら見ていた。
なにしろ、私が本当のディーバだと思っている歌手は、このバーブラとジャニス・ジョプリン、そしてマリア・カラスしかいないので、この3人に関する番組が少しでもあるとかなり興奮してしまう。
私がこの3人を特別視するのには理由がある。この3人、けっして美声ではない。けっしてきれいな声ではないのに、彼女たちの歌には本当の意味での説得力がある。あまり知られていないがバーブラ・ストレイザンドがクラシックの歌曲ばかりを歌ったアルバムがある。別に企画ものでもないしアレンジものでもない。ひたすら真面目にクラシックの楽曲を歌っている。このアルバム、私の中では本当に最高のアルバムのうちの一つになっている。ジャニスの『パール』とほとんど変わらないぐらいの珠玉の価値を持っている。フォーレの『夢の後に』など、バーブラの歌を聞いた後に、普通のクラシックの歌手の歌っている同じ曲を聞くと、「フォーレを本当に理解しているのはバーブラだけなんじゃないのかナ?」とさえ思えてくる。それぐらい彼女の歌には説得力がある。音楽の説得力というのは、音や技術だけではないということのいい見本かもしれない(ヴィラロボスの名曲『ブラジル風バッハ第5番』のヴォカリーズも、どんなに技巧や声に長けたクラシックの歌手が歌ったものよりもジョン・バエズの歌が最高としか思えないのと同様だ)。
それぐらい、バーブラの歌は素晴らしいし、演技も素晴らしい。シェールにしても、ベット・ミドラーにしても、歌のうまい人は演技もうまい。要は表現力なのだからこれって「当たり前」の話しなのだが、それが「当たり前」のようにできる人はそれほど多くない。
この番組の最後に、ゲーテのことばを引用してバ-ブラが言っていた。
「何かをやろうと決めた時、世界は自分の味方になる」。
人というのは「夢を持ってやり続けなければ」誰も味方につけることはできないのだと、バーブラのことばを聞いて改めて思った次第だ。















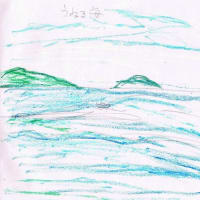


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます