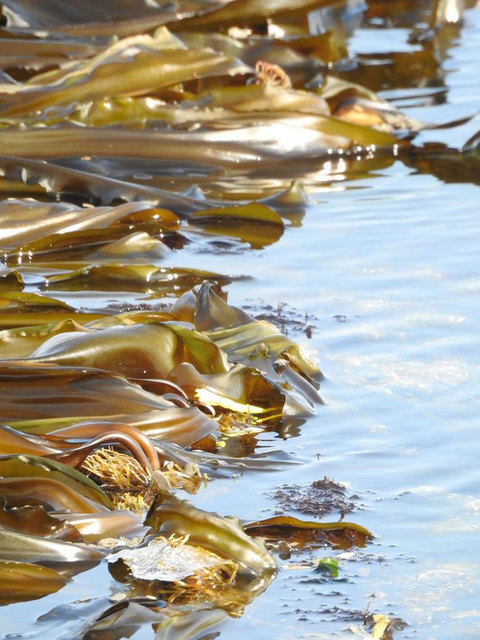色鮮やかなアカアマダイを昆布締めと酒蒸しで味わう至福
スズキ目アマダイ科には、5種がある。最高級とされるシロアマダイと関東にも多いアカアマダイ、数まれなキアマダイが一般に知られるアマダイの仲間だ。
京都では「ぐじ」と呼ばれる。若狭湾から鯖街道を通って運ばれる「若狭ぐじ」は、古くから西京漬けにされて人気がある。アマダイの食文化は関西にあり、関東ではほとんど相手にされない魚だった。
身は水っぽさを感じるほど軟らかいのに、骨が硬い。ぬめるようなウロコも厄介だ。料理が面倒くさくて、パッと食えない。江戸っ子の食いモンは、待っていられないのである。
温暖系の魚たちで、太平洋側では茨城県辺りが北限かもしれない。20年も前になろうか、三浦半島の定置網で50センチ超えのシロアマダイが水揚げされた。当時は買い手がつかず、懇願されるままに安値で持ち帰ったことがある。
関東市場の知名度はそれほど低かったが、今は違う。遊漁船の港には、アマダイ釣りの看板が目立つようになった。そういうところのアマダイとは、アカアマダイのことで、ほかは知らない。
料理屋でもいっぱしのカネを取るようになったが、庶民のスーパーには並ばない。1匹丸ごとでは売れないのだ。
アマダイ料理で嫌われるのはウロコ取りだろう。ぬめりがあって、体はへなへなと軟らかい。力ずくで押さえると、身はつぶれてしまって、上等な刺し身にはならないのだ。
尾の方向から表皮を残して、ウロコだけをそぎ切っていく。難しくはない。家庭に刺し身包丁があると便利だ。面倒ならば出刃包丁で、ゆっくり丁寧にウロコをそぎ切ろう。
腹を開いたら、内臓を取り出して水洗いする。頭部は大きく落として、酒蒸しだ。塩で再度揉み洗いして、酒をふる。好みで青菜などを添えて、蒸し上げる。
胴部の三枚おろしは、基本通り。腹骨と血合い骨を切り取った4本のサクは、昆布で半日ほど締めてから刺し身にする。
丸みを帯びた顔つきで、一目でアマダイとわかる。
背ビレや尾ビレなどを広げると、色彩の美しさに見とれてしまう。水深100メートルもの暗闇にいて、着飾る意味はどこにあるのか。
昆布締めの刺し身と、酒蒸しをサカナに酒を飲む。至福の時間だ。
(YouTubeの日刊ゲンダイ公式サイトにある「魚の伝道師・西潟正人LIVE 俺の魚を喰ってみな!」では、いろいろな魚の捌き方動画がライブラリーになっています。新着動画は毎週火曜正午に公開)