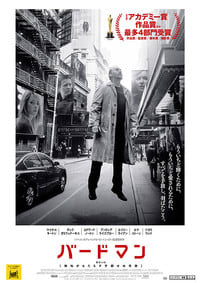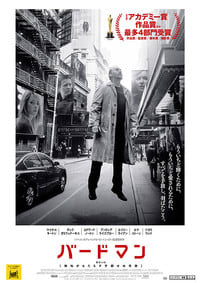
長まわし映像の信仰に、私は疑問を持っている。
キャメラを延々とまわすだけで面白い映像が撮れると考える馬鹿は論外だが、役者の出し入れや台詞のタイミングなどの精緻な計算を過大評価するのも考えものだと思う。
そこで止まると、映画は数学を超えられなくなる。
注意すべき要素はまだある。
シフトチェンジだ。
マニュアルシフトの車では、こまめなギアチェンジが求められる。
カーブの多い道や高低差のある土地ではなおのことそうだ。
長まわしにもシフトチェンジが要る。
「バードマン」のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督は、さすがにそこを見落としていない。
まず彼は刃の切っ先を定めた。
怠惰で貪欲なブロックバスター映画、ショービズ界の自意識過剰、役者たちの肥大したエゴ……
これら3つを串刺しにした上で、主人公の「長い悪夢」を映像化しようと企てたのだ。
そこで彼は工夫を凝らす。
最初は、曲者俳優をそろえたことだ。
リーガンに扮したマイケル・キートンの傍らにはエドワード・ノートンとエマ・ストーン(3人ともスーパーヒーロー映画に出演した過去がある)を配し、その外周にナオミ・ワッツ、ザック・ガリフィアナキス、アンドレア・ライズボローといった渋い脇役を集めたのだ。
劇場の舞台裏という狭い空間に彼らが出没するだけでも、映像は変化球のように曲がったり落ちたりする。
もうひとつの工夫は、キャメラに鳥の動きと水の動きを取り入れたことだ。
リーガンの別自我がバードマンなのだから、これは必然のなりゆきだったか。
この手法は狭い空間と広い空間のコントラストを生かせるし、悪夢特有の幻想性や非連続性も獲得できる。
というわけで、「バードマン」は眼と耳を刺激してくれる悪夢映画になった。
惜しむらくは、黒い笑いの量がやや足りなかったことだが、これはないものねだりだろう。
長まわしの映像ばかりに眼を取られず、役者の投げる変化球や、針の穴を通すようなイニャリトゥの制球力にも注目していただきたい。






 初めてでも、酔った振りして隣のオッチャンとの会話を楽しまなきゃね。
初めてでも、酔った振りして隣のオッチャンとの会話を楽しまなきゃね。