◎主人の不在中に珍しい食物を作るのは不貞
『社会経済史学』第3巻第9号(1934年1月)から、柳田國男による講演の記録「餅と臼と擂鉢」を紹介している。本日は、その八回目(最後)。
八
晴の食物の調整が簡便になつたことは、是と常の日の食事との境が、不明になつて来た大なる原因では有るが、原因は勿論是だけでは無かつた。話が長くなり過ぎたから其分は他日を期し、こゝには唯その要点のみを附加へ〈ツケクワエ〉て置くが、元来食物の晴といふものは、最初からまだ他にもあつたのである。今まで述べて来た節供〈セチク〉がその一つで、是は家々の中で神霊と人との共にするものであるが、尚その以外に家と家との共同に成る酒盛りといふものがあり、是も村限りの内で行ふものと、他所から来た人々との間に行ふものとの二種があつた。村限りの会食も時期が定まつて居て上代には是をニヘと謂つて居たやうである。現在も近畿以西に弘く行はれて居るメオイといふ語は、其ニヘといふ語の変化かと思はれる。誰が亭主といふことも無く、会衆が均等に入用を分担するのを例として居る。後者は之に比べると起りは新しいのだが、今まで親しみの無かつた此処の人たちと、先づ共同の飲食に由つて、心身の連鎖を附ける趣意で、必要は却つて此方が大きかつた。中世の武家移動以来、優れた異郷人の訪問が田舎にも多くなり、是に次いで集落外の婚姻が起つて、其為の酒盛りは将に盛大とならざるを得なかつた。旅人が駅や港に来て酒を飲んだのも、やはり多くは短期の婚姻の為であつて、濫用には相違ないが是も亦一つの晴であつた。酒盛りには必ず肴〈サカナ〉を伴なうた。歌や舞なども御肴と謂つて居たが、其以外にも特に技芸を加へた食物を肴にしたので、料理は専ら是に由つて発達した。簡素を生命とした茶湯〈チャノユ〉の席でも、客は客だから其食品を精撰しなければならなかつた。殊に珍らしい賓客に対しては、ヒノトリモチと称して是非暖かいものを食はせなければならなかつた。吸物あつ物を膳の上に添へることが、欵待〈カンタイ〉のしるしとなつたのも其結果で、他の民族でも同じことかと思ふが、日本の食物が近世に入つて、次第に温かいもの又は汁気のものを多くしたのも、誘因は斯ういふ接客法に在つた。家に火処がたつた一つであつた時代には、是は決して容易の業〈ワザ〉で無かつた。それ故に火の取持ちが優遇を意味し、一方には又次第に私たちの謂ふ火の分裂を引起したのである。建築技術の進歩も亦之を促して居る。住居の変化の主要なるものは、一つには来客が頻々となって、其為に毎回仮屋を建てることが出来ず、出来るだけ主屋〈オモヤ〉と合併したことである。所謂出居〈デイ〉は拡張せられて客座敷といふものが出来た。それから紙の利用が自由になつて、明り障子や唐紙〈カラカミ〉の間仕切〈マジキリ〉が出来、家の中の区画が立つて食物は漸く統一を失つた。即ち常の日の共同の飲食が、次第に主人子女のもの居間の食事となり、小鍋立て〈コナベタテ〉の風を誘ふに至つた。晴の日の食事の簡単なものを、いつでも食ひたい時に製して食へるやうに、小鍋とか火鉢とかいふものが普及したのである。白川楽翁〔松平定信〕の女教訓書を見ると、まだあの頃までは小鍋好みは悪徳であつた。ルスゴトと称して主人の不在中に、珍らしい食物をこしらへることは不貞であつた。それが久しからずして公然と是を褻【け】に混じてしまつたのである。此点は男でいふならば酒や歌舞の楽しみ、女でいふと紅白粉の飾りも同じことで、本来は何れも年に一度か二度の、晴の日のみに許されることであつたのを、自由に任せて毎日の如く之を受用し、結局は節や祭の期日の印象を微弱ならしめたのである。
しかも此自由を富や権力の乏しい常民にまで付与したのは、全く外部社会の力であつた。煮売屋〈ニウリヤ〉即ち飲食店の出現はその一つである。所謂店屋物【てんやもの】の主たるものは餅と団子、一方には亦粗末ながら酒の肴であつた。何れも起りは道中の茶屋からで、是は旅から来た異郷人の、接待だから即ち晴であつたのが、漸次に附近村落の平常生活に持込まれたのである。其傾向の歎ずべきものであるか否かを、判定する迄は我々の任務で無い。我々はたゞ現在の日常生活が、斯うした急激の変遷の結果であることを知れば即ち足るのである。家が日本人の生活の単位であつた時代は過ぎた。さうしてこの食物の個人主義を、促したものは雑餉〈ザッショウ〉即ち弁当であつた。村の労働者がヒルマ・コビルマも食ふ習慣は相応に古いと思ふが其頃から、既に今日の変革は萠し〈キザシ〉て居たのである。〈20~24ページ〉
『社会経済史学』第3巻第9号(1934年1月)から、柳田國男による講演の記録「餅と臼と擂鉢」を紹介している。本日は、その八回目(最後)。
八
晴の食物の調整が簡便になつたことは、是と常の日の食事との境が、不明になつて来た大なる原因では有るが、原因は勿論是だけでは無かつた。話が長くなり過ぎたから其分は他日を期し、こゝには唯その要点のみを附加へ〈ツケクワエ〉て置くが、元来食物の晴といふものは、最初からまだ他にもあつたのである。今まで述べて来た節供〈セチク〉がその一つで、是は家々の中で神霊と人との共にするものであるが、尚その以外に家と家との共同に成る酒盛りといふものがあり、是も村限りの内で行ふものと、他所から来た人々との間に行ふものとの二種があつた。村限りの会食も時期が定まつて居て上代には是をニヘと謂つて居たやうである。現在も近畿以西に弘く行はれて居るメオイといふ語は、其ニヘといふ語の変化かと思はれる。誰が亭主といふことも無く、会衆が均等に入用を分担するのを例として居る。後者は之に比べると起りは新しいのだが、今まで親しみの無かつた此処の人たちと、先づ共同の飲食に由つて、心身の連鎖を附ける趣意で、必要は却つて此方が大きかつた。中世の武家移動以来、優れた異郷人の訪問が田舎にも多くなり、是に次いで集落外の婚姻が起つて、其為の酒盛りは将に盛大とならざるを得なかつた。旅人が駅や港に来て酒を飲んだのも、やはり多くは短期の婚姻の為であつて、濫用には相違ないが是も亦一つの晴であつた。酒盛りには必ず肴〈サカナ〉を伴なうた。歌や舞なども御肴と謂つて居たが、其以外にも特に技芸を加へた食物を肴にしたので、料理は専ら是に由つて発達した。簡素を生命とした茶湯〈チャノユ〉の席でも、客は客だから其食品を精撰しなければならなかつた。殊に珍らしい賓客に対しては、ヒノトリモチと称して是非暖かいものを食はせなければならなかつた。吸物あつ物を膳の上に添へることが、欵待〈カンタイ〉のしるしとなつたのも其結果で、他の民族でも同じことかと思ふが、日本の食物が近世に入つて、次第に温かいもの又は汁気のものを多くしたのも、誘因は斯ういふ接客法に在つた。家に火処がたつた一つであつた時代には、是は決して容易の業〈ワザ〉で無かつた。それ故に火の取持ちが優遇を意味し、一方には又次第に私たちの謂ふ火の分裂を引起したのである。建築技術の進歩も亦之を促して居る。住居の変化の主要なるものは、一つには来客が頻々となって、其為に毎回仮屋を建てることが出来ず、出来るだけ主屋〈オモヤ〉と合併したことである。所謂出居〈デイ〉は拡張せられて客座敷といふものが出来た。それから紙の利用が自由になつて、明り障子や唐紙〈カラカミ〉の間仕切〈マジキリ〉が出来、家の中の区画が立つて食物は漸く統一を失つた。即ち常の日の共同の飲食が、次第に主人子女のもの居間の食事となり、小鍋立て〈コナベタテ〉の風を誘ふに至つた。晴の日の食事の簡単なものを、いつでも食ひたい時に製して食へるやうに、小鍋とか火鉢とかいふものが普及したのである。白川楽翁〔松平定信〕の女教訓書を見ると、まだあの頃までは小鍋好みは悪徳であつた。ルスゴトと称して主人の不在中に、珍らしい食物をこしらへることは不貞であつた。それが久しからずして公然と是を褻【け】に混じてしまつたのである。此点は男でいふならば酒や歌舞の楽しみ、女でいふと紅白粉の飾りも同じことで、本来は何れも年に一度か二度の、晴の日のみに許されることであつたのを、自由に任せて毎日の如く之を受用し、結局は節や祭の期日の印象を微弱ならしめたのである。
しかも此自由を富や権力の乏しい常民にまで付与したのは、全く外部社会の力であつた。煮売屋〈ニウリヤ〉即ち飲食店の出現はその一つである。所謂店屋物【てんやもの】の主たるものは餅と団子、一方には亦粗末ながら酒の肴であつた。何れも起りは道中の茶屋からで、是は旅から来た異郷人の、接待だから即ち晴であつたのが、漸次に附近村落の平常生活に持込まれたのである。其傾向の歎ずべきものであるか否かを、判定する迄は我々の任務で無い。我々はたゞ現在の日常生活が、斯うした急激の変遷の結果であることを知れば即ち足るのである。家が日本人の生活の単位であつた時代は過ぎた。さうしてこの食物の個人主義を、促したものは雑餉〈ザッショウ〉即ち弁当であつた。村の労働者がヒルマ・コビルマも食ふ習慣は相応に古いと思ふが其頃から、既に今日の変革は萠し〈キザシ〉て居たのである。〈20~24ページ〉
*このブログの人気記事 2025・1・8(1・3位になぜか椋鳩十、10位になぜか前進座)
- 椋鳩十の『鷲の唄』、風俗壊乱で発禁(1933)
- 手杵とは、女性が使うタテの杵のこと
- 椋鳩十、『山窩調』について語る
- 宮城県のオシトネは新米の粉を水で固めたもの
- 柳田國男の講演記録「餅と臼と擂鉢」を読む
- 近畿の諸県でいうケンズイは間食の呉音
- 吉事の支度には三本杵が用ゐられた
- 志摩の姉らは何食て肥える
- 東北では正月、カラスに神供を投げ与へる
- 前進座、「歌舞伎王国」で旗あげ(1936)



















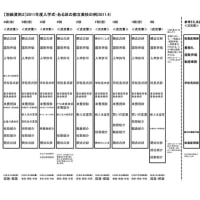








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます