今日の新聞に死生学の先生とやらが投稿していました。
その中の一文が気になりました。
なんでも、中学生の15%が「人は死んでも生き返る」と思っているらしく、
それはテレビゲームの悪影響なのだと・・・。
なんでいつもこうゲームは悪者にされるのかねぇ。
仮にゲームの影響で命の認識が歪んできているとしても、それが全てではないはず。
ゲームを悪者にする人は、なぜ他の可能性を考慮しないのか疑問でなりません。
僕がゲーム愛好家だからゲームを擁護するのもあるけれど、
根拠のないことをさもそれがゆるぎない真実であるがごとく掲げることに、まず反発を覚えます。
せめて統計をとってからそういう主張はしてほしいもの。
ただ、僕自身も一部のゲーマーの感覚が怖いと思うことがあります。
だから、そういう主張に一定の理解を示すこともできます。
例えば、僕が好きなモンスターファームは育成ゲームで、
寿命が設定されたモンスターを鍛えて強くするというものなんですが、
一部のマニアは、ゲーム内で育てているモンスターに「愛」を感じると言うんです。
(一部ですよ?)
僕にはどうしてもそれが解せないんですよね。
愛着が湧くことがあっても、それは愛とは全く異なるもの。
だって対象は生物ですらない、単なるデータ。
所詮ゲームはゲーム。
それが擬している物と本物は全く異なり、
神秘的な「生」がゲームに摸倣しきれるはずもない。
逆に両者が絶対的に違うからこそ、ゲームを楽しめる面も強いです。
普通、そうじゃありませんかね・・・?
ゲームの魅力はその非現実性じゃないんでしょうか。
僕はそう思っているから、彼らの感覚が不思議でなりません。
「寿命」を終えて「死ぬ」モンスターに彼らは涙を流せると言うのだろうか・・・。
死んだらリロードして、死ぬ前に戻せてしまうようなゲームにおいて。
よく言われる「仮想世界と現実世界の区別がつかなくなっている」というやつなんでしょう。
むしろ僕には仮想を現実として捉えたいという願望があるように思えるけれど・・・
データに本物の「愛」を感じるゲーマーは、
最初に紹介した論者の主張にどう反駁するのか、興味がありますね。
僕からすればその感覚からかなり危ういものだと思っています。
mixi上じゃやりにくいけど、1回本気で喧嘩してみたい
たまごっちの開発者も、
一度死んだらもう再び育てることは出来ない仕様にしたかったらしいです。
さすがにそれじゃおもちゃにならないと言うので却下されたそうですが。
僕にはその発想自体がちょっと分かりません。
・・・ドットに生を見出せと?
社会全体が仮想と現実の境界を曖昧にする方向に進んでいると思います。
一人一人の認識が確実に変わってきていると。
ゲームが原因で子供の命への認識が歪んできたのは違うと思うんです。
最初にあったのはそういう社会の流れ。
その流れを汲んで「死者も生き返る」ゲームができ、
それは現代人の感覚にあったからあっという間に浸透した。
あくまでも先にあったのは、社会の大きな流れのほうだと思います。
(ただし、ポジティブ・フィードバック的な作用で、
ゲームがその流れを加速させている可能性も否定は出来ませんが・・・)
そして、この社会の流れは、色々な要素が絡み合っていた結果。
例えば・・・と書き出すと長くなりそうなのでやめておきますが
色々考えられそうじゃありませんか?
可能性の話ならいくらでもできますしね。
僕の考え方は冷たいかもしれません。だけど、譲れません。
AIがどんどん進歩して行って「人格」を持つようになったとき、
僕のような古い人間はきっと生き方を見失うんだろうな(笑
・・・と思ったけど、現時点でもう「生」の定義なんてかなり曖昧なものですね。
既に僕は道に迷っているんだろう・・・。
その中の一文が気になりました。
なんでも、中学生の15%が「人は死んでも生き返る」と思っているらしく、
それはテレビゲームの悪影響なのだと・・・。
なんでいつもこうゲームは悪者にされるのかねぇ。
仮にゲームの影響で命の認識が歪んできているとしても、それが全てではないはず。
ゲームを悪者にする人は、なぜ他の可能性を考慮しないのか疑問でなりません。
僕がゲーム愛好家だからゲームを擁護するのもあるけれど、
根拠のないことをさもそれがゆるぎない真実であるがごとく掲げることに、まず反発を覚えます。
せめて統計をとってからそういう主張はしてほしいもの。
ただ、僕自身も一部のゲーマーの感覚が怖いと思うことがあります。
だから、そういう主張に一定の理解を示すこともできます。
例えば、僕が好きなモンスターファームは育成ゲームで、
寿命が設定されたモンスターを鍛えて強くするというものなんですが、
一部のマニアは、ゲーム内で育てているモンスターに「愛」を感じると言うんです。
(一部ですよ?)
僕にはどうしてもそれが解せないんですよね。
愛着が湧くことがあっても、それは愛とは全く異なるもの。
だって対象は生物ですらない、単なるデータ。
所詮ゲームはゲーム。
それが擬している物と本物は全く異なり、
神秘的な「生」がゲームに摸倣しきれるはずもない。
逆に両者が絶対的に違うからこそ、ゲームを楽しめる面も強いです。
普通、そうじゃありませんかね・・・?
ゲームの魅力はその非現実性じゃないんでしょうか。
僕はそう思っているから、彼らの感覚が不思議でなりません。
「寿命」を終えて「死ぬ」モンスターに彼らは涙を流せると言うのだろうか・・・。
死んだらリロードして、死ぬ前に戻せてしまうようなゲームにおいて。
よく言われる「仮想世界と現実世界の区別がつかなくなっている」というやつなんでしょう。
むしろ僕には仮想を現実として捉えたいという願望があるように思えるけれど・・・
データに本物の「愛」を感じるゲーマーは、
最初に紹介した論者の主張にどう反駁するのか、興味がありますね。
僕からすればその感覚からかなり危ういものだと思っています。
たまごっちの開発者も、
一度死んだらもう再び育てることは出来ない仕様にしたかったらしいです。
さすがにそれじゃおもちゃにならないと言うので却下されたそうですが。
僕にはその発想自体がちょっと分かりません。
・・・ドットに生を見出せと?
社会全体が仮想と現実の境界を曖昧にする方向に進んでいると思います。
一人一人の認識が確実に変わってきていると。
ゲームが原因で子供の命への認識が歪んできたのは違うと思うんです。
最初にあったのはそういう社会の流れ。
その流れを汲んで「死者も生き返る」ゲームができ、
それは現代人の感覚にあったからあっという間に浸透した。
あくまでも先にあったのは、社会の大きな流れのほうだと思います。
(ただし、ポジティブ・フィードバック的な作用で、
ゲームがその流れを加速させている可能性も否定は出来ませんが・・・)
そして、この社会の流れは、色々な要素が絡み合っていた結果。
例えば・・・と書き出すと長くなりそうなのでやめておきますが
色々考えられそうじゃありませんか?
可能性の話ならいくらでもできますしね。
僕の考え方は冷たいかもしれません。だけど、譲れません。
AIがどんどん進歩して行って「人格」を持つようになったとき、
僕のような古い人間はきっと生き方を見失うんだろうな(笑
・・・と思ったけど、現時点でもう「生」の定義なんてかなり曖昧なものですね。
既に僕は道に迷っているんだろう・・・。












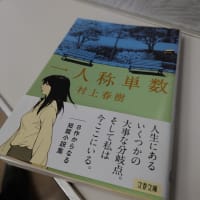






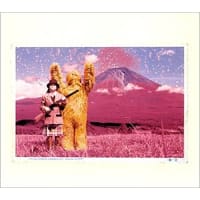
とっても典型的なゲームに愛を持ってる者です
ゲームに愛を持ってないものは、二次を三次(リアル)に昇華できてない愚か者だと思います
確かにゲームはデータです。しかし、そのデータは俺達人間により必ず脳の中で補完されるわけだ
つまり、データは人それぞれにより修飾され
世界で唯一無二の『データ』になるわけで
それはリアルに存在する個と同義といってよくなかろうか?
ちなみにゲーム脳の子供が死んでもリセット理論は違います
なぜなら私は一歳半からゲームしてますが、そんなこと一歳思ったことありません
そもそもゲームは最近の子供の時代だけでなく、もっと以前からあったわけですからね
原因は子供というよりも、最近のバカな親にあると思いますがねwww
あるいは、子供の頃遊んだぬいぐるみを大事にするのも、何も知らぬ人から見れば滑稽かもしれない。
もちろんそこに愛着を感じるのは、大事にする人間の一方的な思いでしかありません。
でも、好きになってしまうことに理由なんて付けられない、それが人間だと思います。
確かに戻すことはできるけど、もう満足に戦うことも育てることもできないじゃまいか
アイマスは似たようなゲームなんだけど、俺は好きすぎてプレイできないんだぜwww
色覚異常でボタン押しミスりまくるんだけど、やり直しに対する罪悪感が強すぎてw
>・・・ドットに生を見出せと?
語弊をおそれず言えば、音楽なんてのは
人為的に仕組まれたタイミングで音を鳴らすだけのゲームじゃないか
歌詞だって小説だってただの文字列だ
今のコンピュータ上ではただの0か1のビット列でしかない
それでも人はそれに意味を見出したり何か感じたりできる
ドットに否定されるならこれらも悉く否定されるべきだろ
死んでも生き返るのはアレだ
その思想に問題があるなら仏教の人と論争してくれればいい
ちょっと違う話だけど、少年犯罪や性犯罪でもゲームやアニメはやり玉にあがるよね
でも現実には急増どころか減っていたりするわけで
http://kodomo.s58.xrea.com/grape.htm
反駁の前に「仮説」の証明をしてもらうべきだろう
端的な説明でいうなら人間は感動したいから
哲学的(?)に言うなら精神的に強い衝撃を受けたいから
欲しい答えを言うならその感動が商売として効率がいいため
(死んでも生き返るのはその中の一つ、ちなみに一番効率がいいのは『愛』)
>仮想と現実の境界を曖昧にする方向
これはその方が金を多くつぎ込むから
つまり悪いのは社会の商業主義なのだ!!(笑)
本気で悩むならかつおさんの言うように仏教でも勉強してくればいい
個人的にはドストエフスキー読むかミシェルフーコの本でも読むといい
>K2
RPGで感動することは大いにあっていいと思うよ。
それで感動するのは小説やドラマ、演劇で感動するのとなんら変わらないだろう。
ただし、RPGでは「蘇生」系のアイテムやアビリティが問題視されると思う。
ゲームでは「死んだ」人を簡単に「生き返らせる」ことができる。
他のフィクションと決定的に違うのはそこだろう。
命の重みがそこでは大きく違っている。
もし小説やドラマでゲームと同じ頻度で人が死んでしまっていたら、命をもって涙をさそうことができるはずもない。
いやらしい表現をすれば、なかなか死なないからこそ死んで涙を誘う演出が可能なはずだ。
ゲーム中での「戦闘不能」は「死」とは全く違うって反論もあるだろうが、
一般にあの状態を「死んだ」というわけだから
その反論はいかがなものかなと思う。
ゲームを問題視する人たちの非難の矛先にあるのはそこなわけで。
>Takemiya
ぇ・・・どういうことだろう?
まぁ色々な考え方があるんだろうけど・・・。
>ごる
それは違うな。
楽器に対する愛着はどこまで言っても愛着に過ぎない。
楽器に大して生身の人間に対する感情と同じ感情を抱けるか?
例えば、楽器に告白したい・・・と本気で考えるか?
子供のぬいぐるみ似たする感情も然り。
現実と非現実の区別がきちんとつかない子供だからこそ、ぬいぐるみを生き物として扱うことができ、それは周りにも許容される。
年齢を経ても現実と非現実の区別、生物と非生物の区別がつかなかったらそれは問題だろう。
僕は愛着と愛を厳密に区別して考えている。
記事で問題提示したかったのは、明らかな非生物を生物として捉えることの危うさなんだ。
>確かに戻すことはできるけど、もう満足に戦うことも育てることもできない
「生」に対する考え方がお前と僕では大きく違うみたいだ。
満足に戦えなくてもこれ以上の成長がなくても、生きているというだけで十分に価値があることなんだぜ?
やり直しをしないという主義は別に問題ないと思う。
どういう意味で罪悪感を感じるのかまでは、そのゲームやってないから分からんが・・・。
それからドット自体を否定しているわけじゃない。
そんなの人間が炭素や水素から出来ているなんて気持ち悪いって言い始めているようなものじゃないか(笑
音楽や小説で人が感動することも否定しないよ。
大いにありうることだし、僕も感動する。
僕が問題だと思ったのは、それを「生き物」であるかのような扱いをしていることだ。
それは生き物じゃないのに、まるで生き物であるかのようにみんな考えている。
それはゲームの中での死と現実における死を混同してしまうことにつながっているんじゃないかと思うんだ。
ゲームの中での「死」と現実の「死」は全く違う。
僕が強調したいのはそこ。
生き返る思想が問題だなんて言ってないよ・・・揚げ足を取りしないでくれ。
命を軽視する風潮があるって言う点を問題視しているんであって。
少年犯罪は減っているのか。それは初めて知ったな。
一方で、グランドセフトオートなんかを見て犯罪起こしたって例が実際に見られるわけだ。
とすれば減っている少年犯罪の中で、明らかにゲームが誘発した少年犯罪の割合は高まっていることにならないか。
数字なんて使いよう。
可能性があるならば、それを考慮に入れる柔軟な視点を持つことが大切だと思うんだ。
>ポメさん
僕が小説などを否定していないことはもう繰り返しになるのでやめておきます。
この社会の流れの背景に商業主義があるというのは自分は考え付きませんでした。
確かにそうなんでしょうね・・・
仏教に興味はあります。
軽く勉強してみたいとは思っているんですが、本業のほうがやばすぎて今その余裕が・・・
ドストエフスキーは罪と罰を何度か読んだことがあって、最近はカラマーゾフを2回読み終わったところです。
あれ、色んな思想に満ちていて、面白いですよね。
ミシェルフーコと言う人は初めて聞きました。
色々読んでみたい気持ちはあるんですが、本業が・・・あぁ。
だから死が頻繁に出てくるゲームになれてしまうと、現実世界での命の重みも薄れてくる。
そのため、ゲームによって命が軽視される思想が広まるのも否定しきれない。
ただし、小説やドラマなどの世界で命を演出に使うこと自体は悪くないと思う。
俺はドラマの狙ったかのような死は嫌いだな
とくに病死
人が一人死ぬだけで中身の無い話にも感動する人の気持ちがわからん
そういえば昔ゲームで
HPが0になると気絶で
その状態でダメージくらい続けると本当に死んで生き返らせれなくなる神ゲーがありました
俺の結論
ゲームはゲームと割り切れwww
ゲームとリアルを混在させるのはゲームのせいじゃない
させるやつがバカ
俺は死の概念より
宿屋に泊まる時パーティーは、どうなってるかのほうが気になる
ベッドが明らかに足りてない時とかさ
ゲーム内の矛盾をつつき始めたらきりがないだろ?
それはしないお約束だと思う。