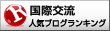国慶節休暇2日目の朝、キャンパスを出て菏澤市博物館へ向かいました。
下は脇門の一つですが、提灯が祝日の雰囲気を醸す他は割と静かな大学周辺です。
多くの学生たちは、家に帰るか旅行に行くかして大学にはそんなに人がいないのです。

行ってらっしゃいと送ってくれるかのような門前の犬。
目が優しいと言うか弱弱しいと言うか……。

大学前からバスに乗って待ち合わせのバスターミナル北門に到着。
菏澤市中心街の一角です。

菏澤に来て初めて、日本語の看板を発見しました。

今回、博物館を案内してくれる二人は卒業生の楊芬さんと、
ボーイフレンドの高さんです。
二人は高校の同級生で、地元菏澤出身。
楊芬さんは菏澤に属する県で就職し、高さんは陝西省西安の大学院に進みました。
せっかくの国慶節なのに、
楊さんに付き合って見ず知らずの私の案内をしてくれる高さん、
こういうのが菏澤気質というのでしょうか。
菏澤は人情が厚い土地柄だとよく言われるのです。
若い二人もその気質をしっかり受け継いでいるようです。

この博物館の目玉は元朝時代の船(実物)なんですって。
博物館好きの楊さんはもう、3回も見たそうです。
とにかく大きい船です。
下の写真は船体の左半分。
真ん中あたりに階段があって、船の中を覗き見ることができます。

階段に上って撮った写真がこれ。
右半分の船体です。中には何百人くらい乗れるのかなあ。
当時の造船技術の最先端を行くものだったそうです。

「なぜ、菏澤にこんなでかい船が?」と聞くと、
菏澤は当時おおきい湖のようなものがあったらしいのです。
黄河とつながっていたのでしょうか。
また、調べなければなりません。
ところで、
今回の菏澤市博物館見学で、この名前を見て興奮しましたよ。

「黄巣の乱」の黄巣です。
唐朝末期の農民の大反乱のリーダーだった黄巣は、
現在の菏澤の西南出身だったんですって。
高校の世界史で中国の歴史は「一世一乱」があると学び、また、
農民が時の権力に対していく度も決起したことを知ると、
(日本とは大違いだなあ)と憧れに似た感想を持ったものでした。
日本にも応仁の乱当時の山城国一揆、室町から戦国時代の加賀一向一揆などをはじめ
農民一揆が多くあったことを知ったのは翌年日本史を学んでのことでした。
やっぱり高校の世界史、日本史は重要です。
今、受験に関係ないからという理由で歴史を教えない高校があると聞き、
その高校は馬鹿を作る教育を目指しているんだなとナットクしました。
(続く)