http://digital.asahi.com/articles/DA3S11759535.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11759535
創業者たちの言葉
静かなひと言が、計画を白紙に戻した。
1980年秋。日差しが照りつけ、暑い夏のような日だった。大阪府門真市の松下電器産業(現・パナソニック)本社の一角にある無線研究所に、社外デザイナーの中禰兼治(なかねけんじ)(64)はいた。広い会議室で、極秘に開発した「パソコン」の説明会が始まろうとしていた。
机の上には、中禰が手がけた試作機。銀色の四角い本体が三段重ねに積まれ、ブラウン管を備えたモニター画面とつながれていた。B5判サイズの「タブレット」もついていた。専用の電子ペンで画面に文字や図形を描くと、パソコンのモニター画面に表示できた。当時としては斬新な機能だった。
松下幸之助が部屋にやってくると、室内は水を打ったように静まりかえった。相談役に退いてはいたものの、新製品を世に出すには「創業者の了承」が必須だった。
研究所幹部の説明を聞きながら、幸之助は自らキーボードに触れて操作を確かめる。終盤にさしかかったときだった。幸之助は説明をさえぎるように言った。「わかった。けど、うちはパソコンはせえへんで」。そして、部屋を後にした。
■アップルは着々
パソコンブームの前夜だった。米国では、スティーブ・ジョブズが自宅のガレージでパソコンを作り、アップル社を起こしていた。頭脳となる半導体の性能の向上はめざましかった。仕事に、遊びに、パソコンの時代が始まろうとしていた。
松下電器は、創業以来、幸之助の「目利き」が成長の支えになってきた。その代表例が、家庭用ビデオだった。ベータとVHS。どちらの規格を選ぶかが運命の分かれ目だった。日本ビクターが独自に開発したVHSを松下電器は選んだ。ビデオ事業部長だった谷井昭雄(87)は、「社内の反発もあったが、創業者が押し切って採用したことがすべてだった」と言う。
しかし、コンピューターの分野で幸之助の「目利き」は発揮されなかった。
幸之助が大型コンピューター事業からの撤退を宣言したのが、64年。開発に資金がかかりすぎる、というのが理由だった。電機メーカー各社が次々とパソコン事業に本腰を入れるようになっても、松下では、グループ会社による参入にとどまっていた。
中禰は「幸之助さんには、コンピューターの未来が見えていなかったのかもしれない」と話す。家電の覇者は、80年代のパソコンブームの中では埋没し、ヒット商品「レッツノート」が生まれたのは、幸之助の死から7年後だった。
■そしてソニーも
戦後の焼け野原から、いくつもの企業が生まれ、復活してきた。中でも、松下と並ぶ家電の雄のソニーは、特別な存在だった。
「モルモット」――。評論家の大宅壮一は58年、「週刊朝日」の記事で、ソニーを実験用の動物に例えた。新しい製品に挑戦するが、成果を他社に奪われることも少なくない状況を皮肉った。
トランジスタラジオ、高画質の「トリニトロンテレビ」、ウォークマン。ソニーからは、世界をあっと言わせた製品がいくつも飛び出した。大宅の物言いに、当初は反発していたソニー創業者の井深大だが、後の社内報では「決まった仕事を決まったようにやるのは時代遅れ。モルモット精神もまた良きかな」と受け入れた。松下電器はというと、模倣して売るのがうまいとして「マネシタ」と呼ばれた。
ソニーのモルモット精神を支えていたのは、数多くの異能の技術者たちだった。奇抜な発想を実現すべく、しのぎを削っていた。それを良しとする社風がソニーにはあった。
しかし、それも、いつのころからか、変わっていったようだ。
「上からダメだと言われたんですよ」。副社長を最後にソニーを去った大曽根幸三(81)は、現役の技術者が悔しそうに言ったのを覚えている。
2000年代、米アップルの「iPod」に押されて、ドル箱のウォークマンの販売はどんどん落ちていった。iPodはテープやCDを使わず、パソコンから音楽をダウンロードして聴く新方式。実はソニーも99年末には先行して商品化していた。だが、ソニーのやり方は「使いにくい」と評判が悪かった。音楽会社を子会社に持つことから、上層部は使い勝手よりも著作権の保護を優先したようだ。
大曽根は言う。「誰がなんと言おうと、自分が使ってみたい、欲しい、と思うものをつくる。そのための技術であり、その結果がイノベーションなんだ」
経済学者のシュンペーターが唱えた「イノベーション」は、技術的な革新にとどまらず、世の中に普及する新しい概念を広く指す。しかし、戦後の日本では、専ら「技術革新」と訳された。その言葉の下、欧米から新しい技術を取り入れていった。
しかし、いちばん大事なのは、技術をもとに、世の中に受け入れられるモノやアイデアを生み出すことだ。日本のメーカーの多くは、そこを見失った。
松下電器でオーディオ商品企画のベテランだった戸田一雄(74)にも、30年以上前の忘れられない失敗がある。
スピーカーとアンプをFM波でつなぎ、コードがいらないステレオセットの企画を担当したときのことだ。どこにでもスピーカーが置ける。前評判は悪くなかったが、まったく売れず、ほどなく生産中止となった。東京・秋葉原の電気街に立つと、理由は明快だった。お客はちょっとした見てくれではなく、音質が一番良いものを求めていた。
「どんな技術を使ってどんな喜びを与えられるのかを考えるのが後回しになった。独りよがりの技術革新だった」
2012年。デザイナーの中禰が手がけた扇風機が、大阪の中堅電機メーカーから売り出された。羽根を横にだけでなく、真上にも向けることができる。室内の空気をうまく循環させることができるので、冬にも使える。ヒット商品になった。
中禰はいまも、自分の試作機を受け入れなかった幸之助の判断を思う。あれはあれで正しかったのかもしれない。「でも、あのとき、松下が本気でコンピューターに取り組んでいたら、ひょっとしたら、松下がアップルのように変わっていたかもしれない」
あるいはそうかもしれない。しかし、そんな「もしも」に現実感が持てないところに、私たちはいる。
=敬称略、おわり (内山修)
感想;
創業者の先を見る目と商品イノベーションで企業は急成長してきました。
ところがその創業者の先を読む力が徐々に衰えてくることもあるようです。
ホンダの本田宗一郎は空冷式に拘っていたそうです。
技術者がいくら訴えても、水冷式にGoを出してくれません。
困った技術者は本田と二人三脚でやってきた副社長の藤沢に訴えました。
藤沢は本田に「経営者で行くのか?技術者で行くのか?」と二者択一を迫りました。
本田は技術のことは技術者に任せる選択を行い、それ以降は技術に口出しをしなかったそうです。
創業者に言える人物がいることも企業成長には必要なのでしょう。
また、聴く耳を持っていた人物だったからこそ成長したのでしょう。
創業者たちの言葉
静かなひと言が、計画を白紙に戻した。
1980年秋。日差しが照りつけ、暑い夏のような日だった。大阪府門真市の松下電器産業(現・パナソニック)本社の一角にある無線研究所に、社外デザイナーの中禰兼治(なかねけんじ)(64)はいた。広い会議室で、極秘に開発した「パソコン」の説明会が始まろうとしていた。
机の上には、中禰が手がけた試作機。銀色の四角い本体が三段重ねに積まれ、ブラウン管を備えたモニター画面とつながれていた。B5判サイズの「タブレット」もついていた。専用の電子ペンで画面に文字や図形を描くと、パソコンのモニター画面に表示できた。当時としては斬新な機能だった。
松下幸之助が部屋にやってくると、室内は水を打ったように静まりかえった。相談役に退いてはいたものの、新製品を世に出すには「創業者の了承」が必須だった。
研究所幹部の説明を聞きながら、幸之助は自らキーボードに触れて操作を確かめる。終盤にさしかかったときだった。幸之助は説明をさえぎるように言った。「わかった。けど、うちはパソコンはせえへんで」。そして、部屋を後にした。
■アップルは着々
パソコンブームの前夜だった。米国では、スティーブ・ジョブズが自宅のガレージでパソコンを作り、アップル社を起こしていた。頭脳となる半導体の性能の向上はめざましかった。仕事に、遊びに、パソコンの時代が始まろうとしていた。
松下電器は、創業以来、幸之助の「目利き」が成長の支えになってきた。その代表例が、家庭用ビデオだった。ベータとVHS。どちらの規格を選ぶかが運命の分かれ目だった。日本ビクターが独自に開発したVHSを松下電器は選んだ。ビデオ事業部長だった谷井昭雄(87)は、「社内の反発もあったが、創業者が押し切って採用したことがすべてだった」と言う。
しかし、コンピューターの分野で幸之助の「目利き」は発揮されなかった。
幸之助が大型コンピューター事業からの撤退を宣言したのが、64年。開発に資金がかかりすぎる、というのが理由だった。電機メーカー各社が次々とパソコン事業に本腰を入れるようになっても、松下では、グループ会社による参入にとどまっていた。
中禰は「幸之助さんには、コンピューターの未来が見えていなかったのかもしれない」と話す。家電の覇者は、80年代のパソコンブームの中では埋没し、ヒット商品「レッツノート」が生まれたのは、幸之助の死から7年後だった。
■そしてソニーも
戦後の焼け野原から、いくつもの企業が生まれ、復活してきた。中でも、松下と並ぶ家電の雄のソニーは、特別な存在だった。
「モルモット」――。評論家の大宅壮一は58年、「週刊朝日」の記事で、ソニーを実験用の動物に例えた。新しい製品に挑戦するが、成果を他社に奪われることも少なくない状況を皮肉った。
トランジスタラジオ、高画質の「トリニトロンテレビ」、ウォークマン。ソニーからは、世界をあっと言わせた製品がいくつも飛び出した。大宅の物言いに、当初は反発していたソニー創業者の井深大だが、後の社内報では「決まった仕事を決まったようにやるのは時代遅れ。モルモット精神もまた良きかな」と受け入れた。松下電器はというと、模倣して売るのがうまいとして「マネシタ」と呼ばれた。
ソニーのモルモット精神を支えていたのは、数多くの異能の技術者たちだった。奇抜な発想を実現すべく、しのぎを削っていた。それを良しとする社風がソニーにはあった。
しかし、それも、いつのころからか、変わっていったようだ。
「上からダメだと言われたんですよ」。副社長を最後にソニーを去った大曽根幸三(81)は、現役の技術者が悔しそうに言ったのを覚えている。
2000年代、米アップルの「iPod」に押されて、ドル箱のウォークマンの販売はどんどん落ちていった。iPodはテープやCDを使わず、パソコンから音楽をダウンロードして聴く新方式。実はソニーも99年末には先行して商品化していた。だが、ソニーのやり方は「使いにくい」と評判が悪かった。音楽会社を子会社に持つことから、上層部は使い勝手よりも著作権の保護を優先したようだ。
大曽根は言う。「誰がなんと言おうと、自分が使ってみたい、欲しい、と思うものをつくる。そのための技術であり、その結果がイノベーションなんだ」
経済学者のシュンペーターが唱えた「イノベーション」は、技術的な革新にとどまらず、世の中に普及する新しい概念を広く指す。しかし、戦後の日本では、専ら「技術革新」と訳された。その言葉の下、欧米から新しい技術を取り入れていった。
しかし、いちばん大事なのは、技術をもとに、世の中に受け入れられるモノやアイデアを生み出すことだ。日本のメーカーの多くは、そこを見失った。
松下電器でオーディオ商品企画のベテランだった戸田一雄(74)にも、30年以上前の忘れられない失敗がある。
スピーカーとアンプをFM波でつなぎ、コードがいらないステレオセットの企画を担当したときのことだ。どこにでもスピーカーが置ける。前評判は悪くなかったが、まったく売れず、ほどなく生産中止となった。東京・秋葉原の電気街に立つと、理由は明快だった。お客はちょっとした見てくれではなく、音質が一番良いものを求めていた。
「どんな技術を使ってどんな喜びを与えられるのかを考えるのが後回しになった。独りよがりの技術革新だった」
2012年。デザイナーの中禰が手がけた扇風機が、大阪の中堅電機メーカーから売り出された。羽根を横にだけでなく、真上にも向けることができる。室内の空気をうまく循環させることができるので、冬にも使える。ヒット商品になった。
中禰はいまも、自分の試作機を受け入れなかった幸之助の判断を思う。あれはあれで正しかったのかもしれない。「でも、あのとき、松下が本気でコンピューターに取り組んでいたら、ひょっとしたら、松下がアップルのように変わっていたかもしれない」
あるいはそうかもしれない。しかし、そんな「もしも」に現実感が持てないところに、私たちはいる。
=敬称略、おわり (内山修)
感想;
創業者の先を見る目と商品イノベーションで企業は急成長してきました。
ところがその創業者の先を読む力が徐々に衰えてくることもあるようです。
ホンダの本田宗一郎は空冷式に拘っていたそうです。
技術者がいくら訴えても、水冷式にGoを出してくれません。
困った技術者は本田と二人三脚でやってきた副社長の藤沢に訴えました。
藤沢は本田に「経営者で行くのか?技術者で行くのか?」と二者択一を迫りました。
本田は技術のことは技術者に任せる選択を行い、それ以降は技術に口出しをしなかったそうです。
創業者に言える人物がいることも企業成長には必要なのでしょう。
また、聴く耳を持っていた人物だったからこそ成長したのでしょう。











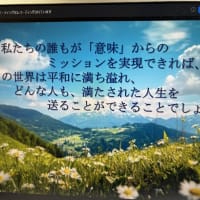

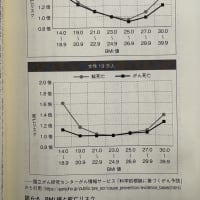

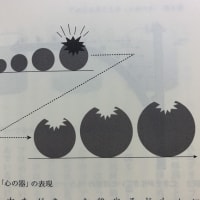
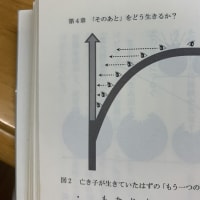



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます