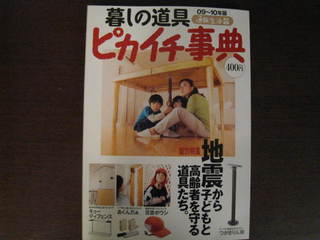きのうの夕暮れ、リビングからふと、お台場上空あたりを見たら、風船のような謎の物体が、ふわりふわり・・・。
気球でしょうか?
それとも飛行船?
風船という言葉が、いちばんぴったりしているような気がするのですが・・・。
とにかく、風の吹くままあちこちに流れていきます
なにかの宣伝かしらと、あわててネットで検索してみましたが、なにも出て来ません。
あれはいったい、なんだったのでしょうか?
あの赤い色といい、ちょっと不気味です。
想像もつかないような事件の起きる時代なので、ちょっとしたことで神経が過敏になってしまいます。
すわ、風船爆弾?・・・なんて。
ですから風にのって、こちらにふわっと近づいてきたときは、思わず身構えてしまいました。
想像力過多?
・・・そうかもしれません。
気球でしょうか?
それとも飛行船?
風船という言葉が、いちばんぴったりしているような気がするのですが・・・。
とにかく、風の吹くままあちこちに流れていきます
なにかの宣伝かしらと、あわててネットで検索してみましたが、なにも出て来ません。
あれはいったい、なんだったのでしょうか?
あの赤い色といい、ちょっと不気味です。
想像もつかないような事件の起きる時代なので、ちょっとしたことで神経が過敏になってしまいます。
すわ、風船爆弾?・・・なんて。
ですから風にのって、こちらにふわっと近づいてきたときは、思わず身構えてしまいました。
想像力過多?
・・・そうかもしれません。