小学校勤務から中学校勤務に変わり、3年経ってから、大学教育学部付属教育実践総合センターで客員研究員として1年間だけ、研修させてもらいました。
長年、小学校で指導していて、それからの中学校という思いがけない勤務の変更だったので、いろんな面でとまどいもありました。
この1年間は、貴重な研修を積むことができました。情報教育・心理学など、今までにないことを学ばせてもらいました。そして、それが今でも生かすことができているのかなと思います。貴重な経験をさせていただきました。

それ以降、毎年、教育同人の方々は、教育実践研究会として、研修会や総会、懇親会があり、参加させてもらっていました。
また現場に戻ってからも、道徳教育の指定研究を受けた時も、サポートをしていただきました。
いろいろと楽しく研究をさせていただいた期間が懐かしく感じることができます。

この大学の実践総合センターが現場と大学をつなぐ架け橋の一つになっていました。そして、現場に研修の充実を図ってくれました。
教育の施策として、教職員大学院などができ、現場も教職員大学院などに連携がシフトチェンジをしていこうとしています。これも教育の流れなのでしょう。
実践総合センターの存在の意義・価値も変化していっています。

土曜日に、教育実践研究会として最後の研修会、総会、懇親会がありました。
総会の中で、事務局から「教育実践研究会」の解散が承認をされました。
総会のレジメを見ると、昭和55年から客員研究員制度が始まり、160名近くの研究員がセンターで実践的な研究を行い、たくさんの大学の先生方がその研究に関わってくれました。
最後の懇親会もにぎわいました。

「教育学部付属教育実践総合センター」の客員研究員の制度も休止され、研修の在り方も変わり、長年の歴史が変化していくことは、寂しく感じますが、これからもますますの発展を願っています。
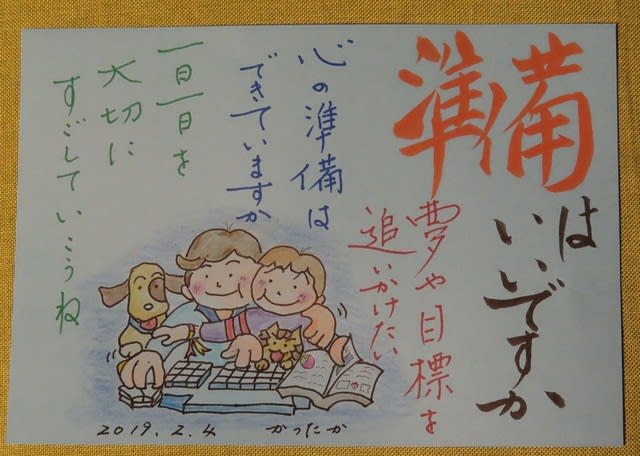
教育実践研究会をこれまで支えていただいた大学の佐藤先生をはじめ、多くの方々に心から感謝申し上げます。
長年、小学校で指導していて、それからの中学校という思いがけない勤務の変更だったので、いろんな面でとまどいもありました。
この1年間は、貴重な研修を積むことができました。情報教育・心理学など、今までにないことを学ばせてもらいました。そして、それが今でも生かすことができているのかなと思います。貴重な経験をさせていただきました。

それ以降、毎年、教育同人の方々は、教育実践研究会として、研修会や総会、懇親会があり、参加させてもらっていました。
また現場に戻ってからも、道徳教育の指定研究を受けた時も、サポートをしていただきました。
いろいろと楽しく研究をさせていただいた期間が懐かしく感じることができます。

この大学の実践総合センターが現場と大学をつなぐ架け橋の一つになっていました。そして、現場に研修の充実を図ってくれました。
教育の施策として、教職員大学院などができ、現場も教職員大学院などに連携がシフトチェンジをしていこうとしています。これも教育の流れなのでしょう。
実践総合センターの存在の意義・価値も変化していっています。

土曜日に、教育実践研究会として最後の研修会、総会、懇親会がありました。
総会の中で、事務局から「教育実践研究会」の解散が承認をされました。
総会のレジメを見ると、昭和55年から客員研究員制度が始まり、160名近くの研究員がセンターで実践的な研究を行い、たくさんの大学の先生方がその研究に関わってくれました。
最後の懇親会もにぎわいました。

「教育学部付属教育実践総合センター」の客員研究員の制度も休止され、研修の在り方も変わり、長年の歴史が変化していくことは、寂しく感じますが、これからもますますの発展を願っています。
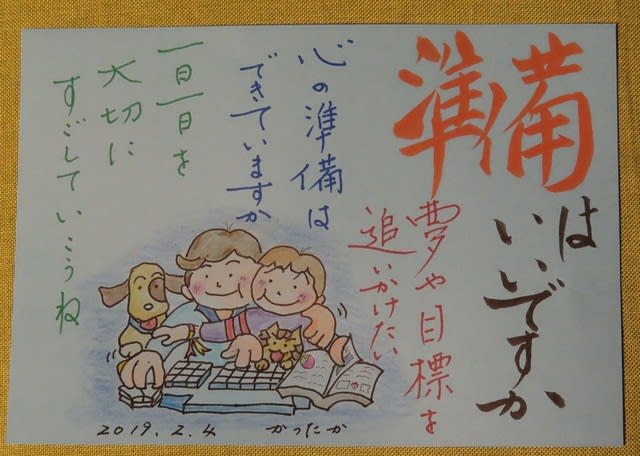
教育実践研究会をこれまで支えていただいた大学の佐藤先生をはじめ、多くの方々に心から感謝申し上げます。










