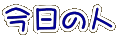【きょうの人】 0507 ■ 足利義満没 金閣寺の建立だけではありません

独善的な判断で、気になる人を選んでご紹介しています。
そこに歴史や思想、人物、生き方などを感じ取って、日々の生活やビジネスに活かしてくださると幸いです。
■ 足利義満没 金閣寺の建立だけではありません
足利義満(あしかが よしみつ)
正平13年/延文3年(1358年)8月22日(新暦:9月25日) - 応永15年(1408年)5月6日
室町幕府第3代将軍(在職1368年 - 1394年)で、金閣寺を建立した人として歴史の時間にも学ぶ人が多いのではないでしょうか。父は第2代将軍・足利義詮で、、母は側室の紀良子といわれています。
南北朝の合一を果たし、有力守護大名の勢力を押さえて幕府権力を確立させました。室町幕府の政治、経済、文化の最盛期を築いたといえます。
その権力を活かして、鹿苑寺(金閣)を建立したのですが、北山文化を開花させた人と言えます。
邸宅を、京都北小路室町に構え、「室町殿」とも呼ばれたことから「室町幕府」という名称が定着しました。
明徳2年(1391年)、山名氏の内紛に介入し、11か国の守護を兼ねて「六分一殿」と称された有力守護大名・山名氏清を挑発して挙兵させ、同年12月に討伐するという、いわゆる「明徳の乱」が起こりました。
持明院統と大覚寺統が交互に即位する「両統迭立」や諸国の国衙領を全て大覚寺統の所有とするなどの和平案が功を奏し、南朝後亀山が保持していた三種の神器が北朝の後小松天皇に戻され、南北朝合一を実現し、58年間にわたる朝廷の分裂を終結させました。いわゆる「明徳の和約」です。
【 コメント 】
半世紀以上にわたる朝廷の南北分裂を収集したとはいえ、仲介に当たらせた大内義弘の功績が大といえます。
結果も、本当にこれで良かったのか、楠木正成が存命であったらどうだったのか、義満の力がどの程度であったのか、研究者により評価は異なるようです。
【若狹晃司先生による追補】
足利義満は「勘合」(通行証)を用いた明との貿易で足利幕府財政の立て直しに成功。明から冊封を受けて貿易の道を切り開いた(朝貢貿易)。その際、天皇陛下よりも自分が上として「日本国王」と明に申し出ている。経済的には繁栄したが日本国王という観念がその後問題を起こした。
それは赤穂浪士事件。
足利幕府時代からの武士である「吉良家」は、朝廷からの勅使下向を接待をする作法について「浅野家」に対し指導をしたが、座席の上座は「幕府側」で下座が「勅使(朝廷)側」だと伝えた。2回の接待で2回とも指導。
足利幕府流で言えば日本の王は幕府。しかし、赤穂藩は山鹿素行(尊王思想)に教育を受けていた為、上座は勅使側でなければならない。よって赤穂藩は「激怒」していた。それが原因で赤穂藩士が殿に言い寄って松の廊下事件になった。しかし、殿は基地外ではなく吉良の頭を刀で切ったわけではない。ただしやり過ぎだった。その後かなり時間をかけて(100年後)上座が勅使側、下座が幕府側になった。
・・・明治維新は江戸時代から既に始まっていた・・・
歴史は繋がっている。
私の郷里は岡山。赤穂は隣のようなもの(応援したくなります)。

◆ 【きょうの人】 バックナンバー
歴史上で活躍したり、仏教など宗教関係の人であったり、ジャンルはいろいろですが、彼等から、学ぶところが多々ありますので、それをご紹介します。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/b57a13cf0fc1c961c4f6eb02c2b84c9f
◆ 【今日は何の日】は、毎日発信しています。
一年365日、毎日が何かの日です。 季節を表す日もあります。 地方地方の伝統的な行事やお祭りなどもあります。 誰かの誕生日かも知れません。 歴史上の出来事もあります。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/b980872ee9528cb93272bed4dbeb5281
◆ 【経営コンサルタントのひとり言】
経営コンサルタントのプロや準備中の人だけではなく、経営者・管理職などにも読んでいただける二兎を追うコンテンツで毎日つぶやいています。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/a0db9e97e26ce845dec545bcc5fabd4e
【 注 】
【きょうの人】は、【Wikipedia】・当該関連サイトを参照・引用して作成しています。