昨日の土曜日、渓流釣りを終えての帰り道、松井田バイパス北側の松井田城址脇を通る坂道の途中の作業道で何やら大きな生き物が見えました。
「えっ、こんな所にカモシカ!」とKさんと思わず叫んでしまいました。直ぐに車をバックさせて良く観察しました。
カモシカ君もこちらを見つめ逃げる気配がありません。慌ててカメラを出して車の外へ・・・カメラを構えたとたん身をひるがえして山中に逃げていきました。何とかピンボケですが後姿を撮る事が出来ましたが惜しいことをしました。車から降りずに窓から撮ればよかったかな?
わが町は田舎ですからイノシシなどは出ていますが、比較的山奥に棲むカモシカがこんな所に姿を現すとは驚きです。碓氷峠や霧積にはいるようですが、生息数が増えてきたのか、山の食料が乏しくなったのか、ただ単に迷ったのか・・・最近はハクビシンやアライグマ、ガビチョウなど外来生物が増えるなどしているのに加え、在来の野生動物の世界にも異変が起こっているような気がします。
後ろ姿だけではつまらないので以前六合村で撮影した正面の写真も掲載しておきます。
今週末も渓流釣り、Kさんと吾妻管内の山奥の沢に行ってきました。
何時ものとおり6時出発、7時到着で山道を登っていきます。前回に終了した場所よりも上流まで行って見ようということで途中をとばして一番目の滝から上に入ります。
前回よりも更に水量が減っていて心配しましたがポツポツは釣れて来ます。大滝までに4~5尾ずつ釣れ、大滝を登り前回大きいイワナに糸を切られた滝まで行き、粘ってみましたが、今回は出ませんでした。
滝を捲いて更に上流まで行きます。此処からは新天地ですが水はどんどん減っていきます。暫く行くと完全にちょろちょろの水になって終了です。イワナ17~26cmを12尾でした。
その後、地元のMさんに案内してもらって結構釣れているという沢に入り2時間ほど釣ってヤマメ7尾追加して終了です。合計19尾でした。
昨日、アユ友釣り解禁情報をアップしました。今年も、いよいよアユ友釣りの季節が近づきました。
アユ釣りが始まる前に、アユ釣り関係者に是非とも読んで欲しい本を紹介しておきましょう。
それは「ここまでわかったアユの本」という本です。
以前、私は「趣味が高じて水産関係の仕事に就いた」と書きましたが、その当時の仕事のほとんどは「アユを釣れるようにすること」でした。
課題はたくさんあって、川の環境、アユの天然遡上、アユ稚魚の養殖や放流、冷水病、カワウの食害、釣り人の資質、漁業協同組合の資質のなどでした。
アユの生態や漁業資源維持の方法などに関して非常に役立ったのが、この本の著者の一人である高橋勇夫さんの話や高知新聞等への連載文でした。
その高橋さんには、第2回「アユを取り戻す全国の集い」の開催時に群馬県に来県していただき講演してもらったこともあります。
この本には、実際に川に潜ってアユを直接観察してきた研究者が分かりやすく語る本当のアユの話がいっぱい掲載されています。川の環境を考える人やアユ釣り師にとって必ず役に立つ本であること請け合いです。
【目次】
第一章 アユの四季
第二章 変化する川とアユ
第三章 アユの放流再考
第四章 漁協が元気な川にアユがいる
第五章 天然アユを増やすには
著者:高橋勇夫+東健作、出版元:築地書館、定価:2000円(税別)
日時は6月20日(土曜日)の未明解禁です。
私が所属する上州漁協の松井田支部(碓氷川:久保井戸浄水場の堰堤~滝名田橋)では、すでに静岡系(群馬県内で養成)のアユ稚魚を約300kg放流済みです。今後も多少の追加放流予定もあるようですが、今のところ順調に育っています。
松井田支部では役員総出で放流を行い、カワウの食害防止のため案山子の設置や糸張りを行ってまいりました。

川の水温と運搬時の水槽の水温差があった時は、全員で川から水を汲み上げて水槽の水を入れ替えて温度調節をする水温馴致という大変な作業を行い、ストレスを与えないように大切に放流しました。

そして暑い中、風の強い中でも1日中カワウの食害防止のため様々な作業を行いました。さらに支部長(理事)さんにあっては何日も続けて早朝からカワウの一斉追い払いに出動するなど涙ぐましい努力を行っております。
ここまで努力してきたのですから、解禁当日には沢山のアユが釣れて喜ぶ釣り人の顔を是非とも見たいものです。

このサシガメは大陸からの帰化昆虫で80年ほど前に九州で初めて見つけられたものが東進を続けているのだそうで、最近では群馬県各地でも普通に見られるようになってしましました。
「こんなところにも大陸から来た横綱が居るのだなぁ」と妙に感心してしまいましたが・・・。

成虫になると黒光りした体とお腹の側面が扇のように張り出し白黒の縞模様になるのだそうです。この縞模様は幼虫にもあって横綱の化粧回しに見えるので名前が付いたのだそうです。
サクラやケヤキなど広葉樹の洞などに棲むことが多く、幼虫は群がって冬を越して5月頃に成虫となります。吸汁性で色々な昆虫を捕まえて口吻を突き刺して体液を吸いとります。
生息域の拡大にはトラックなど交通機関が大きく関わっていると言われていますが、この新たな昆虫が生態系にどのような影響を与えるのか心配ですね。
今日も根強い人気のある山菜です。
ヤマウドはウコギ科タラノキ属の多年生草本で林縁部や谷下の崩積土の場所などよく生えています。同じ仲間のタラノメと葉の様子などは良く似ていますよね。草か木か、刺が有るか無いかの違いくらい良く似ています。
栽培物は香りが薄いのですが、野生のウドは香りやアクが強く、野趣味を好む人にとっては何ともいえない美味しさです。
生で味噌や醤油をつけて食べてよし、おひたしでよし、油いためや胡麻和えなどいろいろな食べ方で楽しめます。
白い根の部分だけでなく、新芽の部分もテンプラやおひたしにして大切に食べましょう。剥ぎ取った皮も捨てないで千切りにしてキンピラにすると美味しいですよ。
山菜の季節ですので今しばらくの間、現在採れるものを中心に紹介していきます。
ワラビは日本全国何処にでも自生しているしだ植物でウラボシ科の多年生草本です。
若芽を採取して食べるほか、根茎を砕いてデンプンを採り蕨餅などを作ります。
若芽は灰汁抜きをして「おひたし」で食べるのが一般的ですが、油揚げなどと一緒に煮付けたものもおいしいですね。
灰汁抜きのやり方は良く洗った後に大き目のボールに入れ、木灰や重曹をまぶしてたっぷりの熱湯を注し、そのまま一昼夜置いておきます。
その後水洗いをしておひたしや煮付けにしたり、塩漬けにして保存したりします。
今日は朝から暑い!30℃を超えています。
昨日の釣りは結構強行軍だったので、魚が釣れなかったかわりに足が攣れてしまいました。そのため吾妻のニジマス放流もK君と一緒に行く予定だったのですが、キャンセルして1日中家に・・・と言っても貧乏性のため、垣根を剪定したり庭の雑草を抜いたりと結局は汗びっしょりでした。
さて、そろそろ終盤に近づいてきたサクラの話題を・・・。
サクラの花というと3月か4月に咲くものと思っている人が多いのですが、日本は南北に長く、標高差もあり、四季咲きや冬咲き、早咲き、遅咲きの種類を組み合わせれば10月~7月くらいまでは何処かでサクラの花を見ることが出来ます。
5月初旬まではサトザクラが平地でも見られますが、その後は北に行くか標高の高い地域に行けばサクラの花が見られると言う事になります。
・・・と言う事で、標高が比較的高い県北西部のサクラです。牧草地から遠望した草津白根山にはまだ雪が残っています。
そして、この付近では自生のカスミザクラやオオヤマザクラが満開でした。
釣り好きの仕事仲間達で毎年恒例の渓流釣りと山菜採りに行ってきました。
吾妻管内の山奥の某沢です。4人で入渓したので交互に釣っていきますが連休で攻められていたのか当りが少なく大滝までは皆1~3尾と貧果です。
KEさん、今日の竿頭
前日飲み会でバテ気味のAさん
吾妻管内の主、KUさん
そして大滝に到着です。滝をバックに記念撮影。
この滝の上流に大きいのがいるとの事で越える事にしますが、直登できずに手前から高巻きます。
そして滝上を釣りあがり数尾を追加して1時過ぎになったので終了。その後は下りながら山菜採りです。
ところが、下山道を歩いていくとKUさんが「危ない!戻れ!」と真剣な顔で私達を押し戻します・・・指差す前方の木に2歳くらいの熊が登っているではありませんか!
熊も私達に気が付いたようです。4人で大声を上げたり笛を吹いたりしていると木から下りてクマザサの密生する斜面にガサゴソと消えていきました。
暫く様子を見て、恐る恐る歩き出し、ここに人が居るぞとばかり大声を上げながら斜面を下り車に帰着です。釣果はイワナ9尾と貧果でしたが色々経験できた釣行でした。
学名は世界で通用する呼称で、ラテン語で記されます。この他に地方名があって方言名とも言われ一つの植物にたくさんの呼び方があります。
これらの呼び名はその姿形や用途、味、匂いなどから付いたもの、外国の名前から付いたもの、アイヌ語などから付いたものなど様々です。
植物学を少しでも囓っている人間は植物名の語源に興味を持っている人も多く、その知識は「牧野新植物図鑑」から身につけた人も多いと思います。
その「牧野」の語源について部分的に疑問を持った著者が私見として、たくさんの資料に基づき、多岐にわたる考えから「植物名の語源に関する独自の論考」を展開したのが「植物和名の語源(著者:深津正、発行元:(株)八坂書房、定価:2800円+税別)」です。
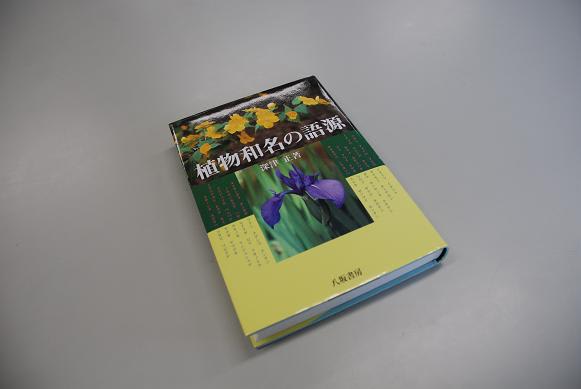
内容的には、Ⅰ植物和名語源私考、Ⅱ植物和名語源論考(1紙の原料植物の語源、2アイヌ語に基づく植物和名と植物方言、3母子草語源考)、Ⅲ植物和名語源散歩 と言う目次で140余種の植物の和名の語源を考察しています。
植物の和名に興味のある方は読んでみてください。

1階はカウンターと座敷で30名ほど座れ、2階の広間では宴会も出来て、マイクロバスの送迎もあったので何度か飲み会でも使わせて貰いました。
私の仕事場に近く、歩いて数分の場所にあるので偶に食べに行きます。特に昼時にはランチメニューがあって「にぎりセット(にぎり寿司3貫と巻物1巻+もりそば)」が1000円です。寿司も蕎麦も好物な私にとって、この店に入れば「にぎりセット」が定番です。(他のセットメニューも700円からあります)
信州の迷人にお誘いをいただき、千釣さんと青木湖のヒメマス釣りに行ってきました。
4時半に出船と言うことで我が家を2時半に出発です。しかし、天気予報とは裏腹に雨は降り続き止みそうもありません。
青木湖に着いてもショボショボと降っています。5時頃に出船して私と千釣さんは岸よりのブイに、迷人は中央のブイに着けました。
迷人は投入後に早速1尾来たようです。こちらは魚探に魚影が映っても釣れずに焦ります。千釣さんも釣れないとぼやいています・・・。
1時間ほどしてやっと当りが出始め1尾、2尾と釣れ始めました。その内に左右の竿に当りが出始め、2尾、4尾、5尾、6尾と一荷が続きます。
千釣さんに頂いた写真です。5点掛け・・・
このまま行けば自己新記録かなと思い始めたら雨足が強くなって当りがほとんどなくなってしまいました。
寒いしカッパを着ていてもビショビショ・・・11時でギブアップ・・・46尾でした。
コシアブラはウコギ科(タラノキ、ウコギ、ウド、タカノツメ、ハリギリなど)の落葉高木で独特の風味があって、最近はタラの芽よりも人気がでてきた山菜です。
大学のときに樹木学の授業で「ウコギ科の植物はどれも食べられるよ」という先生の指導で食べたのが最初でした。その頃は色々な植物を試して見ましたが中でもコシアブラは「美味しいなぁ」と感じた一つでした。
30数年ほど前の群馬県内ではコシアブラはほとんど知られていなかったので一人で密かに楽しんでいましたが、だんだんと広まってしまい最近は至る所で取られてしまっています。
別名の「ごんぜつ」は、この樹液を黄色の塗料(漆がわり)に使っていたため金漆と書いてごんぜつと読むのだそうです。また、トウフノキ・イモノキは木肌が白く木質が柔らかいから付いたようです。
一般的にはおひたしや天ぷらで食べますが、ごま和えや油炒めも美味しいです。小さな芽を生のまま味噌をつけて食べるのもあくが強いのを好む人には喜ばれるようです。
また、農家が早期に発生させて出荷する技術も発達して12月頃から食べられるようになりましたが、やはり自然の中で芽吹いたものが風味があって良いですね。

最初に芽吹く先端の芽を「太郎っぺ」、2番を「次郎っぺ」、3番は「三郎っぺ」と言うのだそうですが、資源保護のため採るのは「太郎っぺ」だけにしましょう。

テンプラ、油いため、おひたしやゴマ和えが美味しいです。あくが強いのが好きな人は、ホイル焼きや皿に並べラップをしてレンジで温めて食べる方が濃厚な味になって良いかもしれません。
連休中は孫達と・・・・そのため、釣りも山菜採りも出来なくなってしまいました。そこでブログは山菜の紹介でにごしておきます。
モミジガサ(キク科)は独特の風味で好き嫌いがあるのですが代表的な山菜です。多くの人が親しんでいる証拠に方言名が多く、北海道や東北地方ではシドキ・シドケなどと称され、キノシタ・トウキチ・ヤマソバなどとも呼ばれています。
森林地帯の樹林下に群生し、あまり葉が開かないうちに手折り、20cm程度で折れるところから上を採取します。
食べ方はおひたしが主ですが、天ぷらや酢の物、油炒めなどでも美味しく食べられます。群生地を見つければ簡単にたくさん採れる山菜ですが、とある地方では人気があって同じ大きさのパック入りならギョウジャニンニクよりも高く売っていて驚きました。
シドキやシドケの方言はアイヌ語から派生したようです。キノシタは樹林下に生えるから。キノシタから符丁でトウキチ(木下と言えば籐吉郎:豊臣秀吉→トウキチロウ→略してトウキチ)という呼び名になったようです。ヤマソバは蕎麦の香気があるからと言われています。
















