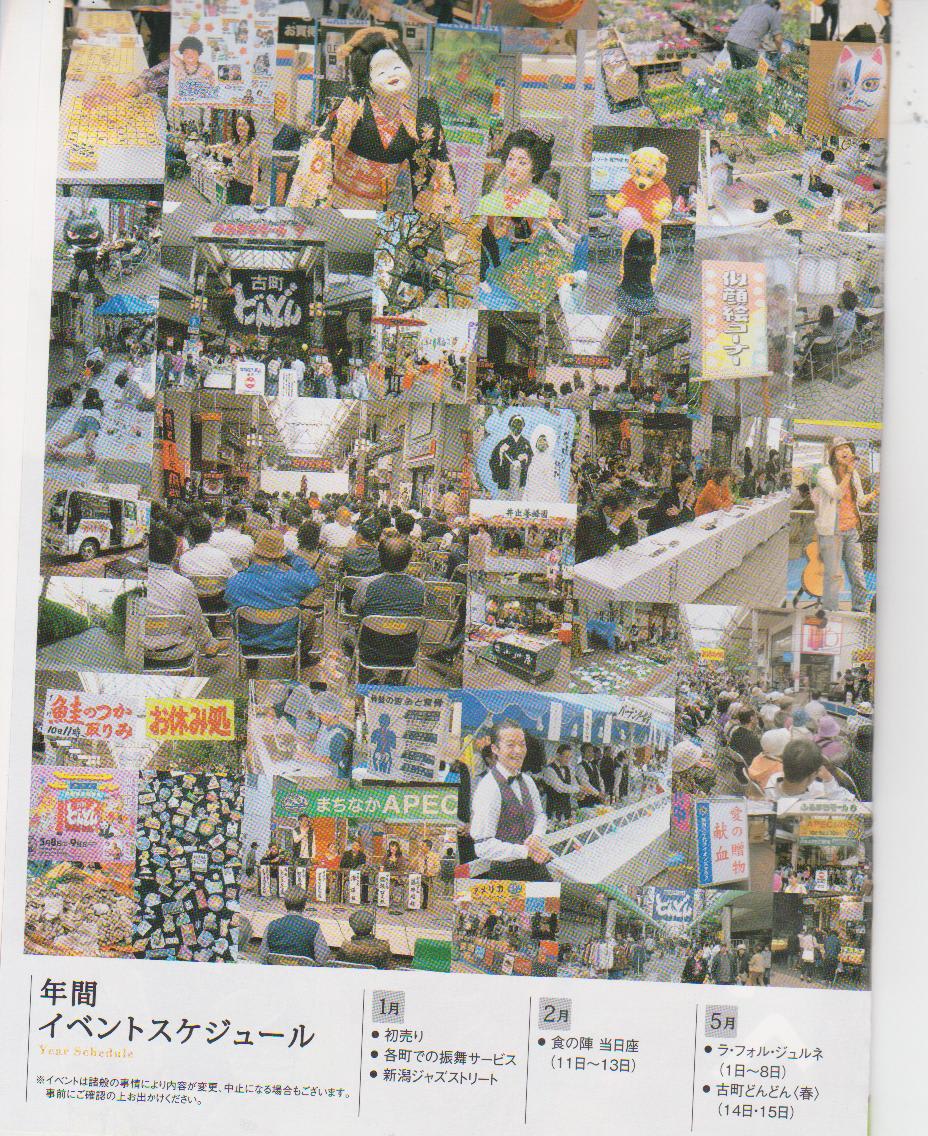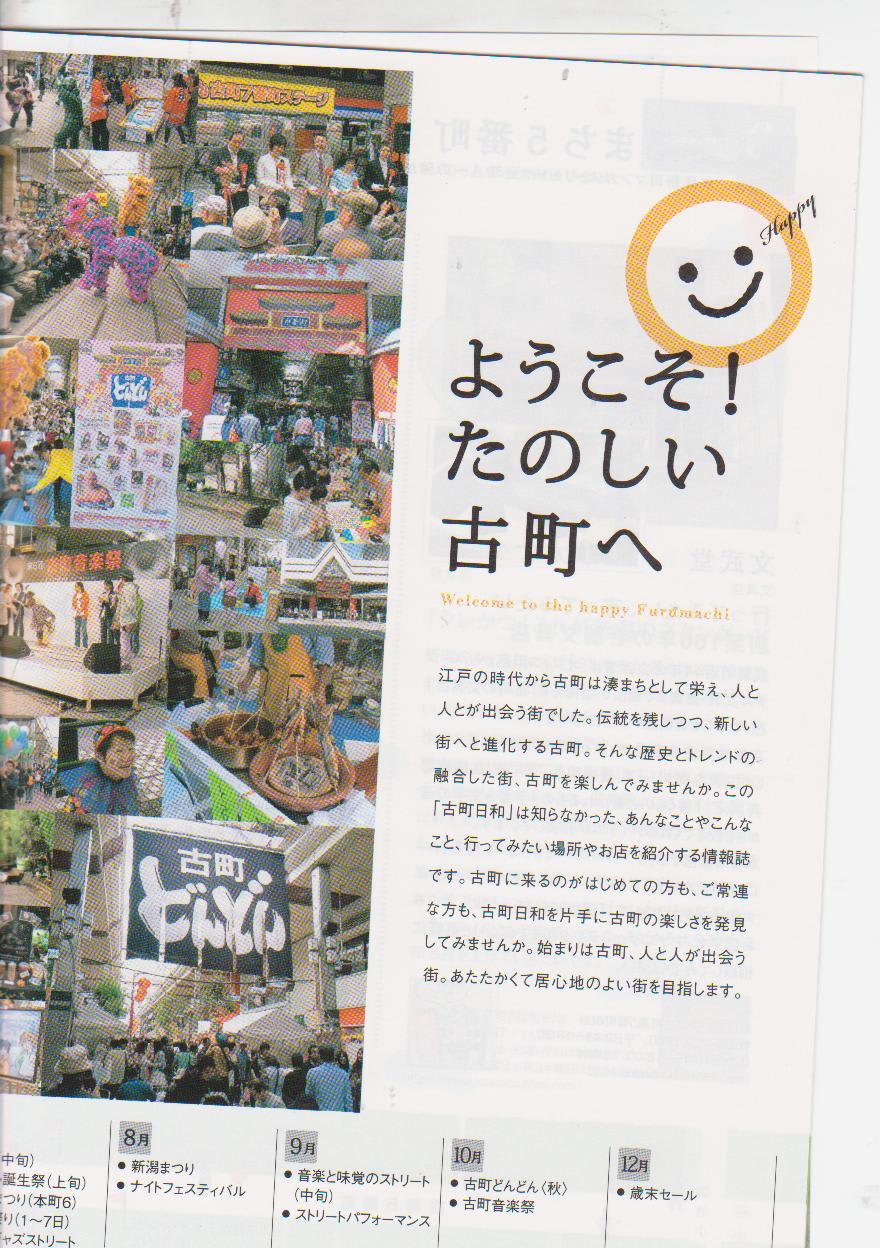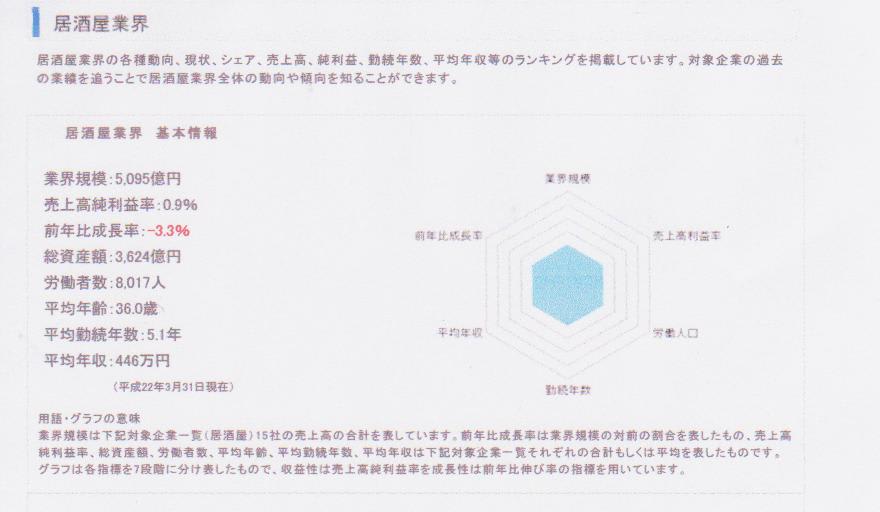相手が出そうとするジェスチャーを見抜くことで、じゃんけんに必ず勝つロボットを
東京大学の研究者たちが開発した。


これは知性をどう考えるかについての重要な要素を含んでいる。
東京大学の石川奥研究室の研究者たちが、相手が出そうとするジェスチャーを見抜くことで「じゃんけんに必ず勝つロボットを開発した。
これは「後出しじゃんけん」のロボット版だが、違うのは、超人的な速さで行われることだ。つまり「後出しの様に見えない」のだ。
このロボットの場合、人間の目では捉えられない速さで相手の動きを認識する。人間が手の形をつくり始めるやいなや、認識を始めるのだ。人間が手の形を完成させるときには、すでに「勝つ手」を出している。

これは人工知能の技術の素晴らしいデモンストレーションだが、知性をどう考えるかについての重要な要素をも含んでいる。
じゃんけんはささやかなゲームだが、人工知能機能の対象になったのは遅かった。
チエスで人間に挑戦するスーパーコンピューターが開発されて10年も後のことだった。AI(人工知能)の研究においては、これまでチエスが脚光を集めて来た。
だがじゃんけんロボットは違う種類の知性を示している。
それは、より身体的な知性だ。われわれは知性について、「脳」対「身体」
という観点から考えることに慣れている。だが今回明らかになったのは、すばやく
反応できるマシンを作るには、かなりの知性も必要とされるということだ。
空間の中で認識して動くような「身体的知性」の能力が重要になってくるだろう。
「The Athantic Tech」の記事から
プロのマジシャンがカードゲームで目にも止まらぬスピードでカードを入れ替える。
シローモーションビデオで見ると「なあんだ」と思うトリックである。
人間の視力は騙されやすい。人間の動体視力の限界はかなり低い。
指の動きの速さに追いつかないのだ。機械的に動きを早める、身体的に動きを早めると
「マジック」の領域に入ることが出来るようだ。
スポーツ科学もこの「知性」の開発にヒントがあるだろう。
2020年「東京オリンピック」実現と優れたアスリートを養成する手段にも
活用できるかも。 ^^
^^
東京大学の研究者たちが開発した。



これは知性をどう考えるかについての重要な要素を含んでいる。
東京大学の石川奥研究室の研究者たちが、相手が出そうとするジェスチャーを見抜くことで「じゃんけんに必ず勝つロボットを開発した。
これは「後出しじゃんけん」のロボット版だが、違うのは、超人的な速さで行われることだ。つまり「後出しの様に見えない」のだ。
このロボットの場合、人間の目では捉えられない速さで相手の動きを認識する。人間が手の形をつくり始めるやいなや、認識を始めるのだ。人間が手の形を完成させるときには、すでに「勝つ手」を出している。


これは人工知能の技術の素晴らしいデモンストレーションだが、知性をどう考えるかについての重要な要素をも含んでいる。
じゃんけんはささやかなゲームだが、人工知能機能の対象になったのは遅かった。
チエスで人間に挑戦するスーパーコンピューターが開発されて10年も後のことだった。AI(人工知能)の研究においては、これまでチエスが脚光を集めて来た。
だがじゃんけんロボットは違う種類の知性を示している。

それは、より身体的な知性だ。われわれは知性について、「脳」対「身体」
という観点から考えることに慣れている。だが今回明らかになったのは、すばやく
反応できるマシンを作るには、かなりの知性も必要とされるということだ。
空間の中で認識して動くような「身体的知性」の能力が重要になってくるだろう。
「The Athantic Tech」の記事から
プロのマジシャンがカードゲームで目にも止まらぬスピードでカードを入れ替える。
シローモーションビデオで見ると「なあんだ」と思うトリックである。
人間の視力は騙されやすい。人間の動体視力の限界はかなり低い。
指の動きの速さに追いつかないのだ。機械的に動きを早める、身体的に動きを早めると
「マジック」の領域に入ることが出来るようだ。
スポーツ科学もこの「知性」の開発にヒントがあるだろう。
2020年「東京オリンピック」実現と優れたアスリートを養成する手段にも
活用できるかも。
 ^^
^^